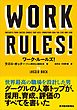コレラ作品一覧
-
3.7リーダーならもっと数字で考えなきゃ!! 黒字上司の言葉 赤字上司の発想 (あさ出版電子書籍) 「すごい上司になる仕事のヒント114」 ◆著者のコメント リーダーが評価される「基準」とは何だろうか? それは “数字”である。 プロスポーツの世界を見ればわかりやすいだろう。 いくら選手からの人気が高いからといって、万年最下位の監督やチームキャプテンが、ずっとその立場に居続けることはない。 リーダーは、チームに求められている結果をきっちり出して、初めて評価されるのだ。 では、求められる結果を出すために、リーダーはどうすればいいのか? その具体的な方策をまとめたのが本書である。 今回も、前著『もっと仕事は数字で考えなきゃ』と同様、 私が見たり聞いたりした関西弁の格言(?)を多数収録した。 ・ひまわりばっかり見てんと、きれいな月見草もしっかり見たれよ。 ・鳩に手品させるって、そりゃなんぼなんでも任せすぎやろ! ・昼メシ後に数字でゴチャゴチャの資料って、自分「ラリホー」使いか? ・ギリギリになってから部下にギャーギャー言うても、そら「今さらジロー」やで。 ……などなど。これらの言葉が、読者の皆さんの数字力向上に寄与すれば、著者としてはうれしい限りである。 ◆著者はこんな人 香川晋平(かがわ・しんぺい) 公認会計士・税理士 大手監査法人在籍時から、自費でビジネススクールに通い、30歳でリフォームの株式会社オンテックスに入社。「従業員1人当たりの会計データ」を導入し、従業員の生産性を向上。入社後、わずか90日で経営管理本部取締役に就任、在任2年は累計利益は業種別ダントツNo.1となった。その後、5期連続50%超増収のベンチャー企業や、従業員平均年収1000万円超の少数精鋭企業などの会計顧問をし、数社の非常勤役員も務める。また、大学で会計数値を使って「会社が従業員に期待する成績」を解説し、学生の仕事に対する意識改革に努める。 著書に『東大卒でも赤字社員、中卒でも黒字社員』(リュウ・ブックス アステ新書)、『「デキるつもり」が会社を潰す 「絶対黒字感覚」のある人・ない人』(中公新書ラクレ)『もっと仕事は数字で考えなきゃ!』(あさ出版)がある。
-
3.6あなたの「読む力」が劇的に進化する! ビジネス書の読み方に革命を起こしたベストセラー『レバレッジ・リーディング』から5年。レバレッジ・リーディング+3つのツール(モバイル、クラウド、SNS)+5つのステップ(インプット、ストック、サーチ、シェア、フィードバック)という、読書とテクノロジーを融合させた「リーディング3.0」によって、読書の方法が劇的に変わる。本書では、「最少の努力で最大の成果」というレバレッジの考え方を引き継ぎながら、できるだけ効率よく、多くのものが読める方法を紹介します。 そのツールとなるのが、iPhone(スマートフォン)、Evernote、Googleなどのクラウドサービス、Twitter、FacebookなどのSNSである。これらを活用することで、時間や場所、物理的に制約されない読書ができるようになっている。「読む」対象範囲をビジネス書だけでなく、新聞、雑誌、ウェブなど「読むこと全般」に広げた、「本田流」情報収集・活用法を紹介します。 ※本書は2011年5月に東洋経済新報社より刊行された『リーディング3.0』を電子書籍化したものです。
-
3.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 教育大国フィンランド発、親子で楽しくプログラミングに触れる絵本 【あらすじ】 『ルビィは大きな想像力を持つ女の子。ルビィの好きな言葉は“どうして?”。ルビィの世界では考えたものがなんでも実現します。パパがお仕事でいないときは、家の中をどたどた・ふらふら歩きまわるのが大好き。ある日、ルビィはパパからの手紙を見つけます――「宝石を5つ、かくしたから、さがしてごらん。ぜんぶ見つけられるかな?」。でもどう探せばいいのか書かれていません。仕方がないので、まずはヒントを探しはじめると・・・パパの机の下に、秘密の数字が書かれた紙きれを発見! ここからルビィの本当のぼうけんが始まります・・・』 日本でも初等中等教育段階でのプログラミング教育の推進がはじまり、テクノロジーやプログラミングに関する知識は子どもたちにも必要不可欠になりつつあります。プログラミングを、子どもたちが身近に感じ、楽しく学んでいける本があればいい――このような思いから生まれたのが「ルビィのぼうけん(原題:Hello Ruby)」です。 これは、フィンランドの女性プログラマー、リンダ・リウカスが、子どもがプログラミングを学ぶ糸口となるように作った絵本です。リンダは、クラウドファンディングによる資金調達ができるkickstarterを活用し、9,000人ものサポーターから約38万ドル(約3,800万円)の資金を集めることに成功。約3年かけて絵本を完成させました。 この絵本では、プログラミングのいわゆる「コード」は一文字も出てきません。4~11歳の子どもが親と一緒に楽しめる工夫がされており、前半の「好奇心いっぱいの女の子、ルビィが宝石集めの冒険をする絵本パート」と、後半の「練習問題パート」を通じて、プログラミングに必要な考え方に触れることができます。たとえば、大きな問題を小さな問題に分けること、ちらばった情報からパターンを見つけること、などです。 これらのプログラミングに必要な考え方は、手に負えないように思える世界をときほぐして、なんとか取り組みやすくするのに、大きな手助けとなります。そして、プログラミングは、自分の考えを、動くかたちにできる楽しさに満ちています。この本がその楽しさを知る一つの入り口になってほしい、そんな著者の願いがこもった一冊です。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-――掲載ページより「創刊に際して」―― ここに「歴史民俗学」を創刊する。本誌は、歴史、民俗学、歴史民俗学に関する諸篇文を収録する研究誌である。本誌は、関東歴史民俗学研究会の機関誌であり、同会会 員がその研究成果を発去する場である。同時に本誌の誌面は、これを会員外にも開いてゆきたいと思う。本誌は、アマチュア精神、在野精神を大切にする研究誌でありた いと思う。本誌は、既成のアカデミズムやジャーナリズムが正当な評価を与えないであろう研究も、これを拒まない。むしろそうした研究をこそ、歓迎したいと思う。本誌は、不定期刊である。ある枠度の研究が蓄積された段階で、順次発刊されることになろう。創刊号に収録した論文は、関東歴史民俗学研究会九四年夏期例会で発表された研究を文章化したものを中心としている。本誌の編集主体は、関東歴史民俗学研究会の常連メンバーである。今の所、具体的な投稿規定などを持っていないが、これらについては、徐々に整えてゆくことになろう (だいたい会そのものが規約などを持っていないのである)。編集姿勢については右に述べた通りで、これは今後も変えるつもりはない。なお当会は、かねてから同好の士の参加を呼びかけている。関心をお持ちの方は、巻末の案内を参照され、ご連絡をいただければと思う。 一九九五年一月二〇日 関東歴史民俗学研究会 礫川 全次 斬首論◎田村勇/人肉再論◎礫川全次/古代の入墨と民俗(1)◎畠山篤/賤種流離譚(1)◎谷万平/山窩資料[幕末から明治初期の一犯罪者による証言]◎半田直/犯罪の記号論◎礫川全次/犯罪と民俗学の方法をめぐって◎長島次郎/野口英世の母の「家」観念[勉強立身の背景]◎尾崎光弘/吉本隆明『共同幻想論』批判(1)◎青木茂雄
-
-――掲載ページより「巻頭の言葉」―― 必要があって、大正期から昭和初年あたりの雑誌を調べている。『人類学雑誌』、『民族と歴史』、『郷土研究』、『民族』、『民俗学」、『旅と伝説』、『土俗と伝説』、『犯罪科学』等々。どの雑誌も、非常におもしろく、これらの雑誌がその個性を競うように共存していた時代に、羨望の念を覚えるのである。これらの雑誌には、だいたい次のような共通性がある。 (1) 学問的な水準が高いにもかかわらず、一般の読者の興味関心にも対応できる通俗性も兼ね備えている。 (2) 多分野にわたる、様々なタイプの研究者が執筆している。 (3) 誌面が、読者にも開かれており、雑報、紙上問答等の欄からも、興味深い情報が得られる。 さて、今日の学術界、出版界を見てみよう。こうした特色を備えた雑誌が、果してどれだけあるだろうか。どうしてこのように日本の知的世界は貧弱になってしまったのか。『歴史民俗学』という雑誌が、(1)~(3)の特色を備えているという自信は、まだない。しかし、その方向性を目指しているという意思は表明しておきたいと思う。冒頭にあげたような雑誌を範としつつ、編集に励みたいと思う。 礫川 全次 高値安定の学術書[私の古書遍歴4]◎鈴木光志/オセタ=三十三度行者についての書簡◎赤松啓介/尾張サンカの研究(3)[廻遊竹細工師「オタカラシュウ」の面談・聞き書き・検証調査]◎飯尾恭之/福沢諭吉と下級武士のエートス[ニッポン民俗学外史3]◎礫川全次/島社会に潜む幻影(4)[『七島日記・図絵』を見取る(二)]◎鈴木光志/菊池山哉小伝(3)◎田中紀子/一石五輪塔は何を語るのか[―書を持ち、墓地を巡ろう―(上)]◎横田明+西山昌孝+小林義孝/古書店通いの魅力[私の古書遍歴5]◎青木茂雄/団左衛門支配の伝承をもつゾウリオモテ作り◎田村 勇/西国巡礼行者「尼サンド」について(2)◎玉城幸男+小林義孝/シシウチ神事と柴祭り[シシウチ神事にみる死と再生]◎吉村睦志/君知るや満洲国の民俗博物館を(監)[藤山一雄の民俗博物館論]◎犬塚康博/魏志倭人伝の示す身分階層について◎西江雄児/「表彰録」のなかの女性像◎尾崎光弘/熊野とダイヤモンド[八十歳の反骨ジャーナリスト]◎礫川全次/吉本隆明『共同幻想論』批判(5完)◎青木茂雄/資料篇 解説◎礫川全次
-
-――掲載ページより「まえがき」―― 『歴史民俗学』創刊10号を記念し、ここに特集号「雑学の冒険」をお送りします。歴史民俗学研究会の会員が、ここ一年ほど間に、ヒマをみて書きためたものを編集したものです。研究の余録あり、趣味的な情報あり、たまたま仕人れた知識あり、これからの研究のアイディアありと、内容はまさに種々雑多です。これらをほぼ年代順に配列してみましたが、項目によっては、年代区分を超えるものもあり、区分と順序はあくまで目安であることをお断りしておきます。従来の雑学本より、記述はやや専門的、またはややマニアックかもしれませんが、むしろそこを、本書の特色として位置づけたいと思います。雑学の可能性を探るための試みとして、ご理解いただければ幸いです。本会(歴史民俗学研究会)は、限りなく開かれた研究会です。また、機関誌『歴史民俗学』も限りなく読者の万々に開かれています。論文、報告、資料、コラムなど、形式を問わず、投稿をお待ちしています。本誌は、年四回発行(季刊)をめざしており、そのうち年一回は、この号のような「特集号」をする予定です。とりあえず次回特集号の(一九九八年一二月発行予定・原稿締切日は一◯月末)のテーマは、「埋もれた偉人・知られざる研究」(仮)です。読者の皆様にも、ぜひこのテーマでご執筆をお誘い申し上げる次第です。推しくは、本会事務局までお問い合わせ下さい。なお、巻末の「歴史民俗学研究会へのお誘い」も、併せてご覧いただければ幸いです。 ー九九八年二月一五日 歴史民俗学研究会を代表して 礫川全次 歴史民俗学研究会が総力を挙げて取り組んだ「雑学」100テーマの集大成! 古代の雑学 / 江戸時代の雑学 / 明治時代の雑学 / 大正時代の雑学 / 昭和前期の雑学 / 戦中の雑学 / 戦後の雑学 / 付録「MEET THE JAPANESE」に見る日本の光景
-
-ケネディ、ガンジー、アキノ、伊藤博文、サダト…彼らの死は、世界に大きなインパクトを与えた。これらの暗殺によって、歴史はどのように変わったのか。もしあの人物が生きていたら、どうなっていただろうか?もうひとつの未来「アナザーフューチャー」をプラスして、暗殺事件の真相と影響を探る!
-
-論理思考、ロジカルシンキングが注目されるようになって久しい。90年代半ば以降、ロジカルシンキングに関する多くの書籍が出され、その結果、世の中のロジカルシンキングに対する感度は上がってきていると実感する。 その一方で、「では、世の中の多くのビジネスパーソンが正しくロジカルシンキングできているか?」と問うと、その答えは「ノー」であろう。 その原因の一つは、ロジカルシンキングそのものの難しさにある。ある程度の経験やトレーニングが欠かせないのだ。一朝一夕にはコツが身につかないのがロジカルシンキングとも言える。 ロジカルシンキングが正しくなされていないもう一つの原因は、典型的な落とし穴に不用心で、それに簡単に嵌ってしまうということだ。 本書では、主にこの後者に着目している。これらは、知っていれば避けられる可能性が高まる、すなわち即効性が高いからだ。 本書では、ビジネスパーソンとして知っておくと有用と思われるロジカルシンキングの落とし穴を4章に分けてピックアップしている。具体的には、第1章で形式論理学の落とし穴、第2章で詭弁や論点ずらしなどの落とし穴、第3章で数字に関する落とし穴、そして第4章ではその他の落とし穴を取り上げている。 ロジカルシンキングの能力を高め、意思決定やコミュニケーションの質を上げたいビジネスパーソン必読と言えよう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ビギナーが一生懸命Logic Pro XやVOCALOID 3 Editorのマニュアルを読んでも思いどおりに演奏させたり、音色を作ったり、ミキシングできないのはナゼ? それは、DTMの各種機能がそのベースとしている基礎知識~楽器法、楽典、物理学、電磁気学、情報工学、生理学、音響心理学など~を知らないから。 本書はヤマハ社の「MEW」やAHS社の「東北ずん子」の公式デモソングの作曲家である著者が、Logic Pro XとVOCALOID 3 Editorの使い方をチュートリアル形式で説明し、かつて著者も戸惑った「取説に載ってない基礎知識」を実際の手順の中でわかりやすく解説した、今までにないディープな解説書です。●本書について、著者より。 本書は、VOCALOID3 EditorとLogic Pro Xとを使って、初心者が楽曲制作を体系的に学習するための本です。 この2つのソフトウェアを使って、演奏させたり、音色を作ったり、歌わせたり、ミキシングしたりできるようになります。 音符の並べ方を扱う作曲の本ではありませんが、その入口までは案内します。 簡単な作曲なら、手探りでできるようになるかもしれません。 音楽は見えません。見えないのでよくわかりません。よくわからないのに心を揺さぶります。まるで魔法のようです。 人類は太古からその謎に迫り、その秘密を少しずつ解き明かしてきました。 コンピュータは、それら先人たちの知恵を駆使して、見えないはずの音楽を見えるようにしてくれています。 どの音楽制作ソフトウェアにも、音楽を「見る」ためのツールが用意されています。 ですが、そこには、得体の知れない「数字/ボタン/ツマミ/グラフ/記号」がずらりと並んでいます。 何も知らないと謎の暗号か呪文でしかありません。 その解読には、以下のようなことを少しだけ知る必要があります。 音 波 : 音を波として扱う物理学。 楽 譜 : 楽譜を扱う楽典。五線譜の読み書きのルールをまとめたものが楽典です。 楽 器 : 楽器を理解する楽器学、管弦楽法。 回 路 : 電子回路を扱う電磁気学。スピーカーもマイクも電気と磁石を使って音を制御します。 数 値 : 数値データを扱う情報工学。コンピュータの扱う音は単なる数値データです。 肉 体 : 人体を理解する生理学。知覚を理解する音響心理学や脳科学。 どれもそれだけで分厚い本になる内容で、筆者がかつて戸惑ったのもこういった箇所です。 ソフトウェアのマニュアルは操作方法を説明してくれますが、その土台となる知識まではカバーしていません。 本書では、これらをわかりやすい言葉でコンパクトにまとめ、楽曲制作の流れに沿ったチュートリアルの中で説明します。 ソフトウェアを使ったちょっとした実験もします。 音の世界は「百聞は一見にしかず」ではなく、「百見は一聴にしかず」だからです。 前半は当たり前だと思っていることに潜んでいる、音の謎を掘り下げて確認します。 後半はそれらの断片を繋げて、音楽の世界を歩くための地図を描きます。 マニュアルやインターネット上の膨大な情報にアクセスできる、そういう地図です。 地図があれば、音楽の世界を自由に探検できます。 VOCALOID3 EditorとLogic Pro Xという白紙のノートに、あなたの音楽が描かれますように。 田廻 弘志
-
3.0
-
4.0「次回繰越金について検討します」「A社のように余剰在庫を置きません」こんな文章を書いていないだろうか。これらは誤解を生んでしまう、あいまい文・欠陥文だ。「次回繰越金について検討します」では、検討するのが次回なのか、次回への繰越金について検討するのか、わからない。さらに言えば、「検討」では具体的に何をするのかわからないから準備のしようがない。「A社のように余剰在庫を置きません」では、A社も置いていないから自社も置かないのか、A社は置いているけれども自社は置かないのか、判断がつかない。こんな不注意な文章がトラブルのもとになりかねない。本書では、正しい情報を相手にわかりやすく伝える方法を、多数の事例を用いて解説する。誤解をなくし、わかりやすく、説得力のある文章を書くことは、ビジネスでは必須のスキルだ。さらに、ビジネス文章に関わってくる法律、クレーム対応や危機管理までを解説する。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 はじめてJavaのオブジェクト指向を学ぶ人のために基本から丁寧に解説した独習書です。著者がオブジェクト指向の理解に苦しむたくさんの学生の悩みや傾向を分析し、入門者にとってわかりやすい内容で解説。姉妹書の「わかりやすいJava入門編」を読み終えた人を対象に、自分のペースで本を読み、通過テストで理解度を確認して着実にステップアップさせてゆける独学・自習に最適な一冊です。Androidやウェブ開発などの実用上、例外やクラスライブラリ、マルチスレッドは必須の分野です。これらも、オブジェクト指向の十分な理解によって、グッとわかりやすくなります。本書のあとに「わかりやすいJava オブジェクト指向編」を読むことで、さらに深く理解することができます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 江戸時代より親しまれてきた中国随筆98種を全20冊に集大成。これら随筆中には傳本が稀で、容斎随筆・困学記聞・唐國史補・日知録のように明治・大正以来えがたかったものも多く、また五雑組・開元天寶遺事・鶴林玉露・荊楚歳時記など国史・国語国文学の分野にも有用な図書も少なくない。
-
3.0古代から現代に至るまで、大衆もまた作者だった。地震、火事、疫病など様々な集団的経験を経て、恐怖や悲しみを乗り越えるために、人々が創り出したものは何だったのか。 災厄と救いの想像力をヒントに、民衆の心性に迫る。『日本大衆文化史』に続く、大衆文化研究プロジェクトの第2弾! 【執筆参加者】 小松和彦、香川雅信、高橋 敏、福原敏男、高岡弘幸、齊藤 純、横山泰子、香西豊子、川村清志、伊藤慎吾 【内容】 序 疫病と天災をめぐる大衆文化論の試み(小松和彦) 第一章 疫病と怪異・妖怪──幕末江戸を中心に 第二章 疫病を遊ぶ――疱瘡神祭りと玩具 第三章 鯰絵と江戸の大衆文化 第四章 幕末コレラの恐怖と妄想 第五章 風の神送ろッ――説話を紡ぎ出すもう一つの世界 第六章 大蛇と法螺貝と天変地異 第七章 岡本綺堂と疫病――病歴と作品 第八章 近代、サイの目、疫病経験――明治期の衛生双六にみる日常と伝染病 第九章 変貌する災害モニュメント――災害をめぐる記憶の動態 研究ノート 火事・戯文・人名――『仮名手本忠臣蔵』のパロディをめぐって
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 和食って?「から揚げって和食?」「豚のしょうが焼きは?」「ビフテキ?」なかなか微妙なところかもしれません。和食って何かな?と考えているうちに私は、作った人、食べる人が、和食と思えば和食、だと思うようになりました。おしょうゆ味だったり、ごはんと食べたいおかずだったり、どこかにその人にとっての“和食のツボ”があるのでしょう。 「米をいただく」「うまみを味わう」「発酵調味料で調味する」、そして「季節感」。私の場合は、これが和食の4大要素。 この本では、これらの要素を入れながら、普通にどこにでもある食材で、難しくなく作りやすく、バランスもいい「和食の献立」を考えてみました。甘酒に漬けて仕込むから揚げや、梅風味のしょうが焼きも登場します。献立にしたのは、毎日のごはんにそのまま取り入れてほしいから、そして献立には、和食のおもしろさがあると思うからです。 【内容】 ・和食は献立で考えると作りやすい。 ・「だし」ってなに? ・基本調味料の賢い選び方 ・和食のルール 〈1〉20分スピード献立(6点) 肉そぼろごはん献立/鶏しょうが照り焼き献立/あじのぱりっと焼き献立/豚肉巻き巻き2種献立 ほか 〈2〉失敗しない定番献立(8点) 肉じゃが献立/しょうが焼き献立/鶏のから揚げ献立/揚げだし豆腐献立/豚汁献立 ほか 〈3〉簡単ごちそう献立(10点) 筑前煮献立/白菜ロール献立/若竹煮献立/煮豚献立/和風ビーフシチュー献立 ほか 体を整える献立 うどん献立/カレーライス献立 副菜カタログ ぱぱっと作れるあえもの/あると助かる作りおきおかず/簡単すぎる箸休め 【著者紹介】山脇りこ(やまわきりこ) 料理家。東京・代官山の料理教室「リコズキッチン」主宰、平成27年農林水産省「和食の保護・継承に向けた検討会」委員。長崎市の旅館に生まれ、季節の料理やしつらい、美しい花々や器に囲まれて育つ。今日のライフスタイルに合った新しい家庭料理を探求し続けている。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 麗澤大学(千葉県柏市)に学ぶ学生たちは、東日本大震災を経験して、ひとつの決意をした。被災者から話を聞き、学生ボランティアの活動をまとめ、自らの思いを述べ、そして記録に残すことを。これらの記録は、明日を見つめるための記録です。
-
3.9全世界話題! Googleの人事トップが採用、育成、評価のすべてを初めて語った。創造性を生み出す、新しい「働き方」の原理を全公開! Googleはいったいどんな仕組みで動いているのか? 誰もが抱くこの疑問に、Googleの人事トップが答えます。21世紀の最強企業をかたちづくる、採用、育成、評価の仕組みをすべて惜しげもなく公開。本書で紹介される哲学と仕組みは、Googleだからできるというものではなく、あらゆる組織に応用できる普遍性を持っています。 古いやり方で結果を出せと言われて困っているリーダー、古いやり方で評価されてやる気をそがれている若手、もっとクリエイティブに仕事をしたいと思っている人に知ってほしい、未来の働き方とは。いま働いているすべての人、これから働くすべての人に贈る、新しい働き方のバイブルとなる一冊。 著者は2006年にGoogleに入社。あらゆる企業の人の扱い方に影響を与えたいという信念の下、Googleに入ることを選択。同社の従業員が6000人から6万人に増えていく過程で、Googleの人事システムを設計・進化させてきた責任者です。Googleは、世界各国で「最高の職場」として認められ、多くの賞を受賞。 いったい、Googleは、どんなやり方で人を選んでいるのか? そうして選んだ人材に、どんな機会を与えているのか? 優秀な社員同士に最高のチームをつくってもらう秘訣とは? 社員をどう評価して、モチベーションを最大に保っているのか? 働き方をめぐるこれらの重大テーマに、次々と答えを出していきます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 WordとExcelの基本操作から、よく使う機能までを幅広く網羅し、WordとExcelの連携技やインターネットを利用したファイル共有方法まで幅広くカバーした機能ガイドです。本書では、実用的な機能を中心に取り上げ、WordではPOPやリーフレット作りに欠かせない写真やイラストの加工から、アウトラインやナビゲーションを使った文書校正機能を、Excelでは、よく使われる関数、新機能のスパークラインやスライサーについて解説。機能名からでは調べにくい機能も、完成例を挙げ、これらの紙面や画面を索引代わりとすることで、解説箇所の章節を引くことができるようになっています。サンプルファイルのダウンロードサービス付き。
-
4.0そのオペレーションは自動化できる! VMware vSphereはハイパーバイザ(仮想化基盤)と仮想マシンを管理するための多彩な機能を備えています。これらはGUIによる操作も可能ですが、vSphereはユーザーに対して多数のプログラマブルインターフェイスも提供しています。コマンドライン操作を実現するvCLI、スクリプティングインターフェイスとなるPower CLI、ワークフローによる操作の定義が可能なvCenter Orchestratorなど、これらを使うことで仮想化基盤の管理業務は高いレベルの自動化が可能になるでしょう。 本書は、今までVMwareに習熟したエンジニアには知られていた外部操作インターフェイスの概略を紹介し、その使いこなし術を紹介します。実用例付きの具体的な操作解説を行うほか、新しいvSphereの自動化機能の動向についても紹介します。仮想化システムの管理がインフラ技術の核になりつつある現在、賢い/効率の良い運用を実現するためのさまざまなノウハウを紹介します。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。 【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。