無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
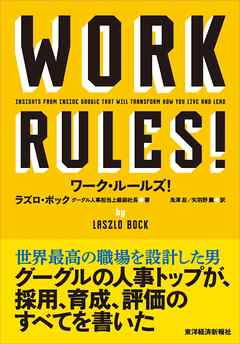
全世界話題! Googleの人事トップが採用、育成、評価のすべてを初めて語った。創造性を生み出す、新しい「働き方」の原理を全公開!
Googleはいったいどんな仕組みで動いているのか? 誰もが抱くこの疑問に、Googleの人事トップが答えます。21世紀の最強企業をかたちづくる、採用、育成、評価の仕組みをすべて惜しげもなく公開。本書で紹介される哲学と仕組みは、Googleだからできるというものではなく、あらゆる組織に応用できる普遍性を持っています。
古いやり方で結果を出せと言われて困っているリーダー、古いやり方で評価されてやる気をそがれている若手、もっとクリエイティブに仕事をしたいと思っている人に知ってほしい、未来の働き方とは。いま働いているすべての人、これから働くすべての人に贈る、新しい働き方のバイブルとなる一冊。
著者は2006年にGoogleに入社。あらゆる企業の人の扱い方に影響を与えたいという信念の下、Googleに入ることを選択。同社の従業員が6000人から6万人に増えていく過程で、Googleの人事システムを設計・進化させてきた責任者です。Googleは、世界各国で「最高の職場」として認められ、多くの賞を受賞。
いったい、Googleは、どんなやり方で人を選んでいるのか? そうして選んだ人材に、どんな機会を与えているのか? 優秀な社員同士に最高のチームをつくってもらう秘訣とは? 社員をどう評価して、モチベーションを最大に保っているのか? 働き方をめぐるこれらの重大テーマに、次々と答えを出していきます。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。