言語・プログラミング作品一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 プログラミング言語は比較して学ぶとよくわかる! 本書の最大の特徴は、PythonとJavaScriptを比較しながらまとめて解説している点です。 プログラミング言語系書籍のほとんどは、基本的に1つの言語に関してのみの解説が書かれています。 ですが、筆者が多くの素晴らしいプログラマーを近くで見てきた経験から言うと、彼ら・彼女らに共通して言えるのは、決して1つのプログラミング言語だけを知っているわけではない、ということです。複数の言語を非常によく理解していて、この言語ならこのように表現する、あの言語ならあのように表現する、ということを知っています。言ってしまえば、イケてるプログラマーは1つの問題を多角的に考えることができるのです。 比較しながら学ぶことによって、1つの事象に関してPythonとJavaScriptでどのように考え方が異なるのか(あるいは同じなのか)を知ることができます。色々な考え方を知ることで、一歩成長したプログラマーになることができるのです。 PythonとJavaScriptは比較的よく似ていながら、まったく異なる面も持ち合わせており、比較して学ぶのにちょうど良いのです。 ぜひ、このPythonとJavaScriptを通じて、プログラミングの奥深く、楽しい世界を体験してもらえたらと思っています。
-
3.51巻3,740円 (税込)開発に関わる全工程の詳細を定量化し より強く、より高パフォーマンスなチームへ 【本書の内容】 本書は Christopher W.H.Davis, "Agile Metrics in Action", Manning Publications 2015 の邦訳版です。 アジャイル開発は、その特性である「反復」によって、経験に基づく継続的な改善に最適な開発手法です。 この手法に、追跡システム、テストおよびビルドツール、ソース管理、継続的統合、およびプロジェクト ライフサイクルといったさまざまなコンセプトとツールを援用することで、製品やプロセス、 さらにはチームそのもののパフォーマンス改善できる豊富なデータを入手できます。 本書は、そういった実際に生成されるデータを計測し、結果を的確に分析し、効果的な対処法を指南してくれます。 パフォーマンスや進捗度合いなどを定量化することで、経験値による知見だけではなく、 より合意しやすいチームへと組織や方法論を改善してくれることでしょう。 【読者が得られること】 ・プロセスやタスクを定量化できるようになる ・定量化したデータから現状を正確に把握できるようになる ・コミュニケーション、生産性、透明性、士気を向上させる ・客観的にパフォーマンスを測定する 【著者について】 Christopher W. H. Davis(クリストファー・M・H・デイビス) ソフトウェアエンジニア。20年以上にわたり、旅行、金融、ヘルスケア、通信、製造業などの分野で開発チームのリーダーを務め、 世界中のさまざまな環境で多様なチームを率いてきました。 熱心なランナーでもあるクリスは、妻と2人の子供とともに、オレゴン州ポートランドの美しく雄大な太平洋岸北西部を満喫しています。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書はiPhoneアプリのUIを作るSwiftUIフレームワークの iOS 16とXcode 14に対応した最新の入門解説書です。 Xcodeの使い方や新機能から、SwiftUIコードの便利な入力補完機能、ツール、ナビゲーション、シート、タブ、レイアウト、マップ、非同期処理などをステップを追って段階的に説明します。 Swiftシンタックス(構文)についても、詳細に図解入りで解説しています。
-
-TinyGoとは、Go言語のコンパイラーでマイコンがターゲットです。 本書では、Wio Terminalというマイコンをターゲットにして、TInyGoを使った組込み開発のハンズオンを行っていきます。 サンプルコードで取り扱うGo言語の基本文法を説明しているので、Go言語に初挑戦でも理解しながら読み進められます。 マイコンに搭載されたネットワーク機能を使って通信をしたり、ディスプレイに描画をしたり、実践的な組込み開発に挑戦してみましょう。
-
-AppGyver(アプガイバー)とはAppGyver社が提供する「Composer Pro」というノーコードのプログラミングツールです。画面上の設定だけでアプリやサービスを作ることができます。プログラミングをしなくてもいいので、かなり短い期間でアプリ開発をすることができるのも特徴のひとつです。現状ドキュメントがすべて英語ですが、本書ではわかりやすく使い方を紹介しています。Todoアプリの作り方をテーマに、詳しく使い方をまとめています。 AppGyverは試用期間もなくずっと無料で使えるツールです。プログラミングをせずにアプリ開発したい人はもちろん、開発にできるだけお金と時間をかけたくない人にとってもぴったりな1冊です。
-
-これまでのVRのソフトウェア開発では、プラットフォームおよびデバイスに依存したソフトウェア開発キットを用いてきましたが、2019年にKhronos(クロノス)コンソーシアムによりロイヤリティフリーのXR用API「OpenXR」がリリースされました。これを使用することにより、ソフトウェアの移植性が向上し、さまざまなプラットフォームおよびデバイスに対応したコンテンツを提供できるようになります。多くの主要企業がOpenXRのサポートを表明しており、これを標準化する動きが進んでいます。 本書は、Unity+OpenXR+XR Interaction ToolkitによるVRプログラミングに必要な各種命令の詳細解説およびC#サンプルスクリプトからなる解説書です。次の3項目に該当する方を対象とし、その方々のVRプログラミングの学習支援を目的としています。 ・VRプログラミングを学び、自作のVRアプリケーションを開発したい方 ・Unityの入門書を読み終えた初学者の方 ・C#言語の基本的文法(データ型、ifなどの基本制御構造、クラスの定義と利用など)を理解している方 本書の主な特色を次に示します。 (1)命令文の汎用的な書式と使用例の提示: (2)自作アプリに転用しやすいサンプルスクリプト: (3)各機能の理解を深める工夫: 本書は次の環境下におけるVRプログラミングについて解説されています。また、本書のサンプルスクリプトは、この環境下で動作が確認されています。 ・Unity 2021.3.8f1 Personal ・OpenXR Plugin ver. 1.4.2 ・XR Interaction Toolkit ver. 2.0.2(その他のパッケージについては本書第1章参照) ・OS: Windows 10 Home 21H2 ・ヘッドセット: Meta Quest2、Windows Mixed Reality(Acer AH101)
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■□■全編マンガだからトコトンわかりやすい!■□■ ゲームを作ってみたい、ゲームクリエイターの仕事に興味がある、 そんな人が最初に手にとる一冊として、 「楽しみながらUnityを使ったゲーム作りが学べる」全編マンガの解説書が登場しました。 Unityに詳しいヒトミおねえさんと主人公の天野リエのやり取りで 横スクロールのシューティングゲームを作りながら、ストーリーが進んでいきます。 プロジェクトの作成、画像の配置、スクリプト、プレハブ化、アタリ判定、背景やスコア表示など、 基本的なゲーム作りのイロハが学べます。 ■■本書はこんな人におすすめ ・ゲームを作ってみたい人、ゲームクリエイターになりたいと思っている人 ・ゲーム作りをはじめたが、思うように進まない人 ・Unityの基本的な使い方を学びたい人 ■■本書の内容 1章 シューティングゲームを作ろう 2章 障害物と敵キャラを作ろう 3章 弾とボスを作ろう 4章 ゲーム進行の仕組みを作ろう 5章 ゲームをブラッシュアップしよう 付録 Unityのインストール
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 図解イラストで楽しくわかる、アルゴリズムのしくみと、主要言語での書き方 アルゴリズムと、それを主要言語でどのように書けばよいのかを、図解とイラストを豊富に使って説明した入門書。 本書の特長は、 1. 「アルゴリズムの意味」をイラストや図でやさしく解説 2. そのアルゴリズムに関する「プログラミング言語」のサンプルを試し、体験して納得 の2点です。 「アルゴリズム」と聞くと難しそうに思えますが、ズバリ『問題を解決するための考え方』です。「このアルゴリズムは、どんな考え方で問題を解こうとしているのか?」「この手順は、何をしようとしているのか?」など、「アルゴリズムの意味」に注目して考えていくと、だんだんとアルゴリズムがわかってきます。本書ではイラストや図を使って、入門者でもアルゴリズムのイメージがつかめるよう、解説していきます。 そして、「意味が理解できただけ」では使えるようになりませんので、実際にプログラミング言語によるサンプルプログラムを用意しました。「理解した意味の通りにアルゴリズムが動くこと」を試して、実感してください。 この「第2版」では、「迷路自動生成アルゴリズム」「迷路探索アルゴリズム」を追加して解説。 「アルゴリズム」をちゃんと把握したい人、プログラムの組み立て方をもっと知りたい人に役立つ1冊です。 【サンプル掲載言語】 Python、JavaScript、PHP、C、C#、Java、Swift、VBA 【本書で紹介しているアルゴリズム】 ・簡単なアルゴリズム 合計値、平均値、最大値、最小値、データの交換 ・サーチアルゴリズム リニアサーチ(線形探索法)、バイナリサーチ(二分探索法) ・ソートアルゴリズム バブルソート(単純交換法)、選択ソート(単純選択法)、挿入ソート(単純挿入法)、シェルソート、クイックソート ・迷路自動生成アルゴリズム 棒倒し法、穴掘り法 ・迷路探索アルゴリズム 右手法・左手法、幅優先探索法 アルゴリズムと、それを主要言語でどのように書けばよいのかを、図解とイラストを豊富に使って説明した入門書。 本書の特長は、 1. 「アルゴリズムの意味」をイラストや図でやさしく解説 2. そのアルゴリズムに関する「プログラミング言語」のサンプルを試し、体験して納得 の2点です。 「アルゴリズム」と聞くと難しそうに思えますが、ズバリ『問題を解決するための考え方』です。「このアルゴリズムは、どんな考え方で問題を解こうとしているのか?」「この手順は、何をしようとしているのか?」など、「アルゴリズムの意味」に注目して考えていくと、だんだんとアルゴリズムがわかってきます。本書ではイラストや図を使って、入門者でもアルゴリズムのイメージがつかめるよう、解説していきます。 そして、「意味が理解できただけ」では使えるようになりませんので、実際にプログラミング言語によるサンプルプログラムを用意しました。「理解した意味の通りにアルゴリズムが動くこと」を試して、実感してください。 この「第2版」では、「迷路自動生成アルゴリズム」「迷路探索アルゴリズム」を追加して解説。 「アルゴリズム」をちゃんと把握したい人、プログラムの組み立て方をもっと知りたい人に役立つ1冊です。 【サンプル掲載言語】 Python、JavaScript、PHP、C、C#、Java、Swift、VBA 【本書で紹介しているアルゴリズム】 ・簡単なアルゴリズム 合計値、平均値、最大値、最小値、データの交換 ・サーチアルゴリズム リニアサーチ(線形探索法)、バイナリサーチ(二分探索法) ・ソートアルゴリズム バブルソート(単純交換法)、選択ソート(単純選択法)、挿入ソート(単純挿入法)、シェルソート、クイックソート ・迷路自動生成アルゴリズム 棒倒し法、穴掘り法 ・迷路探索アルゴリズム 右手法・左手法、幅優先探索法 第1章 アルゴリズムってなに? 第2章 いろいろなプログラミング言語 第3章 データ構造とアルゴリズムの基本 第4章 簡単なアルゴリズム 第5章 サーチアルゴリズム 第6章 ソートアルゴリズム 付録 ●森 巧尚(もり よしなお) パソコンが登場した『マイコンBASICマガジン』(電波新聞社)の時代からゲームを作り続けて、現在はコンテンツ制作や執筆活動を行い、関西学院大学、関西学院高等部、成安造形大学、大阪芸術大学で非常勤講師、プログラミングスクールコプリの講師などを行っている。 著書に『ゲーム作りで楽しく学ぶ Pythonのきほん』『楽しく学ぶ Unity2D超入門講座』『楽しく学ぶ Unity3D超入門講座』『作って学ぶ iPhoneアプリの教科書~人工知能アプリを作ってみよう!~』(以上、マイナビ出版)、『Python1年生 第2版』『Python2年生 スクレイピングのしくみ』『Python2年生 データ分析のしくみ』『Python3年生 機械学習のしくみ』『Python自動化簡単レシピ』『Java1年生』『動かして学ぶ!Vue.js開発入門』(以上、翔泳社)、『そろそろ常識? マンガでわかる「正規表現」』(シーアンドアール研究所)、『なるほど! プログラミング 動かしながら学ぶ、コンピュータの仕組みとプログラミングの基本』(SBクリエイティブ)などがある。 ●まつむら まきお マンガ家・イラストレーター マンガ作品『ルナパーク』(青心社)、『いろいろあるのよ』(朝日新聞社)、『ビスキィの冒険』など。 『おしえて!! FLASH』など、パソコン関係の書籍イラスト、記事を多く手がける。 成安造形大学イラストレーション領域教授。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 国家試験の出題内容に対応した定番教科書 放射線技術学シリーズの改訂3版! 「放射線生物学」の改訂2版は2011年11月に発行し、好評を博してきましたが、この間、ICRP勧告をはじめ、さまざまな基準が改正、変更されたため、全体を通して内容を見直しました。 教科書としての基本的な枠組みは改訂2版を踏襲しつつも、最新の知見に基づいて内容を構成しています。また、改訂2版よりもさらに内容を充実させ、最近の国家試験の傾向も踏まえた、今まで以上に使いやすい教科書としてまとめてあります。 第1章 放射線生物学の基礎 第2章 放射線生物作用の初期過程 第3章 放射線生物学で用いる単位と用語 第4章 放射線による細胞死とがん治療 第5章 突然変異と染色体異常 第6章 放射線の組織影響 第7章 個体レベルでの放射線の影響 第8章 放射線による発がんと遺伝的影響 第9章 放射線障害の防護 第10章 環境と放射線 付 録 放射線生物学基本用語集 演習問題解答 参考文献 索 引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 国家試験の出題内容に対応した定番教科書 放射線技術学シリーズの改訂3版 「MR撮像技術学」の初版は2001年12月に、改訂2版は2008年2月に発行し、改訂2版発行から9年以上が経過しているので、全体を通して見直しています。 教科書としての基本的な枠組みは改訂2版を踏襲し、改訂2版の中で不足している箇所を補完し、最近の国家試験の傾向を踏まえて、今まで以上に使いやすい教科書となっています。また、臨床現場で活躍する技師の方々からも好評を得ているので、卒業後も役に立つ部分を教科書という枠組みを超えない程度でまとめてあります。 第1章 MR撮像技術の原理 第2章 MR装置の構成 第3章 MRの物理と数学の基礎知識 第4章 MRI用造影剤 第5章 アーチファクト 第6章 評価法 第7章 安全性と管理 第8章 各種MR検査法 8.1 頭部領域 8.2 脊椎・脊髄領域 8.3 胸部・心臓領域 8.4 上腹部領域 8.5 泌尿・生殖器領域 8.6 四肢・関節領域:肩関節,股関節,膝関節,四肢筋肉 8.7 大血管領域 演習問題解説・解答 参考文献 参考資料 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Rustは、CやC++に代わる言語として開発され、Web開発にも幅広く利用されているユニークな言語です。本書は、Web開発経験がある方を対象に、Rustの基礎文法から、Webアプリケーション開発までチュートリアル形式で体験学習できる入門書です。解説するサンプルは、Web開発者ならよく知っているお馴染みの教材なので、より理解が深まります。サンプルコードはGitHubからダウンロードできます。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日常生活の中にだって、知っておくべきアルゴリズムはたくさんある 「あなたの100歳の誕生日は何曜日?」 「どうしてエレベータが通過しちゃうの?」 「お釣りの硬貨の枚数を最小にするには?」 本書では、このような“身近な疑問”を解く、有名なアルゴリズムを解説します。 1~9章では、日常生活の中にある“身近な疑問”を問題として取り上げ、それらの問題を解くためのアルゴリズムをわかりやすく説明しています。 コイン問題を解く「動的計画法」、最短経路を求める「ダイクストラ法」や「ベルマン=フォード法」、クラスタリングを行う「k-means法」など、知っておくべき“必修アルゴリズム”を学べます。 プログラミング言語はPythonを使います。 補章では、Pythonを学び始めたばかりの人でも1~9章の内容を理解できるように、基本的な構文や組み込み関数、標準モジュールなどを説明しています。 これからアルゴリズムを学ぶ人、 有名なアルゴリズムの理解を深めたい人、 いろいろなアルゴリズムを知りたい人に、おすすめです。
-
-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13112-8)も合わせてご覧ください。 特集1 [高速|安全|高生産性] Rust入門 言語の強みをWeb開発に活かす Rustは,パフォーマンス,信頼性,生産性に重きを置いたプログラミング言語です。習得が難しいという印象を持たれがちですが,フレームワークやツールの充実とともに,Webアプリケーションの開発もしやすくなっています。本特集でRust習得の一歩を踏み出してみませんか? 特集2 保守性・拡張性に優れた関数型言語 はじめてのElixir 本特集では,パターンマッチをサポートする関数型言語Elixirを取り上げます。第1章~第5章でElixirの基礎的な部分を網羅的に解説し,最終章では前章までの知識を活用して実践可能なプロジェクトの作成を行います。Elixirの魅力は,保守性や拡張性に優れた開発が可能であることです。本特集を読むことで,それらを実感してください。 特集3 実装して学ぶHTTP/3 通信の高速化をいかに実現しているか 2022年6月6日,HTTP/3が正式勧告になりました。HTTP/2に存在した数々の問題点が改善されています。なかでも通信の高速化は,Web開発者にもユーザーにも大きなメリットをもたらす重要なポイントです。本特集ではHTTP/3サーバを実装することで,HTTP/3がどのようなしくみで動作しているかを学びます。どういった情報がやり取りされているのか,どういう工夫により高速化を実現しているのか,HTTP/2から進化した点をしっかりと理解できるはずです。
-
4.4※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13037-4)も合わせてご覧ください。 開発が大規模化・長期化するほど,コードを「読む」コストは増大していきます。そのため「読みやすさ」の向上は,生産性を改善し,プロダクトの成長限界を引き上げる重要な手段と言えるでしょう。 本書は,読みやすさの本質を学び,実践するための考え方をマスターできる一冊です。体系的な理解を実現するため,あらゆる角度から,豊富な例を交えて解説しています。表面的なテクニックではなく,いま目の前にあるコードに最適な改良方法を選び取る力が身に付きます。
-
-読者の声に応えて第2版の登場! データ分析エンジニアに必要な 基本技術をしっかり習得できる 【本書の概要】 本書はデータ分析エンジニアに必要な 以下の基礎技術を丁寧に解説しています。 ・データの取得・加工 ・データの可視化 ・プログラミング ・基礎的な数学の知識 ・機械学習の流れや実行方法 【第2版のポイント】 ・Python 3.10対応 ・よりわかりやすい解説 ・Pythonデータ分析試験の主教材に指定 【本書で学べること】 ・Pythonの基本的な文法 ・データフォーマットについて ・データの前処理技術 ・データの可視化技術 ・既存アルゴリズムでの機械学習の実装方法 【対象読者】 データ分析エンジニアを目指す方 【目次】 第1章 データ分析エンジニアの役割 第2章 Pythonと環境 第3章 数学の基礎 第4章 ライブラリによる分析の実践 第5章 応用:データ収集と加工 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13067-1)も合わせてご覧ください。 本書はUnityでゲーム開発を行いたい人を対象に,1つのゲームを制作する流れを通してUnity 2022の操作が学べる入門解説本です。本書内で武器などを調達し,食べ物を求めながら冒険し,武器でモンスターと戦う3Dアクションゲームを制作していきます。本格的なゲームを実際に制作しながらUnityの使い方を学べますので,楽しみながら学びことができ,かつ実践的なテクニックも身につけることができます。
-
-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13063-3)も合わせてご覧ください。 ロングセラーシリーズ・ポケットリファレンスのRuby on Railsが10年ぶりの改訂。 「逆引き形式で目的からすぐ探せる」 「サンプルコードを見ながら具体的な実装のイメージがつかめる」 という特徴で,困ったときにすぐに役立ちます。 Railsの基本からデプロイまでフォローする充実した内容はそのままに,Action Mailbox/Action Text/Action Cable/Active Storage/Active Jobなど重要コンポーネントを新規書き下ろしで大幅に増強。累計100万部以上の技術書を送り出してきた山田祥寛氏の監修による,現場で役立つ信頼の1冊。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、フロントエンド向けアプリケーションフレームワークの選択に悩んでいる人向けの本です。ネットでもフレームワークの違いについての情報は入手できますが、フレームワーク未経験者にとって、「どれが自分に最適なのか?」は、なかなか解決できません。免許とりたてで運転経験の少ない人が、カタログとクチコミを見て、自分に最適な車を選ぶようなものです。かなり無理があります。最終的には、乗り比べてみないと自分にとっての違いはわかりません。 フレームワークも同じです。使ってみないと違いはよくわかりません。本書では、前提知識を身につけた後、同じ機能を持つ実装コードをフレームワークごとに比較します。未経験者でもコードレベルの比較ができるように、詳しくコメントを付けていますので、違いをしっかりと把握して、納得のいく選択ができます。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Scratchのコードに潜むエラー(バグ=不具合)を見つけて解決しながら、プログラミング力を高めよう! 本書では、よくある典型的なエラーをあらかじめ含むプログラムを示して、その原因を考え、エラーを修正することを通して、より深くプログラミングを学ぶことを目的としています。エラーが発生する原因は複数あり、その原因を学ぶことはプログラミングを学ぶ上でとても役に立ちます。 プログラムには「エラー」がつきものです。エラーの原因を考え、修正のための試行錯誤を繰り返すことになります。この過程で「よく考える」ことになります。そうやって鍛えられた思考力は、別のプログラムを作成する際にも転移し、応用されます。それがプログラミング的思考です。 そのためには、良質な問題による適切な試行錯誤の体験が重要です。既存の教科に良質な参考書や問題集が存在するように、プログラミングにも良質な試行錯誤を提供する書籍が存在するといい――それが本書の存在価値です。エラーを修正していく過程でプログラミング的思考を鍛え、組み合わせ、自分の考えにつなて、さらに改良を加えて、プログラミングの世界の楽しさを味わってください。 「解説(東北大学大学院情報科学研究科/東京学芸大学大学院教育学研究科教授 堀田龍也)」より
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■ 開発の仕事をWebアプリケーションで実体験! 「プログラマーが足りない!」との指摘をよく耳にします。プログラマーやソフトウェアエンジニアを目指している人も多いことでしょう。でも、ゼロから目指すとなると未経験ということに…。何から勉強すればいいか、迷うこともあるのではないでしょうか。 そこで、まずは本書でソフトウェアの開発を“経験”してみませんか? 本書では、たとえプログラミング経験がない人でも、プログラムを作って、サーバーに転送し、誰にでも使ってもらえるようにWeb上のサービスとして公開するところまでできるよう、必要な作業やプロセスを解説しました。プログラミング経験がまったくなくても、本書の解説に沿って作業を進めていけば自分のサービスとしてアプリケーションを公開するところまでひと通りの開発を自分の手で実現できます。 本書を通じて開発したWebアプリケーションは、面接でアピールできる自分の実績になります。面接の場ではぜひ胸を張って「こういうアプリケーションを独力で公開しました」と見てもらってください。 本書で取り上げた主なサービスやツールは、AWS(Amazon Web Services)、Django、Git、Herokuです。すべてクラウドで完結しているので、お手元の環境のOSやスペックに依存せず、Webを利用できる環境であれば誰でも同じように開発プロセスをトレースできます。
-
-Power Automate for desktopで 煩わしい業務を自動化しよう 【本書の概要】 Power Automate for desktopはマイクロソフト社が提供している注目のRPAソフトウェアです。 定型的なパソコン作業をプログラミングせずに自動化することができます。 本書は、Power Automate for desktopを一度は触れたことがある方や、 特定の作業を自動化したい方に向けて、 業務の自動化テクニックをTIPS形式でまとめた書籍です。 実務に即した数々の自動化手法や本格的な手法まで丁寧に解説しています。 【対象読者】 ・Power Automate for desktopを一度は触れたことのある方 ・業務を自動化するテクニックを手早く身に付けたい方 ・業務の自動化を始めたい非エンジニアの方 【本書の自動化処理の一例】 ・Webサイトにログインしてメニューを操作する ・Webページのテキストボックスに入力する ・メールを受信して内容を読み取る 【本書の主な特徴】 ・ニーズの高い自動化テクニックをピックアップ ・節末で関連項目を参照 ・自動化フローのサンプル付き 【目次】 Chapter1 Power Automate for desktopの基本を理解しよう Chapter2 デスクトップの自動操作テクニック8選 Chapter3 業務成果に直結する!Excel操作テクニック11選 Chapter4 超高速化!Webサイトを使った業務の時短テクニック7選 Chapter5 今日から使える!メールを操作する3つのテクニック Chapter6 制御フローを使いこなそう Chapter7 超実践的なテクニックを身に付ける Chapter8 ExcelとWebサイトを操作する本格的なフローに挑戦しよう Chapter9 実践的な業務自動化に使える2つのアイデア 【著者プロフィール】 株式会社完全自動化研究所 代表取締役社長 小佐井 宏之(こさい・ひろゆき) 福岡県出身。京都工芸繊維大学同大学院修士課程修了。 業務完全自動化の恩恵を多くの人に届け、無意味なPC作業から解放し 日本を元気にしたい。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 AWSは、さまざまなサービスを構築・運用するITインフラとして、幅広く使われています。「使いたいときにすぐにサーバーを作れる」「規模や構成の変更が容易」「データベースやストレージ、さらには機械学習などのさまざまなすぐに使えるサービスが提供されている」などの使い勝手の良さだけでなく、負荷分散や冗長性の担保、バックアップなどの安全対策も考慮されているため、保守・運用コストを抑えられるのも人気が高い理由です。 ただしAWSのインフラ構築は、機能が豊富で自由度が高い半面、はじめてAWSを利用する人にとっては、何もない場所に放り出されたようなものであり、何からはじめてよいかわからず、困惑する利用者も少なくありません。 本書は、こうしたAWSの初心者を支援する目的で執筆されました。最初にAWSシステムの概要を説明したあとに、実際にネットワークを構築しながら、AWSにおけるサーバーに相当する「EC2インスタンス」を起動し、最終的に、独自ドメインでWebサーバーを運用できるようにする方法を指南します。その過程で、AWS独特のネットワークの作法を解説します。 また第2版では、これまでの内容を改訂しただけでなく、VPCとAWSサービス、もしくは、オンプレミス環境などの別のネットワークを接続するといった事例を追加しました。具体的には、PrivateLinkを利用して、S3などのAWSサービスとVPCとを接続する方法や、VPNで拠点間を接続する方法など、VPCと他のネットワークとの接続を扱った章を設けました。今後、読者の皆さんがAWSの活用を広げる上で、必ず役立つ情報となるでしょう。
-
-最近のAI開発では、サーバー上でプログラムを直接実行するよりも、GCPのAI PlatformやAWSのSageMakerのような、クラウド上のPaaS(Platform as a Service)を使うことが多くなっています。その際には、GCPであればGCSやBigQuery、AWSであればS3などの、ストレージサービスと接続し、データパイプラインのループ内に機械学習モデルと学習プロセスを埋め込みます。 本書では、Google Cloud Platformでサーバーレスのディープラーニングを行い、GCSやBigQueryなどのストレージとデータパイプラインで接続する方法を紹介します。 また、バックエンド側の経験はあるもののAI開発の経験はない読者のために、TensorFlowの基礎と、AI Platform上での実行方法を紹介します。
-
-「Electron」はWebページをデスクトップアプリにビルドして実行できるようにする技術です。 「React」は世界的に人気のある「HTML5+JavaScript+CSS」のWebページを構築するためのフレームワークです。 本書では「React」を使ってWebページを作成し、「Electron」を使ってWebページをデスクトップアプリにビルドして実行できるように解説します。 紹介するサンプルは「ToDoリスト」「Web APIを使った画像検索ワード当てクイズ」「郵便番号CSV読み込みとハガキPDF書き出し」「データベースでToDoリスト」です。
-
4.6※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13149-4)も合わせてご覧ください。 ITシステムやソフトウェアの基盤OSとして幅広く使われているLinux。エンジニアとしてLinuxに関する知識はいまや必須とも言えますが,あなたはそのしくみや動作を具体的にイメージすることができるでしょうか。 本書では,Linux OS における,プロセス管理,プロセススケジューラ,メモリ管理,記憶階層,ファイルシステム,記憶階層,そして仮想化機能,コンテナなど,OS とハードウェアに関するしくみがどのように動くのか,実験とその結果を示す豊富なグラフや図解を用いてわかりやすく解説します。 改訂に際しては全面フルカラー化。グラフや図解がさらにわかりやすくなり,ソースコードはC言語から,Go言語とPythonにアップデートしています。さらに仮想化,コンテナなどの章が加わりました。今どきのLinuxのしくみを本書でしっかり理解しておきましょう。
-
-1巻1,760円 (税込)アジャイル時代に効果的な品質保証を進めるための23のパターン アジャイル開発において効率的かつ効果的に品質保証を進めるための 具体的で実践的な方法をまとめたパターン集 『Quality Assurance to Agile Quality』(QA to AQ、QA2AQ)。 「QA to AQ」では、ロードマップから日々のモニタリングに至る あらゆるアジャイル開発の段階において品質に取り組むコツを、 頻出の問題に対する実証済みの解決策として提示されています。 本書では「QA to AQ」に収録された各パターンを翻訳して紹介し、 さらに日本語版オリジナルとして、 日本のアジャイル開発における実践事例や、 複数のパターンを組み合わせて組織的に展開する方法を解説します。 ※本書は、ソフトウェア開発者向けメディア「CodeZine」に 掲載された連載を加筆・再編集した内容になります。 【本書収録のパターン】 品質のインテグレート/障壁の解体/QAを含むOneチーム 品質スプリント/プロダクト品質チャンピオン/アジャイル品質スペシャリスト 品質チェックリスト/品質作業の分散/品質エキスパートをシャドーイング QAリーダーとペアワーク/できるだけ自動化/重要な品質の発見 品質シナリオ/品質ストーリー/測定可能なシステム品質 品質の折り込み/着陸ゾーン/着陸ゾーンの再調整 着陸ゾーンの合意/品質ロードマップ/品質バックログ システム品質ダッシュボード/システム品質アンドン ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 R言語によるプログラミングを通じて統計や機械学習の手法を学ぶことができる解説書です。コードを記述して実践することで、プログラミングがはじめての人でも学びやすい内容となっています。
-
-pytestを正しく理解し、風通しの良いPythonプログラムを書く 本書は、 Brian Okken, "Python Testing with pytest, Second Edition: Simple, Rapid, Effective, and Scalable", The Pragmatic Bookshelf の翻訳書です。 【本書の内容】 Pythonを使った開発時に、テストの検出・実行・結果報告を自動で行うpytestの、導入から活用方法の詳細を、実務に沿うスタイルでを解説した『テスト駆動Python』(2018年)の第2版です。 扱う範囲は前版よりも広くなり、軽く触れるに留めていた箇所もより深い解説を加えており、Pythonを使った開発に欠かせない内容に仕上がっています。とくにCIやプラグイン開発など、テスト自動化エンジニア向けのトピックも増えつつ、パラメータ化やモック、デバッグ手法など、プログラマなら知っておくべき知識もてんこ盛りです。 アプリケーションをPythonで構築する際に、テスト駆動開発をストレスなく行いたいプログラマ・エンジニア、およびテスト設計やテストアーキテクチャを知りたい方にはうってつけの1冊です。 【著者について】 ・20年にわたるR&D経験を持つ主席ソフトウェアエンジニア。試験計測機器を開発している。また、Test&Codeポッドキャストを主催し、Python Bytesポッドキャストの共同開催者でもある。 目次 Part 1 pytestの主力機能 第01章 はじめてのpytest 第02章 テスト関数を書く 第03章 pytestのフィクスチャ 第04章 組み込みフィクスチャ 第05章 パラメータ化 第06章 マーカー Part 2 プロジェクトに取り組む 第07章 戦略 第08章 設定ファイル 第09章 カバレッジ 第10章 モック 第11章 toxと継続的インテグレーション 第12章 スクリプトとアプリケーションのテスト 第13章 テストの失敗をデバッグする Part 3 ブースターロケット 第14章 サードパーティプラグイン 第15章 プラグインの作成 第16章 高度なパラメータ化 付録A 仮想環境 付録B pip ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13110-4)も合わせてご覧ください。 本書は,Fluentdについて網羅的に解説した書籍です。 Fluentdは,ログやそのほかのデータの収集および集約,転送,変換,保存を実現するためのソフトウェアです。すでに多くのユーザーに利用されているほか,Kubernetes環境におけるデファクトスタンダードなログ収集方法として扱われています。そのため,AWS,GCPおよびAzureといったクラウド環境においても標準的なツールとして使われています。 本書は,Fluentdがデータをどのように処理しているかから,内部構造やプラグイン機構の詳細,プラグインの開発方法までを網羅的に記述しています。筆者はFluentdの初期からのユーザーであり,Fluentdの主開発者の一人でもあるため,ユーザーとして必要な事項を開発者の視点から解説できているはずです。
-
-定番の入門書シリーズに『C言語』が装い新たに登場! 本書は、「C言語」をこれから学ぶ初心者を対象に、 文法やプログラミングの基本知識をわかりやすく解説する入門書です。 これまで数多くの学生に対してプログラミングの授業をしてきた著者が、その経験を活かし、 基本的な文法から、学習の難所とされるアドレスとポインタの概念まで、 つまずきやすい内容を1つひとつ丁寧に解説します。 本書を読めば、C言語ならではの、 自由度が高く高速なプログラムを書くための、 知識の土台をしっかりと身につけることができます。 掲載するサンプルプログラムはシンプルなものを選び、 何をしているのかがよくわかるように、コメントをしっかりつけています。 また章の最後には練習問題があり、力試しや理解度の確認に活用できます。 ・何から学習すれば良いかわからない ・C言語をはじめて学ぶ、あらためて基本から学びたい ・開発現場で通用する基礎を身につけたい という方に手に取っていただきたい1冊です。 ■特別付録:学習用スライド教材について 本書を授業などで活用していただくことを前提に作成した、 学習用のスライド教材をダウンロード付録として提供しています。 詳細は本書の奥付をご覧ください。 ■著者プロフィール 三谷純(みたに・じゅん) 筑波大学システム情報系教授。コンピュータ・グラフィックスと折り紙に関する研究に従事。 1975年静岡県生まれ。2004年東京大学大学院博士課程修了、博士(工学)。 小学生のころからプログラミングに熱中。大学時代に本格的にプログラミングを学び、 Java、C/C++、PHP、JavaScriptなどによるプログラムを多数開発。 その後、CG分野における、さまざまな研究開発に取り組んできた。 (主な著書) 『Java 第3版 入門編 ゼロからはじめるプログラミング』 『Java 第3版 実践編 アプリケーション作りの基本』 『Python ゼロからはじめるプログラミング』(いずれも2021年・翔泳社) 『立体折り紙アート』(2015年・日本評論社) ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
3.5よりよく、より簡単に、より速く! アジャイル開発でもテストの品質を上げるためのヒント集 ◆◆◆◆◆ Web業界の小規模なスタートアップ企業から世界最大級の銀行組織まで、 さまざまな現場や状況で活用してきたアイデアを集めた 『Fifty Quick Ideas To Improve Your Tests』の邦訳がついに登場! ◆◆◆◆◆ アジャイル開発においても、よりよいソフトウェアを開発するためには、 さまざまなテストを組み込むことになります。 しかしそれは「短い反復」という厳しい時間的な制約のもと、 頻繁に変更されるソフトウェアに対するものとなり、一筋縄ではいかないのが現実です。 本書は、ソフトウェアテストを行う読者に向けて、 アジャイル開発において、ユーザーストーリーにもとづいたテスト計画を立て、 それを短い反復という開発プロセスに合わせた形で整理する方法を提供してくれます。 ・【「代わりに何が起こるか」と尋ねよう】 ・【厳格なカバレッジ目標を持たないようにしよう】 ・【テストコードは書くためではなく読むために最適化しよう】 など、本書で紹介される50のアイデアは、 テストの設計や実行において役に立つ珠玉のものばかり。 そしてさらに、日本語版独自コンテンツとして、 訳者によるCI/CD関連を中心とした5アイデアも追加! 本書を読めば、テスター・アナリスト・開発者など、 あなたのチームメンバーが緊密なコラボレーションを築き、 ステークホルダーを巻き込みながら、ソフトウェア品質を向上させる 多くのヒントが手に入るはずです! ◎目次◎ ◆テストのアイデアを生み出す ・【関係者と品質に関する全体像を定義しよう】 ・【「常にある/決してない」から考えよう】 など ◆適切なチェックの設計 ・【重要な具体例に焦点を当てよう】 ・【テストシナリオの期待値には数式ではなく具体的な値を記述しよう】 など ◆テスト容易性の向上 ・【CPU時間ではなく論理的なビジネス時間を導入しよう】 ・【テストからデータ生成処理を分離しよう】 など ◆大規模なテストスイートの管理 ・【自動テストを開発者の責任としよう】 ・【他のチームと一緒にテストを設計しよう】 など ◆日本語版追加アイデア ・CI/CD関連など ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 ソフトウェアの中で,最も重要かつ基本的なOSの基礎知識をわかりやすく整理. ソフトウェアの中で,最も重要かつ基本的なオペレーティングシステム(OS)の基礎知識をわかりやすく整理した教科書. 現在のカリキュラムやセメスタ制といった大学・高専の実情に対応してコンパクトな説明を心がける一方,現在広く使用されているUnix系OSとWindowsなどの具体例を取り上げ,初学者が無理なく理解できるようにしている.また,演習問題も充実させている. 第1章 OSの概要 1.1 なぜOSが必要か 1.2 OSの構成 1.3 OSの歴史 1.4 組込みシステムのOS 1.5 スーパーコンピュータのOS 演習問題 第2章 コンピュータのハードウェア 2.1 ハードウェアの概要 2.2 プロセッサ 2.3 メモリ 2.4 ハードウェアクロックとタイマ 2.5 入出力装置 2.6 ブートストラップ 演習問題 第3章 プロセス 3.1 プロセスとスレッド 3.2 スケジューリング 3.3 排他制御と同期 3.4 プロセス間通信 演習問題 第4章 メモリ管理 4.1 メモリ管理とは 4.2 物理記憶ベースのメモリ管理 4.3 仮想記憶 4.4 動的リンク 4.5 共有メモリの実現 演習問題 第5章 ファイルシステム 5.1 ファイルシステムとは 5.2 ファイル 5.3 ディレクトリ 5.4 ファイルの保護 5.5 ファイルシステムの実装方法 5.6 さまざまなファイルシステム 演習問題 第6章 入出力制御 6.1 入出力のしくみ 6.2 入出力完了の検出 6.3 割込みレベル 6.4 内部装置との関係 6.5 デバイスファイル 6.6 外部装置の一般化 6.7 ディスク装置 6.8 SSD 6.9 バッファキャッシュとページキャッシュ 演習問題 第7章 Unix系OS 7.1 Unix系OSの概要 7.2 Unix系OSの実装方法 演習問題 第8章 Windows 8.1 Windowsの概要 8.2 システムアーキテクチャ 8.3 カーネルモード 8.4 環境サブシステム 演習問題 第9章 コンピュータやOSの仮想化 9.1 仮想化技術とは 9.2 仮想化のアプローチ 9.3 コンテナ技術 演習問題
-
4.0★確率的プログラミング言語がすぐに使える!★ ・Pythonでのコーディングを前提に、PyMC3、Pyro、NumPyro、TFP、GPyTorchをカバー。 ・回帰モデルの基本から潜在変数モデル・深層学習モデルまでを幅広く解説。 【主な内容】 第1章 ベイジアンモデリングとは 1.1 データ解析とコンピュータ 1.2 ベイジアンモデリングの基礎 1.3 代表的な確率分布 1.4 近似推論手法 第2章 確率的プログラミング言語(PPL) 2.1 ベイジアンモデリングとPPL 2.2 自動微分・最適化アルゴリズム 2.3 PyMC3の概要 2.4 Pyroの概要 2.5 NumPyroの概要 2.6 TensorFlow Probabilityの概要 2.7 GPyTorchの概要 第3章 回帰モデル 3.1 線形回帰モデル:線形単回帰モデル 3.2 線形回帰モデル:線形重回帰モデル 3.3 一般化線形モデル:ポアソン回帰モデル 3.4 一般化線形モデル:ロジスティック回帰モデル 3.5 階層ベイズモデル 3.6 ガウス過程回帰モデル:ガウス尤度 3.7 ガウス過程回帰モデル:尤度の一般化 第4章 潜在変数モデル 4.1 混合ガウスモデル 4.2 行列分解モデル 4.3 状態空間モデル 4.4 隠れマルコフモデル 4.5 トピックモデル 4.6 ガウス過程潜在変数モデル 第5章 深層学習モデル 5.1 ニューラルネットワーク回帰モデル 5.2 変分自己符号化器 5.3 PixelCNN 5.4 深層ガウス過程 5.5 正規化流
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 人工知能・人工生命を創って理解できる 【本書の特徴】 ・人工知能・人工生命について,タスク解決のために自身でさまざまに試しながら理解できる. ・人工知能・人工生命について,物理シミュレーションを通して理解できる. ・Unity(C#)による学習環境を提供し,人工知能・人工生命の挙動を視覚的に理解できる. 本書は,人工知能と人工生命の基本技法を理解するための技術書です.人工知能・人工生命を学びたい,自分で創ってみたい学生やITエンジニアが,人工知能・人工生命を自分で創りながら試して理解できるようにまとめています. とくに,物理シミュレーションを通したタスクを実践的に解決することで ・強化学習 ・進化計算 ・ニューロ進化 ・群知能 ・メタヒューリスティックス といった人工知能・人工生命技術について理解することを目的としています. 本書では,さまざまなタスクを解説することで,多様なAI技法を学びます.まず,強化学習およびニューロ進化によるレーシングカーの自動運転を紹介します.入門として,パラメータ操作のみで基本的な学習の実験が可能な環境を提供します.人工知能における学習設計時の重要なポイントを習得できるでしょう. 人工知能・人工生命を創って理解するための学習環境はUnity(C#)で用意しています.各章では,理論の解説とともにデモンストレーションとなるサンプルプログラムを提供し,読者の理解を助けるようにしています. 第1章 人工知能から人工生命へ 第2章 自動運転の学習をしてみよう 第3章 自動運転学習のしくみ:強化学習とニューロ進化 第4章 ニューラルネットワーク 第5章 進化するプログラム 第6章 アリの知恵と巡回セールスマン 第7章 集団行動と群れの知能 第8章 人工生命から人工知能へ
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1」の対策テキストなら鉄板のこの1冊! 本書は、LPI-Japanが主催する「HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1 Ver2.5」(2022年2月改訂版)に合格するための知識を身につけるための書籍です。 ※「HTML5プロフェッショナル認定試験」は、HTML5やCSS3、JavaScriptなど、最新のマークアップに関する技術力と知識を認定するための資格試験です。デザイン、Web、開発に関わる幅広い職種を対象としています。試験名には「HTML5」が使われていますが、最新の標準仕様であるHTML Living Standardに基づいて作成されており、本書もそれに基づき執筆・制作されています。 本書は、LPI-Japanによって公開されている出題範囲をしっかりと押さえつつ、関連する知識も含めて、読みやすく、覚えやすい形でまとめています。 紙面では、「用語解説」や「注意するポイント」「補足説明」などを適切に切り分けて掲載し、重要な点がスムーズに学べるよう配慮しています。 また、各章の最後には問題集を用意しています。これにより、学習した内容の理解度を確認するとともに、しっかりと定着させていくことができます。 今回の改訂版では、新しい試験範囲と仕様の変更に沿って、HTML、CSSの解説を全面的に見直し、ブラッシュアップしています。 出題範囲の改訂にあわせて項目の追加や削除、内容の修正、順番の入れ替えなどを行い、より読みやすく、理解しやすい内容になっています。 Chapter1 HTML Chapter2 CSS Chapter3 レスポンシブWebデザイン Chapter4 API概要 Chapter5 Web関連の規格と技術 大藤 幹(おおふじ みき) 1級ウェブデザイン技能士。ウェブデザイン技能検定特別委員、若年者ものづくり競技大会ウェブデザイン職種競技委員。現在の主な業務は、コンピュータ・IT関連書籍の執筆のほか、全国各地での講演・セミナー講師など。 著書は『プロを目指す人のHTML&CSSの教科書』(マイナビ出版)、『今すぐ使えるかんたんEx HTML&CSS 逆引き事典』(技術評論社)、『詳解HTML&CSS&JavaScript辞典』(秀和システム)など60冊を超え、HTML5プロフェッショナル認定試験の公式サイトにおけるサンプル問題も多数提供している。 Chapter 1~2、Appendix担当。 鈴木 雅貴(すずき まさたか) NTTテクノクロス株式会社 主任エンジニア。 学生時代にインターネットの世界に出会い、表現場所としての可能性を感じるとともにこの世界に関わりたいと考え、1999年入社。2010年よりHTML関連の業務に従事し、Web技術を中心とした技術支援や技術者育成に力を注ぐ。アヒルが好き。 Chapter 3~5担当。
-
-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13073-2)も合わせてご覧ください。 人気のWebフロントエンドフレームワーク「Vue.js」がバージョンアップして「Vue 3」となり,TypeScriptの標準採用,新機能Composition API,Vite,Piniaの搭載など,大幅に機能が更新・強化されました。それに伴い,Vue 3では,従来のOptions APIを利用したコンポーネント開発とは異なる開発手法が必要となります。本書では,Composition APIによるコンポーネント開発やPiniaによる状態管理,Vue RouterによるSPA開発,非同期処理やユニットテストなどを新機能を駆使して解説しており,Vue 3によるフロントエンド開発手法が1冊ですべて身に付く内容になっています。
-
-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13059-6)も合わせてご覧ください。 自然言語処理分野におけるブレイクスルーとなったTransformerをコンピュータビジョンに応用したモデルがVision Transformer(ViT)です。さまざまなコンピュータビジョンのタスクにおいて,ディープラーニングではスタンダードとなっているRNN,CNN,および既存手法を用いた処理精度を上回ることが確認されています。 本書は注目のViTの入門書です。Transformerの成り立ちからはじめ,その理論と実装を解説していきます。今後のViTの活用が期待される応用タスク,ViTから派生したモデルを紹介したあと,TransoformerとViTを分析し,その謎を解明していきます。今後も普及が期待されるViTを盛りだくさんでお届けします。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 "競プロ" で必要なテクニックを1冊に凝縮! 競技プログラミング(競プロ)は、問題を解くことでプログラミング能力を競う大会です。本書では、競プロで必要なアルゴリズム・データ構造・考察テクニックを丁寧に解説します。さらに、知識を定着させるための例題・演習問題が150問以上掲載されています。 本書は、競プロのコンテストで勝ちたい、アルゴリズムを本格的に学びたい、技術力向上に繋げたいなど、様々な目的で利用できるものとなっています。 [本書の特徴] ・競プロで必要な77個のテクニックを網羅 ・320点超のフルカラーの図でわかりやすく解説 ・知識を身に付ける演習問題153問 ・全問題が「自動採点システム」に対応 ・新傾向の「ヒューリスティック・最適化」も解説 [本書の構成] 序章 競技プログラミング入門 第1章 アルゴリズムと計算量 第2章 累積和 第3章 二分探索 第4章 動的計画法 第5章 数学的問題 第6章 考察テクニック 第7章 ヒューリスティック 第8章 データ構造とクエリ処理 第9章 グラフアルゴリズム 第10章 総合問題 終章 さらに上達するには [本書で扱うトピック(抜粋)] 全探索/2進法/一次元の累積和/二次元の累積和/配列の二分探索/答えで二分探索/しゃくとり法/半分全列挙/部分和問題/ナップザック問題/ビットDP/最長増加部分列問題/素数判定法/ユークリッドの互除法/繰り返し二乗法/包除原理/ゲーム問題/偶奇を考える/一手先を考える/後ろから考える/山登り法/焼きなまし法/ビームサーチ/スタック/キュー/優先度付きキュー/連想配列/文字列のハッシュ/ダブリング/セグメント木/深さ優先探索/幅優先探索/ダイクストラ法/Union-Find/最小全域木問題/最大フロー問題/二部マッチング問題/ほか多数 序章 競技プログラミング入門 第1章 アルゴリズムと計算量 第2章 累積和 第3章 二分探索 第4章 動的計画法 第5章 数学的問題 第6章 考察テクニック 第7章 ヒューリスティック 第8章 データ構造とクエリ処理 第9章 グラフアルゴリズム 第10章 総合問題 終章 さらに上達するには 米田 優峻(よねだ まさたか): 2002年生まれ。2021年に筑波大学附属駒場高等学校を卒業し、現在東京大学に所属。競技プログラミングでは「E869120」として活躍。2020年までに国際情報オリンピック(IOI)で3度の金メダルを獲得したほか、世界最大級のオンラインコンテスト「AtCoder」でも最高ランクである赤色の称号を持っている。また、Qiitaで多数の記事を投稿したり、競技プログラミングの中上級者向け問題集「競プロ典型90 問」を作成するなど、アルゴリズムや競技プログラミングの普及活動も行っている。著書に『問題解決のための「アルゴリズム×数学」が基礎からしっかり身につく本』(技術評論社)がある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 HTMLってなんだろう?CSSってなんだろう?と思っているあなたでも、1週間でスマホ用Webページがちょっとだけ作れるようになる! Webページを作ってみようと思って、いろいろな本を読んで勉強してみたのだけれども、よく分からない…理解できない…。そんな方にオススメの1冊! 本書を読み進めながら、一緒にサンプルソースコードを入力してみることで、HTMLとCSSの基礎が分かるようになり、ちょっとだけWebページが作れるようになります。 本書後半では、少し高度なWebページ作成も解説しています! 途中で読むことを挫折しないよう、ゆるいペースでナビゲートします! ▼目次 1日目 はじめの一歩 2日目 HTMLの構造とさまざまなタグ 3日目 スタイルシート 4日目 ボックスモデル 5日目 Webページのレイアウトを作る 6日目 覚えておきたい知識・Webサイトを作る 7日目 Webアプリ・CMS・BootstrapによるWebサイト制作
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 記述したコードやプログラムが本番環境で正しく動くのかは、Webクリエイターやエンジニアの重大な関心事です。コンテナは、サーバーやネットワークを仮想的に構築するための入れ物のようなもので、Dockerはそのコンテナを手軽に作成できるツールです。本書は、コンテナや仮想化の基本的な仕組みを学びながら、Docker Desktopを使って各種サーバーを構築する方法を解説しています。Dockerは奥が深いツールですが、本書ではLinuxやWebサーバー、データベース、WordPressなどの設定ファイルを掲載して、それらの仮想サーバーをすぐに立ち上げられるような構成になっています。すべての操作手順をステップ・バイ・ステップで丁寧に解説しているので、挫折することなく読み進められます。そのため、これまで仮想化技術などにハードルを感じて敬遠していたWebクリエイターや駆け出しのエンジニアが最初に読む本として最適です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【Pythonプログラミングの“入門の入り口”になる教科書!】 本書はプログラミング経験がない方やPC操作に不慣れな方でも無理なく読み進められる、Pythonプログラミングを始めるための“入門の更にその入口”となる教科書。 プログラムを実際に動かしながら学んでいく構成のため、基礎がしっかりと身に付くだけでなく、米国で成功した著者直伝の実践的知識まで習得できる。応用力アップにつながる例題も豊富に掲載。本書掲載のプログラムはすべてウェブから入手できるので、講義や独習にも役立つ。 Python入門者に、最初に手に取ってほしい一冊。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 Pythonで音作りをはじめよう! ・音のプログラミングが音響楽の基本からわかる! ・音の信号処理もていねいに解説! ・打楽器・管楽器・弦楽器・鍵盤楽器の音が手もとで作れる! ・ソースコードはWebからダウンロード可能! 本書は、コンピュータで音作りをしてみたい方に向けた、サウンドプログラミングの入門書です。音作りに興味があるけど何からはじめたらという初心者のために音響の基本から解説をはじめ、コンピュータでの音の考え方、音を加工するディジタル信号処理の基礎をていねいに説明し、シンセサイザ、エフェクタの音作りなどを解説します。さらに、さまざまな音響合成のテクニックとともに、その具体例として、ゼロから楽器音をつくり出すフルスクラッチ合成のレシピを紹介します。サウンドプログラミングの言語には、音データの読み書きはもちろん、波形、周波数特性、そしてスペクトログラムの描画も簡単に行える、Pythonを採用しています。 Pythonを使ってサウンドプログラミングの第一歩を踏み出しましょう! はじめに 目次 第1章 音響学 1.1 純音 1.2 複合音 1.3 音の三要素 1.4 音の大きさ 1.5 音の高さ 1.6 音色 第2章 サウンドプログラミング 2.1 サンプリング 2.2 標本化 2.3 量子化 2.4 WAVEファイル 2.5 サウンドプログラミング 第3章 コンピュータミュージック 3.1 五線譜 3.2 音階 3.3 音符 3.4 強弱 3.5 拍子 3.6 テンポ 3.7 音楽の三要素 3.8 コンピュータミュージック 3.9 自動演奏 第4章 MIDI 4.1 MIDI 4.2 ノートオンとノートオフ 4.3 ノートナンバー 4.4 ベロシティ 4.5 プログラムチェンジ 4.6 プログラムナンバー 4.7 パーカッションマップ 4.8 MIDIファイル 4.9 DTM 4.10 自動演奏 第5章 ディジタル信号処理 5.1 周波数分析 5.2 スペクトログラム 5.3 楽器音の周波数分析 5.4 フィルタ 第6章 シンセサイザ 6.1 音響合成のアプローチ 6.2 アナログシンセサイザ 6.3 オシレータ 6.4 時間エンベロープ 6.5 加算合成 6.6 減算合成 6.7 FM合成 6.8 カープラス・ストロング合成 6.9 音のリアリティ 第7章 エフェクタ 7.1 リバーブ 7.2 ディストーション 7.3 コンプレッサ 7.4 イコライザ 7.5 モジュレーション 7.6 デチューン 第8章 ミキシング 8.1 モノラル再生とステレオ再生 8.2 音像定位 8.3 ミキシング 8.4 音楽制作 8.5 ボーカルキャンセラ 第9章 打楽器の音をつくる 9.1 グロッケンシュピール 9.2 トライアングル 9.3 チューブラーベル 9.4 マリンバ 9.5 シロフォン 9.6 ティンパニ 9.7 シンバル 9.8 銅鑼 9.9 ハイハットシンバル 9.10 バスドラム 9.11 タムドラム 9.12 スネアドラム 第10章 管楽器の音をつくる 10.1 フルート 10.2 ピッコロ 10.3 クラリネット 10.4 オーボエ 10.5 バスーン 10.6 サキソフォン 10.7 トランペット 10.8 トロンボーン 10.9 ホルン 10.10 チューバ 第11章 弦楽器の音をつくる 11.1 バイオリン 11.2 ビオラ 11.3 チェロ 11.4 コントラバス 11.5 ハープ 11.6 アコースティックギター 11.7 エレクトリックギター 11.8 エレクトリックベース 11.9 スラップベース 第12章 鍵盤楽器の音をつくる 12.1 パイプオルガン 12.2 リードオルガン 12.3 ハープシコード 12.4 アコースティックピアノ 12.5 エレクトリックピアノ 索引
-
-この一冊で 確かな力と幅広い知識を身につけよう 大好評『スラスラわかるJava』が4年ぶりの改訂! プログラミング言語をはじめて学ぶ人に向け、「なぜ」を解決できるように、 図解とサンプルを使用して解説する本シリーズ。 基本からオブジェクト指向、そして関数型プログラミングといった最新の仕様まで、 Javaの世界を広く深く、というポイントはそのままに Java 18に対応しつつ、解説内容をよりわかりやすいものにしました! 本書を読めば、Javaで書かれたプログラムを理解し、 自分でJavaプログラムを書くための基礎的な知識を身につけることができます。 プログラミングの第一歩としても、再入門のおともとしても最良です! ◆◆◆スラスラわかるポイント◆◆◆ 1.必要な知識だけを厳選 Javaの基礎的な文法と言語としての特徴を丁寧に解説しています。 いきなり膨大なライブラリなどの知識を含めることはせず、必要な知識のみを掲載しているので、 スラスラ読み進めることができます。 2.短く読みやすいコード 掲載しているコードはどれも短く、頭の中でイメージしやすい内容にしています。 実行結果もあわせて掲載しているので、自分でコードを入力できない場面でも、 スラスラ理解することができます。 3.テストで理解度をチェック 各節の終わりにはチェックのためのテストを掲載しています。 独学で勉強している人も手軽に理解度をチェックすることができます。 ◆◆◆目次◆◆◆ Ch.01 Javaプログラミングの基礎 Ch.02 値と演算 Ch.03 変数 Ch.04 文字 Ch.05 日付 Ch.06 コレクション Ch.07 制御構文 Ch.08 オブジェクト指向 Ch.09 クラスの基礎 Ch.10 クラスの応用 Ch.11 名前空間とアクセス制御 Ch.12 抽象クラスとインターフェイス Ch.13 ジェネリクス Ch.14 例外 Ch.15 スレッド Ch.16 ライブラリ Ch.17 リフレクションとアノテーション Ch.18 関数型プログラミング Ch.19 ラムダ式 Ch.20 ストリーム ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 Pythonで、本格的な機器分析データの解析 化学分析データの処理プログラムをPythonで作ろう、という本です。自ら作ることにより、目的のはっきりした使い勝手のよいものを作ることができます。本書はそのための指南書です。 第1章 機器分析の世界 第2章 Pythonの基礎 第3章 統計の基礎 第4章 データの前処理と可視化 第5章 ケモメトリックスの基礎 第6章 次元削減 第7章 クラスタリング 第8章 回帰 第9章 クラス分類 第10章 フィッティング 第11章 二次元相関分光法
-
-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13005-3)も合わせてご覧ください。 Microsoft Power Platformは「Power Apps」「Power Automate」「Power BI」「Power Virtual Agents」から構成され,「Office 365」「Microsoft Azure」などと接続できるビジネスプラットフォームです。本書ではPower Platformの導入を考える情報システム担当者,プログラミングの知識はないけれど業務のアプリ化・作業の自動化を行いたいビジネスパーソンなどの方に向けて,各サービスの基礎から具体的なアプリの作成方法までをサンプルアプリのレシピとして解説します。「メール添付ファイルの自動格納」「帳票出力」など,普段の業務をノーコード/ローコードでアプリ化しましょう! なお,Officeライセンスがない方も評価版(1ヵ月有効)でアプリ開発を試すことができます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■□■プログラムが「読めない」を解決する入門書■□■ 人気シリーズ「JavaScriptふりがなプログラミング」を大きくして読みやすく、内容を充実させて改訂しました。「プログラムの読み方をすべて載せる(ふりがなをふる)」という手法で究極のやさしさを目指した、まったく新しいJavaScriptの入門書です。 本書内に登場するプログラムの読み方をすべて載せ、さらに、漢文訓読の手法を取り入れ、読み下し文を用意。プログラムの1行1行が何を意味していて、どう動くのかが理解できます。この新しいアプローチで「プログラムが読めないから、自分がいま何をしているのかわからない」といったプログラミング入門者が途中で挫折してしまう原因を解決しました。 さらにこの増補改訂版では、Chapter 6として「サーバーと通信してみよう」を追加し、実際のWebページでJavaScriptがどう使われているかという実用性を重視した内容も盛り込みました。 ■本書はこんな人におすすめ ・JavaScriptの基本を身につけたい人 ・過去にプログラミングの入門書で挫折してしまった人 ・プログラマーやエンジニア、Webクリエイターを目指す人 ・仕事でJavaScriptを活用してみたい人
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 AI(人工知能)や自動化のプログラミングは、学ぶべき分野が多岐に渡ります。どこから手を付けていいのかわからない、という人も多いでしょう。 でも、これらはポイントをおさえることで、“スキマ時間”で学習できます。 本ムック「スキマ時間で学べる 機械学習&Python自動化」では、今やAIの主流と言える「機械学習」と、Pythonによる作業の「自動化」という2大テーマを、短期間で学べるように1冊にまとめました。 第1部では、機械学習をゼロから解説します。 第2部では、Pythonによる自動化のプログラムを解説します。 本ムックを活用して、スキマ時間で効率よく機械学習や自動化のプログラミングを学びましょう! ≪目次≫ はじめに スキマ時間で機械学習&Python自動化を学ぼう 第1部 「機械学習」を学ぶ 第1章 今から学ぶ機械学習アルゴリズム 第2章 「機械学習」エンジニアになろう! XGBoost超入門 第3章 最適な機械学習アルゴリズムを「PyCaret」で選ぶ 第4章 Pythonで「強化学習」を学ぶ 第2部 「Python自動化」を学ぶ 第1章 Python×Gmail自動化 第2章 PythonでExcel自動化 第3章 「機密書類」自動振り分けプログラム
-
-※この商品は固定レイアウトで作成されています。お使いの端末で無料サンプルをお試しいただいたうえでのご購入をお願いいたします。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、「Pure Data(Pd)」というオープンソースのグラフィカルプログラミング環境を使って、サウンドプログラミングを基礎から学ぶために書かれた本です。Max/MSPと同じルーツを持つPdは、「オブジェクト」という小さな箱を線でつなげていくことでデータの流れコントロールし、音を鳴らします。本書では、レシピとしてリズムマシン、シンセサイザー、そしていくつかのインタラクティブなシステムの作り方をとりあげ、初心者にもわかりやすく解説しています。
-
-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13001-5)も合わせてご覧ください。 特集1 イミュータブルデータモデルで始める 実践データモデリング 業務の複雑さをシンプルに表現! 良いデータモデルとは,モデリングの過程で,考慮されていない要求の穴やエッジケースの発見につながるものです。本特集では,データモデルを書くことを通して,顧客やチームとの対話をいかに進めていくかを解説します。 本特集では,データの更新に着目し,事実の記録は更新されないように整理・分類していくイミュータブルデータモデルという手法を紹介します。「更新」を手がかりに,分析の足りない箇所を洗い出し,堅牢なモデルになっていくさまを皆さんにも体験いただけたら幸いです。 特集2 いまはじめるFlutter iOS/Android両対応アプリを開発してみよう 本特集はマルチプラットフォームフレームワークFlutterの入門記事です。2022年5月にはmacOSとLinuxにも正式対応し,モバイル,Webフロントエンド,デスクトップのアプリケーション開発効率を大きく変える存在になりました。iOS/Android両対応アプリの開発を体験し,導入の足がかりにしてください。 特集3 作って学ぶWeb3 ブロックチェーン,スマートコントラクト,NFT 近年,「Web3」という言葉が注目を集めています。ただ,誇大広告ともとれる話や,暗号資産(仮想通貨)絡みの詐欺的な活動も横行していて,懐疑的な目で見ている方も少なくないと思います。本特集では,Web3の技術的な側面にフォーカスして解説します。どのようなことができるのか,そしてどのようなことができないのか,Web3という技術の,現在の等身大の姿を見ていきます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13035-0)も合わせてご覧ください。 本書はリアルタイムグラフィックスの基本を理解するための解説書です。 リアルタイムグラフィックス,つまり「即時に生成される」グラフィックスはいまやゲームからビデオチャットまで広く利用されており,多くの方が目にするものになっています。 この技術の根本には数学があり,数学的知識を身につけることで,多様なグラフィックスを生み出すコードの中身,グラフィックス生成のしくみを,きちんと理解できるようになります。 ゼロからしっかり理解したいと考える方に,本書は断然おすすめです。
-
3.5プログラミング入門書として広く活用いただいている『独学プログラマー』の姉妹書が登場。第2弾の本書は、コンピューターサイエンス(計算機科学)の入門書です。 アルゴリズムとデータ構造について、図およびPythonのコードで具体的に示しながら、分かりやすく説明します。 「独学プログラマー」が活躍するうえで役に立つ、基本的な概念と実装を紹介します。 本書に登場するコードは、日経BOOKプラスの本書ウェブページからダウンロードいただけます。詳細な目次ページ(PDF)もそちらからダウンロードいただけます。 独学プログラマーが理解しておくべきもっとも大切な分野を学ぼう! 私は当時、スタンフォード大学、カリフォルニア大学バークレイ校、カリフ ォルニア工科大学を出た優秀なプログラマーと一緒のチームにいました。コンピューターサイエンスを十分に理解している同僚たちの中で、不安で、居心地の悪さを感じていました。独学プログラマーとしてコンピューターサイエンスを学ぶことで、このような不安を最小限に抑えられます。 ――「イントロダクション」より
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 初心者から熟練者まで、すべてのWeb制作者のための早引き事典の最新版! 本書は、HTMLの要素(タグ)とCSSのプロパティを解説した事典です。 HTMLの要素やCSSのプロパティの意味、対応ブラウザーなどがひと目で分かるほか、豊富なサンプルコードで、使い方も理解できます。 WordPressなどのCMSで新規サイトを構築するときに、既存サイトのコードを解読したいと思ったときに、タグやプロパティの内容をサッと調べることができる便利な1冊です。 また、HTMLやCSSの基本的な書き方はもちろん、HTML5からHTML Living Standardに標準仕様が移った経緯などの技術的背景、文字参照やURLの構成といったWeb制作者として不可欠な知識も解説しています。 ●このような方におすすめ ・HTML&CSSを記述・修正する必要のある人 ・Webデザイナーや、情報システム部などでWebサイトを内製で構築する担当者 ・HTML&CSSの勉強をしている大学生や新入社員
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 さまざまな意思決定の数理や現象をPythonで体験して学ぼう! 本書は,数理的に扱える意思決定の基礎を,Pythonを用いたシミュレーションや分析によって実際に試しながら学ぶものです. アンカリング効果の評価法,ベイズ推定に基づいた信憑性の変化,エージェントや強化学習を適用した意思決定,不完備情報ゲーム,集団の意思決定などを解説しています. 本書では,意思決定のモデルの立て方,意思の測定分析などの説明に重点を置き,計算やシミュレーションの詳細な説明よりはPythonによる実行に基づいて学ぶ体験学習のかたちをとります.また,すべてのプログラムはJupyter Notebook形式で配布し,読者の手もとで実行ができるようにしています. 第1章 はじめに 第2章 戦略の微分方程式モデル 第3章 基礎的な意思決定の数理的扱い 第4章 ゲーム理論の基礎 第5章 意思決定のための OR の基礎 第6章 組合せ最適化による意思決定 第7章 マルチエージェントベースモデリングによる意思決定 第8章 強化学習による意思決定 第9章 不確定性を含むゲームでの意思決定 第10章 集団の意思決定 第11章 意思決定とメカニズム・デザインの視点 索引
-
-自然言語処理の定番手法となっているWord2Vecを使ってみたい初心者やちょっと手の込んだことをしてみたい中級者向けに、Word2Vecのお役立ちTipsを詰め込みました。 最近はもっぱらBERTやGPTシリーズの登場によってWord2Vecは過去の技術という印象があるかもしれません。ですが今だからこそ知見も溜まっており、安定して使えるようになったとも言えます。 Word2Vecを使い倒すためのノウハウの1つ1つは、どこかの記事などでみたことがあるものかもしれませんが、これ1冊だけで役立つようになっています。使い倒しブックということで、理論的な点よりも、使い方に重点を置き、多くの実装例から結果を見ながら理解できます。
-
-本書はXR Interaction Toolkit を利用した Oculus Quest 向けアプリケーション制作を目的とした本です。VRゲームを作る上で必要になる基礎的な動作をUnityを操作しながら作成していきます。 VRアプリ作成に入門して、VR世界に飛び込もう!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 オブジェクトやクラス、自作関数のライブラリ化など、複雑なプログラム開発に欠かせない“プログラムを設計する考え方”を学べます。ブラウザゲーム「ポーカー」の作成を通して、プログラムを「組み立てる力」を学ぼう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 GmailやGoogleスプレッドシートといった、便利なGoogle関連サービスが多くの企業で導入されています。Google Apps Scriptを使えばこれらのサービスをさらに使いやすくできます。本書は、Google Apps Script(GAS)を用いた業務効率化・自動化に取り組む方のために、メール送付の自動化やシフト管理表をGoogleカレンダーに反映させるなど、9つの活用ケースを通して学ぶ実践書です。また、Google Apps Script基礎文法も解説しています。
-
4.0本書はPythonによる自然言語処理、あるいはテキストマイニングの初歩について解説したものです。 テキストマイニングとは、テキストをコンピュータで探索(マイニング)する技術の総称です。ここで「テキスト」とは、小説や論文、あるいは新聞や雑誌の記事にとどまらず、インターネット上のブログ、あるいはSNSに投稿された文章など、およそ人間の言葉で書かれたものを指します。 Pythonの基本からテキスト分析の手順、形態素解析器の導入、さまざまな分析手法についてわかりやすく解説しています。また、本書の最後に、ディープラーニングを使ったテキストマイニング事例についても紹介します。 なお、本書の一部については解説動画が用意されています。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 おかげさまで8万部突破! 読者の声に応えて 第2版の登場 【本書の概要】 Web開発やデータ分析などの分野で、ユーザー数が増えてきているPython。 最近では、Pythonに触れる方も多くなってきています。 本書はそうしたPython初心者の方に向けて、 ヤギ博士とフタバちゃんと一緒に 基本的なプログラムの作成から、面白い人工知能アプリの作成までを体験。 対話形式でプログラミングのしくみを学ぶことができます。 【対象読者】 Pythonについて何も知らないプログラミング超初心者 【本書のポイント】 ・対話形式で解説し、イラストを交えながら、基礎知識を解説します。 ・初めての方でも安心して学習できるよう基本文法もしっかり解説します。 ・平易なサンプルを用意していますので、安心してプログラムを体験できます。 ・2022年時点の最新の環境(Windows 11、Python 3.10など)に対応しています。 ・エラーでつまづいた場合の対応方法を巻末に掲載しています。 【目次】 第1章 Pythonで何ができるの? 第2章 Pythonを触ってみよう 第3章 プログラムの基本を知ろう 第4章 アプリを作ってみよう 第5章 人工知能くんと遊んでみよう 【著者プロフィール】 森 巧尚(もり・よしなお) 『マイコンBASICマガジン』(電波新聞社)の時代からゲームを作り続けて現在はコンテンツ制作や執筆活動を行い関西学院大学非常勤講師、 関西学院高等部非常勤講師、成安造形大学非常勤講師、大阪芸術大学非常勤講師、プログラミングスクールコプリ講師などを行っている。 近著に、『Python1年生』『Python2年生 スクレイピングのしくみ』『Python2年生 データ分析のしくみ』『Python3年生 機械学習のしくみ』 『Java1年生』『動かして学ぶ!Vue.js開発入門』『Python自動化簡単レシピ』(いずれも翔泳社)、 『ゲーム作りで楽しく学ぶ Pythonのきほん』『楽しく学ぶ Unity2D超入門講座』『楽しく学ぶ Unity3D超入門講座』(いずれもマイナビ出版)などがある。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
3.0※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-12917-0)も合わせてご覧ください。 新しいフロントエンドの入門書決定版! 本書はReact/Next.jsとTypeScriptを用いてWebアプリケーションを開発する入門書です。 WebアプリケーションフレームワークNext.jsはReactをベースに開発されています。高速さに裏付けされた高いUXと,開発しやすさを両立しているのが特徴です。 本書では,Next.jsの開発をより快適・堅牢にするTypeScriptで開発を進めます。 Next.jsによるアプリケーション開発の基礎,最新のフロントエンドやWebアプリケーションの開発方法が学べます。
-
-Vite・TypeScript・Babylon.jsを使ってWebARをするところまでの道筋を解説した本です。 Viteを使ったノンフレームワークなTypeScriptプロジェクトの作成から始まり、最後にはAzureにデプロイするまでをたどっていきます。 Babylon.jsやWebARについての詳細よりも開発環境の構築にフォーカスした内容です。ビルドツールを使って一歩進んだ開発をしてみたいWebAR初学者にオススメしたい一冊です。
-
-Swift 5.5からSwiftは並行処理を言語機能としてサポートするようになりました。それがSwift Concurrencyです。本書はその機能を解説しています。 async/awaitにより、非同期処理をクロージャーよりも完結に記述できます。データ競合を防ぐ新しい型としてActorやデータ競合が発生しない型を表すSendableが登場しました。並行処理の実行単位であるTaskもあります。Swift ConcurrencyはWWDC 2021の目玉機能といっても過言ではありません。 Swift Concurrencyの概要が一冊で日本語で理解できるのが本書の特徴です。Swift Concurrencyには覚えなければいけない概念が数多くあります。async、await、Actor、MainActor、Task, TaskGroup、AsyncSequence、Sendableなどなど。本書は一冊でSwift Concurrencyの概要をほぼ全て網羅しています。各章にそれぞれサンプルコードが付属しているので、どんな動作をするのかを試して理解を深められます。
-
-知識ゼロからでもよくわかる、はじめてのC++ 本書は、プログラミングの基礎知識とC++の言語構文を学ぶ本です。 C++に必須の構文やクラスをしっかり網羅し、初学者向けにやさしく解説しています。 1つのプログラムをテーマに沿ってどんどん改造していくので、自分のやりたいことを 実現していく過程がよくわかります。 ソースコード中の改造箇所は色分けしているので、初学者がプログラミング迷子に なることもありません。 章末には理解度を確認するテストを掲載。学んだことをその場で確認できます。 この第3版ではGNUプロジェクトのコンパイラであるGCCを利用し、Windowsユーザー だけでなくMacユーザー(注)も学べるように配慮しています。 注:macOSでの学習環境の構築方法は、本書の付属データとしてPDFで提供しています。 著者は、IT系を中心に多くの執筆実績がある矢沢久雄さん。 プログラミングの講師を行う際は「わかって楽しい、動いてうれしい」をモットーにしているそうです。 【本書の対象読者】 ・本書ではじめてプログラミングを行う人 ・これまでにC++を学ぼうと思ったことがあるけれど、挫折してしまった人 ・一生使えるプログラミングの知識をC++で身につけたいと思っている人 【目次】 第1章 プログラミングの準備をする 第2章 役に立つプログラムを作る(C++の基本構文) 第3章 条件に応じた分岐と繰り返し 第4章 プログラムを関数で部品化する 第5章 プログラムをクラスで部品化する 第6章 クラスがあるから表現できること 第7章 オーバーライドとオーバーロード 第8章 コピーコンストラクタと代入演算子のオーバーロード 第9章 エラー処理とファイル処理 第10章 テンプレートとSTL 付録 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-C# 10.0に対応して、 “標準教科書”が5年ぶりの改訂! ~C#プログラミングに必要な知識・概念・機能を 体系的、かつ網羅的に習得できる!~ C#言語の独学に最適な教科書として、 長年にわたって読まれてきた『独習C#』。 プログラミング言語入門書の執筆で定評のある 山田祥寛氏の執筆による信頼感をそのままに、 最新バージョンのC# 10.0に対応しました! 本書では、C#でオブジェクト指向プログラミングを 行う際に必要となる基本的な知識・概念・機能、 C#の文法・プログラムの書き方を、さまざまな サンプルプログラムを例示しながら詳細かつ丁寧に 解説します。 プログラミングの基礎知識がない方でも、 解説→例題(サンプル)→理解度チェックという 3つのステップで、C#の文法を完全習得できます。 [ポイント] ●C#言語の独学に最適な教科書として好評の『独習C#』最新版。 初心者がC#言語を学ぶにふさわしい一冊 ●C#でプログラミングを行う際に必要となる 基本的な知識・概念・機能、文法・書き方を、 網羅的かつ体系的に習得できる C#言語の入門者、これからC#言語で開発を始めたい 初学者から、再入門者、学生・ホビープログラマまで、 「一からC#言語を学びたい」「C#プログラミングの基本を しっかり身につけたい」という方におすすめの一冊です。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-12967-5)も合わせてご覧ください。 「プログラミングを学ばせるには,まずなにから教えたらいい?」 「ゲーム作りだけじゃない,プログラミングを学んでもらいたい」 保護者の皆さまのそんな想いに応えるべく,本書ではプログラミングの根っこにある「問題解決」を大切にしています。 ①登場人物たちのお悩みを知る ②タブレット(iOS/Android対応)でプログラミングする ③お悩みを解決し,登場人物に喜ばれる この3つの流れを,はじめてプログラミングに触れるお子さまが,楽しく体験できる1冊です! ★推薦!★ 子どもも大人も,テクノロジーで支えられている世の中の「見え方」が変わる ――信州大学 教育学部 准教授 佐藤和紀 氏 物語を読み進めるとプログラミングの基本が身につく画期的な絵本! ――株式会社ソニー・グローバルエデュケーション 会長 礒津政明 氏
-
-本書では、Kotlin製の軽量Webフレームワークの「Ktor」とモダンフロントエンドフレームワークの「Nuxt.js」でWebアプリケーション開発の基礎を学ぶことができます。 他にもDocker、PostgreSQLやHerokuについても触れており、GitHubにサンプルコードもありますのでハンズオン形式で学ぶことができると思います。Kotlin・KtorやNuxt.jsの言語仕様については掲載していませんが、本書をきっかけにKotlinやNuxt.jsに触れて、ステップアップしましょう。
-
-JavaScriptの関数の使い方を徹底解説します。 関数定義の書き方、関数の呼び出し方といった基礎から、クロージャや再帰の応用、関数型プログラミングの理論的な概要まで扱います。ECMAScript 2021対応です。 入門書ではあまり触れられることのない、ちょっとした応用も扱います。 ・関数のカリー化 ・無名再帰と不動点コンビネータ ・末尾呼び出しとその現状 ・ファンクタやモナド JavaScriptの関数の基本的な使い方を知りたい、関数型プログラミングの理論的背景に簡単に触れてみたいという方におすすめです。
-
-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-12973-6)も合わせてご覧ください。 本書は,世界最先端のAI研究所の一つであるDeepMindが発表した論文を軸に,現代的なAIがどのように作られているのかをまとめた技術解説書です。 「汎用AI」「ゲームをプレイするAI」をテーマとし,おもに深層強化学習の技術を取り上げます。深層強化学習は,いまの世の中で広く使われているディープラーニングをゲームなどの領域に応用した技術です。 深層強化学習には高性能なシミュレータが必要であり,ゲームをはじめとした架空の世界を舞台として最先端の研究が進められています。 本書ではこれまでに発表されてきた論文を通して,「いま技術的に何ができて,何が難しいのか」を紐解きながら,一つ一つの技術を積み上げた先に来る,次の時代のAIについて考えていきます。
-
5.0※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-12947-7)も合わせてご覧ください。 本書は,事業分析やデータ設計のためのモデル作成技術の入門書です。本書で紹介する「TM(Theory of Models)」は,厳密な文法に則ってテーブルを細分化することにより,ITエンジニア同士で共通の言語認識を持ち,変化に強いデータベースの構築を可能とするモデル作成手法の1つであり,事業分析,データ設計の分野で長く活用されています。本書では,モデル作成技術の前提となる理論や知識を解説し,TMによるモデル作成の流れを概観した後,実際のモデル作成に使われる技術・文法の解説を行います。また,学習した内容をきちんと身に付けられるよう,解説の合間には練習問題を用意しました。事業構造を正確に分析し,モデル化するための理論と技術をしっかり学ぶことのできる1冊です。
-
5.0Goは2012年3月にバージョン1がリリースされてから約10年が経ちました。その間Goは多くの企業で利用され、その利用シーンもさまざまです。本書はGoでREST API Webアプリケーションを開発するときに必要な知識に特化した内容になっています。 本書は前半でWebアプリケーション開発の事前知識としてGoの設計思想や知っていると便利な標準パッケージの機能について紹介し、後半でGoを用いたWebアプリケーションのコードをハンズオン形式で解説します。 また、本書ではベテランGopherが暗黙知的に行なっているイディオムの解説や、標準パッケージやメジャーなサードパーティOSSを使った実践的なコーディングテクニックを紹介しています。 ■序文より抜粋 本書ではベテランGopherが普段使っているイディオムの解説、また標準パッケージや主要なサードパーティ製のOSSを使った実践的なコーディング技法を紹介します。 (中略) 本書は主に2つの構成からなります。 CHAPTER 01からCHAPTER 12まではWebアプリケーション開発の事前知識としてGoの設計思想や知っていると便利な標準パッケージの機能について紹介します。他のプログラミング言語の経験がある方や、他のプログラミング言語向けに書かれたオブジェクト指向の書籍をGoに適用しようとした方が疑問に持ちやすいGoの機能や知っているだけでコードがよりシンプルに書ける技法を紹介します。 CHAPTER 13以降ではGoを用いたWebアプリケーションのコードをハンズオン形式で解説します。テストコードを書き段階的な変更を繰り返しながら業務の運用に耐えうるAPIサーバーを構築します。
-
4.0Pythonプログラムを動かしながら機械学習の基礎をしっかり学べる! 【本書の目的】 人工知能関連サービスや商品開発において 機械学習の基礎知識が必要となります。 本書では数式とPythonプログラムをつなげて 機械学習の基礎をしっかり学ぶことができます。 【本書の特徴】 本書は、機械学習の原理を数式でしっかり理解し、 Pythonプログラムによってその理解を深めていくことができる書籍です。 ・数式とコードを連携して解説 ・学習内容を「要点整理」で復習 ・TensorFlow 2.7に対応 ・Python 3.9に対応 【読者が得られること】 機械学習のしくみとPythonプログラムを つなげて理解できます。 【対象読者】 機械学習の基礎を数学的な原理からプログラム実装までしっかり学びたい理工学生・エンジニア 【目次】 第 1 章 機械学習の準備 第 2 章 Pythonの基本 第 3 章 グラフの描画 第 4 章 機械学習に必要な数学の基本 第 5 章 教師あり学習:回帰 第 6 章 教師あり学習:分類 第 7 章 ニューラルネットワーク・ディープラーニング 第 8 章 ニューラルネットワーク・ディープラーニングの応用(手書き数字の認識) 第 9 章 教師なし学習 第10章 要点のまとめ ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-UGCとは User Generated Contents の略で、ユーザーが作成したコンテンツのことです。 ゲーム開発においては、ゲーム内のマップ、イラスト、プレイヤーのスキン(見た目)などがあります。 開発側からすべてのコンテンツを提供するのではなく、 ユーザー側からもコンテンツを作ることで、さらにゲームを盛り上げることができるようになります。 PlayFab の UGC では、以下の機能が提供されています。 ・下書きアイテムの作成 ・下書きアイテムの公開 ・アイテムのモデレート ・アイテムの報告 ・アイテムの検索 ・アイテムの評価、レビュー 2021年10月に一般公開された機能ということもあり、公式以外では情報がありません。Googleなどで検索をしても、英語の情報すら出てこないのが現状です。著者自身公式ドキュメントを読み込みましたが、実装例の記載が少なかったり、全体像を理解するのに難しさを感じていました。 PlayFabの使い方を覚えるのに時間を割いていると、ゲーム開発の時間がどんどん削られてしまいます。「世の中に情報が出ていないのであれば、自分で試してまとめるしかない」と思い、本書の執筆にいたりました。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 特集1 5大人気ボード 電子工作超入門 「半導体不足で在庫が不足し、電子工作のボードがなかなか買えない…」。そんな今にふさわしい特集のほか、5種の人気ボードにすべて対応した電子工作の入門特集などをまとめました。「GPIO」や「I2C」を使った電子パーツの制御方法は、どのボードでも同じです。手に入れられたボードを使って、今こそ電子工作を始めましょう。 ◆5大人気ボードはこう選ぶ、ラズパイをうまく買う方法も伝授 ◆プログラムを開発する環境を整えよう、5大ボードの端子などの違いもチェック ◆デジタル出力 電圧のオン、オフでLEDの点灯などを制御できる ◆デジタル入力 スイッチやセンサーの状態を読み取れる ◆PWM出力 モーターの回転速度などを調節できる ◆アナログ入力 アナログセンサーなどの電圧を読み取れる ◆I2C デジタル通信で多様なデータをやり取りできる 特集2 Picoの強力な機能を引き出す!脈拍のグラフを小型画面に表示 特集3 みんなのラズパイコンテスト2021 グランプリ 走行中の列車を自動で流し撮り「OpenCV」で高速認識して追尾 特集4 古いラズパイをフル活用! Node-REDで楽しい電子工作 IoTクラウドと連携し「天気痛ボタン」を製作 特集5 ラズパイで鉄道模型の自動運転にチャレンジしよう 特集6 ラズパイで楽しむLinuxライフ オンラインのドキュメント編集をNextcloudとCollabora Onlineで実現 【付録冊子】 フルカラー52ページ 温度からにおいまでセンサー200種総ガイド+工作例3種
-
4.0ロングセラーの入門書、9年ぶりにリニューアル! プログラミングの基礎とJavaScriptの基本文法を やさしく解説した入門書の定番が、装い新たに登場です。 変数やデータ型、関数、オブジェクトなどはもちろん、 Webに関する知識やHTML/CSSのベースも解説しているので、 本書を一冊読めば、これからWebサイトやWebアプリを開発するうえで、 ずっと役に立つスキルの土台を身につけることができます。 またDOMやイベント、非同期処理といった少し複雑な言語機能も丁寧に解説。 ブラウザ上で実際のコードを動かしながら、一つひとつ、 「なぜその機能が必要なのか」を掘り下げて理解を深められます。 初心者が自力でプログラムを書けるようになるまで、しっかりフォローするので 知識・経験ゼロでも安心して読み進めることができます。 【本書の対象読者】 ・はじめてプログラミングを学ぶ人 ・これまでに学習で挫折してしまった人 ・JavaScriptでWebサイトやWebアプリの開発を始めたい人 【目次】 第1章 JavaScriptの紹介と準備 第2章 JavaScriptを書いてみよう 第3章 変数 第4章 データ型と演算子 第5章 配列 第6章 条件分岐 第7章 繰り返し処理 第8章 関数 第9章 オブジェクト 第10章 標準組み込みオブジェクト 第11章 HTML&CSS 第12章 ブラウザオブジェクト 第13章 DOM 第14章 イベント 第15章 通信と非同期処理 第16章 総合演習 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-12955-2)も合わせてご覧ください。 データベース製品で世界/国内ともにNo.1のシェアを誇るOracleは,データベースに携わるエンジニアにとって必須知識の1つといえます。本書では,Oracle初心者/新人エンジニアが押さえておくべき知識とスキルを,現場で活躍するOracleエンジニアたちが,わかりやすく丁寧に解説。Oracleの使い方はもちろん,データベースの基礎知識から,データ操作のためのSQL,テーブル設計,データベース運用/管理の基礎までしっかり押さえ,実務で使える入門スキルを身につけられます。 改訂2版では,最新安定バージョンに合わせて解説をアップデート。今後主流となるコンテナベースのデータベース構成についての解説も強化しました。 Oracleやデータベースを学びたいすべての人に最適な入門書です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※電子版にはDVD-ROM付録コンテンツは収録しておりません。ただしDVD-ROMに収録したコンテンツの一部(記事で利用したプログラムなど)は読者限定サイトからダウンロードしてご利用いただけます。 Linuxが初めての人でも分かりやすいように、Linuxのはじめ方を紹介します。 ■Windowsを使い慣れた人ならすぐ理解できるように、Windowsと比較しながら解説しています ■豊富な写真と図を使って「見て分かる」ように解説しています ■基本操作のマスターから始まってスマホやクラウドとの連携など、活用方法までを網羅しています ■一番人気のLinuxである「Ubuntu 22.04 LTS」をベースに、Linuxの最新トレンドについても紹介しています。 ■すべての記事は2027年4月までサポートが保証されている「Ubuntu 22.04 LTS」で動作検証済みです Linux専門誌の「日経Linux」に掲載した記事を選りすぐり、再検証・再編集してまとめました! ≪目次≫ 第1章 これで分かる!Ubuntuの使い方 第2章 実用度MAX!フリーソフト50 第3章 最新版「Ubuntu 22.04 LTS」完全解説 第4章 PC&スマホ&クラウド連携 虎の巻
-
4.0プロダクトマネジメントとDXを成功に導く シリコンバレーの最新解! イノベーションのためには プロダクトのビジョンを明確にして 戦略と優先順位を組織に浸透させなければならない。 しかし、この一連の活動を 日々の仕事にうまく落とし込むことは 非常に難しい。 この難関を超えた一握りの組織こそが イノベーションを勝ち取る。 そこで本書では、小手先の施策ではなく ラディカルに(=本質的かつ根本的に) 組織をイノベーションに導く 思考法を解説する。 具体的には次の5つのアプローチでプロダクトを成功に導く。 1 組織と市場にマッチしたビジョンのつくり方 2 ビジョンを効率的に達成する戦略の立て方 3 戦略を実行する優先順位のつけ方 4 施策の仮説検証の仕方 5 組織へビジョンを浸透させる方法 とくに以下のような方々には必読の一冊。 ・プロダクトマネジメント、プロジェクトマネジメントのリーダー ・DXにかかわるマネージャー、エンジニア ・組織変革をめざす経営層・マネージャー・起業家 〈目次概要〉 序章 ラディカル・プロダクト・シンキングとは何か 第1部 イノベーションのための新しいマインドセット 第1章 ラディカル・プロダクト・シンキングが必要な理由 第2章 プロダクト病~優れたプロダクトが腐敗するとき 第2部 ラディカル・プロダクト・シンキングの5大要素 第3章 ビジョン~変化を想像する 第4章 戦略~「なぜ」「どのように」行うか 第5章 優先順位づけ~力のバランス 第6章 実行と測定~さあ、始めよう! 第7章 文化~ラディカル・プロダクト・シンキングな組織 第3部 世界を住みたい場所に変えるために 第8章 デジタル汚染~社会への巻き添え被害 第9章 倫理~ヒポクラテスの誓いとプロダクト 終章 ラディカル・プロダクト・シンキングが世界を変える ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 いま話題の新しい言語「Julia」を7日間で速習! プログラミングが初めてでも読みやすい解説を通じて、具体的課題に適用しながら基礎から応用まで身につける。簡単、気軽に誰でも科学技術計算ができる! ◇おもな目次◇ 1日目 Julia言語に触れてみよう――「高級電卓」としてのJulia 1.1 インストールしてみよう 1.2 実行してみよう 1.3 電卓のように使ってみよう 1.4 変数を使ってみよう 2日目 数式をコードにしてみよう――Julia言語の基本機能 2.1 関数を作ってみる:function 2.2 条件分岐をしてみる:if文 2.3 繰り返し計算をしてみる:for文 2.4 行列とベクトルを扱う:配列 2.5 型について考える:型と多重ディスパッチ 2.6 パラメータや変数をまとめる:struct 2.7 一通りのセットとしてまとめる:module 2.8 微分方程式を解く:パッケージの使用 2.9 数式処理(代数演算)をする:他の言語のライブラリを呼ぶ 3日目 円周率を計算してみよう――簡単な計算と結果の可視化 3.1 計算を始める前に 3.2 正多角形による方法:漸化式で計算 3.3 無限級数による方法:結果のプロットと複数の方法の比較 3.4 数値積分による方法:区分求積法ほか 3.5 モンテカルロ法:乱数を使う 3.6 球衝突の方法:シミュレーションの可視化 4日目 具体例1:量子力学――微分方程式と線形代数 4.1 時間依存のない1次元シュレーディンガー方程式:固有値問題を解く 4.2 時間依存のない2次元シュレーディンガー方程式:特殊関数を使う 4.3 波動関数の時間発展:行列演算を行う 5日目 具体例2:統計力学――乱数を使いこなす 5.1 手作り統計力学:ヒストグラム表示 5.2 イジング模型のモンテカルロシミュレーション:可視化と動画作成 6日目 具体例3:固体物理学――自己無撞着計算と固有値問題 6.1 強束縛模型:対角化とフーリエ変換 6.2 超伝導平均場理論:自己無撞着計算 7日目 自分の問題を解いてみよう 7.1 用途別必要機能まとめ 7.2 妙に遅いとき:高速化の方針 7.3 さらに速く:並列計算をする ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 占いや数当て、マインスイーパー、落ちものパズルなどの身近なゲーム作成を通して楽しみながらJavaScriptを学ぶ。単に文法を解説するだけではなく、どのようにすると良いプログラムが書けるか、つまずきポイントを提示しながら考え方のコツを丁寧に伝授。詳細なウェブ教材による解説を提供。プログラム全文だけでなく、テキストの解説にあわせた修正箇所の表示機能や、テキストには書ききれなかったTipsや詳しい解説を収録。テキストとの併用でより効果的に学習可能。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「Dockerって何?」「どうやって使うの?」といった、これからDockerを使っていきたいと考えている方のための入門書です。実際に操作をしながらDockerについて知り、使い方を体験することができます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Excel VBAの初~中級者に向け、目的別に網羅して解説した逆引きテクニック集です。構文についての詳細解説はもちろん、コピーペーストしてすぐに使えるサンプルも付属しており、デスクの片隅に常備したい1冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 開発で使用する基本的なプログラミングテクニックから、開発ですぐに役に立つ即効性・実用性の高いテクニックなど、500項目を解説したテクニック&サンプルコード集。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、Visual Basicによるプログラミングを学ぼうとするすべての人のために書かれたものです。Visual Studio 2022のインストールと基本操作からはじめて、その開発環境でさまざまなデスクトップアプリケーションを作成していきます。少しずつステップアップしていくことで、プログラミングがはじめての人にもムリなく理解でき、しっかりとした実力が付くように構成されています。Visual Basicの文法や処理のパターンにまで踏み込んで、そのしくみを詳しく解説しました。「入門」だけで終わるのではなく、その先に進むための「基礎」を身に付けることができます。また、最後の2つの章では、おみくじアプリやデータ分析アプリを作成しており、より実践的な例を確認することができます。
-
-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-12915-6)も合わせてご覧ください。 コンピュータアーキテクチャ,とくにCPUの命令セットアーキテクチャについて,RISC-Vを例に「上のレイヤからアプローチする」ことで理解を深めることを目的とした一冊。本書を一通り読み終えるころには,低レイヤに対する一段上の実力がついているはずです!
-
-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-12891-3)も合わせてご覧ください。 特集1 Reactの深層 最新バージョンから読み解く! 変わる常識と変わらない思想 本特集はReact 18のリリースを受け,これまでのReactについて復習するとともに,React 18の新機能を紹介します。新機能を使いこなすにあたり,前半ではこれまでのReactの使い方やAPIに込められた思想を確認し,後半ではReactユーザーが対応を迫られる新しい常識を解説します。将来にわたってReactらしいコーディングをするための考察です。 特集2 できるところから無理なく導入! 小さく始めるデザインシステム 「デザインシステム」という用語を耳にする機会が増えました。しかし,重要な概念であることはわかっていても,考えなければいけないことがたくさんあり導入に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。もちろんデザインシステムはすべての要素を考慮するのが理想ですが,完璧を目指すあまり採用を見送ってしまうのはもったいないと思います。本特集では「小さく始める」ことをコンセプトに,できるところから無理なく始め,そのメリットを知ってもらうことを目的としています。 特集3 最新レコメンドエンジン総実装 協調フィルタリングから深層学習まで レコメンドエンジンとは,ECサイトやWebサイト上で,ユーザーにお勧めの商品やコンテンツを表示するためのシステムです。本特集では,Python言語を用いてレコメンドエンジンを実際に作成し,理解を深めていきます。実サービスに導入できるレコメンドシステムのしくみ,汎用的なものから深層学習までのレコメンドエンジンの実装,良いレコメンドエンジンとは何かを評価する方法を紹介します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■ プログラムの設計力を身につけよう! 「プログラミングは勉強したのに、自分でプログラム作れない……」 そう悩んでいる人、けっこう多いんです。プログラミングの入門講座や入門書で、ひと通りプログラミング言語の文法やツールの使い方は学んだという人に本書を読んでいただきたい。きっと講座で取り上げられたコードや、書籍に掲載されたコードは、何をやるプログラムかはもう理解できますよね。自分で実際にコードを入力して、動作させることもできましたよね。でも、自分で「こんなプログラムを作ってみたい」と思って、自由自在にコードを書けていますか? 実は、「こんなプログラムを作ってみたい」というアイデアがあっても、それをすぐにプログラムにするのは簡単なことではありません。そうしたアイデアをプログラムにするための過程が欠けているからです。アイデアとプログラムをつなぐのが“設計”です。入門講座や入門書には、この設計の説明がほとんどないのです。プログラムを作れるようならないのは、そのためです。新米プログラマーがすぐに自分でプログラムを書けるようにならないのはもっともなことなのです。 でも悲観することはありません。そんなプログラミングの初心者に向けてソフトウェア設計の初歩の初歩を解説するのが本書です。「設計」といっても難しく考える必要はありません。本書ではじゃんけんやすごろく、あっち向いてホイなど、誰もが知っている遊びを取り上げ、それをプログラムにするために何を考えなければならないか、プログラムにするにはどうすればいいかを、一つひとつステップを踏みながら説明します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Pythonの汎用性とExcelの操作性。 組み合わせれば、みんなで使える実用ツールに! デジタル化(デジタルトランスフォーメーション=DX)による業務効率化や生産性向上が強く求められている昨今、小学校でプログラミング教育が必修化されたこともあって、「これからの時代を生きるには大人も子どももプログラミングを学ぶことが重要」という意識が広がってきています。 特にビジネスパーソンにとっては毎日の仕事に直接的に役立つ大きな利点があります。プログラムを書くことができれば、面倒な業務をコンピューターという労働力に任せて自動化し、もっと優先度が高く重要な仕事をするための時間を生み出せるのです。 本書では、プログラミング言語Python(パイソン)の基礎からスタートして、最終的にはそれをExcelと組み合わせて職場のみんなに広く使ってもらえる自動化ツールを作る方法までを学んでいきます。特に力を入れたのは、Pythonで作ったツールを職場のみんなに使ってもらうための以下のような工夫です。 ・だれでも使えるExcelを使って入力・設定を行う方法 ・Pythonがインストールされていない環境でもプログラムを実行する方法 ・だれにでも理解できるエラーメッセージの書き方 本書の内容をマスターすれば、自分にとって便利なのはもちろん、同じチームで働くみんなに貢献できる自動化ツールを作れるようになります。プログラミング未経験でも大丈夫。PythonとExcelを駆使して、職場のヒーローになりましょう。
-
-本書はプログラマー向けに、Chromebookをメインの開発PCとして使う方法を紹介します。 昨今Chromebookが様々な場面で普及してきましたが、話題に上がるのは価格が低い反面スペックの控えめな製品が多いと感じます。そのため、Chromebookに「2台目、3台目のサブのPCとしては便利」「プログラマーが開発用のPCとして本格的に使うことは難しい」という印象を持っている方が多いのではないでしょうか。 本書は「プログラマーのための本気で使えるChromebook」と題しています。「本気で」というのは、サブのPCとしてではなくChromebookを開発用のメインPCとして本気で使っていくことができる、という意味で命名しています。 本書の前半では基礎知識としてChromebookの紹介や機種の選び方、プログラマーにとって重要なツールやサービスを紹介します。後半では実践編として、ChromebookでWebアプリケーションを開発する方法と、技術同人誌を執筆する方法を紹介します。 WindowsやMacで普段Dockerを活用して開発をしている方は、ぜひChromebookを手にとってその快適さを感じてほしいと思っています。本書がChromebookに興味を持つきっかけになったら幸いです。
-
-現役ゲームクリエイターが教えるゲームUIデザインの実践ノウハウ 【本書の背景】 ゲームのUI(ユーザーインターフェース)デザインは、 ターゲットやゲームジャンルによって開発の方向性が大きく異なります。 また、ワークフローの体系化が難しい職種でもあり、 手さぐりで開発を進めている方も多いのではないでしょうか。 本書はそういった現場の「生の声」から生まれました。 【本書の概要】 ゲームUIのコンセプト策定からプロトタイプの作成、 実際のデザイン手法、実装時のコツ、業務としてUIデザインを行う際のテクニックなど、 著者がこれまで蓄積した現場のノウハウを、開発の工程ごとにまとめた書籍です。 【読者ターゲット】 ・ゲームUIデザイナー ・ゲームUIに関わるプランナーやエンジニア 【目次】 Chapter1 はじめに Chapter2 コンセプト Chapter3 プロトタイピング Chapter4 デザイン Chapter5 実装 Chapter6 スキルアップ Chapter7 おわりに 【著者プロフィール】 太田垣 沙也子(おおたがき・さやこ) 株式会社バンダイナムコオンライン プロデューサー ゲームデベロッパーでの受託開発経験を経て、2015年にバンダイナムコオンラインへ。 IPタイトルを中心としたコンシューマー・スマートフォン・アーケード・PC向けゲームの UIデザインおよびリードビジュアルを担当し、現在はプロデューサーとして新規開発プロジェクトに従事。 また、個人でもビジュアルデザイナーとしてクリエイター活動を展開している。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 データ分析の現場にあって入門書にない「汚いデータ」(ダーティデータ)に対応する、プロのノウハウを解説します。
-
4.0ウォーターフォールでもアジャイルでも、 上流品質を上げまくって、よい製品を楽に作ろう! テスト界の第一人者、高橋寿一氏執筆の 「開発者テスト」実践における必携書、アジャイル開発に完全対応! 本書では、アプリ・システム開発において、バグを減らすために 開発者が行うべきテスト(開発者テスト)についてわかりやすく解説します。 開発者テストを実施するために知っておくべき概念・手法や、 ○単体テスト ○リファクタリング ○アジャイル開発での品質担保 ○テストの自動化 などについて、実例を出しながら解説していきます。 旧版で言及の少なかったアジャイルテストの方法論にページを割き、 アジャイルの現場でも活躍する内容にパワーアップしました。 品質コンサルタントとして長年培ってきた筆者の経験をもとにした、 現場で必須の手法+学術的根拠のエッセンスを詰め込んだ一冊です。 □章構成 第1章 はじめに 第2章 上流品質向上のためのテスト 第3章 開発者テストの基本の基本 第4章 コードベースの単体テスト 第5章 単体テストの効率化――楽勝単体テスト 第6章 機能単位の単体テスト 第7章 リファクタリング 第8章 コードレビュー 第9章 統合テスト 第10章 システムテストの自動化 第11章 探索的テスト 第12章 まとめ――全体テストのデザイン 第13章 アジャイル・シフトレフトのメトリックス 第14章 アジャイルにおける要求仕様 第15章 開発者テストの実サンプル ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-新規プロダクト開発の事例から、一連の流れを学ぶ! プロダクト開発の重要性が認識されつつあるものの、 実際に新規プロダクトの開発に携わったことがある方はまだまだ少ないのではないでしょうか? 本書では、freee株式会社の「freeeプロジェクト管理」の開発事例から、 新規プロダクトの企画検討、ユーザー体験設計、設計と開発、プロダクトマーケティング戦略の 具体的な流れを解説! CodeZine/ProductZineでご好評いただいた連載を再編・加筆してお届けします。 【執筆者紹介】 宮田 善孝 freee株式会社 プロダクト戦略 プロダクトオーナー。 篁 玄太 freee株式会社 プロダクト戦略 UXデザイナー。 竹田 祥 freee株式会社 西日本開発本部 部長。 増田 茂樹 freee株式会社 プロダクトグロース テックリード。 熊倉 洋介 freee株式会社 プロダクトグロース エンジニア。 上村 功一 freee株式会社 プロダクト基盤 QAエンジニア。 伊関 洋介 freee株式会社 プロダクト戦略 プロダクトマーケティングマネージャー ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-12883-8)も合わせてご覧ください。 新学習指導要領によって小中高校でプログラミング教育が義務化されました。 しかし教育現場では本来の目的とされている子どもたちのアルゴリズム理解や理数能力の向上など,思考力や創造力を育てる授業とはほど遠いのが現状で,試行錯誤が続いています。 1970年代はじめ,パソコンの普及以前にアメリカのマサチューセッツ工科大学では世界最初の子ども用プログラミング言語『LOGO』が開発されていました。Scratchの母体となった言語です。そのLOGOを数少ない資料をもとに自作し,日本で最初に小学生にプログラミング教育を始めた小学校教師が著者の戸塚滝登氏です。戸塚氏は80年代初頭から20年間以上に渡ってプログラミング教育を実践しつづけ,日本の先駆者として知られています。 本書は,その教育を受けた子どもたちがどのようにプログラミングの授業を受け,その後どのように育ったのか,また,どのような職業についたのかを追跡調査した内容をまとめた書籍です。 身近な自然現象のおもしろさを探究するプログラミング理科,日常生活にひそむ算数や数学を探究するアルゴリズム算数など,戸塚氏は現在のプログラミング教育の源となった数々の教材と授業を開拓し,プログラミング授業によって生徒たちの探究心と好奇心を引き出し,思考力や創造力を育てました。その実践は新学習指導要領の中に姿を変えながら取り込まれています。 プログラミングによって養われる能力を子どもたちに身につけさせたいと望んでいる現場教師,自分の子どもにどのような教育を受けさせ,どうプログラミングと出会わせたらよいか悩んでいる保護者の方,そしてプログラミング教育の全体像を理解したいと望んでいる教育関係者と研究者の方にとって一助となる一冊です。
-
-本書は、組込みシステムやOSのような低レイヤーシステムの開発経験がないプログラマーが、自作OSをはじめるため解説書です。C言語を用いることが多い低レイヤーシステム開発について、本書ではRustを使います。RustはC言語と比較して、様々なモダンな機能やツールがそろっているだけでなく、C言語の長所である直接のメモリ制御が可能なため、高パフォーマンスな組込みシステム開発での利用が注目されています。本書はRustそのもの解説も含みますが、低レイヤーシステム開発特有のテクニックを中心に解説します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 基本を知るための「リファレンス編」と 現場のスキルを学べる「プラクティス編」が一冊に! 本書は、Figmaを使ってUIデザインをゼロから学べる本です。 「写真投稿アプリ」を題材に、実際のワークフローに沿ってアプリのデザインを作成します。 UIデザインの基礎知識はもちろん、Figmaならではの効率的なテクニックや エンジニアとのコミュニケーションを円滑にする方法など、 リアルな現場の情報を織り交ぜながら初学者の方が最初の一歩を踏み出せる構成になっています。 また、プロトタイピング、プラグイン、アニメーションなどにも踏み込んで解説しており、 Figmaを使ったことのある人にも活用いただける一冊です。 [本書の特長] ・Figmaの機能を網羅的に学習し、なおかつ実践方法も学べる ・基本操作に加え、生産性を上げる効率的なテクニックが身につく ・エンジニアが実装しやすいようなデザインを作成できる [こんな方にオススメ] ・Figmaをはじめて使う方 ・UIデザイナーを目指す方 ・エンジニアとの連携を改善したいデザイナー ・開発ツールとしてのFigmaを学びたいエンジニア ・現場のワークフローを把握したいマネージャー [目次] ・Introduction アプリ開発の工程、企画の確認など ・Chapter 1 基本的な操作 ・Chapter 2 生産性を上げる機能 ・Chapter 3 ワイヤーフレームを作成する ・Chapter 4 プロトタイプを作成する ・Chapter 5 詳細デザインを作成する ・Chapter 6 デザインのハンドオフ ・Chapter 7 ノンデザイナーのためのFigma ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ●プログラミングの基礎から学べる入門書 本書は代表的なプログラミング言語であるC言語の入門書です。これからソフトウェアの開発を始める人が、その基礎から実践的な開発例までを学ぶことができます。 C言語は古くからあるプログラミング言語で、高い記述性と生産性があり、現在でも広く使われています。とくにハードウェアを直接制御するプログラミングでは定評があります。また、文法がシンプルで、プログラミング学習の第一歩としても、よく選択される言語です。 現代の技術環境やコンピュータの利用方法を踏まえ、本書はプログラミングを初めて学びたい方のために書き起こされました。 ●文法と実践的なプログラミングの初歩を紹介 本書ではプログラミング環境の作り方から、変数、制御構文などの文法の基礎、ポインタによるメモリの取り扱いや関数の利用などを学べます。その仕上げとしてArduinoを使ったC言語のマイコンプログラミングをエミュレータを使って学びます。 ●細かなステップと練習問題で学ぶ 本書は基礎知識から実践までを細かなステップに分けて執筆されています。各単元の先頭では学ぶことの概要を知ることができ、見通しよくすこしずつ学習を進めることができます。また、練習問題もステップごとに用意され、学んだことを確認できるようになっています。実践的なプログラミングに入門するための第一歩としてお読みいただける一冊です。
-
-統計学の基礎から 統計モデリング、機械学習の入り口まで しっかり学べる! 【本書の概要】 データサイエンスやAIについて学ぶ上で欠かせない 統計学の知識をPythonを利用して 基礎からしっかり学べる書籍です。 【統計学の学習にPythonを利用する理由】 Pythonは統計学を学ぶのに便利なライブラリが多数用意されており データサイエンス、AIの研究開発に数多く利用されています。 統計学の基礎を学ぶのに格好のプログラミング言語です。 【対象読者】 ・統計学の初学者 ・統計学を学びたいエンジニア 【本書のポイント】 はじめて統計学を学ぶ方でも躓かずに学習できるよう 以下の3つをもとに丁寧に解説しています。 ・データの分析方法 ・分析の意味 ・Pythonによる分析の実践 【目次】 第1部 統計学をはじめよう 第2部 PythonとJupyter Notebookの基本 第3部 記述統計 第4部 確率と確率分布の基本 第5部 統計的推定 第6部 統計的仮説検定 第7部 統計モデルの基本 第8部 正規線形モデル 第9部 一般化線形モデル 第10部 統計学と機械学習 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 正統派の入門書!HTML Living Standardにきちんと準拠したHTML&CSSを学ぼう 本書は、HTMLとCSSの最新の仕様に準拠した、HTML&CSSの入門書です。 ※特にHTMLは2020年4月現在の最新のHTML Living Standardの仕様書ですべて確認済みの内容となっています。 本書では、HTMLとCSSをゼロから少しずつ学んでいきます。読者がつまづかないようにHTMLとCSSの小さなサンプルを書きながら学習していき、最後の章で総合的なサンプルを作成するスタイルになっています。 1つのWeb全体を作ろうとすると手順が長くなり、何を学習しているのか分からなくなったり、どこで間違ったか分からなくなってしまったりしがちです。そこで本書では、小さなサンプルで学習することで、「できた」の喜びを感じながら、少しずつ知識を増やしていけるようになっています。 また、サンプルには登場していない属性やプロパティの値などについてもしっかり説明がありますので、サンプルを書き換えて試してさらに経験を積んでみたり、読了後に疑問に思ったことを、改めて調べたりする使い方もできます。 そして、本書の解説は、表面的に「Webが作れればそれでいい」というものではありません。仕様にしっかりと準拠した使い方で、正しく、読みやすいを作れるように、サンプルを組み立てています。 本書で学習することで、基本的なHTML&CSSの使い方が身につくのはもちろんですが、「なぜそこに、そのHTML、CSSを使うのか」をきちんと説明できるような知識も、手に入れることができます。 また、本書は、すでにプロとしてWeb制作に関わる方が知識をブラッシュアップする際にもお勧めです。HTML 5.2がリリースされてから、すでに5年が経過しており、ふだん何気なく見ている一見普通のHTMLが、現在の最新の文法には合致していない旧式のものとなっている可能性もあります。本書ではそのような旧式となってしまった部分はすべて更新してあり、さらに巻末の特別付録として用意した「HTML全要素一覧」「HTMLの要素の分類」「HTMLの要素の配置のルール」は、中級以上の方にもご活用いただける内容となっています。 ※本書は、2018年11月発行の『よくわかるHTML5+CSS3の教科書【第3版】』をベースに、HTML Living Standardの仕様に合わせて多くの箇所を変更するとともに、最近のトレンドに沿って修正・加筆したものです。 <本書の構成> 第1章 はじめる準備 第2章 オリエンテーション 第3章 文法的なカタい話 第4章 全体の枠組み 第5章 テキスト 第6章 CSSの適用先の指定方法 第7章 内の構造 第8章 フレキシブルボックスとグリッド 第9章 ナビゲーション 第10章 フォームとテーブル 第11章 その他の機能とテクニック 第12章 をまるごと作ってみよう 付録 HTML全要素一覧/HTMLの要素の分類/HTMLの要素の配置のルール 第1章 はじめる準備 第2章 オリエンテーション 第3章 文法的なカタい話 第4章 全体の枠組み 第5章 テキスト 第6章 CSSの適用先の指定方法 第7章 内の構造 第8章 フレキシブルボックスとグリッド 第9章 ナビゲーション 第10章 フォームとテーブル 第11章 その他の機能とテクニック 第12章 をまるごと作ってみよう 付録 HTML全要素一覧/HTMLの要素の分類/HTMLの要素の配置のルール 大藤 幹(おおふじ みき) 1級ウェブデザイン技能士。大学卒業後、複数のソフトハウスに勤務し、CADアプリケーション、航空関連システム、医療関連システム、マルチメディアタイトルなどの開発に携わる。1996年よりWebデザインの基本技術に関する書籍の執筆を開始し、2000年に独立。 その後、ウェブコンテンツJIS(JIS X 8341-3)ワーキング・グループ主査、情報通信アクセス協議会・ウェブアクセシビリティ作業部会委員、ウェブデザイン技能検定特別委員、技能五輪全国大会ウェブデザイン職種競技委員、若年者ものづくり競技 大会ウェブデザイン職種競技委員などを務める。 現在の主な業務は、コンピュータ・IT関連書籍の執筆のほか、全国各地での講演・セミナー講師など。著書は『HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1 対策テキスト&問題集 Ver2.0対応版』『よくわかるHTML5+CSS3の教科書』『自由自在に動画 が作れる高機能ソフト DaVinci Resolve入門』(マイナビ出版)、『今すぐ使えるかんたんEx HTML&CSS 逆引き事典』(技術評論社)、『詳解HTML&CSS&JavaScript辞典』(秀和システム)など60冊を超える。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Node.jsでのWeb開発において「主要なフレームワークの使いみちや開発方法」「用途別にどれを使うのがベストか?」を解説。「これ一冊読めば、Node.jsの主要フレームワークが一通りわかる」という書籍です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Excel VBAは、非常に学びやすいプログラミング言語です。本書は、プログラミングがはじめての人でも理解しやすいように、かわいいイラスト満載で、Excel VBAの基本と考え方を優しく解説した教科書です。



![詳細!SwiftUI iPhoneアプリ開発 入門ノート[2022] iOS 16+Xcode 14対応](https://res.booklive.jp/20051075/001/thumbnail/S.jpg)









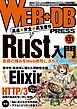


![作って学べる Unity本格入門 [Unity 2022対応版]](https://res.booklive.jp/1247062/001/thumbnail/S.jpg)
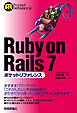



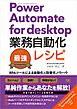



![[試して理解]Linuxのしくみ―実験と図解で学ぶOS、仮想マシン、コンテナの基礎知識【増補改訂版】](https://res.booklive.jp/1239786/001/thumbnail/S.jpg)

![R統計解析パーフェクトマスター(R4完全対応)[統計&機械学習第2版]](https://res.booklive.jp/1230842/001/thumbnail/S.jpg)

















![Microsoft Power Platformローコード開発[活用]入門 ――現場で使える業務アプリのレシピ集](https://res.booklive.jp/1215762/001/thumbnail/S.jpg)





























![[改訂2版]Oracleの基本~データベース入門から設計/運用の初歩まで](https://res.booklive.jp/1180182/001/thumbnail/S.jpg)





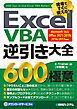
















![プロを目指す人のHTML&CSSの教科書 [HTML Living Standard準拠]](https://res.booklive.jp/1146843/001/thumbnail/S.jpg)

![世界でいちばん簡単な ExcelVBAのe本[最新第4版]Excel2021/2019完全対応版 ExcelVBAの基本と考え方がわかる本](https://res.booklive.jp/1143087/001/thumbnail/S.jpg)