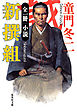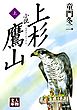童門冬二のレビュー一覧
-
- カート
-
試し読み
-
Posted by ブクログ
新撰組マニアでもなければ歴史好きでもない……いやむしろ疎い方。そんな新撰組初心者中の初心者が読むのにちょうど良い作品かと。
新撰組の成り立ちから崩壊までを、時代の背景に即して俯瞰できた感じ。
新撰組ってそもそも何だったのかということが、やっと分かったかな、とね。
……しかし、結局彼らは、完全な一枚岩となっていた時期はほぼ皆無だったというのが、驚き。
……あくまで“小説”なのだから心理描写などには多分に脚色が加えられているのは当然としても、結構に史実に基づいて書かれているのだろうと思われたこの作品に始終出てきた憎まれ役“車一心”が、実は完全な創作キャラだったというのには、さらに驚き(笑) -
Posted by ブクログ
童門さんの話は、いつも優しく、ハッピーエンドの匂いがするから結構好きだ。でも、箇条書きにする癖はあまり好きでない。
私は上杉景勝が好きで、ここ最近直江兼続の本をいくつか読んだ。童門さんらしく、直江はかっこよく、そして物語の半分を占める上杉景勝もかっこいい。
私も補佐役が向いていると思っている。決断力に欠けるからだ。補佐するということは、つまり補佐する相手がすべての責任を持ち守ってくれるということだと思う。部下の提案を受け入れ、信頼し、責任を引き受ける景勝がかっこいい。
ただ、以前読んだ立花宗茂より、下の話が多く、女の人がちょっと下品なのが気になった。この本の兼続は可愛いです。賢い奥さんに歯 -
Posted by ブクログ
ネタバレ小説作品としては、「??」と言わざるを得ないかな…。
“史実をフィクション仕立てに”といったコンセプトであるのだろうが、筆者の説明が俗っぽすぎて鼻白む箇所がいくつもあった。(分かりやすい例えではあるのだけど)
反面、
作品中に入れ込まれた“フィクション風に描かれた史実の情報”の多さは、相当なもの。(筆者なりの史実解釈と思われる)
少年少女向け読み物のように平易な文章で、これだけの情報を分かりやすくまとめるのは、さすが!!
……というわけで、日本史オンチな自分にとって、ささやかな歴史の勉強にもなった一冊♪
★3つ、7ポイント。
2015.01.14.図。 -
Posted by ブクログ
会社の研修で推薦図書を読みなさいということで、数あるビジネス書や自己啓発本のリストに歴史小説を発見。JFケネディが尊敬している日本人政治家らしい。
なるほど、江戸時代の士農工商の厳格な身分制度の時代に、身分の頂点である武士(藩士)という当時は疑うこともありえない考え方から、藩民の幸せのために奉仕する藩士たれという民主主義的な考え方への大転換を目指すという志の高い話である。
この改革は遅々として進まず、進んできたら信頼厚い家臣の背信が発覚したり、隠居したら元の古いしきたり重視の藩政に逆戻りしたり、とにかく改革を進めるには抵抗勢力が邪魔に入り、進んでも維持し続けるのも大変な苦労が伴い、高い志だけで