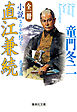童門冬二のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
2025.5.31
題名の通りの内容を、経験を基に著されている。五十歳以降の日々を有意義で、実りあるものにするためには『学び』が有効な方法であるとし、未知なものではなく既知なものから探すことを提案している。
また、都庁勤務時代の経験からたくさんの事を教えてくれています。
・よく『時間がない』という人がいますが、それは怠け心が言わせている言い訳に過ぎないことが大半です。たいていの『時間がない』は、『時間を作る気がない』と同義語なのです。時間は『ある、ない』ではなく『その事をやる気があるか、ないか』の事なのです。
・人に動かされ組織に埋没するのではなく、できる事なら人を動かし、組織を束ねられる主体 -
Posted by ブクログ
自分の歴史観を持つという事は、つくづく重要な事だと感じる。沢山の歴史を書籍で読んできて、学校の授業でも学んだりして、単に過去の出来事として記憶するのと、そこからどの様な教訓を得るか、自分ならどうしたかを考える事は全く違う。多くの書籍を読んでいると、書いた人物、書かれた時代によって内容が異なっている事は多くある。時代が進めば新しい発見や説を唱える者も出てくる。何を参考にしたか、見聞きしたかで、だいぶ捉え方も変わっているのがよく分かる。良い例かどうかは判らないが、次々とバージョンアップされる歴史ゲームでは、登場人物(武将)のステータスはコロコロ変わる。新しい文献や大河ドラマの様なものの影響を受ける