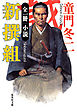童門冬二のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
ネタバレ江戸城の無血明け渡し前後、特に明け渡された後の東京への政策方針などを描いた作品。
高校時代に購入して、何度か読みました。
小説ではなく、(語り手である勝海舟を通して)小栗忠順から始まり、西郷隆盛、江藤新平、新門辰五郎、渋沢栄一といった人物を紹介・論評するスタイルで綴っています。
作品全体の鍵になっているのが、老中松平定信の時代から始まった七分積立金。
この備蓄金が幕府には残っており、使い道をどうするか?ということが話を進める上でのテーマになっています。
新政府軍との徹底抗戦を標榜していた小栗忠順は、本来、軍費として使いたいところでしょうが、「江戸市民への還元を目的として積み立てられた」とい -
Posted by ブクログ
ネタバレこの書籍が伝えるものから自分が注目したのは以下の2点。
①和魂洋芸の伝授
学問所へ学びに来る者たちに対しては、常に儒学をもととする東洋の道徳を叩きこむのと同時に、砲術などの西洋の技術も学ばせていたようだ。また、本などで学ぶだけの座学に留まらず、実際に海防施設などを見学させる実地調査も勉学の一つとして取り入れていたようである。
②「飛耳長目」という言葉を大切にしていた吉田松陰の姿勢
「吉田寅次郎ほど日本を歩き回った青年はいない」と佐久間象山に言わしめた人物で、著者の童門冬二氏は「『何でも聞いてやろう、見てやろう』という果敢なジャーナリズム精神(中略)単なる好奇心とは違う。聞いたこと、見たこと -
Posted by ブクログ
ネタバレ赤禰さんを扱った小説はあまりないので、読んでみた。
奇兵隊とタイトルにあるほど奇兵隊の同行を追うわけでもなく
淡々と赤禰さんの行動を作者が述べている、というような
時代小説の基本形で、あまり燃えるような展開や感情描写は
なかったように思う。
資料が多いとは言えない人物なだけに
丁寧に調べて書かれているのだろうし
だからこそ想像の余地があるのも良いところだと思うが
童門氏の見解が地文や赤禰の言葉に多分に入っており
けして中立な立場から描かれた物語ではない。
また、新選組との関わりがあったと聞けば
作家としてそこを膨らませたくなるだろうとは思うが
個人的には、だからと言って屯所に預かってしま -
Posted by ブクログ
小説上杉鷹山を読んでから、すぐに読んだので、読み物としては小説の方が情緒的で重厚で良かった感ありつつ、確かにダイジェスト版として鷹山というか治憲のすごさを把握できる本。
象徴的な箇所を引用致します。
「経済の低成長期の湿潤な時期においても、発想の転換をし、複眼の思考方法を持ち、歴史の流れをよく見つめるならば、閉塞状況の中でも、その壁を突破する方法はあるのだということを、鷹山の軌跡は如実に示している。」
「鷹山が甦らせたのは、米沢の死んだ山と河と土だけではなかった。彼は、何よりも人間の心に愛という心を甦らせたのである。現在の世でもっとも欠けているのは、この愛と労りと思いやりの心であろう。この心を -
Posted by ブクログ
・攘夷のトップは船に乗せ、大阪湾から陸の防護を見せ、贅沢合戦をしていた奥の院は庶民の場に遊ばせる。何を見せ、その人の世界を覆すか、その気にさせるか。
・京都、大阪の攘夷過激派の若者が幕府方(新撰組など)とぶつかり、人財が無為に失われるので一時攘夷の若者を北海道に移しのちに海軍に組み込もうとしていた。新撰組の池田屋襲撃がなければ幕府も志士側を承諾していた。
・凡人と非凡の差は、職責を超える仕事ができるか、できないか。また、求められたらそういう職責を超える仕事をやる勇気があるか、ないか。
・海舟が唯一師と公言した喜仙院(くじの祈祷師)。「女の目とすっぽんの目が屈託になってしまった。それは、恐 -
Posted by ブクログ
元々 黒田官兵衛孝高については詳しくない。増して隠居後の如水となると 号の名くらいは知っていても そもそも一体どうして急に隠居を決め込んだのかについてさえ 何の知識ももたずに過ごしてきた。あんなに明晰な頭脳をもった人が まだ充分働けそうなのに……と その「明晰な頭脳」こそが彼の宿痾だったことを知ったのは 竹中半兵衛を学ぶようになってからである。この物語は私が初めて特に触れる官兵衛であり 題名通り隠居後の姿を描いたものだから その現役時代については未だ疎いということになる。
物語は 新本拠地となった筑前(福岡県)福崎の地名を 一族の故地:備前(岡山県)福岡の再興をかけて「福岡」に改めたい如水と -
Posted by ブクログ
ネタバレ■太陽系における一個の彗星たり
書籍「坂本龍馬に学ぶ」(新人物文庫・堂門冬二・287頁)から。
以前から、堂門冬二さんの歴史人物作品が好きで
機会あるごとに、彼の作品は読んでいたが、
今回は、NHK大河ドラマ「龍馬伝」にあわせて、
この作品を読んでみた。
龍馬を、ワンフレーズで表現したい、と考えていた私には
「坂本龍馬は、太陽系における一個の彗星たり」が心に残った。
「維新土佐勤王史」に書かれている、
龍馬と武市半平太との関係らしい。
「坂本龍馬は、太陽系における一個の彗星たり。
故に必ずしも瑞山(武市半平太)を中心とする軌道を
回転するものにあらずして、時には遠ざかり、時には近づく。
又こ












![[新装版]勝海舟の人生訓](https://res.booklive.jp/125738/001/thumbnail/S.jpg)