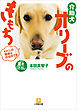福祉 - セール作品一覧
-
4.0もうイライラしない もっとやさしくなれる 認知症の人に伝わりやすい声かけで、コミュニケーションがラクになる! 認知症研究の第一人者が教える、すぐに使える「言いかえ」フレーズ 「何度も言っているでしょ?!」 「約束したんだからちゃんとやって!」 「いいかげんにして!」 認知症の人と話していると、イライラしてついこんなふうに言ってしまうこともあるのではないでしょうか。 しかし認知症の人にその言い方ではうまく伝わらないため、同じことを繰り返してさらにストレスが大きくなってしまいます。 大切なのは、認知症の人の心を理解して、伝わりやすい言葉かけをすること。 認知症の人に伝わりやすい言葉がけができると、コミュニケーションが改善され、結果的に家族もラクになります。 本書では、具体的な場面ごとに、○✕形式で認知症の人にスッと伝わる言いかえフレーズを紹介します。 著者は認知症研究の第一人者で、40年間にわたって認知症の人の心理学を研究してきました。 その研究をもとに、認知症の人とうまくコミュニケーションが取れる話し方をわかりやすく紹介していきます。 また、認知症の基礎知識や、実際によくある質問へのQ&Aも掲載。 普通に読むことはもちろん、自分に必要な部分だけつまんで読むなど、事典のような使い方もできます。 <掲載されている言いかえフレーズ例> CASE01 同じことを何度も質問する ×さっきも聞いたでしょ? ⇒ 〇カレンダーにメモしておくね CASE05 外出するのを嫌がる ×病気になっちゃうよ ⇒ 〇気が向いたら散歩にでも行こうか CASE08 同じものを何度も買ってくる ×もう買わないで! ⇒ 〇同じものがたくさんあるからメモしておこうね CASE12 無気力、無趣味になる ×今からそんなに無気力でどうするの! ⇒ 〇音楽でも聴いてみる? CASE17 薬を何度も飲もうとする ×もう飲んだでしょ ⇒ 〇(サプリメントを渡して)これを飲もうね CASE24 町内を歩き回って迷子になる ×どこに行ってたの!? ⇒ 〇そろそろご飯の時間だから帰ろうか CASE29 食べられないものを口に入れる ×こんなもの食べてはダメ ⇒ 〇こっちのほうがおいしいよ CASE30 家族のことがわからなくなる ×ふざけないで! ⇒ 〇あなたの息子の○○です
-
-【ご注意】※この電子書籍は紙の本のイメージで作成されており、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 手話を学ぶ人に最初に読んでほしい一冊。 本書は、ろう者の言語である「日本手話」の基礎表現や文法、ろうの文化など、手話を学ぶ上で知っておきたい基礎知識を、小中学生向けにやさしく解説する本です。 アヤ・セナ・ユイの3人のろう学校の子どもたちが、会話と写真で楽しく手話について紹介。二次元コードで手話動画を何度でも見られるので、手や顔、体の動きもよくわかります。 「そこが知りたい手話Q&A」、手話を使ったゲーム、コラム、50音や数字の指文字など、手話についての情報も満載。 初めて手話を学ぶ大人の方にもぜひ読んでいただきたい1冊です。 ※本書に掲載されている二次元バーコードは、デバイスの機種やアプリの仕様に よっては読み取れない場合もあります。その場合はURLからアクセスしてください。
-
4.5【ご注意】※この電子書籍は紙の本のイメージで作成されており、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 キャリアを活かすボランティア、始めよう! 近年、注目を集めているプロボノ。プロボノとはラテン語で「公共善のために」を意味する「pro bono publico」の略で、各分野の専門家が持つスキルや経験を活かして社会貢献するボランティア活動や、そこに参加する人々を指します。本書は、キャリアのターニングポイントを迎えた50代以上の社会人をはじめ、毎日の生活にどこか物足りなさを覚えている全ての人々にお届けしたいプロボノのマンガ版入門書です。「社会の役に立ちたい」「お金よりも充実感を得たい」と思いつつも何から始めてよいか迷っている方々、ぜひお読みください。
-
4.350万部超の大ベストセラー『80歳の壁』著者の最新作! 92歳の母を持つ高齢者医療の医師がいまいちばん伝えたいこと [「認知症=人生の終わり」ではない][わがままぐらいが愛される!][お金をたくさん使って思い出をつくろう] 「壁」の先にある人生最後の“ごほうび”の時間! 【健康】【お金】【生活習慣】【介護】人生100年時代、気楽に「老い」を楽しむコツ 60歳以上の高齢者や90代の親を持つ人は必読!
-
3.542万部超の大ベストセラー『80歳の壁』著者の最新作! 歳を取れば取るほどに、将来に対する不安から「食事や嗜好品、お金などを節制して、老後に備えなければならない」と考える日本人が、非常に多いように感じます。 でも、その考えには真っ向から反対です。 むしろ60代からは「やりたい放題」に生きることこそが、若々しさを保ち、頭の回転も鈍らせないための秘訣だからです。 「心」、「体」、「環境」が激変する60代が第2の人生を楽しむためのターニングポイントです。 変化に対する正しい対応策を知ることで、必要以上に将来を怖がらず、みなさんが自分の生きたいように生きられることを心から願っております。
-
3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 病院ではなく、住み慣れた自宅で、人生の最期をむかえる時代がやってきます。自宅で納得して最期を迎えるための必読書です。 ●超高齢化が進む中で、病院ではなく、住み慣れた自宅で、人生の最期をむかえる時代がやってきます。自宅で納得して最期を迎えるための必読書です。 ●マンガ……「母を看取って」「命が燃え尽きる死はこうして訪れる」「17年間の闘病の辛さを忘れさせてくれた讃美歌」「最期まで自分の意思を貫き通した父」「一人暮らしの父親の最期を看取った息子たち」……自宅で迎える人生の最期を、徹底取材で実例マンガ化。 ●実用情報……「自分の最期をどうすごしたいか、周囲に知らせよう」「痛みや苦しみをやわらげるには」「最期の3か月にかかる在宅医療費」「在宅医の探し方・選び方」「ひとり暮らしの療養を支える介護サービス」……自宅での最期を後悔なく迎えるために必要な情報を紹介。 ●1000人以上の最期を看取ってきた医師の千場純先生がアドバイス。マンガ担当のたちばないさぎさんは病院のスタッフとして、数々の看取りの現場の取材にあたっています。 千場 純(チバジュン):三輪医院院長。医学博士。1975年名古屋大学医学部卒業後、横浜市立大学附属病院第一内科、国立横須賀病院(現横須賀市うわまち病院)内科第一医長、医療法人社団聖ルカ会パシフィック・ホスピタル院長などを経て現職。在宅死率全国第1位(およそ4人に1人)の神奈川県横須賀市で「在宅看取り」の普及に取り組む。「在宅看取り医」として今までに1000人以上を看取り、2019年1月には日本医師会が主催する「赤ひげ大賞」を受賞。各地での講演活動も活発に行っている。医療を中心とした地域作りに力を入れており、地域住民の交流の場「しろいにじの家」を開設している。さらに病院スタッフとしてマンガ家を採用し、患者の体験談をマンガ化して病院発行の冊子に掲載するなど、情報発信にも努める。 1968年神奈川県横須賀市生まれ。現在も横須賀在住。1992年漫画家デビュー後、少女漫画誌、女性誌、猫漫画誌などに作品を多数掲載。宝塚大学東京メディア芸術学部マンガ分野非常勤講師、日本漫画家協会会員、日本マンガ学会会員、日本在宅医療連合学会会員。2016年より社会福祉法人心の会三輪医院非常勤職員(地域支援員)として、患者さんの人生を伝える漫画やイラストを作成し、病院が発行する冊子などで発表している。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 不安や不満、ためらいなく親の介護をする自信はありますか? 本書を読めば「私にもできる」ヒントと勇気が見つかります。 「病院で死ぬ」時代は終わり、 誰もが介護にかかわる時代がすぐそこまできています。 介護も医療も看取りも自宅で、地域でと病院を出されても、 何の不安も不満もなく老親をみる、と胸を張って言える人がいるでしょうか。 先が見えない介護は、「忍耐」と「辛抱」、 その上での「優しさ」だけでは、介護する側とされる側も疲弊するばかりです。 家族に介護が必要になったとき、 たいせつなことは無理なく長く続けられること。 そのためにはストレスをためない、 犠牲にならずに生活を営むことが重要です。 誰に、どんなふうに手助けを頼めば良いのか。 どのように親と向き合えば良いのか。 困りごとの原因をつきとめて 民間のサービスや公的サービスを組み込むことです。 各種施設の見極め、 そして認知症状が出始めたかも? というときの対応方法、 離れて暮らす親の場合の対応方法など、 漠然とした不安と疑問の原因を紐解きながら、在宅でできる納得の介護を考えます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 どこの誰に、どのタイミングで何を聞けばいいのか。 素早い対応が大切。 入院・介護の「はじめに」必要な情報にしぼり紹介します。 「病院で死ぬ」時代は終わり、 介護も医療も看取りも地域で自宅で、 という時代に変化しつつあります。 「介護に関する世論調査」では、 家族に介護が必要になった場合に困るのが 「肉体的負担」、「精神的負担」、「経済的負担」。 遠方に暮らす老親や、 認知症症状が表れ始めた親を どう支えれば良いのか、を苦慮する声です。 これら負担を軽減するには、 介護を家族だけで背負わず 介護保険制度を理解し、利用する、にほかなりません。 ところが「介護支援」についても、 「在宅医療」についても、 内容もシステムもわからない、 どんな手続や準備をすればいいのか、 どこに尋ねれば良いかもわからない、 そもそも行政とあまたある事業所の区別さえもつかない、というのが実情です。 本書では在宅介護を行ううえで、 すぐに役立つ「知っておくべき制度の利用方法と費用」について、 入院時からわかりやすく紹介します。 待っているだけでは、誰も手を差し伸べてはくれません! 服部 万里子(はっとりまりこ): 一般社団法人日本ケアマネジメント学会副理事長。NPO渋谷介護サポートセンター事務局長。服部メディカル研究所所長。公益社団法人長寿社会文化協会理事長。 早稲田大学卒。一般企業で勤務の後、病院に勤務しながら看護師資格を取得。 10年間勤めた病院を退職の後、高齢者医療看護福祉のコンサルティング事業(服部メディカル研究所)を看護師3名で立ち上げる。 1999年にNPO渋谷介護サポートセンターを設立し、2000年より居宅介護支援単独事業開始、現在もケアマネジャーとしても活動。 2011年、産業能率大学経営情報学研究科卒(MBA取得)。 東京医科歯科大学非常勤講師、大妻女子大学現代社会研究専攻 非常勤講師、和歌山県立医科大学大学院 非常勤講師。 看護師、社会福祉士、介護支援専門員。 黒田 尚子(くろだなおこ):CFPR 1級ファイナンシャルプランニング技能士。 立命館大学法学部修了後、1992年(株)日本総合研究所に入社、SEとして、おもに大学関係のシステム開発に携わる。 在職中に、自己啓発の目的でFP資格を取得後に同社退社。 1998年、独立系FPとして転身を図る。 現在は、各種セミナーや講演・講座の講師、新聞・書籍・雑誌・Webサイト上での執筆、個人相談を中心に幅広く行う。 CNJ認定 乳がん体験者コーディネーター、消費生活専門相談員。
-
-住み慣れた家で安らかな最期を迎えるには? 最期のときは、住み慣れたわが家で穏やかに迎えたい。 親や家族もそうして看取りたい。 多くの人の切実な願いは、団塊世代が後期高齢者になり「多死社会」を迎えるこれから、かなえることができるのか? 「できる」、と著者は答える。 わが家での看取りは病院よりお金がかからない。 ちゃんと家で亡くなれば、警察沙汰にはならない。 家族に迷惑をかけずにひっそり死ぬという考えこそ、実はいちばん迷惑。 既婚者で子どもがいたとしても最後はひとりで死ぬ覚悟が必要。 ひとりで死ぬことと、さみしく死ぬことは違う。 長生きすると、ラクに死ねる。 「あの世」はあると思ったほうが人生を終(しま)いやすい。 ――など、在宅看取り医として、多くの亡くなった方から教わった大切なことを伝える一冊。
-
-私たちが本気でめざしてきたのは、「介護業界のディズニーランドになること」 仕事と人生が楽しくなる職場をつくる――。 筒井社長の想いと志が、スタッフの方々のキラキラした姿から、しっかり伝わってきました。 たんぽぽ介護センターには、いつも笑顔があふれています。 施設を利用されるお客様も「いろいろなデイサービスを利用したけれど、こんなに元気になれる施設はない」と感動してくれます。 その声が、私たちにとってはとても喜ばしいことです。 1999年に事業をスタートして以来、私たちが本気でめざしてきたのは「介護業界のディズニーランドになること」だからです。 さらに、ディズニーランドのキャストの9割はアルバイトが占めているといわれますが、私たちたんぽぽ介護センターも、スタッフのほぼ9割がアルバイトやパート。 ディズニーランドと同様、スタッフが輝き、イキイキと働ける環境が必要です。 その目標を実現するために、私たちが歩んできた中で培った考え方やしくみを、本書では紹介しています。 本書が、たくさんの笑顔と感動を生み出す一助となれば、著者としてこれほど嬉しい事はありません。 ■著者 筒井健一郎
-
-親がなくなったあとの生活には、どのくらいお金がかかるのか、障害のある子どもにお金をどう残して渡せばいいのか、だれが管理してくれるのか。 本書では、親なきあとの経済的な問題にフォーカスして、くわしく解説していきます。 第1部では、ひとり暮らしになった障害のある子どもに入ってくるお金と、必ず出ていくお金にはどんなものがあるか。 また、どのようなサポート体制があるのかを紹介。 第2部では、生活のために必要なお金が、確実に本人のために使われるようにするにはどんな管理方法があるのかを紹介します。「親あるあいだ」に準備すべきことを、具体的な事例を参考にしながら考えます。
-
4.3肩書き無き県庁職員の痛快「お役所改革」記。 佐賀県庁職員でありながら、行政発信の救急医療改革を全国に広める活動を続けている著者は、県庁舎の席に座っていることも少なく、「そろそろクビか?」「はみ出し過ぎ」と揶揄される毎日。それでもくじけずに目的に向かって歩いていくのは、「助けを求める人がいる」「助けられる命がある」という現実を実際に目にしているからに他ならない。 自ら救急車に乗り込み、救急搬送に時間がかかるのは受けいれる病院探しのシステムが確立されていないことが原因と知った彼は、周囲の反対と冷たい目にもひるまず、県内の全救急車両にiPadを配備、病院とのネットワークを構築し、全国で初めて救急搬送時間短縮に成功する。 また、協力する人がほとんどいない中でドクター・ヘリ導入に奔走し、すでに多くの命を救うことに成功している。 歴史好きで、幕末の志士に魅せられ、地元・佐賀をこよなく愛する著者に、県庁での肩書きはない。それでも、全国から講演を依頼され、「お役所仕事」変革のために走り続けている。 お役所版「半沢直樹」のような、痛快なエピソードも満載。全国の公務員、またあらゆるビジネスマンの心に火をつける、情熱のノンフィクション!
-
-「老人=良い人」は過去の話。電車で席を譲ろうとして睨まれたり、道で挨拶をしてキレられたり…。最近の老人は、「賢くて穏やか」とは限らない。周囲を見回せば、気分を害する変な老人が大勢見つかる。問題は、こんな「ダメ老人」にどう対処するか。 ダメ老人を舐めてはいけない。侮ると痛い目に会う。自分の年齢に甘えて傍若無人な振る舞いをするのがダメ老人だ。特に、自己満足のボランティア老人には要注意! 自分の間違いを疑わないので始末に負えない。 「最近の老人はこんなにヒドいのか!」と思わず声が漏れる、驚きの観察記。
-
-電子書籍は障害者の読書をどう変えるか。 本書では、まず視覚障害者の読書環境の実態と、電子書籍の普及がそれをどう変えていくのかについて述べていきます。 電子書籍のネット書店、ソフトウェア、機器の普及が進んでいます。読書環境は大きく変化してきています。 視覚障害者の世界では、以前より全視情協が提供するサピエというウェブサービスを通じて、点字データやデイジーと呼ばれるデジタル録音図書にアクセスして読書をするという環境がありました。しかし、サピエには十数万のデータが揃っているとはいえ、晴眼者が利用できる本の数に比べれば、ごく一部に過ぎません。 電子書籍の普及のスピードはめざましく、紙の単行本が発行されると同時に電子書籍を利用できる状況になりつつあります。これにより、視覚障害者の読書環境にも大きな変化がもたらされるのではと期待されています。 これからの電子書籍がどうあれば、視覚障害者によりよい読書環境を提供できるのかを、機器環境や仕様の問題だけでなく、出版社と著者との関係、法整備の問題にまで踏み込んで提言をしています。
-
4.5
-
-密着取材してきた著者が、犬のきもちになりきって綴った、「オリーブ」一人称の半生記。 わたしの名前はオリーブ。盲導犬より介助犬に向いているといわれた、3歳半のラブラドール・レトリーバーです。ユーザーの山口さんは車いすに乗った千葉市の職員で、毎日一緒にご出勤。でもこれまでには、子犬時代からの訓練の日々があったのです―。働く犬の事情に精通し、オリーブに密着取材してきた著者が犬のきもちになりきって綴った、オリーブ一人称の半生記。元気でかわいい写真を満載し、小学校高学年からひとりで読める、絵本感覚の書き下ろし文庫を電子化! この電子書籍の売り上げの一部は、公益財団法人日本盲導犬協会、社会福祉法人日本介助犬協会に寄付されます。
-
3.6
-
4.2カンボジアの児童買春をなくすため、生活に困った親がお金目当てに子どもを売らないですむように、新しい産業を興した「かものはしプロジェクト」の村田さん。進路選択にさしかかった高校生が、大学生や社会人と互いの思いを真剣に語り合う「カタリ場」を創設した今村さん、竹野さん――本書に登場する社会起業家の人たちの使命感の強さ、バイタリティ、発想の豊かさには、驚かされるばかりです。こんな熱い働き方、生き方をしている人がいる!どうすればこんな活動ができるのか?社会起業家として生きていくには?本書は社会起業家の今とこれからが掴める、格好の“教科書”です。