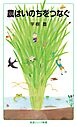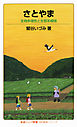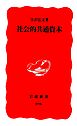ビジネス・実用 - 岩波書店作品一覧
-
4.3つまずきの原因を「読解力が足りない」で済ませては支援につながらない.著者らは学習の認知メカニズムにもとづいて,学力の基盤となることばの知識,数・形の概念理解,推論能力を測るテストを開発.その理念と内容,実施結果を紹介し,それで測る力が算数・国語の学力とどのような関係にあるのかを質的・量的に検討する.※この電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており,タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています.また,文字だけを拡大すること,文字列のハイライト,検索,辞書の参照,引用などの機能は使用できません.
-
-さまざまな現象を合理的に分析するためには,現象の記述・モデル化と,そこからえられる方程式の計算が要求される.結果の信頼性は,その手法において数学の原理を活かせるかにかかっている.より深い理解に役立つよう選択した具体例から,微分方程式で表される問題の導き方,数値的に解く方法を最低限の予備知識で示す.※この電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており,タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています.また,文字だけを拡大すること,文字列のハイライト,検索,辞書の参照,引用などの機能は使用できません.
-
4.0線形計算とは行列に関する数値計算法であり,応用数理において重要な役割を果たす技術体系である.連立一次方程式と固有値問題という2つの話題を中心に数学的基礎を解説.同時にDM分解やマルチグリッド法の収束性解析,共役勾配法の原理など数学的に興味深いテーマを取り上げ詳説.線形計算の数学の魅力と真価を示す.※この電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており,タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています.また,文字だけを拡大すること,文字列のハイライト,検索,辞書の参照,引用などの機能は使用できません.
-
-
-
4.4
-
-月刊誌『科学』は1931年に石原純、寺田寅彦らによって創刊された総合科学雑誌です。第一線の研究者がみずから執筆し、科学に関心を寄せる多様なバックグラウンドの読者に向けて、高度な研究成果を紹介することが、創刊以来変わらない本誌の大きな特徴です。純粋に知的好奇心をかきたてる話題から、社会との関わりの深い話題まで、幅広く取り上げます。 ※本電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており、タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大すること、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能は使用できません。
-
4.0
-
-
-
-
-
-
-
4.1晩年のニーチェ(一八四四―一九〇〇)がその根本思想を体系的に展開した第一歩というべき著作。有名な「神は死んだ」という言葉で表わされたニヒリズムの確認からはじめて、さらにニーチェは、神による価値づけ・目的づけを剥ぎとられた在るがままの人間存在はその意味を何によって見出すべきかと問い、それに答えようとする。
-
4.0【特集1】ふたつの戦争、ひとつの世界 2022年2月24日、世界中が「いま、なぜ」と問うなか始まったロシアのウクライナ侵攻。その終わりはいまだ見えず、戦禍は拡大している。2023年10月7日に起こったハマスの襲撃が引き金となり、イスラエルはガザ地区への凄惨な攻撃を開始した。人質解放のための束の間の「戦闘休止」は平和に結実するのだろうか。 私たちが生きている世界では、いまも人が殺し、殺されている。その現実を直視しつつも、けっして平和をあきらめないために。停戦への道と世界のこれからを考える。 【特集2】ディストピア・ジャパン 世界各地で戦火がやまないなか、日本はそれでも平和を享受している――。それは事実なのか? 上がらない賃金と長時間労働、ジェンダーギャップ指数125位、横行するハラスメント、G7最下位の報道の自由度、根深い外国人差別……。 同じ人間であるにもかかわらず、人間が貶められる現実が広がってはいないか。それは「平和」なのだろうか。私たちの足もとのディストピアを見つめる。 ※本電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており、タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大すること、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能は使用できません。
-
4.3
-
4.3柳田国男・渋沢敬三の指導下に、生涯旅する人として、日本各地の民間伝承を克明に調査した著者(一九〇七―八一)が、文字を持つ人々の作る歴史から忘れ去られた日本人の暮しを掘り起し、「民話」を生み出し伝承する共同体の有様を愛情深く描きだす。「土佐源氏」「女の世間」等十三篇からなる宮本民俗学の代表作。 (解説 網野善彦)
-
4.5
-
4.5ウチダが増えてニホンが消える!? 江戸時代は万能薬だった? ザリガニスープ? 青白黄色に変わる仕組みは? 脱皮に隠された秘密とは? 新種を見つけたらどうする? 驚きの生態から知られざる歴史まで、日本に生息する全3種を多数のカラー写真で徹底解剖。ザリガニ博士が教える〈採り方・飼い方・増やし方〉ガイド付き。
-
4.0世界有数の森林国,日本.その豊かな森は,かつて人の営みとともにありましたが,次第に放置され,今では厄災につながるケースも増えています.そんな現状を改善し,豊かな森を取り戻そうとする取組が,いま各地で行われ始めています.歴史をふまえ,環境問題の視点も取り込み,森と人とのよりよい未来をどう作るかを論じます.※この電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており,タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています.また,文字だけを拡大すること,文字列のハイライト,検索,辞書の参照,引用などの機能は使用できません.
-
4.1文化が違えばことばも異なり、その用法にも微妙な差がある。人称代名詞や親族名称の用例を外国語の場合と比較することにより、日本語と日本文化のユニークさを浮き彫りにし、ことばが文化と社会の構造によって規制されることを具体的に立証して、ことばのもつ諸性質を興味深くえぐり出す。ことばの問題に興味をもつ人のための入門書。
-
4.5意識と脳の関係性の謎に立ち向かうお膳立ては整いつつある! これまでの研究における発展と限界,トノーニによって提唱されて意識の理論として有望視されている統合情報理論,そして著者が取り組んでいるクオリア(意識の中身)を特徴づける研究アプローチを解説.意識研究の面白さ,研究者が抱いている興奮を伝える.
-
-
-
4.0峻厳な山のように私たちを寄せつけようとしない現代の数学。数学とは一体どんな学問なのだろうか。数学者とはどんな人たちなのだろうか。研究の最前線にいる幾何学者が、日々の研究や教育、フィールズ賞をめぐる思惑、現代数学の動向などについて軽妙に語りながら、私たちには伺い知ることのない数学者の世界をいきいきと画き出す。
-
4.11941年にナチス・ドイツの侵攻を受けたソ連白ロシア(ベラルーシ)では数百の村々で村人が納屋に閉じ込められ焼き殺された。約40年後、当時15歳以下の子供だった人たちに、戦争の記憶がどう刻まれているかをインタビューした戦争証言集。従軍女性の声を集めた『戦争は女の顔をしていない』に続く、ノーベル文学賞作家の代表作。(解説=沼野充義)
-
4.1
-
4.0
-
4.5周波数の高い音が低く聞こえる.右にある音が左に聞こえる.同じ音の聞こえ方が変化する.存在しない音が聞こえる.そんな不思議な錯聴を体験できるウェブサイト〈イリュージョンフォーラム〉を知っていますか.聴きどころの紹介から,錯聴の背後にある脳内の音の処理メカニズムの解説まで,耳と脳にビンと響く一冊です.
-
3.9
-
4.7
-
3.0
-
4.4
-
4.1「これ食べたら死む?」どうして多くの子どもが同じような、大人だったらしない「間違い」をするのだろう? ことばを身につける最中の子どもが見せる数々の珍プレーは、私たちのアタマの中にあることばの秘密を知る絶好の手がかり。言語獲得の冒険に立ち向かう子どもは、ちいさい言語学者なのだ。かつてのあなたや私もそうだったように。
-
4.3
-
4.0
-
4.1『徒然草』の面白さはモンテーニュの『エセー』に似ている.そしてその味わいは簡潔で的確だ.一見無造作に書かれているが,いずれも人生の達人による達意の文章と呼ぶに足る.時の流れに耐えて連綿と読みつがれてきたこのような書物こそ,本当の古典というのであろう.懇切丁寧な注釈を新たに加え,読みやすいテキストとした.※この電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており,タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています.また,文字だけを拡大すること,文字列のハイライト,検索,辞書の参照,引用などの機能は使用できません.
-
4.6
-
3.8「ほんとうに悲惨なのは、誰もほしいものを手に入れていないということだ」──若者の暴力、増加する自殺者、行き迷う「いい子」たち。自分の欲しいものが分からず苦しむ私たちは、どうすれば「生きる意味」を見いだせるのか? 文化人類学者として世界を旅した著者が、自らの体験をふまえて熱く語る、骨太の生き方指南!
-
3.0
-
3.5
-
3.9
-
3.8
-
4.2営利の追求を敵視するピューリタニズムの経済倫理が実は近代資本主義の生誕に大きく貢献したのだという歴史の逆説を究明した画期的な論考。マックス・ヴェーバー(一八六四‐一九二〇)が生涯を賭けた広大な比較宗教社会学的研究の出発点を画す。旧版を全面改訳して一層読みやすく理解しやすくするとともに懇切な解説を付した。
-
3.0古代の中国から伝わった漢字は,日本語の内部に深く入りこんだ.はなしことばを視覚化することを超え,漢字は日本語そのものに影響を与えつづけてきた.『万葉集』から近代まで,漢字に光をあてて歴史をたどろう.漢字がつくるさまざまなかたちを楽しみながら,文字化の選択肢が複数ある,魅力的なことばを再発見する.
-
4.2自分の人生に意味はあるのか,自分に存在価値はあるのか….誰にでも訪れる「むなしさ」.便利さや快適さを追求する現代では,その感覚は無駄とされてしまう.しかし,ため息をつきながらも,それを味わうことができれば,心はもっと豊かになるかもしれない.「心の空洞」の正体を探り,それとともにどう生きるかを考える.
-
4.8
-
-
-
5.0
-
4.5岩波文庫版『失われた時を求めて』(全14冊)の完訳を達成したプルースト研究第一人者が作品の核心に迫る解説書.この不世出の大長編は,なにを,どのように語った作品なのか.全体の構成,特長,勘所を分かりやすく読み解く.魅惑の読書体験へといざない,全篇読破に挑戦する人には力強い羅針盤となるスリリングな一冊.
-
-
-
3.8
-
3.5
-
4.3「冷凍庫に入れる」はput it in the freezerなのに「電子レンジに入れる」だとput it in my microwave ovenとなる.どういう論理や感覚がこの英語表現を支えているのか.著者が出会ってきた日本人の英語の問題点を糸口に,従来の文法理解から脱落しがちなポイントをユーモア溢れる例文で示しつつ,英語的発想の世界へ読者を誘う.
-
4.4アフリカ各地での実地調査をもとに,文化人類学の神話研究の成果をとり入れて描き出されたアフリカの神話的世界.異なった地域の原住民に伝わる神話を比較・分析し,神話の「伝播」と「変身」,さらに,その「構造」を考察する.原住民の世界を内側から理解することを通して,私たちの世界との関係,「第三世界」の真の意味を明らかにする.
-
3.0
-
3.5
-
3.9
-
5.0
-
4.0