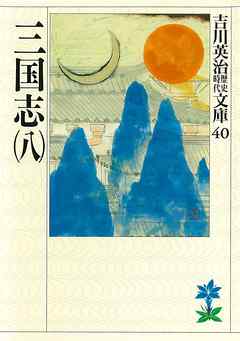あらすじ
曹真をはじめ多士済々の魏に対して、蜀は、玄徳の子劉禅が暗愚の上、重臣に人を得なかった。蜀の興廃は、ただ孔明の双肩にかかっている。おのが眼の黒いうちに、孔明は魏を叩きたかった。――かくて祁山の戦野は、敵味方五十万の大軍で埋まった。孔明、智略の限りを尽くせば、敵将司馬仲達にもまた練達の兵略あり。連戦七年。されど秋風悲し五丈原、孔明は星となって堕ちる。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
孔明の死によって三国志の物語が完結したという最終巻。呂布や董卓の頃とは大きく戦の形が変わって、知謀によって進むことから、勇猛な武将が少なくなってしまったという点は、少々寂しくもある。
孔明の歿後、晋が統一するまでは淡々と描かれており、作者がいかに孔明に執心していたかがよくわかる。
これほどまでに魅力的な歴史譚は世界でも皆無だといっても良いんじゃないだろうか。
Posted by ブクログ
2回目の再読。歴史小説として純粋に面白く、2週間で全巻読破。改めて、三国志の主役は劉備ではなく、孔明(と曹操)であることを認識。
・「三国志」は晋の時代に陳寿により記された魏、呉、蜀の国別の史書の総称。基本は史実をまとめた本だが、多少の虚構あり。その後、明の時代に、「三国志」やその他の伝承本等をもとに歴史物語として作られたのが羅貫中の「三国志演義」。こちらは7割が事実で3割が虚構とも言われている。「吉川三国志」は「三国志演義」をもとに、日本人向けに一部脚色も加えながら書かれたもの。
Posted by ブクログ
最終巻は、諸葛孔明の章といえる。
戦の天才でありながら、平凡であることに誇りをもち、劉備玄徳の願いを実現することだけを考えつづけた真っ直ぐさに感銘を受けた。
吉川英治の三国志、大作であり時間がかかってしまったが、読むことができてよかった。
Posted by ブクログ
いえいややっぱりおもろいです、何度読んでも。
こういうエンターテインメント、やっぱり皆好きなんでしょう、当方もご多分に漏れずですけれども。
解説で曹操と孔明の話、と整理されていましたが、その通りかと。でも個人的には、悪役的要素も兼ね備えている曹操が一番面白いキャラかと。
またいつか再読するんやろうなぁ。
Posted by ブクログ
初めて読んだのが高校1年の時で、
もう30年も前なのか。
私の趣味はこの三国志から始まりました。
とにかく三国志に関する書を探して読みました。
そこから楚漢・春秋戦国と時代を遡って、
宮城谷昌光さんの「重耳」に出会い決定打。
今も興味が尽ることなく楽しい趣味になってます。
今はインターネットですぐに調べられますけど、
当時は本を探す事が楽しみの1つでした。
今でも本を探すが楽しくて楽しくて、
ほんと良い趣味見つけたのかもしれませんね。
この三国志は元は三国志演義です。
演義も完訳等色々と読みました。
しかし吉川三国志と言われるように、
他の三国志演義とやっぱり違うのです。
引き込まれるのです。
何度読んでも。
また必ず読みます。
絶対。
Posted by ブクログ
長かった三国志もついに終幕。ついに読み終えたと感慨深い。
燃えるように生きた武将たちの、その灯火の消えるのを見るのは辛い。趙雲の生き方も凄かった。
何よりも孔明の働き。この上ない正しい政治。そして激務をこなし亡き主君に忠義を尽くしたその心は痛ましいほど胸に届く。人材に恵まれなかった孔明や蜀の運命を見ると、人こそが大事なのだと思った。今ここに関羽がいたら、と思いを馳せる孔明が切なかった。代わりはいないのだ。
Posted by ブクログ
およそ三ヶ月かけて読破。孔明の無念さだけが残る、あまりにも寂しい結末。関羽・張飛・趙雲らの様な良将すでに亡く、自らの命を削って劉備の遺詔を守ろうとした姿に心打たれる。孔明がもう十年存命であったら、中国の歴史は変わっていたかもしれない。何にせよ「どこに救いを求めて良いのか」そんな気持ちが漂う読後感だった。
Posted by ブクログ
8巻と分量は多いが、非常に読みやすく、あっという間に読み終えることが出来た。
以下、この本から示唆を受けたことを列記。
・信賞必罰は組織を強くするために必要。
・何か事を起こす時は、十分な下調べをして、必勝の態勢で臨むことが大切。
・敵を欺くのであれば、味方すら欺くことも大切(要は、大事は慎重に進める必要あり)。
・苦手なことは手を付けてはいけない。(劉備玄徳の最後は・・・)
Posted by ブクログ
初めてこの作品を読んだのは、某無双ゲーム(灰色っぽいパッケージで、弩兵が最強なあれ)の影響で三国志に興味を持ったのがきっかけで、中学生の頃だった。
その後しばらく三国志からは離れていたのだけれど、つい最近、手持ちの本を整理していたら、半ば黄ばんだこの文庫本が出てきた。
懐かしいなぁ〜という思いから、第一巻の冒頭を眺め始めたが最後、半月くらいで全部読んでしまった。
三国志を初めて通しで味わった時の印象は、中盤までが劇的で面白いということだった。
貧しい劉備が決意とともに立って、呂布や董卓が討たれ、袁紹を平らげて着実に力をつけていった曹操が、孔明の登場によって赤壁で苦渋を舐め、孔明の意図通りに、天下が三分される。
言ってしまえば、三国志は三国になるまでがピークで、そのあとはおまけみたいなもんだと。
そんな僕が今回再読してみて思ったことは……
蜀末期の悲壮感にこそ、この作品の魅力があった。
読んで、想像して、思いを馳せて。
孔明の劉備に対する想いとか、彼にのしかかる重圧とか、そこには華やかなものは微塵もない。
けれど、派手な合戦や権謀術策よりも、「三国志」の「志」が一番染みてくるのはここだったということに、今更気づいたよ。
でもやっぱり確かに、映画化して面白いのは間違いなく董卓とか赤壁、これは揺るぎないっすね。
Posted by ブクログ
とうとう最終巻。
孔明率いる蜀軍が魏の大軍を迎え撃つ。
人材の不備を嘆くが、老将趙雲もまだ健在、関羽・張飛の子も大活躍。姜維という若手も獲得し、優勢かに思われたが…。
孔明すでに五十半ば。
司馬仲達率いる敵軍と交戦を重ねるうちに将星を不幸に失い、馬謖を斬り、味方からは内紛の気配が。いよいよ蜀の衰亡強くなる。そして五丈原へ。
孔明の早すぎる死は、連戦続く最前線に立ったことによる過労死ともいえる。ストレスも半端なかったろう。上司(二代目のボンクラ息子)がもっとしっかりしていれば。
孔明を「偉大な凡人」と称した著者の観察はおもしろい。智が働くがゆえにストイックだった彼には、次世代が育たなかった。天下三分の計を描いたのは孔明だったが、その没後、蜀も魏も、さらに呉までもが後継者の無能により亡国の憂き目に遭う。
英雄、名軍師と呼ばれる者にも欠点はあり、欠点よりも美点を見出し活用すべしとの劉備や孔明の仁政は,現代にも参考になろう。
Posted by ブクログ
面白かった。
三国志は一回途中で挫折したことがあったので、再度チャレンジ。横山漫画が何回読んだかわからないくらい読みましたが。
読んでみると、やっぱり面白い!なんで途中で挫折してしまったんだろうって思うほど。読みやすいし、一気に読めました。
孔明の人生は涙しない人はいないのではないかと思います。あれほど才能がありながら、驕ることなく先主との誓いを果たすことだけに生きた。しかも、孔明の誓いは様々な要因から結局は果たされずに終わる。事を計るは人にあり、事を成すは天にあり。
秋風五丈原…、胸を打たれます。
Posted by ブクログ
長かった。疲れた。全8巻。
曹操の活躍に始まり、劉備、関羽、張飛の活躍。
魏呉蜀が入り混じる赤壁の戦い。戦国時代の様相。
曹操も死んで、劉備、関羽、張飛も死んで、次の時代、魏の司馬懿仲達と蜀の諸葛孔明の戦い。孔明の死まで。
諸葛孔明はすごい人でした。
晩年の蜀は有能な武将がいなくなる中で、戦略によって、魏とわたりあう。苦しいのを状況のせいにせず、状況の中で最善を尽くす姿勢がすごいと思いました。
体力のある人は是非。
Posted by ブクログ
やっと読み終わった。長かった。やっぱり関羽が一番好きかな。でも、最後の巻を読んで初めて、孔明が好きになった。それまでなんとなく面白味のない人物だと思ってたけど、玄徳が亡くなった後のストーリー、それから篇外余録を読んだら孔明という人が好きになったし、もう一度最初から読み返したくなる衝動にかられた。ま、長いからしばらく読み返さないと思うけど…。
Posted by ブクログ
三国志を生きた当時の人たちと、今を生きる人々の価値観は全く違うだろう。しかし、諸葛亮の劉備に対する忠誠心にはいつの時代でも感動するものがあると思う。全8巻、本当に面白かった。
Posted by ブクログ
やっと再読完了。夕飯時のみタラタラ読んでたので2年半かかってしまったけどその分感無量といったとこかな。諸葛亮の不利とは分かっていても蜀のために尽くす姿に感動した。それにしても蜀滅亡の後、魏で生きることになった暗愚劉禅の蜀の頃より今の方が幸せと言っているのは驚きを通り越して呆れてしまった。やはり国を牽引するものが愚かだと衰退の一途を辿ってしまうものなのだな。
Posted by ブクログ
これにて完結。全編通して読みやすく、面白かった。
とはいえ、話のピークは劉備が蜀を建国する前後くらいかなぁ。英雄たちが次々と去っていき、趙雲に及んだ際は、孔明でなくてもため息が出る。
日本の三国志観を固めたシリーズを読み終えられて、一満足。
Posted by ブクログ
小4以来38年ぶりに5週間かけて再読。
日中戦争の最中1939-1943年に新聞連載されたもの、というのが意外に感じるくらい、当時の「敵国」の英雄譚への愛情溢れる筆致です。(本作品によって少しでも当時の敵国感情が薄らいだのであれば、吉川先生も本望だったんでしょうか。。)
なんと言っても諸葛亮孔明が格好よく描かれていて、他の人物はどこまでいっても引き立て役な感じですが、主役級以外では、周瑜、陸遜、司馬懿、黄忠、趙雲、姜維、が鮮烈に記憶に残ります。
赤壁と五丈原には、いつか行ってみたいなあ。
Posted by ブクログ
蜀の孔明と魏の司馬仲達との争いがずっと続く。孔明の戦略が際立っているが財力等で勝る魏は呉を味方につけ最後はどうなるのだろうか?今日の味方は明日の敵、戦わないことを是とする、後出師の表、作戦や構想が大切、三国志からは色とりどりなことを教えられた。日本の歴史と比べるとスケールが大きいと感じた。
Posted by ブクログ
蜀をまとめた劉備と魏王として対峙する曹操が、漢中で激突し、関羽・黄忠らの奮戦もあり、この地を収めることに成功します。
漢の故地である漢中を収めてもなお、なぜ劉備が天下を治められなかったのか、残り2巻をたどります。
Posted by ブクログ
・昨年から読み続けていた三国志を漸く読み終えました。
・実際にところ、これまでの三国志についての僕の知識は、小学生時代に父親に買ってもらった小学生向けの超短縮版と、ゲーム「三国無双」くらいのものでしたが、最近漫画「キングダム」にハマっていることもあって、今回改めて読んでみたのでした。
・最終巻に作者自身が記した通り、物語の「華」は、やはり、曹操と、中期までの諸葛亮孔明の2人でしょう。晩年の孔明は、綺羅星の英雄たちが流星のごとく散っていったのち取り残され、彼に関する記述も勢いが失われたように思います。司馬懿仲達という好敵手が現れてなお、物語の奥底に漂う寂しさは拭いようもありませんでした。野心家で冷酷な面も大いにあるも人間的魅力に溢れた曹操と、知識と知性において他を寄せ付けず劉備への忠義に厚い孔明。この2人こそが物語の主役に思えました。
・そして、会話を短く繋げる歯切れの良さや、文語表現の多彩さに溢れた筆致がどんどんと物語にのめり込ませました。素晴らしかった。
Posted by ブクログ
最終巻。
読み終わった!!
劉備がなくなってからいまいち読む速度が上がらなくてちょっと苦戦。
でも、趙雲すら老将と呼ばれ、息子たちも次々と亡くなり、遺されてる孔明も年老いていく。
眉間に皺なくしては読めなかった。
孔明の死で話は終わってるが、後蜀30年を読んでも、つらくて仕方なかった。
Posted by ブクログ
吉川三国志の最終巻。
諸葛孔明と魏との戦いが描かれる。
このあたりまで話が進むとようやく孔明に好感をもてるようになる。彼の魅力が存分に書かれているからか、それとも人物が皆退場してしまい最後の英雄諸葛孔明に感情移入するしかなくなるからか。
長かった。ようやく全8巻読破。
再読にもかかわらず飛ばし読みせず丁寧に読み進めたから本当に疲れた。
しかし、長編ものを読み終えたときの達成感はとても心地よい。
吉川三国志。また10年後くらいにページを開いてみようと思う。
Posted by ブクログ
この吉川三国志シリーズもようやく読破できた。
孔明の北伐は成功を見ることはなく、無念のうちに病死、その後の蜀は孔明の後継者争い、人材不足、劉禅のリーダーシップの欠如などのため疲弊し、魏に滅ぼされてしまう。その魏も司馬炎に滅ぼされてしまうという混沌とした時代が続く。本作品はハッピーエンドではなく、一抹の淋しさが残るのだが、それでも読破後の満足感はたっぷりだった。吉川英治氏の格調高い且つ躍動感あふれる文体のお陰もあるのだろう。
これを機に、吉川英治氏の他作品、例えば水滸伝や宮本武蔵なども読んでみようと思う。私が最も尊敬する作家である司馬遼太郎氏とはまた違った歴史小説が楽しめるはずだ。
以下に二点だけ、興味深かったシーンを引用したい。
・所詮、敵わぬことを知って、なおこれ以上ぶつかってゆくのは勇に似て勇ではない。貴公達二人は大急ぎで諸葛丞相にまみえて、いかにせばよろしいかご意見を求めて来てくれ。
→曹真に協力した西羌軍の鉄車隊に蹴散らされた馬岱が、関興と張苞に諭した言葉。敵との力の差が明らかな場合に無理と知りながらぶつかるのは勇ましいことではないのだ。
・今もしこの陣に関羽の如き者がいたら、こんな小戦果を以って誇りとするのはおろか、到底満足はしなかっただろう。かえって、「丞相からこれほどの神謀を授かりながら、肝腎な司馬懿を取り逃がしたことは、何とも無念であり、申し訳もありません」と慙愧叩頭してその罪を詫びて止まないに違いない。
→北伐において司馬仲達を取り逃がしても戦果を誇る部下に対し、自身が求めるレベルに達しない部下(廖化、姜維、張嶷、王平)を淋しく思うシーン。関羽とはしょせん格が違うということか。
Posted by ブクログ
いやー「沈まぬ太陽」以来の長編小説、長かったけど、おもしろかったです。
三国志。
三国志自体が登場人物が星の数程いて、それぞれにドラマがあって泥臭いところから煌びやかなところまで幅が広くておもしろいってのもそうなんだけど、俺は読み進めていく中で、このおもしろさは著者である吉川英治の文才によるところも大きいんだろなって思いました。
すごいなー、これだけの大作を書き上げることって、大仕事だ。
でも、この三国志を読んでる3ヶ月間で、いろいろ新しい価値観に触れることができたのがなによりの収穫でした。
個人と組織との考え方の違いを、自分の仕事に照らし合わせながら実感として得られたところ。まぁ答えはこれから仕事をしていく中で得ていかなきゃなって思うけど。
あと、この三国志に限らずだけど、今まで読書の話をしなかった人と話ができて、「あー俺も昔読んだよ」って人と登場人物の話とか場面での話とかして仲良くなれたり、レッドクリフの影響もあって時事ネタでも出てくるようになった追い風も受けて(まさにレッドクリフの話じゃねーか)、相手のことがもっとわかったり少し仲良くなれたり、作品に対しての読んで良かったことと同時にそんな経験もできてとっても楽しい3ヶ月間でした。
1巻完結的な本を読むのもいいけど、こういう長編じゃなきゃ書き表せない、何代にも渡るようなスケールの大きいものの見方を学んだ3ヶ月だったなと思います。
俺も、これを読んでくれてるみんなも、じーちゃんばーちゃんがいて、両親がいて、自分がいて、兄弟がいて、そして俺達からまた次の世代が生まれて、そうやって続いていくんだ。今は家族じゃない人たちとだって、どっかでつながってたかもしれないし、これから先のどこかで俺か俺と縁のある誰かとつながっていくかもしれない。その中で、脈々と受け継がれていく大事な価値観や、教えなくても伝わるものがあったり、家庭の味とかそれぞれの家庭ならではの形もあって、そんな時の連続の中で、そばにいる人たちの幸せをみんなで守りながら暮らしてきた人生の先輩たちがいて、俺もそうやって暮らしていくんだよな、とかしみじみ感じてました。
そんな価値観から言えば、年を取っていくことってそんなに捨てたもんじゃないですね。
年を取っていかなきゃ、自分の先の未来は見えてこない。これから先、5年後、10年後になればじーちゃんばーちゃんが生きてる人も減ってるだろうけど、その人たちに代わる役割を担う人が、そういったところだからこそ見える人生の起伏や人情の機微を後世に伝えていく。それが何も意識せずに当たり前にできてるような循環が本来あるべき姿なのかな、とか思いました。
今の自分は誰かのために何ができるかな。
5年後に、できることは増えてるかな。伝えられることはより深く、大きくなってるかな。
いつまでも変わらないものも大事にしたいけど、周りの人を助けられたりできる自分をもっと大きくできるよう頑張っていきたいなと思いました。
なんか、三国志の感想からちょっと話がずれてるけど、登場人物それぞれ自分なりの思いを持って自分の人生を生きている。それは、今も変わらずに大事なことだし、俺も自分の人生をもっともっと(金銭て意味じゃなく)豊かに生きていければ楽しいなと思いました。
欲しいのは物じゃなく、人物。
仲間がいて、笑いがあって、そんな時の連続を自分の人生として送っていきたいと思います。
Posted by ブクログ
あぁー、遂に読み終わった。最後まで読んでみて、吉川英治の三国志は、本当に劉備〜孔明へと続いた壮大な戦記であったとつくづく思った。孔明の聡明さ、人としての生真面目さ、知謀家が物語後半の随所に見られて、面白かった。孔明が。亡くなる間際から孔明死後の、吉川英治の解説は、物語を十分に引き立たせてくれた。
Posted by ブクログ
中学時代の同級生が読んでいて、三国無双とかゲームもやっていて、歴史上の人物に興味を持って読み始めた本。
劉備亡き後、孔明が中心。司馬仲達、公明の智略戦。策士、策に溺れす。
1人のカリスマが歴史を作ることはできるが、1人のカリスマだけでは長く世を束ねることはできない!
Posted by ブクログ
文庫で全8巻という長さと、馴染みのない異国の、しかも想像しにくい歴史を描いた作品で忌避していたが、なかなかどうして非常に読みやすい小説だった。
玄徳が関羽張飛と出会い、曹操が起ち、三顧の礼で孔明を得て、と中盤までの盛り上がりは凄まじい。一方、歴史文学なので仕方ないことだが、後半には一人、また一人と役者が欠けていき悲壮感を増していく様は寂しい。本当の英雄が戦の後まで残らないのは彼の国でも同じである。
三国志という誰もが知っているタイトルを、今更ながらでも手にできて良かった。