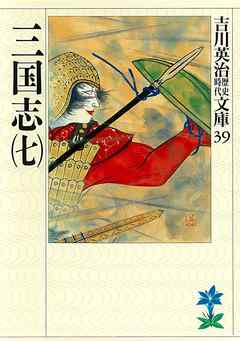あらすじ
「三国志」をいろどる群雄への挽歌が流れる。武人の権化ともいうべき関羽は孤立無援の麦城に、悲痛な声を残して鬼籍に入る。また、天馬空をゆくが如き往年の白面郎曹操も、静かな落日を迎える。同じ運命は玄徳の上にも。――三国の均衡はにわかに破れた。このとき蜀は南蛮王孟獲に辺境を侵され、孔明は五十万の大軍を南下させた。いわゆる七擒七放の故事はこの遠征に由来する。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
劉備が病没するわけだが、それに至らしめた陸遜恐るべし。やはり呉は人材の宝庫。
そして孔明の南蛮進行、神がかり的な勝利をおさめ続けて、もはや蜀に敵なしとすら思わせるに十分だった。そして満を持して北伐に挑む。
世界にこれ程魅力的で壮大な物語があるだろうか。
次巻いよいよ物語は終結、結果は知っているけどワクワクが止まらない。
Posted by ブクログ
物語として考えた時、曹操というキャラが本作の本当の主人公という気がする。
曹操亡き後、もぬけの殻ではないけれども、若干あっさりした感じでストーリーが進んでいる。
Posted by ブクログ
いよいよ、世代交代の波が訪れる巻だった。
ここまで読んできて長く連れ添ったような気持ちになっていて、切なくてなかなかページを進められなかった。
中でも関羽の死は無念だった。張飛も失い、残された玄徳の苦しみはどれほどだっただろう。それがあの敗戦へと繋がったのだろうから悲しさも一層増す。
どんな者にも平等に、死によって分かたれる時が来て、そうして時代は移り変わっていくのだと思いながらも、そう簡単には気持ちが切り替えられなかった。
南洋諸国での孔明の手腕は流石としか言いようがなく、面白く読んだのだが、夥しい死者を前にどう折り合いをつければいいのかまだはっきりとした答えは見出せていない。
Posted by ブクログ
桃園の義も今は昔。関羽、張飛、劉備、また曹操も。およそ主要な人物は没してしまって一抹の寂しさを憶える。孔明の南蛮遠征も何故か虚しく感じる。この寂寥感も三国志の味わいのひとつなのだろうか。
Posted by ブクログ
面白い!!!!!!
「『我もまた人生六十歳』
と、やがて自分の上にも必然来るべきものを期せずにいられなかったに違いない。年をとると気が短くなる――という人間の通有性は、大なり小なりそういう心理が無自覚に手伝ってくるせいもあろう。」
Posted by ブクログ
この巻は前半は面白くて面白くてあっという間に読み終わった。やっぱり関羽、張飛、玄徳の話が好きなんだよなー。みんな亡くなってしまった後は一気に読書ペースが落ちた。。
Posted by ブクログ
図南の巻、出師の巻。荊州の守りについていた関羽の死から、相次ぎこれまでの主要登場人物(張飛、曹操、玄徳等)が死んでいく。残された孔明は南蛮を治めるため戦い、ついに曹操亡きあとの魏へ乗り込んでいく。
Posted by ブクログ
羅貫中の三國演義をもとにした小説の名作である。古風ゆかしく美しい文章は読みやすく、物語の世界に読者を引きずり込む力がもの凄い。私は学生の時に読んだが、大げさでなく寝食を忘れるようにして1巻から8巻までを一気に読んでしまった。
なお第7巻は、諸葛孔明の出師の表まで。
Posted by ブクログ
「三国志」をいろどる群雄への挽歌が流れる。武人の権化ともいうべき関羽は孤立無援の麦城に、悲痛な声を残して鬼籍に入る。また、天馬空をゆくが如き往年の白面郎曹操も。静かな落日を迎える。同じ運命は玄徳の上にも。――三国の均衡はにわかに破れた。このとき蜀は南蛮王孟獲に辺境を侵され、孔明は50万の大軍を南下させた。いわゆる七擒七放の故事はこの遠征に由来する。
Posted by ブクログ
曹操、劉備、関羽、張飛…みんな死んでしまって、人材の少ない蜀の中で孔明が孤軍奮闘しかけるところで終わり。次がラスト。
長かった三国志の旅も終わりが見えると、早く終わってほしいような、ずっと続いててほしいような。
Posted by ブクログ
着々と読み進めてきた三国志も次巻で終わり。しみじみ。
私の知ってた名将たちが没した後、果たして孔明はどうなっていくのだろう。
早く読み終わりたいような、終わってほしくないような。
Posted by ブクログ
ホントは去年の課題図書だったけど、やっと7巻。関羽が散り、張飛と劉備も後を追い、更には曹操も退場と主役が一気にいなくなったので、途中、ちょっと読むのがストップしてしまったのも正直なところ。
三国鼎立でそんなに安定も続かないよね。
ここから最後への主役は丞相孔明か。
荊州を守っていた関羽の首塚が洛陽郊外にあった理由が分かった。去年お参りしたけれど。
さて、続きはいよいよ第8巻。次は成都近辺にも聖地巡礼に行こうと思っているので、さっさと読み終えるようにします。
Posted by ブクログ
関羽、曹操、玄徳、張飛が亡くなり蜀の孔明の軍師ぶりが目立ってくる。蜀という不利な地形、軍力が無いのに戦略で勝っていくところは見習うべきものがある。出師の表、刎頸の交わり、趙雲、馬超、孫権、曹丕、諸葛瑾、孟獲、夏侯淵と志士が多く出てくる。結末はどうなるのであろうか?
Posted by ブクログ
唐突に赤壁の大戦、そして巻末では劉備の入蜀と、天下三分に近づいてきました。
それにしても、合従連衡の時代から数百年、弁舌で生きていく諸家の多いのに、宋代の水滸伝との違いを感じます。
Posted by ブクログ
結末がわかっているので、なかなか頁が進まない。
劉備帝国の設立もまもなく、関羽が痛恨の死。老いた曹操も病に没し、やがて悲運は張飛、さらには玄徳の身にも。
英雄と言えども人の子、些細な油断が命取りになるという教訓。関羽の短慮さは年のせいなのだろうか。
玄徳はお人好しだったのか、後継者に恵まれていない。養子は部下を見捨て、実子の王太子は愚直。劉備亡き後の孔明の苦悩が目に見えるようだ。
その孔明が呉に競り勝ち、さらには南蛮国への大遠征にのりだす。五度戦って五度敵を許すいたちごっこは、コメディみたいで笑ってしまう。ただ中国内の英傑との決戦ではないので、冗長で退屈だった。自策を楽しむあまり、遠征に軍費をかけすぎたきらいもある。
いよいよ次の最終巻では、孔明が魏と直接対決。
Posted by ブクログ
吉川三国志の第6巻。
関羽の最後から、前出師の表あたりまで。
巨星堕つ。乱世の奸雄が逝き、劉備三兄弟が舞台から降りた。
まさか今更三国志でうるうるしてしまうとは・・・。
Posted by ブクログ
いよいよ終盤に入ってきた。関羽も張飛も劉備も、また敵方の曹操もなくなり、主人公は完全に孔明のものとなった。
本巻で興味深かった部分を紹介したい。言うまでもなく、両者とも孔明の言である。
・「戦いというものは、あくまで人そのものであって、兵器そのものが主ではない。故に、これらの新兵器を蜀が持つことによって、蜀の兵が弱まるようなことがあっては断じてならないと、それを将来のために今から案じられる」
→南蛮征伐を終えた後の訓示である。これは現代でも通じる原理だと思う。機械、情報技術が高度に発達してきた現代においても、世界を動かすのは人そのものであって、機械ではないのだ。
・「初め、藤甲軍の現れた時は、ちょっと自分も策に詰まったが、それは彼の有利な行動のみ見せつけられていたからで、翻って、彼の弱点を考えてみると、当然ー水に利あるものは必ず火に利無しーの原理で、油漬けの藤蔓甲は火に対しては何の防ぎにもならぬのみか、かえって彼ら自身を焼くものでしかないことに思い当たった」
→一つ目の続きで語られた訓示である。強敵が現れたからといっても、弱点はあるものだし、視点や発想を広げることでそれが見えてくるものなのだ。私が今後、仕事等で困難にぶつかった時に思い出してみよう。
Posted by ブクログ
哀しいかな、錚々たる英雄達が、雪崩れのごとく落命する。
いよいよ、三国志の物語は、終焉に向かう。
「黄巾の乱」に始まった三国志序曲は、
「董卓軍対連合軍」「中原争乱と曹操台頭」「荊州攻防、赤壁の戦い」と、ここまで一気に駆け上がっていく。
そして、本巻「美髯公関羽の死」から、次巻クライマックス「五丈原の戦い」へ突入していく。
やはり、三国志は、生身の人間を描く。
-"老い"とは。
孔明渾身の未来への手紙 "出師の表"とは。
涙なしには、、、
どうぞ、泣ける詩を。
そして、語る、吉川英治。
いや改めて、この長編は深いと思った今日。
Posted by ブクログ
時間が空いてしまった。劉備、関羽、張飛、曹操と死んでいき、なんか悲しい。
主役が孔明となり、そのすごさも改めて感じられるのだが、蛮族との戦いはちょっと長い気もした。
今読むと、呉がすごいよね、って思う。
Posted by ブクログ
中学時代の同級生が読んでいて、三国無双とかゲームもやっていて、歴史上の人物に興味を持って読み始めた本。
三国時代も終盤に差し掛かり、主力武将が終焉を迎えていく。関羽、曹操、劉備、、、
それでも三国志はまだ終わらない。。
最後まで歴史を味わいたい!
Posted by ブクログ
世代交代。
今か今かとおもっていたけれど、ついに名将たちが亡くなって行く。
最初は読みにくかった三国志もすっかり登場人物に愛着がわいていたらしく、とてもさみしい!
Posted by ブクログ
関羽・・・・・・遂に死せり。
弔い合戦が始まる。
7巻は、とにかくみんなが死んでしまう。
ひとつの時代が終わりを告げる。
(そして私の集中力も・・・)
ただひとり残された孔明の孤独はいかほどか。
まるでそれを紛らわすかのように、南蛮へと侵攻し、矢継ぎ早に北へと向かい、留まることを知らない。
*印象に残ったこと*
・張飛のむごい死に様は、仏教の因果応報を彷彿とさせた。
・関羽は、確かに思慮深く、人望も厚い。が、神とまで崇められるようになった所以が、一読しただけではわからなかった。
(本の感想ではないけれど、それを考えていて改めて実感したのは、自分の中で”神”像があまりにも清廉潔白だったこと。そうじゃないよな、と改めて形として捉えてみてわかった。八百万でもなんでも、時に非情で残酷であることを、どうして忘れていたんだろう。)
三国志の戦いでは(とくに孔明は)よく自然の力を利用している。
映画”Red Cliff”では、曹操は風向きに負けた。
自然の力は国の将来を、多くの人命を大きく左右する。
時にはげしすぎるほどに、風は轟き、豪雨は地面を打つ。
それを、昔の人は、身体の一部として、知っていたのだ。
Posted by ブクログ
この巻は結構読むのに時間が掛かりました。というか途中でほかの本に浮気してたからなんですが、なかなか続きに手が伸びなかった…というのも。これまでメインで活躍してきた人物たちから次の世代へと交代していく時期で、いよいよ終わりが見えてきた感じはしますが、まだあと1冊あるのか…。
Posted by ブクログ
羽将軍の骨の手術に、名医華陀現る。
呉の国の華陀が敵国の関羽の病を聞きつけ、医に国境なし、ただ仁に仕えるのみと、
関羽の毒矢で腐りかけている骨を骨髄から削る大手術を行う。
側近が皆、蒼ざめてしまうほどの手術にも、羽将軍は、差していた碁盤から目を離さない。
毒で眠れぬ日々をすごしていた、羽将軍もその晩は熟睡して、回復に向かう。
しかし、荊州を失った蜀軍大将。
呉の孫権の願いも空しく、終に武人関羽将軍は、忠義に落命する。
赤兎馬は、悲しくて、ごはんを食べず、ただ嘶くばかり。
ああ、なんて、かなしい・・関羽先生のいない三国志なんて・・
関羽先生は208年の昔の人で、元より生きちゃいないのに、
今、突然死を知らされたようにショックだ。
そんなに悪い感じでもなかった、呂蒙も、
だからこそか、怪に憑かれて、死んでしまった。
忠義勇智、恩に生きることが、いかに心の充実と生きがいと
良心たる人のそのものとと不可分だったのか。
いや、今でもそれが本能なのかもしれないと直感する。