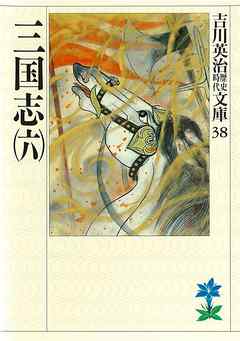あらすじ
赤壁の大敗で、曹操は没落。かわって玄徳は蜀を得て、魏・呉・蜀三国の争覇はますます熾烈に――。呉の周瑜、蜀の孔明、両智将の間には激しい謀略の闘いが演じられていた。孫権の妹弓腰姫と玄徳との政略結婚をめぐる両者両様の思惑。最後に笑う者は、孫権か、玄徳か? 周瑜か、孔明か? 一方、失意の曹操も、頭角を現わし始めた司馬仲達の進言のもとに、失地の回復を窺う。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
六冊目にしてやっと三国が形を成してきた。
孔明はいよいよ天才軍師ぶりを顕しつつ、魏から司馬懿、呉からは陸遜が登場。
ついにクライマックスに向けて大きく物語が動き始める。
しかしながら、老いてなお盛んな黄忠が堪らなく推しである。
Posted by ブクログ
既に話の行く末を知っている前提で読み返すと、玄徳を中国の人も好きなんだろうと推察す。
そして日本の人間もおそらく一番好意を寄せる為政者かと。アジアを感じまする。
Posted by ブクログ
去年から読みだして、いよいよ6巻。
曹操が魏王になり、玄徳が蜀を得て漢中王になる。
魏・呉・蜀、まさしく三国志って感じになってきた。
曹操も玄徳も人間味を見せて入るけれど、やっぱり玄徳の義の人柄に惹かれるよな。やっぱり、今の世の中、独裁強権政治には嫌気を感じる。
武漢とか成都周辺に聖地巡礼ツアーに行こうかと思っているけど、いつ行けるかなぁ。
Posted by ブクログ
土地や気候を活かし状況をよみ智恵や計略を巡らせる、そして人を動かし勝つということの難しさ。
もうここまでくると武将の好き嫌いが自分の中で決まってきて、この巻では胸のすく思いをするシーンが多くあった。
劉備玄徳の軍の活躍を待ち望んでいる自分がいる。
曹操の智より孔明のほうが一枚上手だったこと。趙雲の見捨てない心意気。そして張飛の戦い方に特別グッときた。成長が見られたので…
Posted by ブクログ
劉備率いる蜀の陣容は、関羽、張飛、趙雲に加え馬超、魏延、黄忠、馬良など、いよいよ役者揃いの模様。
こうした武将たちが魏、呉を相手に立ち向かうシーンは読んでてわくわくした。そしてこの役者たちを最大に活かすのが、軍師諸葛孔明。最高の作戦は勝利に欠かせない。相手の戦力分析もまことに鋭く、的を射ている。
この時が最も蜀に勢いがあって、非常に面白い。
孔明に並ぶ参謀である龐統が若くして死んでしまうのは誠に悲しいが、これも過去世の宿業所以なのか。因果の法理の厳しさを痛感。
曹操、劉備も歳を重ね、考え方も固まり、保守的になりなんとなく老いてきているのが伺える。この2人がそれぞれ一国を築けたのも、周りの人物の存在が大きい。
人は誰しも完璧ではない。人材の城がなければ、国が栄えるのは難しいであろう。
Posted by ブクログ
ようやく劉備が蜀を治め、一国の王となる。馬超もついに帷幕に入り、重厚な陣容となってきた。黄忠と厳顔のお年寄りコンビの活躍は一読の価値あり。龐統の死は残念。
Posted by ブクログ
魏の曹操、赤壁の痛手より西涼州の馬騰をもって蜀にあたろうとするも、途中馬騰は曹操に首を切られる。
孔明の活躍で蜀が盛り返し、魏・呉・蜀、ますます三国の力強大となる。
Posted by ブクログ
面白い!!!!!
「人と人との応接は、要するに鏡のようなものである。驕慢は驕慢を映し、謙遜は謙遜を映す。人の無礼に怒るのは、自分の反映へ怒っているようなものといえよう。」
「百計尽きたときに、苦悩の果てが一計を生む。人生、いつの場合も同じである。」
Posted by ブクログ
望蜀の巻から図南の巻。
孔明と並ぶ名声をもつ龐統が玄徳の元へ来るが甲斐なく終わる。蜀を攻めていた玄徳の元に参じるため、荊州を関羽に任す。玄徳の妻の呉の孫権の妹は、偽りの理由で呉に帰す。蜀と荊州は玄徳の支配下へ。一方魏の曹操は王位に昇り贅を貪る。漢中を玄徳にとられ、曹操、孫権と腹の探りあいは続く。
馬超、黄忠、魏延など。
Posted by ブクログ
ついに玄徳が蜀を手にする。
漢中との戦いの最中、龐統がさずけた上中下の策を選ぶとき、「中庸。それは予の生活の信条でもある」と玄徳が口にした台詞が記憶に残った。
龐統が落鳳坡で命を落とした。
鳳凰とも呼ばれた人が、孔明との差に嫉妬を感じたかどうかは少し疑問に思った。ストーリーとしてはその方がおもしろいのだろうけれど、龐統が好きだっただけに悲しい・・・。
玄徳の考に厚い生き様・信条に触れていると、自分もそうありたいと、願わずにはいられない。
Posted by ブクログ
劉備玄徳、未だ領土を持たず。
しかし、彼の周りには人が集まる。
よく言うには、
曹操は天の時を、孫権は地の利を、そして劉備は人の和を得たと。
集う、人たちの物語。
Posted by ブクログ
羅貫中の三國演義をもとにした小説の名作である。古風ゆかしく美しい文章は読みやすく、物語の世界に読者を引きずり込む力がもの凄い。私は学生の時に読んだが、大げさでなく寝食を忘れるようにして1巻から8巻までを一気に読んでしまった。
なお第6巻は、劉備が漢中王になるところまで。
Posted by ブクログ
赤壁の大敗で、曹操は没落。かわって玄徳は蜀を得て、魏・呉・蜀三国の争覇はますます熾烈に――。呉の周瑜、蜀の孔明、両智将の間には激しい謀略の闘いが演じられていた。孫権の妹弓腰姫(きゅうようき)と玄徳との政略結婚をめぐる両者両様の思惑。最後に笑う者は、孫権か、玄徳か?周瑜か、孔明か?一方、失意の曹操も、頭角を現わし始めた司馬仲達の進言のもとに、失地の回復を窺う。
Posted by ブクログ
読んでから時間が経ってしまって細かいことは忘れてしまった、、。
劉備玄徳のもとに逸材たちが集まり、強固な地盤をもつ一国となった。人材が集まるだけでなく、玄徳の元にいる武将はゆっくりと成長もしている。
張飛は武将として玄徳が驚くほどの活躍をみせる。人が時間をかけて、自分の弱さを克服して強くなっていく姿に勇気をもらった。
Posted by ブクログ
三国志もすでに後半に入り、いよいよ諸葛孔明の縦横無尽な活躍が描かれます。
何度となく劉備の死地を救い、今また魏と呉の争いにも神慮を示す知謀には、この後の活躍も楽しみです。
Posted by ブクログ
山場なんだろうな。
劉備も関羽張飛、みんないい年齢になってきてそろそろ退場もありえちゃうのかなとドキドキしながら読んでます。
曹操の周りの将たちも、勇将ばかりだと褒められていたけれど
いまや劉備の周りの将軍たちがすごすぎる。
Posted by ブクログ
名軍師孔明とともに龐雛を得た玄徳。しかし、龐雛は孔明に嫉妬したがため計を誤って落命する。赤壁の戦いののち、周瑜没し、呉は魏に大敗し、孫権の妹姫を帰国させた玄徳との仲も険悪に。
玄徳はついに蜀一国と三城を攻略、さらに黄忠、法正らの名将も傘下に加わり一大勢力に。
魏王曹操の横暴ぶりが目立ち、部下までも誅する非道ぶり。叛乱の手が上がり、玄徳とも因縁の対決を見るが、敗走する。
劉備やっと五十を超えて漢中王として即位する。いまが蜀の隆盛期なのだろう。知略に長けるようになった張飛や、あいかわらずの趙雲の武勇もめざましいが、養子の腑甲斐なさに傾国の兆しが見える。
才人才に亡ぶ、という言葉が身にしみる盛者必衰の歴史の連続。才能も大事だが、心映えこそが自分を活かす、という教訓をつくづく感じざるをえない。
Posted by ブクログ
諸葛亮孔明と並び称される龐統も軍師として加わり、劉備がいよいよ蜀を取って一大強国になるのがこの6巻。
酒癖悪く粗暴だった張飛が将軍として成長を見せたのもこの巻でとても好きな場面です。
曹操は西涼の馬超に苦戦し、劉備にも連戦連敗で漢中という重要拠点を失ってしまう。老齢による翳りがこの英雄にも見え始めていた。
呉の孫権も、劉備と孔明の仕組んだ荊州返す返す詐欺によく我慢しながら、魏に戦いを挑むものの、名将張遼の前に大敗北をしていた。
蜀の隆盛を苦々しく思う魏と呉は密かに軍事同盟を結ぼうとしていた…
大人になって改めて読むと、呉の孫権は実によく我慢したなあという印象。
こういう乱世の駆け引きとはいえ、赤壁の勝利の報酬たる荊州を何もしない劉備にかっさらわれて胸中察するに余りあります。
Posted by ブクログ
魏の張遼、呉の甘寧、蜀の趙雲子龍が今回は大活躍。
老将の黄忠も、快勝!
そしてとうとう玄徳は、王位に即位し漢・呉・蜀の三国志の形になった。
相変わらず孔明にしてやられる曹操が愉快だ。
この巻では、残念ながら関羽の活躍はなかった。
Posted by ブクログ
吉川三国志の第6巻。
龐統が仕官するところから、劉備が漢中王に就くあたりまで。
赤壁も終わり劉備が蜀の地を手に入れたことにより、いよいよ三国時代の到来。
しかし、ここら辺から大国同士の小競り合いが続くこととなり物語は少しだれる。
それにしても、恩を仇で返すこと数知れず、遂には一線を頑なに守っていた劉姓の同族にまで牙を剥いた劉備玄徳の仁の心とは一体・・・。
後半に入り、曹操が優秀な家臣を次々と死に追いやったりなど魅力的な人物が少しずつ老い衰えて変化していくのは寂しい部分だ。
Posted by ブクログ
「聞説、曹丞相は、文を読んでは、孔孟の道も明らかにし得ず、武を以ては、孫呉の域にいたらず、要するに、文武のどちらも中途半端で、ただ取柄は、覇道強権を徹底的にやりきる信念だけであると」
自分の認識もこれに近い。
だから曹操はダメなのだ、ということではなく、だからこそ曹操は偉大なのだ、という意味で。
曹操の偉大さを讃えんがために文武の才を称揚するパターンが多いけど、ちがうと思うんだよね。
文武の才がとやかくじゃなく、何よりもその覇道を貫こうとする信念こそが何よりも彼の強みなんじゃないのかなあ。
いたずらに文武の才を褒めそやすのは大事なところを損なってる気がしてならない。
Posted by ブクログ
続いてもう1巻。
孔明すごい!「最小の労力で最大の効果を」ってのが自分のここ最近のテーマなんだけど、まさにこれを地でいく孔明はすごい才能の持ち主だったんだろな、と思います。
ただ、頭がいいのはもちろん、相手に合わせて振る舞いを変化させることができる、適した形でアウトプットできることができて初めてあの明晰な頭脳は活きてくるんじゃないかな、とも思いました。文官には論破することで、武官には詳しい説明をせず主の威光と結果で。納得が得られなくても盲目的に説得ばっかりしないとこが、部分的な最善よりも大局的な最善を見ていて、なるほどなぁと思いました。
やっぱり、常に大局を意識した仕事ができる人ってなかなかいないけど、俺はそういう人になりたいと思います。世界を見通す。これができたら、気持ちいいだろうなぁと。
もう一つすごいところが、存在感というか相手に危険人物と思わせてしまう程の圧倒的な力量の差をさりげなく見せてしまうところ。
賢者中嶋さんが「臥竜」を名乗っていたけど、今さらながら納得がいくことが多いです。確かに、今思えば思い当たる節は多々ある。
圧倒的な知識を背景にしたピンポイントの指摘、自慢はしなかったけど連れてきてくれる日々交流してる人たちのレベルの高さ、自分は十分稼いでいるだろうけど「世の中の為になるなら」って動いていく姿勢(一銭にもならない俺ら向けの勉強会しかり)、、、実際に見てしまってるから、余計に実感としてわかるってのもあるけど、こういう人っているんだよなぁ。
まだまだ目指す頂は高いです。
あと4巻。俺はその間に何を学べるかな。
Posted by ブクログ
中学時代の同級生が読んでいて、三国無双とかゲームもやっていて、歴史上の人物に興味を持って読み始めた本。
赤壁の戦いを勝利した劉備が、蜀。曹操が魏。孫権が呉。魏呉蜀の時代が到来。まさに戦国時代!
諸葛亮、周瑜の策士の頭脳戦も痺れるおもしろさ!
Posted by ブクログ
吉川先生の代表作。随分前の作品ながら文体は読みやすくて改めて感心。
この巻では、臥龍鳳雛の両軍師や五虎将軍が勢揃いするなど
立ち後れていた蜀もようやく、って感じで体制が整った様子。
現実的には蜀はこのあたりがピークのひとつなのかな、と。
個人的には、龐統って、人間的にどうかと思うよ。
あっ、歴史、ではなくて、個人的にはこのカテゴリーとしてます。
Posted by ブクログ
多少の停滞はあれ、とんとん拍子で蜀を制覇していく劉備である。文武ともに優れた部下も揃ってきた。
以下に興味深かった点を引用したい。
・「帰らなければ、彼が信義を失うので、予の仁愛の主義に傷はつかない」
→劉備の益州攻めの際、生け捕った敵方の冷苞を解放した際に、魏延から「あいつ、きっと帰ってきませんぞ」と危ぶまれた時に返した言葉である。なるほど、これは現代にも通用しそうだ。尽くした相手に裏切られた際に、このような考え方が出来れば恩知らずを感じることもない。今まで曹操の言葉を幾つか引用してきたが、劉備の言葉は珍しい。あまり格好の良い言葉を吐くキャラには設定されていないためであろう。それだけに新鮮。
・「漢王は、その前時代の秦が苛政、暴政を布いて民を苦しめた後なので、いわゆる三章の寛仁な法をもって、まず民心を馴染ませたのだ。前蜀の劉ショウは暗弱でほとんど威もなく、法もなく、道もなく、かえって良民の間には国家に厳しい法律と威厳がないことが、淋しくもあり、悩みでもあったところだ。民が峻厳を求める時、為政者が甘言をなすほど愚かなる政治はない。」
→長いセリフだが、劉備が蜀を平定後、新しい憲法、民法、刑法を起草した孔明に対して、法正が「漢の高祖のように法は三章に約し、寛大になすってはいかがですか」と忠告した際に返した言葉である。前例に拘らず、シチュエーションごとに方法論を変化させていく孔明の巧みさは見習うべきである。
・才人才に亡ぶの喩えに漏れず、楊修の死は、楊修の才がなした禍いであったことに間違いない。彼の才能は惜しむべきものであったが、もう少しそれを内に包んで、どこか一面は抜けている風があってもよかったのではあるまいか。
→「鶏肋」事件により曹操に打ち首とされた楊修に対する吉川英治氏の感想である。つまり、才はあっても隠すか、才がないように振舞うくらいの配慮を持てば良かったのに、という同情である。