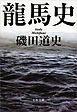磯田道史のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
幕末、加賀藩の猪山家は家計簿をつけていました。
その家は代々、加賀藩の「御算用者」
いわゆる経理を勤めており
仕事柄というか性格というか
私用の家計簿も実に細かい!
ところが当時の生活を調べるのに
これほど適した資料は他にありません。
武家社会の出と入りの実態もさることながら、
この家計簿と猪山家の歴史を通して
幕末から明治において
武家から士族へどうやって変わっていったのか
までがわかるのです。
というようなことを原本から読み解き
平易な言葉で伝えてくれる本。
この古書にめぐりあったとき
著者はすごく興奮したみたいですが、
そのワクワク感そのままに書いているので
おもしろいですよ。 -
Posted by ブクログ
防災について、歴史に学び、先人の教えを遺し伝えることは不可欠。そのために歴史書を発掘し明らかにしていくのも重要。当地で伝えていくメッセージにもなりそうだ。
例えば富士山が噴火するときには5年前から軽い地震が増え、二か月前から富士山中だけの火山性地震が毎日続いたと、宝永噴火のときのことが記されていたり(p.44)、噴火後振動は4日間、火山灰は12日間続いたという記録も貴重(p.56)。和歌山で、津波の前に、井戸の水が枯れたという前兆現象を濱口が指摘していたというのも興味深いし(p.172)、三陸で東日本大震災で神社が流されなった、鳥居の位置まで水がきたという話も(時々きくような話だが)メッセー -
Posted by ブクログ
はじめに ではこんな文章がある。教科書で学ぶ歴史は「歴史のココを見ろ」と指定されたミカタ。ちょっと大人になって司馬遼太郎などの歴史小説を読むのは「団体バスツアー」の歴史のミカタ。歴史の本当のおもしろさはある程度歴史知識ができた時点で、大人の人生経験をもとに、自分のみたい歴史の部分を「自分のミカタ」で見るところにある。
井上章一と磯田道史の対談の本だったが、楽しく読めた。
日本は中継ぎとはいえ、女帝が多い(8人10代)というのは意外だった。
本当にさまざまな観点から歴史は捉えられるんだなと、いうのが感想。ただ、やっぱり対談形式は内容が薄い気がしてしまう。