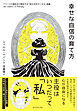児島修のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
理論と実践が入り混じった印象。大きく3部構成で各部に項目が立てられてTo Doに当たる部分はわかりやすく明示されている。が、洋書特有の長い導入が引っかかって正直読みづらさは感じた。
しかし、学ぶこと・試したいことは非常に多い1冊なので、仕事を楽しく出来ていない多くの人には、腰を据えて読むことを薦めたい一冊。
仕事を通じて幸福感などを感じるにはどうしたらいいのか、どういった時にそのような感覚を覚えるのか整理がついていなかった。
本書にはその疑問に対する答えがはっきり書いてあった。"人が仕事に満足感を覚えるのは、「進捗を実感している時」"、"職場で幸福感と充実感を高 -
-
Posted by ブクログ
ありのままの自分で人がついてくる リーダーの習慣
著:ナイジェル・カンバーランド
訳: 児島 修
「常に賢明であれ。リーダーは、日々の選択、思考、行動の積み重ねによってつくられていくのだから」
自分自身を見つめ、自己成長のための努力を欠かさないリーダーこそが、これからの時代を担う真のリーダーシップを身につけられる。自己を磨き、ありのままの自分で誠実に接することで、初めて部下はついてきてくれる。
本書は、それを実現する100個の有益なアドバイスが、具体的な実践方法と合わせて記されている。
リーダーシップの原書にあるような基本的なリーダー論を根底としてしっかりと網羅した中で、不確実な現代と -
Posted by ブクログ
【ポイント】
☆なぜ頼み事をするのは難しいのか?
・人は頼み事が成功する確率を実際よりもはるかに低く見積もっている。
・頼み事をされた側は断るのにかなりのプレッシャーを要する。
・同じ人からの頼み事を断った人は2度目にはイエスという確立が高まる。
・嫌な印象を抱いている人の頼みに応じることで、その相手への嫌な印象が薄れ、大きな頼み事に応じると、その相手が良い人のように思える効果が生じる。
・誰かを助けることで気分が良くなり、人生に対する満足度があがる
☆良い頼み方、ダメな頼み方
・鍵は自律性。相手はコントロールされていると感じた瞬間相手を助けようとするモチベは下がる。
・頼む時は誰に向け -
-