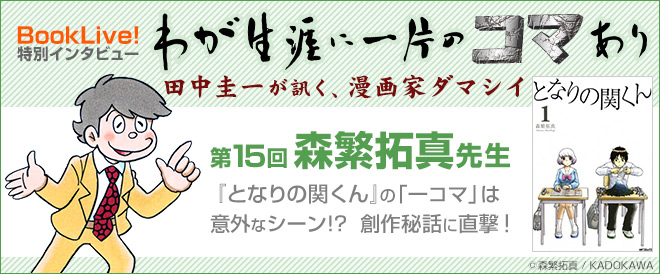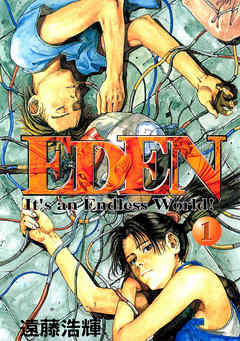田中圭一×『となりの関くん』森繁拓真先生インタビュー

手塚治虫タッチのパロディー漫画『神罰』がヒット。著名作家の絵柄を真似た下ネタギャグを得意とする。また、デビュー当時からサラリーマンを兼業する「二足のわらじ漫画家」としても有名。現在は京都精華大学 マンガ学部 マンガ学科 ギャグマンガコースで特任教授を務めながら、株式会社BookLiveにも勤務。
インタビューインデックス
- 作品の核となる「フォーマット」から逃げないこと
- コマ割の呪縛から解き放たれて、道が開けた
- 「立てるのはキャラじゃなくていい!」それに気づいた“一コマ”
- 物語に読者を引き込む「横井さん」のキャラ作り
- 姉弟でこんなにも違う「コメディの方向性」
作品の核となる「フォーマット」から逃げないこと
――『となりの関くん』は、アニメ化される前からずいぶん話題になっていて、僕もちらちらと読んでいたんですけれども、漫画家としては、あのフォーマットを守ったまま続けていらっしゃるご苦労を、まずお聞きしたいと思います。
はじめは、「単行本1巻分くらいで終わるんだろうな」と思って描いていたんですけど、やってみると思いのほか好評で、頑張る気になりまして(笑)。つらさもありましたが、なんとか乗り越えて、だんだん慣れてきましたね。
――毎回のテーマは、前回までの流れなどを考慮して決めていくんですか?
そうですね。前回が和風だったら今回は洋風、みたいな。そういう繰り返しですね。近い話でやっているオチを避けながら組み立てています。
――気になったのは、各回の一コマ目(表紙に相当する部分)で関くんが机の上でやっているネタが、本編のネタと違うところ。冒頭のネタが本編で使われていないのは、すごく贅沢というか、もったいないというか(笑)。

でも先に冒頭の方のネタが切れてきましたね(笑)。ストーリーにすると描けるんですけど、一コマのイラストで描くほうが難しかったりもして。
――お話として話を膨らませなくていい代わりに、一枚の絵としてインパクトがあるようにに心がけないといけないですもんね。僕の推測としては、2パターン考えておいて、ボツになった方が表紙になっているのかなぁと……。
実際、それはよくあるパターンなんです(笑)。けっこう再利用します。あと、音が出たり、においが出たりする遊びだと、やっぱり授業中にはできないので、それを冒頭イラストにもっていきますね。
――確かに、冒頭と中身を同じにすると、一コマ目でバレちゃいますもんね。『となりの関くん』は、毎回毎回、「何を始めるんだろう?」という楽しみがすごくあります。例えば、将棋が始まるかと思ったら、将棋だけで終わらないじゃないですか。将棋のコマを使って「あんなことも!」「こんなことまで!」みたいな。あれは、最初にオチを考えてから、広げていく感じなんですか?
実は、オチは用意しないまま考えていくんです。逆に先に考えるのは、「一番盛り上がるシーン」ですね。最初はクライマックスだけ考えています。オチは最後に残しているので、ちょっと苦しみます(汗)。
――なるほど。毎回アイデアが豊富なので、森繁先生はさぞ大変な思いをしているのかなと思ったんですけど、わりと今は楽しんでやっている感じなんですね。
そうですね、思ったよりは。コメディ的な適性があったのか、そんなに苦労はなかったですね。
――読んでいてすごく感じたのは、『となりの関くん』は「Mr.ビーン」(※1)に似ているなってことなんです。サイレントコメディみたいなノリがありますし、「Mr.ビーン」でも「この道具をこんなふうに使うのか、これをこんな用途で使っちゃうのか」みたいな面白さがあるじゃないですか。読んでいて鉄道模型が出てきたから、ジオラマでもやるのかと思っていたら「引き出しの中で地下鉄かよ!」と。あれは予想つかないですね。しかも机に穴を開けて覗いているっていう(笑)。

あれは好評でしたね。僕としてはちょっと手抜きしたかっただけなんですけど(笑)。「無理だ、今回時間ない!」ということで机の下に隠したんですけど、妙に好評だったので意外でしたね。
1990年代に人気を博したイギリスのTVコメディ番組。極めて自己中心的なイギリス紳士・ビーンが、さまざまな騒動を起こす。ビーンの行動のおかしさで笑いを誘うスタイルで、世界でカルト的な人気を獲得。日本でも一大旋風を巻き起こした。主演はローワン・アトキンソン。
――鉄道模型は、普通だと、山を作ったり駅舎を作ったりするイメージが強いですが、考えてみると、地下鉄だって電車としてはポピュラーなものですもんね。
ジオラマみたいなものを作るのは読者の予想の範囲内ですから、そこをまず裏切らないと、と思っています。いつも読んでくれる人だと、僕のネタのパターンも含めて予想してくるので、それもサッと上手にかわしながら……。そうやってアイデアを順番に考えていくのが、毎回の仕事ですね。
――それは同じギャグマンガを描いているので分かります(笑)。「読者はたぶんこっちを読んでくるだろうから、まさかこっちは分かるまい」みたいな、作り手の快感はありますよね。読者との駆け引き、頭脳戦みたいなところですね。
ところで、今までで一番苦しんだネタはどれでしょうか?
ロボット家族のネタですね。描くのが大変なので……(笑)。かといって人に任せると、なんか違うロボットになっちゃったりするので、やっぱり自分で描くしかないんですけど。

3回目、4回目になるとネタが被ってきますから、ネタ出しするのが大変ですね。将棋ネタも2回目までは平気だったんですけど、続きの3回目、4回目あたりから難しくなってきました。同じことをやっているわけですからね。「同じテーマのシリーズもの」を考えるのは、どんどんハードルが上がっていきますね。
――逆に、すんなりパパっと決まって、しかも気に入っているテーマはあります?
将棋は最初にやろうと思ったくらいですし、やっぱり簡単なものが多いですね。ボードゲームも、読者にある共通意識を裏返して作るので、1回目は楽ですね。あと、囲碁のネタをやった時は、読んだ人から「私は囲碁は分からないけど、とっても面白かったです」と言われました。逆に、まったく知識がないから面白いという場合もあります。なんにしても、ルールを無視してやっているので、誰でも分かるというものが作りやすいですね。

――しかも、ルールに縛られないというところが、斜め上にいっている感になっていますよね。ボードゲームになると、必ずバックグラウンドがドラマになるじゃないですか。横井さんの妄想が出てきて。単調になりそうな盤面だけではなく、後ろに背景があった方が「マンガならでは」って感じがしますね。
スターウォーズとか大河ドラマとか、みんなの知っている知識を使わないといけないですからね。ゾンビネタの場合だと、ゾンビは読者もある程度の「ルール」が分かるので、みんながなんとなく知っている映画なんかを持ってきて、乗り移らせるみたいなのは手っ取り早いですよね。最大公約数を狙うという。
――でもたしかに、最大公約数をどう掴まえていくかっていうのは、さじ加減が難しいですよね。
そうですね。先ほど出てきた「Mr.ビーン」とかは、なんとなくみんなが知っているので、昔ながらの海外コメディとかは、最大公約数的には使いやすいのかなと思っています。
――『となりの関くん』は、毎回同じフォーマットのネタの面白さでずっと続いているというのが、すごい力だと思いました。普通だったら、描き手がルーティーンワークに飽きてきて、違う世界にいこうとすると思うんですが、「絶対出ちゃいけない領域」をキープしながら、ちゃんと回していますから。
作品の核になるルールから出たら、「逃げたな」と思われますよね。ある意味、負けず嫌いで頑張っている部分もあるかもしれません。「逃げたな」って言われたら、言い訳ができないですから (笑)。
――やっていることがブレていない。その安心感って大事ですよね。これからこういうマンガにチャレンジする新人さんがいるなら、「絶対に出ちゃいけないエリアがあって、その土俵の中で勝負することが美しい」ということを、『となりの関くん』で学んでほしいところですね。
学んで、苦労してほしいですね! で、途中で逃げて、読者に「逃げたな」って思われてほしい(笑)。
――そこを逃げないのが、本当のプロですもんね(笑)。
コマ割の呪縛から解き放たれて、道が開けた
――ご存じの方も多いかもしれませんが、森繁先生のお姉さんは、同じく漫画家の東村アキコ先生なんですよね。
最近は忙しくて僕からの連絡をサボりがちなんですが、姉の近況はテレビなどで分かるという不思議な状況です。
――東村アキコ先生は、僕が教えている京都精華大学で、客員教授として年に2回ほど、特別講義で来ていただいているんです。東村アキコ先生の授業になると、生徒の出してくるネームのスキルがワンランク上がります。教えるのも上手いですよね。そんなお姉さんも、森繁先生のルーツの一つではないかと思うんですが、幼少期はどんな感じだったんですか?
父親が、レンタルビデオ屋でいつも「ポリス・アカデミー」(※2)を借りてきて、延々と姉弟に観せられてきました(笑)。父が真面目な映画を借りてきたことは1度もありませんでしたね。僕ら姉弟は、「自分で見たいものを借りる」という発想がまだまだなかったので、疑いもなくずーっと「ポリス・アカデミー」でした(笑)。笑える海外コメディしか観せてもらえなかったので、それが刷りこまれて、姉弟揃って“ポリス・アカデミー魂”みたいなものを持ってしまいましたね。
1984年から1994年まで全7作品が公開された、アメリカのコメディ映画シリーズ。警察学校への入学を条件に起訴を免れた主人公ケーリーをはじめ、怪力、銃器オタク、声帯模写、天然ドジなど、個性豊かな面々が警察学校でドタバタ劇を繰り広げる。
――それは見事な英才教育ですね! だからこそ子どもたちがギャグ漫画家になれたのですね、それもふたりも!
先ほど話に出た「Mr.ビーン」もまさにそうで、僕が大学くらいの時に、父から「おまえ、Mr.ビーンって知ってるか?」と興奮した電話がかかってきて(笑)。あぁ、やってるねって言ったら、「あれは面白いよ!」と強烈に勧めてきました(笑)。
――素晴らしいお父さんですよ、ホントに。姉弟で同じマンガを読んでいた、なんてことも?
よく交換して読んでいました。僕が買った少年マンガも姉は全部読んでいましたし、逆に、姉の少女マンガも僕は全部読んでいたので、読書量が倍増したというのはありますね。
――マンガに目覚めるきっかけになった作品は、『少年サンデー』のコメディ系の作品だそうですね。ゆうきまさみ先生の『究極超人あ~る』(※3)と島本和彦先生の『炎のニンジャマン』(※4)、中津賢也先生の『徳川生徒会』(※5)を挙げていただきました。
はい。『徳川生徒会』は、いかにも学園都市みたいなのを作って、その中でいろんな事件を起こすシチュエーションが決まっていて、すごく大好きな作品なんです。
1985年から1987年にかけて連載された、ゆうきまさみの代表的学園コメディマンガ。「光画部」を舞台に、個性豊かな生徒・OBたちと、アンドロイドR・田中一郎との非常識な日々を描く。
1991年から週刊少年サンデーで連載された忍者学園コメディ。バラ色の学園生活を夢見る新入生・久ノ伊千草は、入学早々現れた忍者、忍火満太郎に逆さ吊りにされ、あられもない姿を見られてしまう。復讐を誓った千草だが、満太郎の正体は忍術忍法部の頭で、留年の末同級生として過ごすことになり……!?
1984年から週刊少年サンデーで連載。舞台は300を超える中学・高校が林立する学園都市。学園都市の創始者であり総理事長の一人息子、徳川家夷(自称IQ300)が学園内の揉め事から徳川家に対する謀反まで、全てを解決していく学園ドタバタコメディ。
――こういう学園コメディの、手の届く範囲でのドタバタ劇は、すごく病みつきになりますよね。
『究極超人あ~る』は、写真部なのに、やることがなかったら野球のノックをして過ごすんですよ。しかも結構真剣に。野球部でもないのに野球ごっこをして、すごい汗を流して一日を終えたりするんですけれど、そういう無駄なことに労力をかけることに「かっこよさ」を覚えていました。
それは『となりの関くん』に直結しているところですね。無駄だけど、それに全身全霊注いでいるところは、面白いしかっこいいと思うんです。
――まさに『究極超人あ~る』のあたりから、「オタクってかっこいい」という風潮が出てきましたよね。もっと言えば、当時、僕らが大学生の頃って、吾妻ひでおさんとかのブームで、みんなが「ロリコン」と言い出した時に、「ロリコンってかっこいい」という風潮になっていましたからね(笑)。
島本和彦先生の作品もマインドは同じで。あの当時は、70年代の『巨人の星』とかの熱血を茶化している風潮があったんだけど、島本さん自身は笑い飛ばしているんじゃないんですよね。島本さんもその渦中にあって、熱血をやっているんだけれども、もう一人の島本さんが俯瞰しているみたいな感じがある。
すごく命がけで取り組んでいても、やっていることはすごく無駄という、ね。
――『炎のニンジャマン』、『究極超人あ~る』、『徳川生徒会』の共通項としては、学校が舞台のコメディということですね。
そうですね。あと、少年誌のレールから外れたマンガだったとは思いますね。少年誌に載っているのに「大人と子どもの間向け」というか。作者のセオリーはあるけれども、少年誌のセオリーを背負っていない感じが独特でしたね。
――一方で、「漫画家を目指すきっかけとなった作品」として、遠藤浩輝先生の『EDEN It’s an Endless World!』(※6)も挙げていらっしゃいますが、これは作風が全然逆方向というか、ギャグでもないんですね。
僕が大学生ぐらいの頃は、『EDEN It’s an Endless World!』が掲載されていた『アフタヌーン』がすごく面白くなっていた時だったんですけど、一番のポイントはコマ割りが簡単ということです。
――縦にぶち抜くようなコマがないですもんね。基本的に3段構成で1ページという、淡々としたコマ割りですよね。
大学で就職しようかどうしようか、という時に、この作品を読んで、「これなら僕もマンガを描けるかも」と思ったんです。
マンガって、もっと難しいものだと思っていたんですね。コマの演出とか、勉強しなきゃ無理だろうと思っていましたけど、遠藤先生はシンプルな縦横だけのコマ割りで描いていて、これだけストーリーが面白い。ならば、これを真似すればいいんだと思って、描き始めました。だから、描く背中を押されたきっかけは、遠藤浩輝先生なんです。
1997年より『アフタヌーン』(講談社)で連載されたSFマンガ作品。帝国主義的な巨大政権が世界を握る近未来を舞台にした、南米最大の麻薬カルテルのボスを父親に持つ少年・エリヤの物語。
――確かに、絵は緻密ですけれども、コマ割りはシンプルですよね。ダイナミックな絵がバーンと出るマンガではなく、対象と距離を置いて、客観的に淡々と進む。バンドデシネ(※7)っぽい感じもありますね。
もっと難しいものだろうと思っていたマンガに対して、コマ割りは関係ないんだ、ということを教えてもらった。だから『となりの関くん』でもそれは守っていて、なるべく縦横を守っていますね。
ベルギー・フランスを中心とした地域のマンガ作品を指す。内容もさることながら「絵」に重きを置くものが多く、アートとしての価値も高い。1980年代以降の日本マンガに革命をもたらした大友克洋は、バンドデシネを代表する作家・メビウスに多大な影響を受けていると言われる。
――『アフタヌーン』は当時、さまざまな表現を許容できる読者を持っていたということですよね。
そういう媒体に、こぞって才能が流れこみますよね。『週刊少年サンデー』がちょっと固くなっていったあたりから、『ヤングサンデー』が盛り上がったりして。
――90年代の『ヤングサンデー』も面白かったですもんね。
最高でしたね。僕は、最初に投稿したのが『ヤングサンデー』だったんです。あまりに好きなマンガが多かったので。
――ちなみに、マンガを初めてペンで描いたのはいつですか?
21とか22の時……大学生になってからですね。高校の時に遊びで描いたことはありましたけど、ペン入れをちゃんとしたのは20歳を過ぎてからです。
――東村アキコさんも大学を出てから、最初の投稿作品もつけペンじゃなくて、サインペンかボールペンで描いちゃって載らなかったと言ってました(笑)。
ハイテックです(笑)。宮崎県の田舎だったので、マンガ用品があんまり売っていない。周りを見ても、そういうものを持っている人がいないので、つけペンやGペンを目にすることがないまま投稿するという文化でした。
――姉と弟の両方が、プロでヒットを飛ばしているので、子どもの頃から家につけペンがあったとか、お父さんがマンガ好きで描いていたとかなのかな、と思っていたんですが、そうではないんですね。
残念ながら、そうじゃないんです(笑)。
――マンガはお好きだったということですが、「描き手に回ろう」と思ったのは、何かきっかけがあったのでしょうか。
どうしてでしょうね……。「人の顔色を伺って面白いことをする」みたいな性格は、転校が多かったのが理由かもしれません。僕、小学校は3、4回変わっていて、姉も同じくらい変わっているんです。
学校が変わると、そのクラスに溶けこむために、ウケないといけないじゃないですか。だから絵が描けて、面白いものが描けることで、その地位を得られるんですよ。その繰り返しですね。
小説家の重松清さん(※8)も、「転校生だったから、行った先でなにか人の顔色を伺って、その場の空気を読むから、だんだんと人を見る必要が出てきて」というようなことを書いていて、すごく納得しました。転校し続けると、人にウケる人間にならないと途中入場できないですから。それが僕と姉の共通点として大きかったのかなと思います。
編集者、フリーライターを経て、1990年代から作家に。1999年『ナイフ』での坪田譲治文学賞受賞を皮切りに、『エイジ』で山本周五郎賞、『ビタミンF』で直木賞などを受賞。
――僕のところに10年くらいアシスタントに来てくれている人も、全く同じ境遇でした。お父さんが転勤族で、やっぱり行った先でマンガを描いて、「絵が上手い」というきっかけで溶けこむ、って言っていましたから。でも、転校を続ける子どもたちには朗報ですね(笑)。そうやってクラスに溶けこむために、マンガや絵を勉強しようというね。
何かに秀でていると溶けこみやすいですからね。スポーツとかでもいいですし。
――あと、お父さんがコメディ映画ばっかり観せてくれたのも大きいですよね。
父は、僕が頑張って考えたネタよりも、全然面白いことをやりますから。「天然」の実力を思い知らされますよ。まだまだだなと(笑)。
――「ここでなぜこんな行動に出るの!?」という、絶対に思いつかないことをやってウケを取りますからね。そういう意味では、遺伝子を受け継いでいますし、独特な英才教育も受けていますから、なるべくしてギャグ漫画家になったみたいなところもあるのでは?
マンガとは全然関係ないんですけど、慣れない人との飲み会の席とかでは、「自分はいまお父さんだ、お父さんだ」と思って、父を降霊させて、「君は面白いね」と言われて帰るみたいなことはありますね(笑)。
「立てるのはキャラじゃなくていい!」それに気づいた“一コマ”
――今回選んでいただいた「一コマ」は、『となりの関くん』の第1巻、第2話の将棋の回で、「金が王将を裏切った」という場面。キャラが出ているコマではないので少し意外だったんですが、これを挙げていただいた理由は?
-
-
【期間限定無料】となりの関くん 1
0円(税込)
-
アプリ
立ち読み -
ブラウザ
立ち読み
ドミノ、折り紙、避難訓練、そしてネコ……。多種多様にしてその展開はナナメ上。謎の男子生徒・関くんの遊びは、なんでもない机の上を遊園地に変え、隣の席のマジメ女子・横井さん... -
-
プリンセス 2026年3月特大号
<上田倫子が描く平安ロマン「桜と揚羽」表紙&巻頭カラーで登場!! 原画展開催情報も掲載中!> ●「リョウ」の上田倫子が贈る最新作「桜と揚羽」が、第1巻発売を記念して表紙&... -
となりの関くん じゅにあ 1
「となりの関くん」の横井さんが、ママになって帰ってきた!! 関くんそっくりな個性派2才児の遊びは、やっぱり一筋縄じゃいかないようで、悪戦苦闘の毎日…。 でも、絶対に諦めない...
-