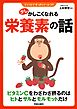ビタミンB1作品一覧
-
-健康食材として、誰もが知っているにんじん。 ドレッシングにすることによって、その健康効果がさらにアップすることを知っていますか? にんじんと親和性の高い、オイルやお酢をドレッシングに使うことで、驚きの抗酸化力を発揮するんです! ◎β-カロテンが約1.5倍! ◎ビタミンB1が約1.5倍! ◎α-カロテンが約1.5倍! 5分で作れる、基本のドレッシングに加えて、更なる高い健康効果を発揮する、アレンジドレッシングが10。 ●高血糖対策 ●高血圧改善 ●認知症予防 ●ガン予防 などなど。 おいしくて気になる症状も改善される にんじんドレッシング健康法 ぜひ お試しください!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 毎日のみそ汁は、免疫力アップと健康への近道 毎日、何気なく飲んでいるみそ汁。その健康パワーが今、注目されています。 免疫力アップや老化予防、生活習慣病を予防する効果が期待される発酵食品「みそ」。このスーパー食材を手軽にとれ、野菜や肉、魚と一緒に食べられるのがみそ汁です。 最近の研究で、腸内環境を整えると免疫力が上がることがわかってきました。みそ汁には、みそに含まれる乳酸菌、オリゴ糖、色素成分のメラノイジンのほか、具材からとれる食物繊維など、善玉菌を増やして腸内環境を整えるのに役立つ成分がたっぷり。また、みそには体の主要な構成成分であるタンパク質をつくるのに不可欠な、必須アミノ酸9種がすべて含まれています。このほか代謝を促すビタミンB1、ビタミンB2、神経を健康に保つ働きのあるビタミンB12、老化の原因となる活性酸素を抑えるビタミンE、コレステロール値を下げる働きのあるレシチン、体の調子を整えるのに必要なミネラル、食物繊維など、まさに栄養の宝庫。これだけ多くの栄養が含まれているみそを手軽にとれるみそ汁は、毎日、積極的にとりたい料理です。 この本では、みそ汁がいかに健康にとって優れているかを医師の石原新菜さんが豊富なデータとともに解説。さらに、気になる不調を予防・改善できる「体調別みそ汁」、ダイエットにも活用できる「タンパク質たっぷりなおかずみそ汁」など、飽きずに取り入れられる具だくさんみそ汁を紹介しています。 材料を「切る」→「煮る」→「みそを溶き入れる」の3ステップでできるみそ汁は、だれがつくってもおいしくできる料理ですし、具材を替えればバリエーションは無限大。食べ飽きることがないので、無理なく長く続けられます。 100歳までの長生きだってかなうかも! 毎日のみそ汁で、おいしく健康を目指しましょう。 ※本書は『1日1杯で病気を防ぐ!免疫力アップの健康みそ汁』(2018年12月発行)のサイズを変更して再編集し、コンパクト版として発行したものです ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 スポーツで勝つための身体を作りたいと考える人はトレーニング方法に注目しがちですが、身体を作る3大要素は「トレーニング」「睡眠」そして「食事」です。 「筋肉を付けたいからプロテインを飲んでいる」という声も聞きますが、必要な栄養が食事で摂れていれば、サプリメントは不要です。ですが、その「必要な栄養素」を摂るためには、何を食べれば…? そんな疑問を持った人にこそ、読んでいただきたいのが本書です。 スポーツマンに必要な栄養素は? ということを突き詰めると栄養学の話になりますが、スポーツマンやその家族、コーチなどが知りたいのは「具体的には何を食べればいいの?」という答えですし、トレーニング時や試合前など場面が変われば食べるものも変わりますし、体型や体質によっても、お勧めすす食べ物は変わります。 そこで本書では以下のような場面別に、お勧めの食事を紹介しています。しかも「ビタミンB1」など栄養素の名称だけではなく「ハンバーグ」「シチュー」「ポテトサラダ」など、具体的な食品名が記載されているのもポイント。 <場面別に食べたい食事> ・運動中の水分補給は何を飲めば? ・練習の合間に食べるもの ・運動後の疲労回復に適したもの ・試合前に食べるもの ・疲れを取る食事 ・外食する時のメニュー選び ・コンビニ食選びのポイント ・サプリメントの上手い摂り方 ・体脂肪を減らして筋肉をつける食事 ・子供の身長を伸ばす食事 ・骨折を早く治す食事 ・体重を減らす食事 ・体重を増やす食事 ・よく足がつる人向けの食事 ・貧血体質を治す食事 ・生理痛を和らげる食事 ・便秘を改善する食事 ・下痢を治す食事 ほか
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「ピーマン特有のにおいの元、ピラジンには血液サラサラ効果が!」「ねぎの辛み成分、硫化アリルと豚肉のビタミンB1を組み合わせると、疲労回復や睡眠改善に!」知っているようで知らない、野菜の持つ健康への効果効能を、キーワードで分かりやすく解説。 おいしい家庭料理のレシピやより効果が期待できる他の食材との食べ合わせのアドバイス付きです。 また、野菜の旬の時期はもちろん、「ピーマンはへたの切り口が新鮮なもの」「ねぎは指でつまんだときにフカフカしていないもの」を選ぶなど、野菜を買う時にすぐに役立つ情報も満載。男女問わず、1家庭1キッチンに1冊常備したい教科書です。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 食生活をもっと楽しく、そして健康に過ごすために! 「食材の効果」「食べあわせ」「民間療法」がわかる、日常の食生活に幅広く役立つ本! ●疲労回復、ストレス緩和、がん予防、かぜ予防……など食材のパワーや栄養素をわかりやすく解説 ●またそれらの食材(野菜、肉、魚など)の栄養素を効果的に吸収するための「食べ合わせ」も収録 例)「鶏肉(たんぱく質)」と「かぼちゃ(Bカロテン、ビタミンC)」で=かぜ予防! 例)「レタス(ビタミンC、食物繊維)」と「豚肉(ビタミンB1)」で=肌荒れ解消! ●そして「カラダを暖める唐辛子風呂」「口内炎にはトマトジュース」「鮭はカラダを温める効果がある」など民間療法としての知識も豊富に掲載しました 野菜、果物、魚介類、肉、豆類150種以上の食品の栄養素とカラダへどのような効果をもたらすかをわかりやすく解説した食材BOOKです。
-
4.0欧米の先進国に比べ、科学力ではるかに劣っていたとされる戦前の日本。しかし、実は当時の日本にも現代の技術立国の礎となる驚異的な科学力が育っていた。 科学や軍事の分野はもちろん、国家を挙げて発明を推奨した結果、産業の分野でも次々と画期的な大発明が続出。その中には現代社会でも使われているものも少なくないのだ。 昭和元年に世界で初めてブラウン管テレビの公開実験を成功させた高柳健次郎、明治44年にビタミンB1を発見した幻のノーベル賞候補・鈴木梅太郎、明治18年に世界初の乾電池を開発した屋井先蔵など、戦前の日本であった驚くべき大発明・大発見の数々に迫る!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 『デザイナーフーズ・ピラミッド』の頂点に君臨する「にんにく」! そのにんにくの5大成分、アリイン・アリシン・アリチアミン・ビタミンB1・メチルアリルトリスルフィドと「酢」の効果で便秘改善から動脈硬化、血圧、悪玉コレステロール値まで… 今回、最強のユニット石原新菜先生×管理栄養士北嶋佳奈さんで 酢にんにくのパワーをお届けします! 身体の疲れ、ストレス、免疫力強化、腸内環境改善、コレステロール、血液サラサラ、動脈硬化、高血圧、糖尿病 ダイエット、カゼ、アンチエイジングなどに効果的! 酢と、にんにくの良い所をうまく引き出し、毎日使いやすいように工夫されたレシピを集めました。 どの料理も、管理栄養士が考案したレシピです。 ご家庭に合ったレシピを試してください。 ※デザイナーフーズ・ピラミッドとは、1990年にアメリカのNCI(国立癌研究所)が打ち出したプロジェクトです。
-
-免疫“食”は強さじゃなくバランス! ウイルスに負けない「最良の食材」「最善の食事法」とは いまだ特効薬のない新型コロナウイルス感染症に対して、食事の面でどう免疫力をつけて、感染予防を心がけるか? 本書では、ヨーグルト博士としてテレビ番組に出演した、食品免疫学のプロ・戸塚護氏が「免疫とは何か」「免疫食は強さでなくバランス」といった基本的な仕組みから、「具体的にはどんな食材が免疫力の向上・調整に効果があるか」といった具体的な食事法まで、最先端の食品免疫学の研究などを多数紹介し、わかりやすく解説。 この本を読めばもう、どの食材を買い、どう調理したら「免疫にいいか」を迷うことはありません! たとえば、ヨーグルト+きなこ、はちみつ、キムチ+納豆といった食事の組み合わせは、体の中で最も大量に免疫細胞を生み出し、体内の免疫バランスを整える大腸の活性化に最適です。 大腸で免疫力の活性化に貢献している乳酸菌、納豆菌などプロバイオティクス(体にいい影響を与える微生物)の働き、役割、そしてそれらを含む食材や食べ合わせについても多数紹介。 新型コロナウイルス感染症の蔓延で注目された食品各社の商品別ヨーグルトの機能分析もとても参考になるはず! オメガ3脂肪酸、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンB1、ビタミンD、亜鉛、セレン…など、体内免疫を高めるために必要な栄養素やそれを含む食材なども幅広く取り上げ、この1冊で「ウイルスに負けない最高の食事術」がわかる、画期的な食事術の本。 この本を読んでウイルスに負けないための食材選び、免疫向上レシピ、免疫細胞を活性化し最高のバランスで備える食事術をどうぞ学んでください!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ビタミンCをわざわざ取るのはヒトとサルとモルモットだけ、出て行くからこそ体にいい食物繊維、二日酔いに渋みが効くタンニン、「江戸わずらい」の原因はビタミンB1など、周りのひとにも教えたくなる、身近な食べものに潜む、栄養素のびっくりするような力を、イラストでわかりやすく解説。※電子版では、紙で出版された内容と一部異なる場合や、削除及び修正している写真、イラスト、ページなどがある場合がございます。予めご了承の上、お楽しみください。
-
3.0欧米の先進国に比べ、科学力ではるかに劣っていたとされる戦前の日本。しかし、実は当時の日本にも現代の技術立国の礎となる驚異的な科学力が育っていた。 科学や軍事の分野はもちろん、国家を挙げて発明を推奨した結果、産業の分野でも次々と画期的な大発明が続出。その中には現代社会でも使われているものも少なくないのだ。 昭和元年に世界で初めてブラウン管テレビの公開実験を成功させた高柳健次郎、明治44年にビタミンB1を発見した幻のノーベル賞候補・鈴木梅太郎、明治18年に世界初の乾電池を開発した屋井先蔵など、戦前の日本であった驚くべき大発明・大発見の数々に迫る!
-
-ボディラインや肌の吹き出物、気になっていませんか? そんなときには「豚こま」です。豚こま切れ肉には代謝アップ効果のあるビタミンB1や、美しい肌を作るビタミンB2が豊富! そのうえ安いのもうれしいところ。毎日の食卓の強い味方です。電子書籍版限定で井澤由美子さんによるレシピも掲載。豚こま切れ肉をおいしく食べて、燃えやすい体、キレイな肌を目指して!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「夏バテ防止に効果あり!」と宣伝されることが多い豚肉。ビタミンB1の含有量が多いことはよく知られていますよね。そのほかにも、私たちには欠かせない栄養素がたっぷり含まれている豚肉の栄養価について、管理栄養士さんにお話を聞きつつ、人気ブロガーさんにおいしい豚肉レシピをたくさんご紹介いただきました。美味しくヘルシーに、豚肉の栄養効果を摂取して元気に暮らしていきましょう。 【ご利用前に必ずお読みください】■誌面内の目次やページ表記などは紙版のものです。一部の記事は、電子版では掲載されていない場合がございます。■一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。■電子版からは応募できないプレゼントやアンケート、クーポンなどがございます。以上をご理解のうえ、ご購入、ご利用ください。 ●表紙 ●巻頭特集 栄養の宝庫!毎日でも食べたい健康食材 豚肉のおいしい秘密 ●第1章 豚バラ肉(スライス&ブロック) ◎番外編 すぐ作れる豚加工肉レシピ【ハム編】 ●第2章 豚こま切れ肉レシピ ◎番外編 すぐ作れる豚加工肉レシピ【もつ編】 ●第3章 豚ロース肉レシピ ◎番外編 すぐ作れる豚加工肉レシピ【ソーセージ編】 ●第4章 豚ひき肉レシピ ◎番外編 すぐ作れる豚加工肉レシピ【ベーコン編】 ●第5章 豚ヒレ&もも肉レシピ ●豚肉雑学エトセトラ
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※本ムックはカラーページを含みます。お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。 甘酒は、昔から夏バテ防止の栄養ドリンクとして飲まれてきました。 栄養学などなかった時代に麹の持つ健康効果がわかっていたからです。 このムックでは、アルコールと砂糖は一切使わず、お米と米麹だけでつくられる 「麹甘酒」に焦点を当てています。 いま、腸を整えることが健康につながると言われていますが、 腸を元気にするために簡単にできるのが毎日、食後に麹甘酒を飲むことです。 甘酒には腸の善玉菌のエサとなるオリゴ糖と食物繊維が豊富で、 弱った腸の粘膜や腸のバリア機能を高めて悪玉菌の増殖を抑えます。 また脳の働きを促すビタミンB1、老化の元となる活性酸素を消去するビタミンB2、 健やかな肌を作るパントテン酸、がんや動脈硬化を予防する葉酸など ビタミンB群が豊富に含まれています。 みずからも甘酒を毎日欠かさず飲んでいる、医師や麹研究者など5人に 甘酒と麹の最新の健康と美容効果について取材しました。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 脳がよろこぶ食材がたっぷり! 認知症予防にスープがおすすめな理由 1. 手間なく作れるから毎日続けやすい 2. 食材の栄養をまるごと食べられる 3. 水分を定期的にしっかり補給できる (以下「はじめに」より) 認知症予防に効くというエビデンスのある物質を含む食品の代表が、次の4つです。 ①抗酸化作用の強いβ-カロテンを含む「ニンジン」 ②認知機能の維持に役立つケルセチンを含む「タマネギ」 ③脳の機能維持に欠かせないビタミンB1を含む「かつおぶし」 ④動脈硬化を予防するイソフラボンを含む「きなこ」 この4つの食材で作ったのが、「脳がよろこぶスープ」のスープベースです。電子レンジで簡単に作れて、作り置きもできるものです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「やっぱり米が最強だ!」 元WBAミドル級スーパー王者 ロンドン五輪ボクシングミドル級金メダリスト 村田諒太さん推薦! 元ボクシング世界チャンピオンの著者が教える! 健康的に痩せる細マッチョルーティーンで 1ヵ月で4キロ痩せる! 細マッチョルーティーン 白米はがっつり食べてOK! コンビニ・ファミレスも活用して 健康的なルーティーンをつくりあげよう。 白米を食べれば、 ・腹もちがよく、満たされるので、リバウンドしない ・ごはん1杯に含まれる栄養は、 炭水化物、たんぱく質、食物繊維、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、 鉄、ビタミンB2、ビタミンB1、脂質など10種類もある ・お米に含まれる多糖は、ゆっくり消化吸収され、 血糖値の上昇もゆるやか。カラダへの負担も軽いし、脂肪にもなりにくい そして、 白米:おかず=6:4で太らずしっかりしたカラダづくりができます。 明日から実践できるよう、タイプ別メニュー例なども掲載。 実践あるのみ!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 やせたいために、カロリーを減らすことに専念していると、栄養が偏って糖質や脂質を燃焼しにくい体になり、ダイエットにはかえって逆効果です。最近では、カロリーが少しくらい高めでも効率よく糖質や脂肪を燃やすダイエット法が注目されています。そこで注目したいのが豆料理です。豆は「鉄」「カルシウム」などのミネラル分をはじめ、糖質代謝に役立つ「ビタミンB1」、脂質代謝に役立つ「ビタミンB2」などを豊富に含み、食物から摂ったカロリーをエネルギーに変換し、燃えやすい体をつくります。また特に大豆に含まれる「βコングリニシン」を摂ることで内臓脂肪が減少すると言われています。さらに、ごぼうよりも食物繊維を多く含み、その一種「フィチン酸」の働きで有害物質を体外に排出する解毒効果も期待できます。その上大豆のタンパク成分が消化されるときにできる「ペプチド」は満腹中枢を刺激し、食事量を減らせます。こんないいことずくめの豆ですが、豆好きの人でも料理の種類をそれほど知らないのが現状です。下準備がたいへんと思っている人も多い。実はレンズ豆や緑豆、小豆など、水で戻さずに調理できる豆もあるのです。本書では、おなじみの浜内千波さんが、栄養バランスがよく、ダイエットにつながる豆レシピをふんだんに用意しました。おためしあれ!
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 基本ルールはひとつ。 炭水化物を今の半分に減らし、 血糖の上昇を抑える食品(水溶性・不溶性食物繊維)、 糖の分解を助ける食品(分解酵素アミラーゼを含む食品)、 糖の代謝を促す食品(ビタミンB1を多く含む食品)、 糖質を燃えやすくする食品(硫化アリルを多く含む食品)に置き換えるだけ。 加えて、ベジファーストを守り、20時以降の食事は控えめに。 これをベースに、自分の生活スタイルに取り入れやすいマイルールを決め、突き進む。 「働き盛りの男は太る」「食べないと体力が落ちる」「飲み食い、宴席は仕事の一部」 「深夜の食事に朝食ぬき」をアイデンティティに90kg台に達した男たちが、 3カ月のダイエットに挑戦。 50%オフの原理原則をいかにマイルールに落とし込んで行ったか、 50%オフレシピとともに紹介する。 糖化はさまざまな病気を引き起こし、見た目印象も老けさせる。 今こそやせる食べ方をマスターして、健康とカッコイイを手にしよう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 幅広い料理に使えて、晩ごはんに登場する回数もピカイチの豚薄切り肉。 包丁いらずで簡単・手間なしの豚こま肉もプラスした、使えるレシピ集の登場です! 豚肉は、良質なたんぱく質、脂質のほか、疲労回復ビタミンといわれるビタミンB1が豊富で、 夏の疲れが残る季節には、特におすすめの食材です。 にんにく、しょうが、玉ねぎ、梅干しなどと組み合わせた、元気になれるおかず、 酢豚、肉野菜炒め、肉じゃがなど、くり返し作りたい人気レシピを集めました。 野菜がたっぷりとれるメニューも豊富だから、1品で栄養バランスもバッチリ。 さらに薄切り肉で野菜を巻いたり、こま切れ肉をぎゅっと丸めたり、のアイディアおかず、 冷凍できる豚肉の作りおき、 ボリュームたっぷりの豚丼など、盛りだくさんです。 手間はかけずにおいしく元気に、は豚薄切り肉で!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 <b>アズキの解毒力に注目! 多くの研究で実証済み、砂糖ゼロでやせ体質に―― アズキと発酵のWパワーで病気知らずの体づくり 「アズキ博士」として知られる名寄市立大学の加藤敦先生が実施した さまざまな研究により、アズキには血糖値、血圧、中性脂肪値が下がる などの効果があることがことがわかっています。 また、発酵に欠かせない「米こうじ」は腸内環境を整える伝統的な食材。 腸内に善玉菌を増やして、免疫力をアップしてくれます。 この「アズキ」を「米こうじ」で発酵させた「発酵アズキ」は、 まさに健康効果の宝庫! ビタミンB1が豊富で、血行を促進し、冷え予防や美肌・美髪に。 また、脳も活性化し、疲れが取れてリラックス効果も。 さらに腸内環境が整うことで便秘やアレルギーも改善。 そして発酵アズキは砂糖を使用していないのに甘みがあるため、 スイーツや料理に使うことでカロリーを抑えることができて、 ダイエットにも効果的なのです。 「発酵アズキ」を毎日の食生活に取り入れて、健康な心身をつくりましょう。