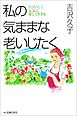エッセイ・紀行 - いのち作品一覧
-
4.5
-
4.0
-
3.8
-
4.0看取り士(みとりし)――逝く人の最期に寄り添い、見送る人。また、家族だけでの看取りをサポートする人のことをいう。本書は、25年ものあいだ、生と死に向き合い続けた看取り士・柴田久美子のエッセー。 日本人のおよそ8割が病院で最期を迎える一方で、その約5割が「自宅で最期を迎えたい」と願っているといわれる。しかし、自宅で看取る文化が薄くなった現代社会では、看護・介護する側がその望みを叶えてあげたくても難しい事情があるのが現実だ。こうした状況から、著者は「尊厳ある最期が守られる社会を創りたい」と願い、自らを「看取り士」と名乗った。 200人以上のケースをもとに、看取りの際の心構えや実際の触れ合い方に加え、エンディングノートの活用の仕方、旅立つ人から魂(いのち)を引き継ぐ大切さなどを紹介。厚生労働省が在宅医療・介護への方針転換を始めた今、自らの、そして大切な人のQuality of Death(QOD/死の質)を考え、より良い人生、より良い最期を送るための手引書となる。 巻末には、医師・鎌田實氏(諏訪中央病院名誉院長)との対談を収録。看取り士の誕生秘話をはじめ、死に対する二人の考え、地域包括ケアという共通の夢について語り合う。
-
4.0
-
4.5
-
4.0
-
4.3《ささやかだけど、かけがえのないことが、世界を変えていく》 環境問題の先駆者として名高い科学者レイチェル・カーソンが、愛する甥に遺した『センス・オブ・ワンダー』。 その小さな本には、危機の時代を生きるための大きなヒントが詰まっている。 仕事や人間関係など身近な生活のレベルから気候変動までを貫く不滅のメッセージを、批評家・若松英輔が読み解く。 -------------------------------------- 私たちは確かに自分に必要なものを、自分で見つけることができます。ただ、 そのときの「自分」とは他者に開かれた「自分」なのです。 「よろこび」が先にあれば、必ず「学び」は起こる。本当に、深いところでよろこびを経験すると、私たちのなかで「学ぶ」というもう一つの本能が開花する、そうレイチェルは感じています。 ――「ただ、相手と共にいて、一緒に驚き、よろこぶこと」が育む、未来を切り開くちからとは。 --------------------------------------
-
3.3【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 脳科学者も絶賛! 91歳、ボケを恐れすぎない樋口恵子さんの暮らし方、考えグセなど老いのトップランナーの生きざまを綴る。 「老いの地平線」には何があると思いますか? 老いのトップランナー・91歳の評論家 樋口恵子さん。 脳科学者・瀧靖之教授(東北大学加齢医学研究所)から「樋口さんの生活・習慣は、脳によいことばかりです!」と絶賛された暮らしとは?「いやいや、自信をもっていいます、年齢なりにボケてますよ」 「老いても老いても、果てがない。何歳になっても老いは続く」とは樋口さんの談。 2人の夫を見送り、80代で家を建て替え、超高齢期に2度目の乳がんの手術をし、91歳の今なおヒット本を連発。 月刊誌で新連載もはじまった。介護保険制度の改正や、ヤングケアラー問題へも目を光らせる。 認知症と老後貧乏・孤独への不安、超高齢期に多少ボケても、自分の美点や尊厳を失わずに生き続けたいと願う人へ、 樋口さんの暮らしグラビアや痛快エッセイは、必ずよき老いへのヒントをくれるはず。 ボケるのが怖い人、老後の暮らしを心配している人、まだまだ夢をもって超高齢期を迎えたい人、 親や祖父母世代が認知症になったらどうしようと悩む若い人、 どんな世代にでも、男女差なく読んでいただきたい本です。 猫と暮らす樋口恵子さんの普段の暮らし、考え方、人生のなかから「ボケにくい8の習慣」を紹介。 その習慣とは、 『モノは捨てない・おしゃれ心を忘れない・たわいもない話をする&筆まめに・ 猫を愛する・社会に関心を持ち続ける・花を愛でる・なるべく自力で歩く・いつまでも食いしん坊』。 ほかに巻頭グラビアで、「91歳が安心して住める家実例」「100歳へ向けて 人生アルバム」を紹介。 また、「老い方、ボケ方、人生いろいろ」「多病息災 百歳確実」 「91歳、本当はひとりでも大丈夫じゃない」など痛快新作エッセイも多数掲載。 樋口さんのように生きれば、「老いの地平線」=最晩年まで脳を育て続け、ボケすぎずに社会とつながり、 大夢を画(えが)き、自分の長所を残したまま、笑って生きられる! 上野千鶴子さん(社会学者)との「貧乏ばあさんの生きる道対談」、脳科学者・瀧靖之さんとの「ボケにくい!健脳対談」も収録。 樋口 恵子(ヒグチケイコ):1932年生まれ、東京出身。東京大学文学部卒業。時事通信社、学習研究社勤務などを経て、評論活動に入る。東京家政大学名誉教授。同大学女性未来研究所名誉所長。NPO法人高齢社会をよくする女性の会理事長。内閣府男女共同参画局の「仕事と子育ての両立支援策に関する専門調査会」会長、厚生労働省社会保障審議会委員、地方分権推進委員会委員、消費者庁参与などを歴任。『大介護時代を生きる』『老~い、どん!(2) どっこい生きてる90歳』『老いの玉手箱』『BB(貧乏ばあさん)の逆襲』など著書多数。
-
4.0【こだま最新作、刊行決定!】 おしまいの地シリーズ、ついに完結! 『ここは、おしまいの地』、『いまだ、おしまいの地』に続く、 “おしまいの地”シリーズ三部作の完結編! 累計22万部突破した衝撃のデビュー作『夫のちんぽが入らない』、 第34回講談社エッセイ賞を受賞した『ここは、おしまいの地』、 名エッセイストの仲間入りをしたこだまが放つ最新刊 <内容> 10年以上夫に誕生日を告げられない話、マルチ商法に漬かった母の話、ヨガ教室で反コロナに目覚めた父など、珠玉のエッセイを多数収録予定。 【目次】 先生のお葬式 きょうが誕生日だってずっと言えなかった ピカチュウの凧 花火きれいでしたね 抗鬱の舞 何かに目覚めた私たち タイムカプセルの行方 日記(2021年~) 父の終活 直角くん あの時の私です ほか ※本書は『Quick Japan』連載「Orphans」(2020年10月~2021年12月)/ブログ『塩で揉む』(2021年~)/『OHTABOOKSTAND』(2022年6月、7月)に大幅な加筆・修正を加えたものです。
-
-人の心模様や日常も様変わりしています。 2002年から2019年までに起こった 日本や世界のできごと、旅先での気づき、 家族のことや身近な人の死について綴った 珠玉のエッセイ集。 そのエッセイを読むことで 「こんなこともあった」と思い返したり、 追体験をすることができるかもしれません。 【目次】 まえがき 1 拉致問題と現代日本若者像 2 乳母制度考 3 高円宮様追悼~“もったいない” 4 2003年頭に想う 5 南の島から帰国して 6 早春の診察室~親子学歴戦争 7 virtualとreal~時の流れの中で 8 いのち 9 教育審議委員会から~学ぶ意欲と学力の定着 10 故郷の山々に想う 11 笑顔 12 心の祖父の死 13 JR福知山線脱線事故に想う~日本社会の強迫性 14 清宮様のご結婚~母から娘へ 15 ガーデニング~植物への愛 16 愛犬モエム 17 ダイビング~地球は生きている 18 水泳にはまる 19 絵画と美術的趣味 20 グローバリゼーション 21 桜咲く? 22 過呼吸発作、パニック発作 23 5月病と梅雨鬱 24 ジャパンマスターズ 25 日本列島猛暑2013年夏 26 台風18号の大掃除の後…… 27 長い記憶 28 モーターショー 29 2014年初頭に想う 30 大雪とソチオリンピック 31 春が来た! 32 アメリカの対極 33 2014ブラジルW杯 34 海水まみれの夏 35 御嶽山の噴火 36 健さんの死 37 中国人の爆買 38 レジリエンス 39 カンクン旅行 40 「癌死」について 41 飛んで○○○に入る夏の蜂 42 人生を変える時 43 叔父に捧げるレクイエム 44 ニューヨーク~バハマ父娘旅行 45 鏡がなくなった 46 結婚の意味とパートナー制 47 スポーツメンタルにおけるグローバリゼーション 48 平成最後のニュース~プラス思考とマイナス思考の人間 49 イチローの引退~平成から令和へ あとがき
-
-朝日新聞家庭欄に、 1997年から連載中の好評コラムを、 単行本にまとめた実用エッセー。 ●著者は1918年、東京生まれ。 生活評論家として新聞・雑誌で活躍中。 「老いは死を待つ時間ではなく、 未知への道すがらなのですから、 すべてを終える日まで、無理なく、 素直に自分らしく生きていくのが一番いい。 旅じたくのバッグに旅の楽しみを入れていくように、 未知の老いへの道すがらにも、 楽しいことはいっぱいあるにちがいない、 と思いついたのです」と、 この本の「はじめに」で語る著者。 年ごとに出会う自分の老いを、 「はじめまして」という気分で、 面白さに変えていく著者の発想が実に前向きだ。 きりりとした姿勢で生きるさわやかさと、 いのちを見つめる目のあたたかさが共感を呼ぶ、 中高年のバイブル。 第1章*年を重ねたら、毎日が発見 第2章*季節がくれる恵み、食する幸せ 第3章*おしゃれ心を忘れず、はつらつと暮らす 第4章*人とつきあう、いのちをはぐくむ 第5章*賢く楽しく使いたい、お金と時間 第6章*心と健康を守る、日々の心配り
-
-
-
3.5〈 迷い、悩み、疲れているあなたへ 〉 NHK「100分de名著」の人気指南役が贈る、目まぐるしい日々を生きるあなたに寄り添う言葉。 --------- 〈 自分を支える言葉は、実は自分自身の中にすでにある 〉 生きていくうえで、何が大切なのか。どこを目指して進めば良いのか。 迷いのなかから再び立ち上がり、前を向いて歩き始めるために、「自分だけの一語」を探す心の旅の導きとなる一冊。 --------- 年齢を重ねると自然に生活の幕は開く。勉強の期間を終え、仕事に従事するようになれば、生活との格闘はいやでも始まる。 だが、人生の扉が開く時期は人それぞれだ。早ければ早いほどよい、というのではない。ただ、どこかでその扉にはふれなくてはならない。 人は、自分の人生を生きない毎日を送り続けることはできないからである。 生活は水平的な方向のなかで広がりを求めて営まれるのに対して、人生は一点を掘り下げるようにして深まっていく。 生活のなかで人は、多くの言葉を知る。そうすることで会話も読書も執筆もできるようになる。 だが人生の一語は、そうした場所では出会わない。それはいつも切実な経験とともにある。 その言葉とは、広がりのなかではなく、深みにおいて遭遇する。 〈「人生の一語」より〉 --------- 【目次】 ■人生の一語 ■自分を愛する ■人生の羅針盤 ■かなしみの国 ■願いと祈り ■ひとりの時間 ■メモと「書く」 ■沈黙を感じる ■言葉と食べ物 ■生きがいとは何か ■見えない涙 ■似て非なるもの ■眼のちから ■五つの眼 ■黄金の言葉 ■心の水 ■時を取り戻す ■拙いものと切なるもの ■最期の言葉 ■人生の土壌 ■尊い姿 ■よろこびの花 ■いのちのコトバ ■いのちの使い方(一) ■いのちの使い方(二) ■見えない手 ■言葉のひびき──あとがきに代えて ■探していた言葉に出会うためのブックリスト
-
-「生まれてきてくれてありがとう」 悪性リンパ腫で2022年2月に余命宣告を受けた父親が、 一人娘に在りし日の自分の姿を残そうとYouTubeを始めました。 愛娘・風花さんに伝えておきたい“いのちのメッセージ”とは? 2019年に悪性リンパ腫になった加治川健司氏。 その後、2回の抗がん剤治療を行うも、完治には至りませんでした。 2020年、3回目の抗がん剤治療を行わない選択をします。 そして2022年2月、2回目の余命半年の宣告を受けます。 そのとき加治川氏が考えたのは、一人娘の風花さんへのこと。 そこで、加治川さんが死を直面して心残りとなる娘さんへの想いを語った加治川家の家族の絆が強く感じる一冊です。 【内容】 第1章 突然のがん告知――。そこから始まった闘病 第2章 自分と靖子が出会って、そして風花が生まれてきてくれた 第3章 2回目のがん告知。抗がん剤治療への苦悩 第4章 2022年2月、YouTubeを始めた理由 第5章 がんになったからこそ、わかったこと、そして伝えたいこと
-
4.0「並外れた悩む力を持っている牧師だからこそ、 人の悩みを受け止められるのかも。 」 ──帯文・末井昭 ネットで誰もが石を投げあい、誰もが傷つけあう時代に、牧師の祈りはいのちとつながっている。 かつて精神を病み、閉鎖病棟での生活も経験した牧師。何度もキリストにつまずき、何度もキリストと繋がってきた牧師が営む街のちいさな教会は、社会の周辺で生きる困難な事情を抱えた人たちとの出遭いの場でもある。宿を求めて夜の街で男をラブホにさそう少女、大人たちから裏切られ続け人を信用できなくなった青年、完治が難しい疾病で苦しむ患者、「いまから死にます」と深夜に電話をかけてくる人……。本気で救いを必要とする人びとと対話を重ねてきた牧師が語る、人と神との出遭いなおしの物語。 「本書のなかで、わたしは自分が遭遇し、巻き込まれてしまったイエス・キリストの話を語っていくだろう。それはキリスト教についての神学的な叙述にはならない。なぜなら、わたしがこれから話すことは、そのほとんどすべてが、目の前に現れた他人たちとの出遭いについてだからである。わたしにとって神について語ることはすなわち、目の前の人と出遭い、そこで生じた共感や対立、相互理解の深まりや訣別、その喜びや怒り、悲しみなどの、生々しい出来事を語ることだからである。」(まえがきより) 【目次】 まえがき──自由意志なのか。奴隷意志なのか。 ■第1章 割り切れぬものを噛み締めて アイドルとキリスト ねえ、ラブホいかへん? 放っておいてくれませんか。あなたには分からない わたしは償ったのか? 伴走し続けることの難しさ、大切さ 聖書のなかの「かわいそうランキング」 赦しを語ることができない ■第2章 背負えることと背負えないこと 結婚式の祝辞 「独りで抱え込まないで」の背理 こちらも無傷では済まない 誰がその責任を負えるだろうか 仏教的文脈のキリスト教 自分を責めてしまうことからの回復 わたしは加害者であり、被害者である ■第3章 いのり、いのち 彼女にはまぶしすぎた 十二使徒たちの確執 後にいる者が先になり、先にいる者が後になる 謝罪から新たな関係の模索へ 悔いのない人生はおくれるか 誰もが石を投げる時代で キリスト教にはカルトになる要素があるのか? あなたは憐れみの目を向けてはならない あとがき
-
4.0なんだこの文章! これはほんとうに人間の生身の男の人が書いた文章なのか? 家や森や草や風が書いたんじゃないのか? すごい人だ。 ―――吉本ばなな 『こといづ』とは「コトが出づる」という意味の造語です。 丹波篠山の小さな村で暮らす日々の驚きと発見、高木夫妻の家にたびたび遊びにくる80代のハマちゃん・昔気質の大工職人スエさんをはじめとする愛すべき村人たちとの交流、映画音楽ができるまでの苦悩と喜び、ソロモン諸島・エチオピアをはじめとする旅の話、自然と人間の限りあるいのちについて……。ピアノを弾くように、歌をうたうように綴られる言葉を、2012年から現在まで続く雑誌ソトコトの連載から収録。高木正勝による初の著書であり、この世界のすべてがいとおしくなるエッセイ集です。 この本にもよく出てくる86歳のハマちゃんがよく言います。「あるんだから」。そう、あるんだから。ついつい、あれがあったらなあ、ここがこういう場所だったらなあと、ない物ねだりをしてしまいますが、目の前にいっぱいある、あふれるようにあるものごとにこそ気づいて、一緒に楽しく心安く暮らしていけるだけで、だいたいいつも幸せでいられるのだなと知りました。 (本書「はじめに」より)
-
-本書は、季刊『道』に掲載したインタビュー集です。 戦争を生き抜き、その理不尽、悲惨さを語ってくださった方々のお話をまとめました。その体験、思いを後世に伝え残したいと願うものです。 園田天光光 日本初女性代議士 元外相夫人 やり抜く意志が肚をつくる 中沢啓治 『はだしのゲン』作者 広島原爆の惨状を生き抜いて 踏まれて育つ麦のように強くあれ 坪井 直 日本原水爆被害者団体協議会代表委員/広島県原爆被害者団体協議会理事長 ネバーギブアップ!「命が一番!」の祈りがかなうまで 谷口稜曄 長崎原爆被災者協議会会長 「原爆を背負い続け67年」 笑顔の奥にあるものを伝えたい 苦しみ憎しみを乗り越えて今こそ核廃絶への思い 山里和枝 沖縄戦 語り部 沖縄の祈り 語り伝えるために生かされて 根本益伊 軽巡洋艦五十鈴乗組員 命をつないだ一本の手拭い 木村 孝 中国帰国者定着促進友の会 元事務局長 終戦から始まった戦禍 ― 8月9日ソ連侵攻~引き揚げまで ― 原田 要 最後の零戦パイロット 命をかけた 平和を守り抜くために 太田リセ 日本赤十字社従軍看護婦 軍国少女、あこがれで看護婦に 金子兜太 元海軍主計大尉/俳人 信念のままに伝え続ける 反戦の思い 木内信夫 元陸軍飛行兵/シベリア抑留生存者 世界の人は みんな仲良くなれるのです 三村 節 シベリア抑留体験者 絶望の中を生き抜いて 未来永劫の平和を守るために
-
4.0日記文学の到達点! 私たちが過ごした“緊急事態の日常"を真空パック ――緊急事態宣言におののきながら、マスクに悩み、赤子をあやし、犬と遊び、朝顔を育て、断酒を続け、本を読み、原稿を書く……「徹底的な凡人」を自任するフリーライターが綴るコロナ禍下の日々。平日17時毎日更新で人気を博した連載エッセイ「モヤモヤの日々」(晶文社スクラップブック)全251回分を完全収録。 「自分にとっては切実だけど人から見たら割とどうでもいい事。そんな物事が渦巻く人間の頭の中味がそのまま書かれてありました。実は偉大な思想家の頭の中も九割はこんなことで占められているのではないかと思いました」(町田康さん) 「日々のささいなことに"いのち"を吹き込んでいく実践。コロナ禍で鈍った感性が活性化する、そんな言葉の数々。想像力も生き生きと、そして、もぞもぞと蠢き始めます。花、ダンゴムシ、犬、赤子、父親、福生――」(小川公代さん) 目次 序 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 主な引用・参考作品