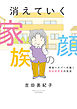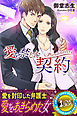若年性認知症作品一覧
-
-『第三文明』2024年7月号 【特集】〈「ケア」をしあう社会〉かけがえのない他者と支え合って生きる――「ケア中心社会」へ 竹端寛/現代社会に必要なダブルケアという視点 相馬直子/高次脳機能障害と若年性認知症支援を 駒井由起子/【特別企画】〈プチアウトドアのすすめ〉心身ともに健康に! サイクリングの魅力 渋井亮太郎/イスを持って出かけよう! 「チェアリング」で自然を満喫 パリッコ/身近な非日常 「ベランピング」を楽しもう! 小雀陣二/【インタビュー】[ワハハ本舗40周年記念対談]今後も誠心誠意〝くだらないこと〟を続けたい! 柴田理恵×佐藤正宏/[対談]"あきらめない心"が結実した世界初の薬事承認 茂木健一郎×織田友理子/500年の時を超えて受け継がれた楠木正成の志 一坂太郎/福島の知見を生かして情報災害に対峙する 林智裕/[講演会]「水墨画と法華文化を語る」 傅益瑤/政治改革は公明党が主導すべし 藪野祐三/[寄稿]田村委員長の"嘘"と相次ぐ民事訴訟 柳原滋雄/【TOPIC】[映画紹介]石原さとみ主演『ミッシング』が映し出す社会と人間――悪意、暴力、苦しみ、そして一筋の光/市民社会や若者が地球規模の課題を解決する時代の到来/【連載記事】《希望の源泉・池田思想を読み解く*佐藤優》(96)リーダー論として読み解く「観音品」/《人生を切りひらく力~池田大作の読書論》(16)/《シリーズ震災からの歩み》(146)地域は大きな家族――循環型支援の取り組み 馬場照子/《シリーズ「こどもまんなか社会」への道》(4)保護犬を介した子ども・若者への自立支援 上山琴美/《戦間期の世界と遷移期の米国――不確実な時代を日本はどう歩むか》(2)恩師・五百旗頭真先生のご逝去――人間愛ほとばしる師の志を継承 簑原俊洋/《池田大作と中国――万代にわたる日中友好*胡金定》(57)敦煌のロマンが結んだ交流/《RE:THINK~青年たちの仏法探究~》(14)/《生まれ変わるような朝に*柳美里》(8)親心のアンビバレント/《二宮清純presents対論・勝利学》自ら立てた目標に対する強烈なこだわりと挑戦 木村敬一/《柳生九兵衛のおでん食うべえ!》(25)青森生姜味噌おでん/《作家・雨宮処凛が見る世界》「こわれ者の祭典」/《笑顔の世界へ*アグネス・チャン》会える時を逃さない/《連載漫画 子連れ宇宙人パテラさん》(37)「"子持ち様"上等!?」/ほか/*電子版は、印刷版とは一部内容が異なります。掲載されないページ、写真があります。また、機能上の制約その他の理由により、印刷版と異なる表記・表示をした箇所があります。
-
4.3【あらすじ】 「ある日突然、45歳の夫が若年性認知症と診断された」 佐藤彩は、夫・翔太の物忘れが増えたことを最初は気に留めていなかったが、決定的な出来事が起き、病院へ連れていくことに。 そこで医師から言い渡されたのは「若年性認知症」という残酷な宣告だった。いずれ時間や場所の感覚がなくなり、家族の顔でさえわからなくなる病。 なんとか前を向こうとする彩だったが、病状が徐々に悪化するにつれて夫は知らない一面を見せるようになっていき―――。 若年性認知症と向き合う家族の3年間を描いた闘病セミフィクション。 【解説】 古和久朋(認知症専門医) 「認知症の共生社会を目指して」 【「シリーズ 立ち行かないわたしたち」について】 「シリーズ 立ち行かないわたしたち」は、KADOKAWAコミックエッセイ編集部による、コミックエッセイとセミフィクションのシリーズです。本シリーズでは、思いもよらない出来事を経験したり、困難に直面したりと、ままならない日々を生きる人物の姿を、他人事ではなく「わたしたちの物語」として想像できるような作品を刊行します。見知らぬ誰かの日常であると同時に、いつか自分にも起こるかもしれない日常の物語を、ぜひお楽しみください。
-
4.3★ニューヨーク・タイムズ ベストセラー ★ジャーナリストと医師が食べ物と脳の関係を徹底解明! ★脳のモヤを晴らし、最高のパフォーマンスを発揮するための具体的なガイド ★精神科医樺沢紫苑氏絶賛!!! ◎母親の若年性認知症にショックを受けた筆者が、 脳の健康とパフォーマンスについてさまざまな文献を読み、 世界中の科学者や臨床医に相談。そこで学んだ「食べ物と脳の関係」をまとめたのが本書。 ◎医師ポール・グレワルの臨床経験をもとに、 脳を一生守りながら、もっと賢く、 幸せになる食生活やライフスタイル=「ジーニアス・プラン」を具体的に紹介。
-
4.3
-
4.8いつもの朝食、私のパンにだけ蛆虫が這っている。 「何かがおかしい 自分も 怖い」 現役ヘルパーの筆者が描く主人公は「認知症患者」。 アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、若年性認知症…さまざまな認知症患者が 多数登場し、その「心」を紡ぎます。 例えば ●便器の水で家中の衣類を洗濯し始めた80代母 ●読み書きを忘れた50代男性が文字を求めて本屋を徘徊 ●90代寝たきり母はマンションの一室に閉じ込められる ●妻を24時間拘束し精神崩壊させた60代の全身まひ夫 ●90代でモテ期到来…? 男性ヘルパーに恋した老女 徘徊、せん妄、失禁、幻視、暴力、抑うつetc…。 その時、認知症患者が感じている気持ちとは? 単行本限定の特別描きおろしも多数収録‼ 掲載時のカラーページを完全補完した、電子だけの特別版にてお届けします! ★単行本カバー下画像収録★
-
4.3
-
4.4「結婚はしない。抱きたいときに君を抱く」。法律事務所で働く26歳の夏海は、若年性認知症を患う母の病院代を払ってもらう条件で、上司であり事務所の経営者である弁護士の一条聡と愛人契約を結んでいる。同じマンションに住み、自宅でもオフィスでも彼の望むままに抱かれる日々…。夏海は出会った時から聡を愛していたが、お金のために愛人となってしまったため、本当の気持ちを言い出せない。そして、結婚に失敗して心に深い傷を負った聡は、夏海に惹かれる自分の気持ちから目を背けていた。だが、強烈すぎる聡の婚約者の出現で、二人の運命は大きく変わっていく。本当の気持ちを伝えらないまま、すれ違う二人を描くジレジレラブストーリー。
-
-明るかった夫から、笑顔が減った? そう思ったのもつかの間、日に日にできないことが増え、転げるように症状は悪化した。藁にもすがる病院巡り、一人で抱え込んだ介護地獄――愛と罵倒と悔恨の日々を綴った、壮絶な夫婦間介護手記。巻末には相談窓口や介護のコツをまとめたアドバイス集「もしもあのとき、知っていれば」収録。
-
-若年性認知症を発症した主婦を取り巻く苦しみと家族の愛情の残酷さを描く! 喜怒哀楽に満ちた珠玉のエンターテイメント作品! ※この作品は「最凶ストーカー~粘着ブス女の呪詛~」に収録されております。重複購入にご注意下さい。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 認知症のある人の気持ちがわかれば、よりよいケアがみえてくる 医学的知識にもとづき、認知症カフェ「SHIGETAハウス」(神奈川県平塚市)で認知症のある人や家族の悩みに向き合い続ける医師が実践。 認知症のある人の気持ちを知り、認知症そのものへの不安を解消し、家族との関係から起こる「情緒が不安定になる」「ケアを拒絶する」「家族を責める」などを防ぐためにできることを中心に、認知症のある人とのよりよい向き合い方・寄り添い方を紹介する。 家族に認知症があっても今までどおりの生活を続けるためには? 日々のケアで気をつけることは? どんな制度が利用できるの? 若年性認知症のときは?
-
-40代働き盛りの夫が「若年性認知症」になった。会社への行き方がわからず、怒鳴りだす。たとえすべてを忘れてしまう日が来ても私たちは家族でいられる? ※本作品は、他コンテンツに収録されている場合がございます。重複購入にご注意ください。
-
4.446歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断された夫とそれを見守る妻 絶望の淵にさした光、仲間たちとの出会い、当事者とその家族だから伝えられること。 京都市の下坂厚さんは46歳の夏、アルツハイマー型若年性認知症の診断を受けました。 簡単な計算を間違えたり、家に忘れ物をしてきたり、なんだかおかしいな……ということが少しずつ増え、もの忘れ外来を受診。 「病名を聞いたときは、比喩でなく、本当に目の前が真っ暗に……」。 診断後、働いていた鮮魚店を辞め塞ぎ込んでいた下坂さんを、妻の佳子さんは見守り続けました。そんな絶望の淵に光がさします。 認知症当事者を支援する団体との出会いをきっかけに、下坂さんは介護施設でケアワーカーとして働き始めます。 そして、同じ病気の人の姿を見て勇気づけられたように、自分を見て勇気づけられる当事者や家族はきっといるはずという思いから、現在は認知症について広く知ってもらうための啓蒙活動にも尽力しています。 若年性アルツハイマー型認知症と診断された夫とそれを見守る妻が、当事者とその家族だからこそ伝えられることを綴る1冊です。 第一章 46歳、認知症になる 第二章 絶望から希望へ 第三章 当事者だから、できること 第四章 認知症と向き合うということ 第五章 夫婦のこと、写真のこと、これからのこと 関係者に聞く 「認知症の当事者の方に働く場所を提供するという取り組み」
-
4.5「何よ、あんな女――殺してやりたい!」恋人の永二と交際中の美沙には大きな悩みがあった。それは永二をストーキングする自称「蛍姫」という、デブでブスな女! 永二が引っ越しても付きまとい続けて3年。新しい会社に初出勤した永二は会社に先回りした蛍姫がいることを知る。さらに蛍姫は永二の婚約者だと触れ回っていた! 逃れられない最凶ストーカーに狙われたカップルの苦難を描いた表題作「最凶ストーカー~粘着ブス女の呪詛~」のほか、セレブ妻になった若主婦の知らない“もうひとりの自分”が男を漁りまくっていた! あれは自分に似た誰かなのか、はたまた自分自身なのか? 暴走するもう一人の自分を描いた「ドッペルゲンガー」、もらいっ子だった百合が実の母の危篤で病室に駆けつけたら、自分とそっくりなさくらという女に遭遇して! 金持ちで余裕のありそうなさくらと洋服を交換し髪色を染め直して帰宅した家は、百合の想像を超えていた! 入れ替わりの落とし穴を描いた「もう一つの人生」、さらに若年性認知症を発症した主婦を取り巻く苦しみと家族の愛情の残酷さを描いた「家族の残像」を収録。喜怒哀楽に満ちた珠玉のエンターテイメント作品4作をお見逃しなく!
-
5.0親の介護は、遅かれ早かれ、いつか、突然やってくる。著者にとって、それは30代のときだった。 父が若年性認知症となり、同時期に母が末期がんを宣告され、突如として介護キーパーソンに!! 本書は、そんなダブルケアの日常をほのぼのとコミカルに描いたイラストエッセイ。 幻冬舎×テレビ東京×noteコミックエッセイ大賞にて準グランプリを受賞したブログに、新たに描き下ろしマンガを加え、書籍化。
-
4.5
-
-※年齢や職業、その他データは雑誌掲載当時の情報です。ご了承ください。 貧困、起業、闘病、障害、事件、離婚、死別ーー 懸命に生きる方々の、それぞれにある波乱万丈な人生の煌きを 経験豊富なライター陣が渾身のドキュメント。 『週刊女性』で2003年から続く人気の連載を電子書籍化。 題字は永六輔さんに生前揮毫していただきました。 【目次】 1.「障害者が当たり前に暮らせる社会に」/伊是名夏子さん(コラムニスト) 2.「今度産むときも、自閉症児がいい。息子より1日でも長生きしなきゃ」/立石美津子さん(著述家・講演家) 3.「若年性認知症の私だから発信できる〝笑顔の秘訣〟」/山田真由美さん 4.「認知症の母を介護中に今度は私が、乳がん!!」/篠田節子さん(作家) 5.「母の命をつないだ5000通の葉書」/脇谷みどりさん(童話作家) 【著者紹介】 はぎわらきぬよ 大学卒業後、週刊誌の記者を経て、フリーのライターになる。 '90年に渡米してニューヨークのビジュアルアート大学を卒業。 '95年に帰国後は社会問題、教育、育児などをテーマに、週刊誌や月刊誌に寄稿。 著書に『死ぬまで一人』がある。
-
-
-
4.2元脳外科医で、最高学府の教授でもあった夫・若井晋。 その彼が若年性認知症になるとき、本人は、そして家族は、どうしたのか。 長い苦悩をへて病を受け入れ、新たな道へと踏み出した 夫婦の軌跡を、妻・若井克子が克明に描き出す。 ●当事者・若井晋が語る「認知症の人から見た世界」とは? 「最初は『何でだ』と思っていました」 「けれども私は私であることがやっとわかった」 「私が見ている感じと、みなさんが見ている感じが違うんです」 「僕の住んでいる世界は、たいへんなんだよ」 「『大変だったなあ』と一言、言ってくれればよかった」 【著者・若井克子の言葉・・・本文より】 晋は若年性アルツハイマー病になって、知識を、地位を、職を失った。 それは、世間からは「地獄」に見えるのかもしれない。 だが私には、むしろ、すべて失ったことで「あるがまま」を得て、 信仰の、人生の本質に触れたように感じられるのだ。 病は人生の一過程に過ぎない。認知症になっても、私は私であることに変わりはない――。 認知症患者800万人時代を生きるための必読書がここに!
-
4.0詩人兼絵本作家と若年性認知症の画家が、 一人の女性をめぐり繰り広げる、遅れてきた青春――。 詩人で絵本作家の笹原、画家の石黒、40代後半の美しい珠代という名の女性の三角関係を描く長篇小説です。 笹原は編集者に紹介され石黒と出会います。 二人はたまたま中学の同級生であると分かり距離が縮まっていきます。 石黒は愛想は極めて悪いが憎めない魅力的な男です。 一冊の絵本を一緒に仕上げますが、その後、石黒は突然仕事をすべてやめてしまった。 石黒は若年性アルツハイマーを病んでいるのでした。 そして、ナックルボールを投げることだけに異常に執着します。 ナックルボールを仲立ちにして、マドンナたる珠代に出会った二人は、まったく違ったように仲良くなるのでした。 笹原はじりじりしながら友人と珠代の間を行き来しますが、ある日石黒は失踪してしまい、笹原と珠代は必死で石黒を探し始めるのでした。 中年男女三人に遅れてやってきた青春を描く、さわやかで感動的なドラマです。
-
-37歳まで仕事一筋できた私は、結婚相談所で出会ったバツイチ40歳のサラリーマンとスピード婚。幸せをつかんだはずだったのに…彼が若年性認知症になり!? ※本作品は、他コンテンツに収録されている場合がございます。重複購入にご注意ください。
-
-3,630円 (税込)はじめに 目次 ●第1章 認知症の症状、特徴、考え方 認知症の原因疾患別特徴 アルツハイマー型認知症 脳血管性認知症 レビー小体型認知症 前頭側頭型認知症(ピック病) 正常圧水頭症 若年性認知症 軽度認知障害(MCI: Mild Cognitive Impairment) <Column> まだまだ意外に覚えている?! 認知症の世界観ととらえ方 「心」の在りかはどこか? 災害と認知症 <Column> モーツァルトリハ ●第2章 認知症コミュニケーション・メソッド 認知症コミュニケーション・メソッド 【基礎編】 01 普通に接する 02 ただいるだけでいい 03 声のかけ方 04 ジェスチャーの力 05 スマイルの力 06 タッチの力 07 名前の呼び方 08 相手の言葉を繰り返す 09 相手の言葉と調和させる 10 もうひと声! のマジック 【中級編】 11 専門家として扱う、頼る 12 昔の逸話 13 師匠として接する 14 いつだって褒める! 15 男女でこんなにも違う?! 16 ストーリーテリング 17 話しが長くなりがちな方に 18 相手の世界観に思いをはせる 19 As If~(もし~だったら)の視点をもつ 20 感情を反映する 21 言葉遣い「リスペクトの精神」/タメ口問題 【応用編】 22 エンパワーの視点 23 具体的に言う 24 ダジャレ、冗談のパワー 25 下ネタの効能(?) 26 考えるきっかけと認識を高める 27 リアリティ・オリエンテーション(RO) 28 リハビリ時の効果的な声かけ 29 価値観をあぶり出す質問 【発展編】 30 役割設定の力 31 おもちゃなどの活用 32 チラシだってネタに 33 レクリエーションの考え方 34 感謝ケア 認知症とともに生きる人たちの心理的ニーズ <Column> 黒い虫が現れた! ●第3章 認知症のある方との関わり、現状の課題、困りごと 認知症の症状とその行動 BPSDの出現モデル 【認知症相談室】 1 「家に帰りたい」と言って聞きません 2 いつも同じ不安感…… 3 物が無くなった! 4 ご飯を食べてない! 5 易怒性 6 気難しい方 7 お風呂に入りたがらない 8 落ち着きがない(車イスから立とうとする) 9放尿 10性的な行為 11リハビリをして元気になったら、また徘徊して困ります 12介護者に対するハラスメント 「説得」ではなく「納得」を引き出す すべての行動に理由がある <Column> 100歳を越えて、なおお元気 <Column> 主介護者の娘、認知症になる…… ●第4章 認知症がある方のご家族とのコミュニケーションのとり方、ポイント ご家族とのかかわり方 いたわり、ねぎらい いい情報をお伝えする 認知症ポジティブ クレームへの対処法 ご家族への啓発活動 <Column> 徐々に変化する母親の介護 ●第5章 利用者さんの気持ちの安定のために 気持ちを安定させる要因 心地よい空間 匂い BGM あくせくしない 便秘 運動 ADL介入 栄養(食事・水分)の重要性 ●第6章 私たちケアする側のメンタル ケアする側のメンタル メンタルを安定させる 睡眠・栄養・呼吸・運動 セルフコーチングスキル 朝通勤時 仕事中 勤務後 前向き思考のつくり方 “怒り”のマネジメント こだわりを手放す 身体から変えていく! 自分を癒す チームメンバーへのコーチング <Column> 近所を徘徊しているおじさん <Column> 現役理容師のナミさん ●第7章 抑制しない介護を目指して リスク管理の考え方 認知症ケアだからこその視点 介護ロボットの活用法 車イス・ベッドからの転落防止 拘束ケアを選択しない施設とは ●第8章 他職種との連携、チームとしての協働 アイデアを出し合う組織風土をつくろう やっぱり「ホウレンソウだね」 他のメンバーの対応の仕方を注意したい 雰囲気は伝染する! チームの活性化を目指して ケアの前提条件 <Column> 否定形の会話は毒 ●第9章 地域で暮らし続けるために 「共生」の観点から 「早期発見・早期予防」の考え方 認知症を見落とさない 当事者交流 住みやすい町づくり 「予防」の観点から 社会参加 ライフスタイルの見直し スーパーシニアから学ぶ 引用文献・参考文献 ●おわりに
-
-本書では、★今すぐ簡単にできることを具体的に提言 ★高血圧/糖尿病/脂質異常症/喫煙/飲酒/肥満/心房細動/慢性腎臓病/食事/運動/フレイルのリスク/アンチ・エイジングとサクセスフル・エイジング ★増えている若年性認知症や若年性脳卒中にならないためにどうしたら良いか! ★大学教授として多くの研究や臨床経験を持ち科学的根拠に基づいた内容を厳選して解説 ★脳外科手術、ビタミンやホルモンの補充療法で治せる認知症/レカネマブなど新薬/最新情報を掲載。 【主な内容】 第1章―認知症と脳卒中の危険因子は共通しており、これらの危険因子から神経血管ユニットを保護すれば認知症と脳卒中を同時に予防することができるのです。 第2章―認知症は長い潜伏期(軽度認知機能障害MCI)があり、脳梗塞には、一過性脳虚血発作という前兆があります。認知症と脳卒中の初期症状や前兆を知り、最新の画像検査を活用して早期発見をめざしましょう。 第3章―認知症にはアルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などがあり、脳卒中には脳梗塞、脳出血、くも膜下出血があり、各疾患の要点を解説します。 第4章―若年性の認知症と脳卒中には特殊な原因が多く、症状にも特徴があり、近年増加傾向にあります。なお若年性認知症は18歳から65歳未満に発症する認知症の総称です。 第5章―認知症と脳卒中の症状や検査を知って理解することは、早期発見や発症時の正しい対処のために重要です。 第6章―認知症と脳卒中の具体的な予防法 第7章―最新のガイドランに基づく認知症と脳卒中の治療法、最新情報 【著者】内山真一郎 山王メディカルセンター脳血管センター長、国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授、東京女子医科大学名誉教授
-
4.0認知症と紛らわしい別の疾患とは? 治る認知症を見逃すな! 薬の飲みすぎが認知症に似た症状を起こすことも。認知症はここまで分かった!認知症は高齢になると発症しないか心配になる病気ですが、予防するための食事・運動法から早期発見法、診断・治療まで、日本各地の臨床医、医学研究者、福祉従事者に新聞記者が広く取材し、ホットで役立つ情報をかみくだいた形で提供します。新聞協会賞、日本ジャーナリスト会議・JCJ賞、ファイザー医学記事賞の大賞、日本認知症ケア学会・読売認知症ケア賞特別賞を受賞、絶賛された新聞連載の医療編をまとめたものです。カラーのイラストや写真や説明図版をそのまま再現、アルツハイマー病や最近注目されているレビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症、若年性認知症などを分かりやすく解説します。さらに新しい治療薬やワクチン、症状を抑える漢方薬、原因タンパクを分解する酵素の話題にまで目配りされています。自分や家族が直面したときどう向き合うか、とても役立つ1冊です。
-
3.543歳の時に若年性認知症の診断を受け,いったん家に閉じこもったが,認知症当事者や支援者に出会い,変わっていく.障害のある息子の子育て経験からも培った「ひとりでは抱え込まない」を大切に,当事者・家族の相談,学校での講演など全国各地で活躍中.「いまの自分が一番好き」という著者の言葉に耳を傾けてみませんか.※この電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており,タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています.また,文字だけを拡大すること,文字列のハイライト,検索,辞書の参照,引用などの機能は使用できません.
-
5.02025年には患者数700万人に達するとも言われている認知症。もはや他人事ではありません。 あなたならどうする? この本のなかに、答えがきっと見つかります。 京都大学教授を定年退官した直後に、異変が起きた夫。 若年性認知症の症状が進行するパートナーを抱えることとなった妻。 苦悩から安らぎへの道を模索した、こころ温まる二人三脚の物語。 【目次】 ●緑いっぱいの地へ ●スケッチ開始 ●初孫誕生 ●疑念 ●惑いの日々 ●孫に会いに ●義姉とのわかれ ●ただ一通の手紙 ●神経内科に相談 ●要介護認定申請 ●乳癌の疑い ●体験デイサービス ●毎日を楽しく ●交換ノートより ●ふたたびのゆりかご
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 認知症と診断されたけど「まだ働きたい」「自立した生活をおくりたい」 そんな方のために当事者の工夫と 支援者のアドバイスを1冊にまとめました! 本書では「認知症と診断されたけど、仕事や自立した生活(ひとり暮らし)を続けたい」と思ったときに、できること・しておくといいことを紹介しています。 ■本書で扱っているテーマを一部紹介! ・第3章:「自立した生活」をできるだけ続けるためには? カギのかけ忘れ防止/忘れ物対策/スケジュール管理のコツ/自転車や交通機関を使うときの注意点 日用品や食品の在庫管理/主治医とのコミュニケーションのポイント など…… ・第4章:「仕事」をできるだけ続けるためには? 事例紹介/職場で症状とつきあう方法/会社から理解を得る方法 休職や退職を考えたときにすべきこと/障害者雇用などの選択肢 など…… ■認知症の人が読みやすい工夫が盛りだくさん! また、認知症になると「文章が読みづらい」「脳の疲労で集中力が続かない」などに悩まされることがあります。 そんな方でも読みやすいように、さまざまな工夫を取り入れました。 ・文字は大きく、ゆとりを持たせたデザイン ・文章をしっかり読まなくても要点がつかめる ・「当事者」「支援者」の解説を別々に読むことができる ■こういった方におすすめ! ・認知症と診断されたけど、まだまだ働きたい・働かないといけない ・できるだけ自分の生活は自分で管理したい ・症状(もの忘れ・外での迷子など)への対策を知りたい ■目次 第1章:認知症・若年性認知症って? 第2章:認知症と診断されてから 第3章:「自立した生活」をできるだけ続けるためには? 第4章:「仕事」をできるだけ続けるためには? 第5章:症状が変化してきたときのつきあい方 ■■著者紹介 来島 みのり(きたじま・みのり) 東京都多摩若年性認知症総合支援センター、センター長。若年期アルツハイマー病と診断された方と出会ったことをきっかけに、若年性認知症当事者と家族の会を立ち上げる。2016年11月より東京都多摩若年性認知症総合支援センターに勤務。 かもした まこと 認知症(若年性認知症)当事者。2016年に「レビー小体型認知症」と診断されたものの、部署異動などを経て、現在も仕事を続ける。また、ひとり暮らしも続けながら、認知症当事者の会などへも積極的に参加している。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 認知症カフェの開設から運営、支援まで紹介! 「認知症の人や家族が気軽に立ち寄れる場」として注目の認知症カフェ。その開設と運営のノウハウを、オシャレにイラストいっぱいでご紹介!「認知症カフェに行ってみたい!」「認知症カフェのことが知りたい!」という人にも最適なガイドブックです。 【認知症カフェとは?】 オレンジカフェともいわれる認知症カフェは、認知症の人やその家族、介護の専門家、地域の人などが集まり、情報交換をしたり、懇談をしたりする場です。国が本格的に開設を後押しし、今、急速に普及が進んでいます。 【本書の特徴】 ●モノ集め、各種手続き、資金の調達、地域との連携、若年性認知症 etc、知りたい情報が満載。 ●オシャレで魅力ある空間づくりや、飲食の出し方もご紹介。 ●認知症の基礎知識・法令資料、認知症に関係する専門用語も収載。 【こんなときに活用できる(一例)】 ●認知症カフェ(オレンジカフェ)って、どんなところ? ●どういう人が開設するの? ●開設・運営費用はどうするの? ●どんな手続きが必要なの? ●運営資金はどのように調達すればいいの? ●ミニレクチャーの講師やミニコンサートの演奏者はどうやって探すの? 【認知症カフェを魅力あふれる場にするための一例】 ●ちょっとワクワクするような異空間をつくろう ●カップやランチョンマットなどの小物でオシャレ感を出す ●芳しい香りで異空間を演出する ●健康によい漢方茶やハーブティーをメニューに加える ●参加者に喜んでもらえるお菓子を出す ●認知症の予防や症状緩和に役立つレクリエーションを企画する ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-いまのままでは、10年後、こんな病気が待っている! 国立長寿医療研究センターのトップのもと、各分野の名医が集結。 人生100年時代と言われますが、重要なのは、病気に悩まされずに生活できる「健康寿命」を延ばすこと。そのためには老化が進む前から備えておかなればいけません。 そこで基礎疾患にはじまり、こわい心臓の疾患、脳の疾患、認知症にいたるまで、40~80歳代の年代ごとに、発症しやすい病気は? どんな人たちのリスクが高いのか? その原因は? 前ぶれは? 予防法は? これらを9人の名医がやさしく解説します。 それに加えて、「現役世代向けの運動メニュー」「シニア世代向けの運動メニュー」「人間ドックの上手な利用法」などのコラムも収録。 (目次より) 第1章 40歳代--老化の加速がはじまる年代 高血圧/脂肪肝/メタボリック・シンドローム/痛風・高尿酸血症 乳がん/緑内障/歯周病 など 第2章 50歳代--三代疾病のリスクが高まる年代 胃がん/大腸がん/肺がん/くも膜下出血/脳梗塞/糖尿病 若年性認知症/睡眠時無呼吸症候群 など 第3章 60歳代--健康状態の曲がり角 心筋梗塞・狭心症/脳出血/肝臓がん/膵臓がん/前立腺がん 軽度認知障害/加齢性難聴/オーラル・フレイル など 第4章 70歳代--人生の一大事が増える時期 認知症/不整脈/脳梗塞/弁膜症/アミロイド・アンギオパチー COPD(慢性閉塞性肺疾患)/誤嚥性肺炎/白内障 など 第5章 80歳代--頼りになるのは体力 サルコペニア/老年症候群/誤嚥性肺炎 など