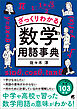ベクトル 意味作品一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 マンガのストーリーで最適化の数式の意味(数学記号、計算式など)と具体的な例題で実務が学べる。 中学、高校の数学で関数の最大、最小を学習したのでないでしょうか。それが実務の何の役に立つとかというと利益は最大がよいし、損失は最小がよいのがわかります、つまりこれが最適化なのです。最適化は大学ではOR(Operations Research)または経営科学という学問で勉強します。数学のレベルは大学1年で学ぶ線形代数がわかっていることが前提になります。とはいえ最大、最小のイメージがあれば複雑な計算を100%理解していなくても実践することはできます。 本書はマンガを使ってまず概要をつかみ、マンガを補う本文部分は実務に役立つ例題で数式は最小限でできるものを用意し、まずは苦手意識を取り除きます。近年はPythonで簡単にできるのでプログラムを作ろうとしますがその前にこの本を買って勉強していただければPythonによる最適化もスムースにできるようになります。 プロローグ 週末の深夜バイトと、月曜1限の講義 第1章 数理最適化とは 1-1 「 最大」と「最小」が、最適になる ・現実の課題を、簡単に表してみよう ・定式化は3点セット ・ふわっとした気持ちも数値化できる ・最適化問題には、色々な種類がある ・グラフに慣れていこう ・ グラフは強い味方になってくれる! 1-2 最適化に必要な数学はこれだけ抑えればよい ・ベクトル、行列ってどう役立つの? ・スカラー、ベクトル、行列 ・ベクトルの特徴を図で理解しよう ・表記の仕方 ・連立一次方程式は、行列とベクトルの積で表せる ・微分、傾きってどう役立つの? ・勾配ベクトルってどう役立つの? ・微分を使っていこう ・勾配(勾配ベクトル)の式 ・傾きと勾配 ・2回微分してみよう、ヘッセ行列 フォローアップ 第2章 線形計画問題 2-1 線形計画問題の例 ・最大の利益になるように生産したい! ・調味料の問題も定式化 ・実行可能領域と目的関数 ・複雑で大規模な問題を扱うために 2-2 単体法と内点法 ・2つの解き方のイメージ ・単体法は、どんなアルゴリズム(計算)なのか 2-3 双対理論 ・双対のイメージをつかもう ・双対問題のおかげで、ラクに解ける ・調味料の問題の、双対問題とは フォローアップ 第3章 非線形計画問題 3-1 非線形計画の例 ・3次元空間の線形・非線形 ・ビールの注文数を予測しよう ・誤差を最小化する ・複雑な形の関数でも、予測式が作れる ・非線形計画問題は、制約条件があったりなかったり 3-2 単体法と内点法 ・大域的最適解と局所的最適解 ・まずは停留点を見つけよう ・停留点の見つけ方 ・凸集合と凸関数 3-3 反復法 ・解の更新 ・直接法と反復法 ・反復法の更新式 ・最大化の場合は、山登り ・大域的収束性と局所的収束性 ・探索方向の選び方 フォローアップ 第4章 整数計画問題と組合せ最適化問題 4-1 整数計画・組合せ最適化問題の例 ・整数という制約 ・組み合わせ的な構造とは? ・効率よく巡回するためには ・ナップサック問題 ・0-1の制約のある色々な問題 4-2 近似解法と厳密解法 ・2つの解き方がある ・近似解法、厳密解法とは? ・貪欲法(欲張り法) ・分枝限定法 フォローアップ エピローグ 付 録 さらに勉強するために 索 引
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 Pythonを使って線形代数学を見える化して学ぼう! 本書は、大学初年次に学ぶ基礎数学科目の一つであり、具体的なところでは機械学習やコンピュータグラフィックス、ゲームプログラミングなどの基礎となる線形代数を、Pythonを使って学ぶものです。 線形代数は、微分・積分とならび基礎的な数学の一つですが、ふつうに勉強するとベクトル・行列計算が面倒くさく、また定義や概念が多く抽象的な表現も多いため、なかなか理解しづらい学問といえます。そこで本書は、Pythonによるプログラミングを用いて以下の工夫を施すことで、よりわかりやすく、またビジュアルにベクトルを見るなどの体験を通して、線形代数を学べるようにまとめたものです. 1)2次元平面や3次元空間のベクトルを視覚的に表現する 2)関数をグラフ化することで、ベクトル計算の意味を理解しやすくする 3)面倒なベクトルや行列の計算をプログラミングで表現する 4)手計算では不可能な高次の線形計算を、具体的なデータ(音や画像)を用いて表現する 5)通常の教科書の演習問題レベルの計算問題をプログラミングによる数式処理で求める 第1章 数学の基礎とPythonによる表現 第2章 線形空間と線形写像 第3章 基底と次元 第4章 行列 第5章 行列の基本変形と不変量 第6章 内積とフーリエ展開 第7章 固有値と固有ベクトル 第8章 ジョルダン標準形とスペクトル集合 第9章 力学系 第10章 線形代数の応用と発展
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 深層学習をベースとした自然言語処理の基礎が体系的に身につく! 本書は、深層学習に基づく自然言語処理の基礎となる知識や考え方を、丁寧に展開し解説するものです。自然言語処理技術の概観から始め、機械学習の基本的枠組み、言語モデル・系列変換モデルとして非常に有用なTransformerとそれを活用した事前学習モデルの詳解、さらに自然言語処理の基本的なタスクである系列ラベリング、構文解析、意味解析と、自然言語処理を学ぶうえで必須の基礎知識や背景となる仕組みを幅広くカバーし、体系的に身につけることができる構成としました。 大学の学部上級から大学院の学生、さらには自然言語処理を学び始めた若手技術者にお薦めの教科書です。 第1章 自然言語処理の概要 1.1 自然言語処理の応用 1.2 コーパスと自然言語処理 1.3 自然言語処理の難しさ 演習問題 第2章 自然言語処理のための機械学習の基礎 2.1 機械学習とは 2.2 教師あり学習 2.3 特徴量表現 2.4 パーセプトロン 2.5 ロジスティック回帰 2.6 ソフトマックス回帰モデル 2.7 機械学習モデルの評価 2.8 正則化 2.9 ニューラルネットワーク 2.10 計算グラフと自動微分 2.11 ニューラルネットワークに関するその他の話題 演習問題 第3章 単語ベクトル表現 3.1 記号からベクトルへ 3.2 素性関数による単語のベクトル表現 3.3 分布仮説と単語文脈行列 3.4 特異値分解による次元削減 3.5 Word2Vec:ニューラルネットワークによる学習 3.6 単語ベクトルの応用 3.7 FastText:単語よりも小さな単位の利用 3.8 単語ベクトル表現の課題と限界 演習問題 第4章 系列に対するニューラルネットワーク 4.1 単語ベクトルの合成 4.2 再帰型ニューラルネットワーク(RNN) 4.3 勾配消失問題と勾配爆発問題 4.4 長期短期記憶(LSTM) 4.5 ゲート付き再帰ユニット(GRU) 4.6 畳込みニューラルネットワーク(CNN) 演習問題 第5章 言語モデル・系列変換モデル 5.1 言語モデル・系列変換モデルの導入 5.2 言語モデルの定式化 5.3 言語モデルの利用例 5.4 言語モデルの具体例1:nグラム言語モデル 5.5 言語モデルの具体例2:ニューラル言語モデル 5.6 系列変換モデル 5.7 言語モデルの評価:パープレキシティ 5.8 未知語問題への対応 演習問題 第6章 Transformer 6.1 Transformerの歴史的背景 6.2 自己注意機構(セルフアテンション) 6.3 Transformerの構成要素 6.4 学習時の工夫 演習問題 第7章 事前学習済みモデルと転移学習 7.1 事前学習済みモデルの背景 7.2 デコーダの事前学習:GPT 7.4 エンコーダ・デコーダの事前学習:BART 7.5 事前学習済みモデルと知識蒸留 7.6 事前学習済みモデル利用上の注意点 演習問題 第8章 系列ラベリング 8.1 系列ラベリングとは 8.2 系列ラベリングの定式化 8.3 点予測による系列ラベリング 8.4 線形連鎖に基づく条件付き確率場 演習問題 第9章 構文解析 9.1 構文解析とは 9.2 句構造解析 9.3 依存構造解析 9.4 さまざまな構文解析手法 演習問題 第10章 意味解析 10.1 意味解析とは 10.2 テキスト間含意関係認識 10.3 ニューラルネットワークによる意味解析 10.4 述語項構造解析 10.5 論理表現 10.6 セマンティックパージング 10.7 意味解析のその他の話題 演習問題 第11章 応用タスク・まとめ 11.1 機械翻訳 11.2 質問応答 11.3 対話 11.4 自然言語処理の過去・現在 演習問題略解 参考文献
-
-いまやイノベーションは時代の合い言葉であり、その必要性が多くの企業で語られている。 しかし、その一方でイノベーションという概念に対するそもそもの誤解が蔓延している。 イノベーションは技術進歩ではない。 次々と市場化される新しい製品やサービスや技術。 こうした現象のほとんどは「進歩」であって、「イノベーション」ではない。 クレイトン M. クリステンセンが提唱した「破壊的イノベーション」という概念の最大の功績は、イノベーションの「古典的定義」に立ち戻りつつも、経営が置かれている今日的な文脈に注目してイノベーションの本質を再発見したことにある。 「新しい何か」という意味では共通しているものの、イノベーションと技術進歩は一面では正反対のベクトルであり、トレードオフの関係にあるとすらいえる。 筆者である一橋大学大学院教授の楠木建氏は、イノベーションと技術進歩の違いを理解したうえで、目の前にある日々の「技術進歩の競争」を安直に追いかけないことが重要だと指摘する。 腰を据えて本来の意味でのイノベーションを追求するのであれば、技術進歩に逃げてはいけない。*『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー(2013年6月号)』に掲載された論文を電子書籍化したものです。
-
4.0潰れかけの千葉ジェッツふなばしを「集客力リーグNo.1」「天皇杯2連覇」に導き、増収増益を続ける超・骨太組織へと変貌させた経営のプロが、マネジメントメソッドの全てを初めて明かす! 千葉ジェッツの圧倒的な成功の裏には、経営理念に基づく徹底的なPDCAがあった! 人を束ね、動かし、組織力を強化して成果を出し続けること。それは企業の経営者やマネジメント層にとって、もっとも基本的であり、もっとも難しいともいえる至上命題です。 どうすれば社員のモチベーションが高まるのか。 どうすれば社員が主体的に動くのか。 どうすれば本気で生産性を高められるのか。 どうすれば絶対に目標をクリアする強い組織になれるのか。 ……わかっていてもなかなか解決できない課題に、多くの経営者が頭を悩ませています。 こうした課題をクリアし、「組織の力を高めて確実に成果を出す」ためのメソッドをまとめたのが本書です。 著者の島田慎二氏は、存続すら危ぶまれた千葉ジェッツふなばしの立て直しを託され、収益力・人気・実力ともにBリーグ屈指の球団へと見事に再生した経営者。その手腕は川淵三郎氏にも高く評価され、リーグから請われる形でBリーグの副理事長を務めた経歴も持ちます。 島田流マネジメントの根幹は、「経営理念」と「PDCA」です。 経営理念は掲げるだけでは意味がなく、事業戦略、中長期の目標、そして社員の行動一つひとつにまで明確に落とし込んでこそ機能します。 お客様に挨拶することも、電話をかけることも、オフィスのゴミを拾うことも、その先に目指す理念と紐付けることによって、組織の全員を同じベクトルに向かわせることができるのです。 「オフィスにゴミが落ちていたら拾いなさい」 その理由を経営理念に紐付けて説明できたとき、あなたの組織は最強のチームへと生まれ変わります。 <本書の主な内容> ・ 経営理念は会社の存在意義 ・ 理念は抽象的で絶対に辿り着かないもの ・ 経営とは勝つ確率を上げること ・ 組織は桶。桶の大きさは経営者の器 ・ 計画は悲観的に、実行は楽観的に ・ 「やりたい」より「やるべき」で判断せよ ・ 弱小組織ほど「キャラ化」せよ ・ あらゆる人の「首を縦に振らせる」 ・ 説得は説明+納得
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 東進のスーパーエース数学講師である志田晶による「中堅国公立大学~難関大学」対策用の数学参考書。 数学の学習における「解答を読んでもわからない!」「問題文の意味すらわからない!」と悩みを解決することを主眼に置く。 本書では、数学の実力を向上させるためのモノの考え方を詳説することで「わからない」を克服できる構成となっている。 1つのテーマについて5~6題の問題を収録しているので大いなる成果が期待できます。 ※本書は2010年に小社から刊行された『トコトンくわしい 決定版 志田晶の ベクトルが面白いほどわかる本』を改題の上、再編集したものです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 電験三種受験に必須の数学をていねいに解説! 「完全マスター電験三種受験テキスト」シリーズの別巻的な位置づけである「電気数学」の改訂版です。 電験三種の4科目で出題される計算問題では、電気数学の知識が必要になってきます。そこで、本書は、電験三種の計算問題に必要な電気数学を題材に、図やグラフを多く用い、視覚的にわかりやすいようにするだけでなく、ポイントとなるところには吹出しで補足説明を入れていますので、文系出身やあまり予備的な知識がない方でも学習しやすい1冊になっています。 また、電気数学の基本的な知識だけではなく、電験三種の問題を例題として取り入れることにより、学んだ電気数学の知識を実践でき、より理解が深まるような紙面構成になっています。 今回の改訂では、初版発行後の2009年以降の出題傾向を精査し、追加・修正(例:過渡現象に関する出題の追加、正弦波交流の様々な表し方の追加等)を行い、併せて計算例や例題の見直し等を行い、内容の充実を図っています。 また、2014年に発行したシリーズ4巻(各科目)に準じた紙面構成になっています。 Chap1 数学の基礎事項 1-1 数の分類と整数・分数・小数 1-2 数学で使われる記号とその意味 1-3 電験で使われる単位と国際単位系(SI) 1-4 約数と倍数 1-5 数値計算の順序と加減乗除のきまり 1-6 無理数,虚数,複素数 1-7 代数式と書き方の約束 1-8 等式と不等式 1-9 比例と反比例 1-10 百分率と単位 1-11 総和(シグマ) 練習問題 Chap2 式の計算 2-1 計算問題を文字式に直すコツ 2-2 整式とその計算方法 2-3 因数分解と式の展開 2-4 分数式の計算 2-5 無理数・無理式の計算 2-6 指数式の計算 2-7 最大定理、最小定理、近似値の計算 練習問題 Chap3 方程式とその解き方 3-1 方程式とその性質 3-2 一元一次方程式の立て方と解き方 3-3 行列式の計算 3-4 二元一次方程式の立て方と解き方 3-5 三元一次方程式の立て方と解き方 3-6 二次方程式とその解き方 3-7 分数方程式とその解き方 練習問題 Chap4 関数とグラフ 4-1 関数の表し方 4-2 座標とグラフ 4-3 一次関数、二次関数のグラフ 4-4 ピタゴラスの定理、円の方程式とグラフ 4-5 指数関数とグラフ 4-6 対数と計算方法 4-7 関数の変化率と微分の基礎 練習問題 Chap5 三角関数 5-1 角度と角度の測り方 5-2 鋭角の三角関数 5-3 特別な角、一般角の三角関数 5-4 三角関数のグラフ 5-5 正弦波交流の表し方 5-6 三角関数相互間の関係 5-7 逆三角関数 5-8 正弦定理 5-9 余弦定理 練習問題 Chap6 ベクトルと複素数 6-1 ベクトル量とスカラー量 6-2 複素数 6-3 ベクトルの各種表示法 6-4 複素数の加減算とベクトル表示 6-5 複素数の乗算とベクトル表示 6-6 複素数の除算とベクトル表示 6-7 ベクトルオペレータjと? 6-8 ベクトル軌跡 練習問題 Chap7 伝達関数と周波数応答 7-1 伝達関数 7-2 ブロック線図 7-3 周波数伝達関数と周波数応答 7-4 増幅度、利得と対数 7-5 ボード線図 練習問題 Chap8 2進法と論理式 8-1 2進法の計算 8-2 論理代数と2進法 8-3 論理代数の基本定理 8-4 論理回路の簡単化 練習問題 付 録 付-1 微分の基礎(続き)と積分の基礎 付-2 ラプラス変換と逆変換 付-3 ギリシャ文字の読み方 付-4 図形と面積・体積の求め方 付-5 電験三種に必要な数学の範囲と使用頻度 付-6 電験三種の計算問題を解く学習のコツ 練習問題解答
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【数学の不安を吹き飛ばす! 数学の意味と目的をとことんわかりやすく解説。】 役に立つ数学とは?何から手を付ければよいのか、できるだけ苦労せずに使える数学を身につけるにはどうすればよいのか? こう捉えるとよいのか…と合点がいく内容が盛沢山です。 高校まで数学が得意だった人が、大学の数学になった途端に躓いてしまうことがあります。なぜ難しいと感じてしまうのか、どう取り組んでいけばよいのかを、現役のエンジニアライターが実体験をもとに解説していきます。捉え方をちょっと変えれば、意外とすんなりと先へ進むことができるかもしれません。 ■こんな方におすすめ 大学の数学の授業についていくことができない人、専門ではないけれども数学をやらないといけない人、数学が何の役に立つのか知りたい人、工学系で数学を使う人、数学の応用を知りたい人……など。 ■目次 ●第1章 なぜ大学数学は難しいのか 大学の数学が難しい理由 高校の数学と大学の数学の違い 役に立つ数学とは? 数学の3つの性質 数学界の絶対的なルール「0で割ってはいけない」 ε-δ論法がなぜ必要なのか? 無限なんて現実には存在しない 大学数学を学ぶ時の心構え ●第2章 高校数学の学びなおし f(x)とは何か?(関数) 大きい数/小さい数を扱う(指数・対数) 実は三角でなくて、波を表す関数(三角関数) 「i^2=-1」を忘れた後に残るもの(複素数) 微分=傾きの概念をしっかりと(微分) 積分=面積の概念をしっかりと(積分) スカラーより便利なことに気づいて欲しい(ベクトル) 「同様に確からしい」の本質(確率) ●第3章 大学数学の学び方 本格的な大学数学に進む前に 行列を変換と考える(線形代数) ∂とdは何が違うのか? (多変数関数) ネイピア数の大事さがわかる(微分方程式) 微分系ではなく積分系で考えよう(ベクトル解析) 実は実関数の積分で活躍する(複素関数論) 現実世界の数字を理解する(数値解析) 統計学は標準偏差が8割 ■著者プロフィール 蔵本 貴文(くらもと たかふみ):香川県丸亀市出身、1978年1月生まれ。関西学院大学理学部物理学科を卒業後、先端物理の実践と勉強の場を求め、大手半導体企業に就職。現在は微積分や三角関数、複素数などを駆使して、半導体素子の特性を数式で表現するモデリングという業務を専門に行っている。さらに複業として、サイエンス・テクノロジーを中心に執筆するエンジニアライターとしての一面も持つ。著書に『数学大百科事典』(翔泳社)、『解析学図鑑』(オーム社)、『「半導体」のことが一冊でまるごとわかる』(共著、ベレ出版)などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ロングセラー『1冊でしっかりわかる本シリーズ』に、待望の『高校の数学II・B版(新課程対応)』が登場! 高校の数学II・Bを短時間で予習・復習! 基礎から学び直したい社会人にも大人気です。 ●2022年度以降に高校に入学した生徒さんへ 最少の時間で最大限に理解できるように、『数学II・B』の大切なことを1冊に凝縮しました。順番に読むだけでスッキリ理解できるつくりになっています。また、ミスを減らす方法や、学校では教えてもらえない解きかたのコツを満載。知っているだけでまわりの人と差がつきます。 新課程で新しく加わった「仮説検定」についてもしっかり解説しています。 ●旧課程対応の大学受験予定の生徒で、ベクトル以外の数学II・Bを学びたい方へ 本書は新課程対応のため、ベクトルは収録していませんが、新旧共通の内容である『式と証明』『複素数と方程式』『図形と方程式』『三角関数』『指数関数と対数関数』『微分』『積分』『数列』『確率分布と統計的な推測』について、しっかりカバーしています。 そのため、旧課程対応の大学受験予定の生徒にとっても、十分役に立つ内容です。 ●学び直しや頭の体操をしたい大人の方へ つまずきやすいポイントや、覚えづらい公式を理解できるよう、ていねいに解説しました。新課程で内容が充実した『確率分布と統計的な推測』も、用語の意味からしっかり理解できます。 本書の7つの強み その1 各項目に「コレで完璧! ポイント」を掲載! その2 「ココが大切!」に各項目の要点をギュッとひとまとめ! その3 高校の数学II・Bの全内容が短時間で「しっかり」わかる! その4 「学ぶ順序」と「ていねいな解説」へのこだわり! その5 用語の理解を深めるために、巻末に「意味つき索引」も! その6 範囲とレベルは高校の教科書と同じ! 新学習指導要領にも対応! その7 高校生から大人まで一生使える1冊!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 新課程にバッチリ対応! 定期テスト対策から、共通テストの基礎固めまでしっかりカバー! ●これから「物理基礎」の学習を始める初学者に最適 ●解答にたどりつくまでの「原理」の解説が充実 ●物理基礎に必要な数学的な内容もしっかり復習できる。 【この本の5つの強み】 その1 テーマのポイントが瞬間的につかめる! その2 適度に「まとめ」が入っているから頭の中を整理しながら進められる! その3 解説は最大限シンプルにしました! その4 「三角比」と「ベクトル」が復習できる! その5 意味つき索引が暗記に役立つ!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「数学を学びなおしたい」「用語の意味がわからず困っている」「何のために計算しているのか理解したい」といった方に向けて、中学や高校で習う数学の用語100項目をざっくり解説!【大学入試でも使う算数用語】【√にまつわる数学用語】【数と式にまつわる数学用語】【方程式にまつわる数学用語】【関数にまつわる数学用語】【複素数にまつわる数学用語】【数列にまつわる数学用語】【確率にまつわる数学用語】【統計にまつわる数学用語】【微分積分にまつわる数学用語】【ベクトルにまつわる数学用語】【図形にまつわる数学用語】の全12章。著者は、『世界が面白くなる!身の回りの数学』(あさ出版)や『いちばんやさしいベイズ統計入門』(SBクリエイティブ)、『図解かけ算とわり算で面白いほどわかる微分積分』(ソーテック社)などが人気の佐々木淳先生。ざっくり理解から、本質的な理解へと導く、数学の基礎体力がつく「数学用語事典」!
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 この本の目的は、一般相対論までの内容をごまかしなく伝えることである。しかし私が挑戦したいのは、第一の目的を少しも損なうことなく、読者の負担が最小となるような形でまとめ上げることである。そういう本を手にすることが可能かどうか、私自身が知りたくて作るのだ。(「序文」より抜粋) 【著者略歴】 広江 克彦(ひろえ かつひこ) 1972年生まれ。岐阜県出身。静岡大学理学部物理学科卒。同大学院修士課程修了。'00年より、物理学を解説するウェブサイト「EMANの物理学」の運営を開始。その内容が徐々に評価され、'07年に『趣味で物理学』を、'08年に『趣味で相対論』を続けて上梓。現在は農業に片足を置きつつ、執筆に励む。EMAN(エマン)は中学の頃からのあだ名であり、ネットでも主にその名前で活動している。 【目次】 第0章 準備 第1章 特殊相対性理論 1.1 相対論はなぜ生まれたか? 1.2 エーテル理論の失敗 1.3 アインシュタインの指針 1.4 同時であるとはどういうことか 1.5 ローレンツ変換の求め方 1.6 時空回転と不変量 1.7 悩むのは無駄 1.8 固有時の意味 1.9 4元速度 1.10 E=mc2 を導く 1.11 質量は増大するのか 1.12 物体は縮むのか 1.13 なぜ光の速さを越えられないのか ~哲学~科学とは何だろうか 第2章 座標変換の理論 2.1 座標変換とは何か 2.2 見かけの力 2.3 ガリレイの相対性原理 2.4 4次元的世界観 2.5 光はなぜ一定速度か 2.6 多変数関数の微分 2.7 運動方程式のローレンツ変換 2.8 偏微分の座標変換 2.9 マクスウェル方程式が不変となる変換 2.10 反変ベクトル・共変ベクトル 2.11 縮約の意味 2.12 省略記法の導入 2.13 テンソル解析の基礎 2.14 計量とは何か 2.15 反変・共変の変換 2.16 4次元の演算子 第3章 相対性原理の実践 3.1 相対論的な運動方程式 3.2 運動量ベクトルの変換 3.3 エネルギー運動量テンソル 3.4 相対論的なマクスウェル方程式 3.5 電荷の保存則 3.6 ゲージ変換 ~豆知識~ローレンツは二人いる! 第4章 一般相対論の入り口 4.1 結論から始めよう 4.2 代表的な二つの公式 4.3 測地線の方程式の展開 4.4 重力場の方程式の展開 4.5 項の数を数えてみる 4.6 式の簡単化 4.7 質量は2 種類ある 4.8 アインシュタインの解決法 4.9 質量は錯覚だ ~豆知識~重力と引力の違い 第5章 リーマン幾何学 5.1 共変微分 5.2 平行移動2 5.3 測地線 5.4 局所直線座標系 5.5 テンソルの共変微分 5.6 リーマン曲率 5.7 リーマン・テンソルは本当にテンソルか 5.8 リッチ・テンソル 5.9 スカラー曲率 5.10 ビアンキの恒等式 5.11 アインシュタイン・テンソル 5.12 ニュートン近似 5.13 重力場の方程式へ 5.14 係数の値を決める 第6章 一般相対論の検証 6.1 シュバルツシルト解 6.2 光の湾曲 6.3 水星の近日点移動 6.4 重力赤方偏移 6.5 加速系の座標変換 あとがき
-
4.0シュレーディンガー方程式に焦点を絞り,数学的な基礎から学べる入門書.ベクトル,固有関数などの概念を,量子力学との関係を示して解説し,方程式の物理的意味,不確定性原理,ポテンシャル問題への応用に進む.理解度を確かめられる「クイズ」,応用を通して力がつく「演習問題」を収録.解答付きで自習にも最適.※この電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており,タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています.また,文字だけを拡大すること,文字列のハイライト,検索,辞書の参照,引用などの機能は使用できません.
-
-薄毛は「隠す」「ごまかす」「諦める」から「治す」時代へ! AGAに悩む老若男女にとって、自然かつ確実に悩みを解消できる方法が「自毛植毛」である。 その手法や効果、そして費用やメリットやデメリットについて、現役の医師も訪れる業界の権威でもあり「親和クリニック」総院長を務める音田正光氏が、その全てを語る。 ─本書の内容─ 第1章 あふれる広告、都市伝説... 高度AGA情報社会をさまよう “薄毛難民”が正しく増やすためには ■薄毛難民を惑わせるものたち ・毛生え薬ができたらノーベル章もの ・現代社会には薄毛に関する情報が氾濫しすぎている ■薄毛にまつわる困った迷信 ・その情報に根拠はあるか? ・育毛・発毛商品を検証してみると... ・増毛法とカツラに潜むワナ ・カツラのメリット・デメリット ・AGA治療・比較表 ■人は見た目が9割 ・どの年代がAGAになりやすいのか ・薄毛治療は人生への投資 薄毛に定義はない ・AGAの種類/AGAの境界線 ■よくある質問〈知識編〉 ■[座談会]適齢期女子たちの“髪”へのホンネって 第2章 植毛の進化論! 薄毛は「隠す」から治る時代に... 自毛植毛で人生を好転させる ■自毛植毛が薄毛解消の最適解 ・「隠す・増やす」ではない「治す」というベクトル ・二つの「植毛」法の大きな違い ・自毛植毛手術ではメスは使わない ■自毛植毛で変わるのは髪型だけではない ・本来の自分を取り戻した83歳の男性 ・自毛植毛の流れ 〜カウンセリングから手術まで〜 ■自毛植毛の内容 ・最先端技術「MIRAI法」 ・大量の移植を世界一のスピードでこなすチーム医療 ・髪の「癖」にまで配慮した驚異の移植法 ・自毛植毛の費用は長い目で見れば安い ・「患者ファースト」は“言葉”だけでは意味がない ・自毛植毛【MIRAI法】ビフォー・アフター! ・ 1年後に再会した“元・薄毛”の皆さん ■よくある質問〈心理編〉 第3章 人生100年時代の「髪」の未来 失われた過去から自分を取り戻す【自毛植毛治療体験記】 ・植毛体験記 PART 1 ・ 【薄毛・育毛の現実】失われたお金と時間の悪循環を止める ・植毛体験記 PART 2 ■あとがき ■よくある質問〈手術編〉
-
-1巻1,780円 (税込)●おもに高専を対象にした数学のテキスト。 ●大学初年次のリメディアル教育用のテキストとしても利用できます。 ●ていねいな説明で読んで理解しやすいテキスト。 ●本文を補助してよりわかりやすくするために、横に注意、補助解説、具体例などを随所に掲載。 ●豊富な図で視覚的にも理解しやすくなっています。 ●選択式の教材として研究で「三角形の面積」「点と直線・平面の距離」「ベクトルの外積」「クラメルの公式」「原点を通る直線に関する対称移動」「ベクトル空間「ベクトル部分空間」「基底」「正方行列の三角化およびジョルダン標準形」を扱っています。 ●コラムで「内積の図形的意味」「阿弥陀籤」を掲載しました。 ●各章のとびらには、その章で学ぶことを授業の導入として掲載。 ●準拠問題集を完備。
-
4.6「主体的・対話的で深い学び」「AL」「カリマネ」の目指すベクトルは、すべて「授業改善」に向けられています。 「学びの質に着目して、授業改善の取組を活性化しようというのが、今回の改訂が目指すところである。平成26年11月の諮問において提示された『アクティブ・ラーニング』については、子供たちの『主体的・対話的で深い学び』を実現するために共有すべき授業改善の視点として、その位置付けを明確にすることとした」 (中央教育審議会答申、平成28年12月) 「学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、第3の1に示す主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で、次の(1)から(3)までに掲げる事項の実現を図り、児童に生きる力を育むことを目指すものとする」 (小学校学習指導要領第1章総則2、平成29年3月) 新しい学習指導要領が求める、これからの授業改善とは? 授業には、あなたの授業を改善するために欠かせない「見方」があります。それを解き明かすことが本書の目的です。 他者の授業を見るという行為は、言うなれば教師自身の問題解決的な学習そのものです。いくつかの視点に基づいて見ることによってはじめて、参観者(自分自身)にとってその授業に意味と価値が生まれます。そして、その意味と価値を材料として自分の授業の問題解決を図っていく、そういう種類の問題解決的な学習なのです。 授業は生き物です。同じ内容、同じ指導案であっても、教師と子供が違えば授業の姿もまた様変わりします。そのため、偶発性や固有性に頼ると見誤ります。重要なのは、授業の根底に流れる法則や本質を「見抜く目」です。 その目は、知らず知らずのうちに、あなたの授業を変えてくれます。そのような意味で、「授業の見方」とは、授業改善のための自動装置にほかなりません。授業を見る目が磨かれれば、授業はどんどんよくなる、もっとおもしろくなるのです。 ----------------- 本書は、学習指導要領改訂のキーマンの一人である澤井陽介・文部科学省視学官が、新しい学習指導要領が求める教師の指導力とは何か、授業をどのように改善していけばよいのか、「授業の見方」を通して、その手法のすべてを明らかにします。
-
-数学の入試対策は「網羅系参考書」をやり込んで「過去問」を解くことが主流となって久しいです。 「ない袖は振れぬ」という意味で、いわゆる解法パターンや定石を身につけることは大切ですが、単純な解法暗記で覚えたことは宝の持ち腐れと言わざるを得ません。 本書は、「学校ではあまり教わらない」「ちゃんとした予備校講師なら教える」ような解き方に触れ、考察を深めることより数学力を上げることを目的とした参考書です。 学校で習わないものは「裏ワザ」だろうと言う人もいますが、入学試験を採点する大学の先生は「書かれていることが正しいかどうか」を基準にします。 ぜひとも「高い意識」を持って学び、ワンランク上の「知識」と「技能」を身につけ、「スマートな解き方」で高得点を獲得してください。 【目次】 グラフに不等式を解かせる/大小の視覚化/整式のTaylor展開/パラメーターaの扱い方/効率的な面積計算/微分法の華麗な使い方/領域を利用した三角不等式の解法/連立方程式の同値変形/座標の導入/交点をスマートに求める/行列式/外積と正射影ベクトル/ベン図を巧みに使う/特殊解/最小多項式
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ☆経済学で使う数学を理解するための最初の一歩は、微分と積分の理解から 高校で履修した「数学」の知識を前提として、きちんとしたステップを踏んで学習をすれば、大学で経済学・社会科学を学ぶために必要な数学の考え方・知識・技法、社会人になっても役立つ数学の知識を身に付けることができます 【本書では経済数学を以下のステップで学習します】 (1)経済学における数学の役割を実感する (2)関数および関数の連続性について正しく理解する (3)関数の性質を記述する微分法を学ぶ (4)消費者や企業の最適化問題を解決する (5)変数が2つに増えたらベクトルを用いる (6)ラグランジュの未定乗数法がこれでわかる (7)確率論や統計学の基本の正規分布は積分から理解できる (8)行列を利用すれば2次元正規分布もわかる 本書「序」より………本書で行う数学の学習は高校の授業とは違った雰囲気になるはずである。もちろん計算は頻繁に現わるが、どうしてその計算がなされるのかという理由や動機に重点がおかれ解説は比較的長くなる。 したがって、焦らずにゆっくり読み進めてほしい。諸君がこれまでに学んだ数学の意味を再認識してもらえることを期待している。 本書で試みた高校とはいくぶん雰囲気の違う数学の学習を通じて、社会科学にとどまらず、これからの諸君の長い人生を豊かにする教養の1 つとして数学を付け加えてもらえれば、著者として望外の幸せである。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 現代の理工系に必携。学生から職業的プログラマーまで、必須の教養「線形代数」を身につけよう! 数学的基礎がしっかり理解でき、課題をPythonで解く力が得られる。サンプルコードによる演習も豊富な、一挙両得の入門書! 【目次】 第1章 行列と連立方程式1 第2章 行列と連立方程式2 第3章 逆行列 第4章 行列式・ブロック行列 第5章 行列式の余因子展開・クラメルの公式 第6章 対称群による行列式表示・終結式 第7章 幾何学的意味 第8章 ベクトルの一次独立性・直交基底 第9章 行列と線形写像 第10章 固有値と固有ベクトル 第11章 行列の標準化 第12章 特異値分解・低ランク近似
-
3.2「この本を読めば非効率、非生産性という言葉と無縁になるのではないか」 諏訪中央病院名誉院長 鎌田實氏 推薦 不登校の女子高生が偏差値85を突破! 仕事・勉強・趣味……あらゆる場面で 脳が自然とフルドライブする 診療実績17000人超 マッキンゼーで学んだ脳神経内科医が教える 「無意識」の活用 ◎頭の中のノイズが消える ◎意思の力に頼らず没頭できる ◎ぐるぐる思考をかき消す ◎気分の浮き沈みがなくなる ◎ストレスに強くなる 脳の仕組みを理解すれば、どんなことにも集中できる! 【著者からのメッセージ】 本書は集中について書かれた本ではありますが、同じ脳の強化というベクトルでは、 病的なぐるぐる思考の状態から、健康な思考回復をおこなう医学書でもあるのです。 医学書として通底する真のメッセージをまとめると次のようになります。 世界を認知するのは、まずは脳内の現実世界からの予測から始まる。 そして五感を通じて取り入れた外部の事実世界と照合して、 もし誤差があれば「意識」を使って脳内の現実世界を修正してより事実世界に近接する。 適切な現実世界をつくるために、脳の唯一の機能は「予測と予測誤差の修正」である。 つまり、現実世界は、五感と「わたし」を通した脳内の写像である。 私たちは脳内の現実世界に生きている。 その現実世界が生きづらい世界だったら、その現実世界を生み出す「わたし」、その価値観を修正すれば世界は変わる。 その価値観は、正しく高尚な価値観でなく、新しい現実世界を生み出すための適切な、快適な価値観である。それを自ら選択すれば、世界は新たに創造できる。 起こった現象にはすべてに意味がある。症状、病気さえ、その人にとって大きな意味をもつ。 起こった症状でなく、その原因を生み出した世界観を修正することが、私たちの脳機能の本質である。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 はじめに基本的な理論のみを議論し、例題では法則の応用例を紹介や、法則の導出を行いました。また、章末問題では読者が問題を解きながらstep by stepで理解を深め、より高度な理論を把握できるようにしました。 章末問題には難易度に応じて★~★★★を付け、また問題の番号が小さい場合に、後の節で学ぶ知識も必要な問題には☆を付けました。解答の解説では、わかりやすくするために関連した式の番号をできるだけ多く示しましたが、これは、その式を天下り式に使うことを勧めているのではなく、式の意味を十分理解した上で使用することを強く望みます。 例題はもちろん、章末問題の解答にも図を多用しました。その理由は、問題を解くときには、問題文を読みながら図を描き、図を見ながら(数式の計算に注意を奪われることなく)考える習慣を身につけて欲しいからです。問題には実際の機器や自然現象の原理に関係する題材を多く含めるように努力しました。電気電子工学や物理学への興味を少しでも喚起できれば幸いです。 電気磁気学の法則は、ベクトルや微積分などの難解な数式で書かれている場合が多く、法則そのものも難しいと誤解されがちです。本書では電気磁気学の法則を段階的に理解できるように、最初は初級の数学のみを用いて説明し、理論についての基本的なイメージができ上がった後にそれを拡張するようにしました。
-
-※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 数学を専門とする立場の者と数学を応用する立場の者が協同して、数学的正確さと応用を意識した内容を盛り込んだシリーズの1冊。理学か工学かを問わず、さまざまな分野で必須の数学的素養となっているベクトル解析を、大学初年級で学ぶ微分積分と線形代数のみを予備知識として、ていねいに解説する。とくに、ベクトル解析で現れるさまざまな数学的概念を、読者が具体的にイメージできるようになることを目指し、流体における例を多くあげて、その物理的意味についても述べた。また各章末の練習問題については、巻末におよそ20ページにおよぶ解答を収めている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 薬学系コアカリ「薬学の基礎としての数学・統計学」に対応したテキスト。解法がしっかり身につくよう、解答を導く過程や各数値の意味まで、フルカラーでていねいに解説した。 【本書の特徴】 ・薬学教育で要求される比例計算、濃度計算、指数・対数、数列、三角関数、微積分、確率、統計、線形代数をすべて網羅 ・式の展開を省かず、懇切丁寧に解説を書いているので、自主学習にも役立つ ・例題と演習問題を豊富に掲載し、計算力を高める学修ができる ・薬剤師国家試験に出題された基礎的問題や実務的問題も取り入れ、学んだ数学が専門科目の授業や国家試験でどのように活かされるのかがわかる 【目次】 第1章 数値の扱い 1.1 連分数 1.2 割合・比・率 1.3 薬学への応用 第2章 指数関数 2.1 指数と計算 2.2 指数関数とそのグラフ 2.3 薬学への応用 第3章 対数関数 3.1 対数とその性質 3.2 対数関数とそのグラフ 3.3 薬学への応用 第4章三角関数 4.1 一般角と三角関数 4.2 三角関数のグラフ 4.3 加法定理と三角関数の合成 第5章 数列 5.1 等差数列と等比数列 5.2 無限数列とその極限 5.3 薬学への応用 第6章 微分法 6.1 微分の定義 6.2 導関数 6.3 指数関数、対数関数、三角関数の導関数 6.4 偏微分・全微分 6.5 薬学への応用 第7章 積分法 7.1 不定積分 7.2 定積分と面積 7.3 薬学への応用 第8章 微分方程式 8.1 変数分離形の微分方程式 8.2 1階線形微分方程式と身近な微分方程式 8.3 薬学への応用 第9章 行列 9.1 平面ベクトルと空間ベクトル 9.2 行列 9.3 行列式 第10章 確率 10.1 順列と組合せ 10.2 確率と確率変数 10.3 代表的な確率分布 第11章 統計 11.1 データの尺度水準 11.2 母集団と標本 11.3 基本統計量 11.4 相関と回帰分析 11.5 推定と検定 11.6 薬学への応用 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。