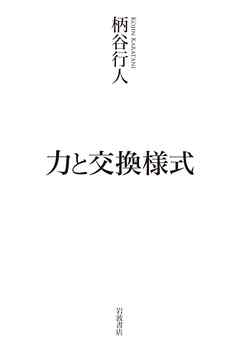あらすじ
生産様式から交換様式への移行を告げた『世界史の構造』から一〇年余,交換様式から生まれる「力」を軸に柄谷行人の全思想体系の核心を示す.戦争と恐慌の危機を絶えず生み出す,資本主義の構造と力が明らかに.呪力(A),権力(B),資本の力(C)が結合した資本=ネーション=国家を揚棄する「力」(D)はあるのか.
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
成田悠輔さんの22世紀の民主主義と22世紀の資本主義を読んで、どうしてこんなことを思いつくんだろうと感心した。調べると、この本の著者・柄谷行人さんと交流があったらしい。成田悠輔さんに影響を与えた人物かもしれない、といった経緯で本書を手に取った。
交換様式から生じる観念的な力が、経済的・政治的な諸問題を生み出すという考え方を提示している。交換様式A(互酬)に取って代わった交換様式B(支配と保護)とC(交易)が生み出す戦争と恐慌の果てに、交換様式D(交換様式Aの高次元での回復)が「やってくる」として締めくくっている。豊富で深い学術的知見と、洗練された見通しのよい議論の展開には感動を覚えた。
面白いのは、成田悠輔さんのが上述の著書2冊で述べていたことは、まさに交換様式BとCの揚棄であり、かつ、交換様式Dを「つくりだす」ことを構想している点である。柄谷行人さんが「やってくる」と主張するDを、待つのではなく生み出そうという実験的な試みが垣間見える。
力と交換様式のなかで、交換様式Dの発生条件や発生形態について具体的な記述はなかったように思う。後書きで世界史の構造という本でAからCまで論じたと言っていた。Dを直接理解するのは難しそうであるが、AからCまでをもう少し理解すれば、少なくとも現実の諸問題がどのような交換様式から来るのかの理解には役立つかもしれない。ということで、次は世界史の構造を読んでみようと思う。
Posted by ブクログ
星6相当
じんぶん堂 『柄谷行人回想録』より
16回 その頃僕がよく使っていた“批評”という言葉がある。自分は、“哲学”とか“文学”じゃなくて、“批評”をやるんだ、と。それは簡単にいえば、批判的である、ということです。既存の思考を組み合わせて新しいものをつくるのではなく、既存の思考を成り立たせているメカニズムを解明しようとすべきだ、と考えた。そういう作業がないと、思想は、既存の体制を追認して、そこでできる範囲のことに甘んじることになる。既存の思考体系は、どんなにラディカルなものであっても、それを反復しているだけだと、既存の体制に吸収されて、それを支えるものになってしまう。
四つの交換様式
A互酬(贈与と返礼)
B服従と保護(略取と再配分)
C商品交換(貨幣と商品)
D Aの高次元での回復
序論
2 つまり、宗教のような観念的上部構造は、たんに経済的ベースによって受動的に規定されるだけでなく、むしろ能動的に後者を変える「力」をもつとみたわけである。
4 ウェーバーもフロイトも、いわゆる上部構造に下部構造から来るものでないような何かが潜んでいる、と考えたのである。したがって、経済的下部構造だけでなく、それから相対的に自立した上部構造の次元を探求することが不可欠だと考えた。そのとき、彼らは、上部構造の観念的な「力」が、経済的下部構造、ただし、生産様式ではなく交換様式から来るということを見なかったのである。
14 マルクスが資本論で書こうとしたのは、商品物神(物に憑いた霊)が貨幣、資本へと発展し、社会総体を組織してしまう歴史である。
15 資本論は、したがって、物神が自己実現するにいたる全過程を、ヘーゲル的論理に沿って書いたものである。
16 ヘーゲルが言わんとするのは、次のことだ。人間の社会史は、何らかの意図・設計によって作られたものではない。それは人間の意図を超えたものであり、むしろ「無意識」によって強いられたものである。
ex カエサルやナポレオンは、彼らの野心あるいは意識を超えたものを実現してしまった。
21 マルクスは、貨幣をスミスのように商品に内在する労働価値を表示する記号として片付けるのではなく、なぜ貨幣が特異な力を持つのかを解明しようとしたのだ。この力は、物の生産においてではなく、その交換において生じる。
22 重要なのは、交換が共同体の内部ではなく、その外にある共同体との間、つまり、見知らぬ、従って不気味な他者との接触において始まるということである。だからこそ、そのような交換は、人々の単なる同意や約束ではない、強制的な力を必要としたのである。それがフェティシズム(物神)である。
・物象化とは、人と人との依存関係が、物と物との関係としてあらわれるという事態を指す。
25 つまり、貨幣とは物に、一般的価値形態あるいは貨幣形態、つまり霊が付着した状態である。ゆえに貨幣を得ようとする欲望を齎す。その欲望は、いつでも物を手に入れることができる権利、すなわち観念的な「力」への欲望である。
31さまざまな霊的な力は、異なる交換様式に由来する。
マルクスは『資本論』において、貨幣や資本の亡霊(物神)を、交換様式Cとともに生じた観念的な力として考察する道を切り開いた。
34「社会主義の科学」=社会主義を交換様式において見ること
35 DはA・B・Cのいずれをも無化するような力としてある。重要なのは、Dが人間の意志や企画によって生じるものではない、むしろ、それに反してあらわれる、ということである。それは「神の力」としてあらわれる。
36マルクスは『資本論』で、人間と人間の関係を交通から見るにいたったとき、同時に、人間と自然との関係を交通として見ようとした。ただこの時彼は人間と人間の間の「交換」と、人間と自然の間の「交通」を区別した。
37 アニミズムはAが支配的であった時期の考え方。
38 マルクスはここで、資本主義的生産が労働者を搾取するだけでなく、いわば自然を搾取=開発(exploit)すること、つまり、人間と自然の間の交通を破壊してしまうことを指摘した。
40 人間と人間の間の交換様式がAであったとき、人間と自然との「交通」もそれに似たものと見なされた。それがアニミズムである。その後、交換様式Bの優位、すなわち国家が成立した後にも、それは自然との関係において残っていた。それが完全に消滅するに至ったのはCが支配的となった段階、すなわち産業革命の後である。
41 われわれが今日見出すような環境危機は、人間社会におけるCの浸透が、人間と自然の関係を変えてしまったことの所産である。それによってこれまで"他者"であった自然がたんなる物的対象と化した。
第一部 力とは何か
45 「力」とは物理的な力ではなく、観念的、あるいは霊的な力を指す。そして、それは人間と人間の間の「交換」から生じる。
47 マルクスは『資本論』で、物神が商品物神、貨幣物神、資本物神へと発展する姿を描いた。それは、資本がそれ自体商品として売買されるものとなった時点、すなわち、株式資本において終わる。と同時に始まる。
48 国家の「力」の源は、支配することと保護することの交換(B)である。すなわち、支配する者は服従する者を保護しなければならない。征服することは武力によって可能であるが、支配を継続するためには、それだけでは済まない。
51 要するに、たとえ霊的な存在であろうと、現にそこに一種の力が働くことを認めた者が近代科学をもたらしたのだ。
54 イオニアの自然哲学者らは、生物の進化、さらに人間社会の歴史的発展について考えたのである。それは彼らが商工業に従事したことと切り離せない。そこから見ると、ヨーロッパにおける"ルネサンス"とは、ある意味で、イオニア的な商工業と自然哲学の復興に他ならない。
55 ダーウィンの進化論は、近代に生じた資本主義、また、それとともに生じた経済学と無縁ではない。つまり同じ欠陥をもつ。
57 ダーウィンがスミスから影響を受けたのは、経済学というよりも、むしろその根底にある考え方であった。スミスはエゴイズムから出立して、その逆に見える同情あるいは良心が成り立ちうることを説明した。ダーウィンは同情を「社会的本能」と言い換えた。
58 スミスが対峙したのは重商主義である。先ず金銀貨幣を重視する重金主義が現れ、さらにそれが広く、重商主義として広がったのである。それは金銀貨幣を交易によって増大させることを一国の経済政策の要とするものであった。それに対してスミスは、金銀貨幣を特別視する考えを否定した。
64 それは人類が長く定住しても、本格的な農耕・牧畜には向かわず、狩猟採集を続けたこと、ゆえにまた、国家を形成しなかったことを意味する。
交換様式A
74 次のように区別される。一つは、人間の欲望や意志に従属するものであり、その働きは人間中心的である。したがって呪術となる。もう一つ、神から来る霊は神中心的であり、人間の欲望に反する。したがって、それは人々を律する掟となる。
80 放浪生活民が定住するに至ったのは、それが楽で快適なものであったからではない。
・しかし定住化と共に、小さな集団が多く集結するようになった。それとともに形成された共同体は、その内部での規律を必要とした。と同時に、他の共同体との交換を必要とした。そこに始まったのが交換様式Aである。これは単に人々の合意や協力によって出来たのではない。それを成り立たせたのは、各人の意志を超えた「霊」の力である。
84 兄弟同盟(トーテミズム)が壊れたあとに、原父的な存在あるいは国家が出現したのである。つまりフロイトが言う原父なるものは、後に出現した家父長や王を前代に投射したものに過ぎない。それは、ニーチェの言葉で言えば「原因と結果の遠近法的倒錯」である。
86 ルネ・ジラールは「欲望」から出発する。彼の言う欲望とは、ヘーゲルが定義したような意味で、他者の欲望、つまり、他者の承認を欲することである。それはまた次のような意味にもなる。すなわち、欲望とは他者が欲するものを欲することである。それを得ることによって他者の承認が得られるからだ。
88 簡単に言うと、前期フロイトの考えには、快感原則と現実原則の二元的枠組がある。
WW1後は考えを修正し、快感原則および現実原則よりも根源的なものとして反復強迫を見出した。それを齎すのは「死の欲動(無意識)」である。フロイトの考えでは、死の欲動とは、有機体が無機質に戻ろうとする欲動である。そして、それが外に向けられた時、攻撃欲動となる。
↓
「死の欲動」の受動的役割と能動的役割
↓
90 つまり、毎日戦争の夢を見て飛び起きることが、むしろショックを再現してそれを乗り越えようとする意味を持つ。この限りにおいて、反復強迫とは、能動的な自己治癒の企てなのだ。ただし能動的ではあるが、意識的なものではない。
・「検閲官」が他律的であるのに対して、「超自我」はいわば自律的、自己規制的である。死の欲動を持ち出すことによって、むしろ社会的規範(現実原則)を越える「自律性」を見出した。
91 フロイトは超自我に、抑圧し検閲するものではなく、「おびえて尻込みしている自我に、ユーモアによって優しい慰めの言葉をかけるもの」を見出している。
超自我は自我を抑えるというよりもむしろ、自我の自律性を支援するものである。超自我は内部から来るものだ、とはいえ、それは自我にとって、あたかも外から来たかのように強迫的に到来する。
93 トーテミズム(兄弟同盟)という力を齎すのは、無意識から到来する反復強迫である。
94 遊動的な狩猟採集民たちは、社会的な葛藤や縛りを持たなかった。しかし定住した後、彼らは未曾有の危機に出会った。一口で言えば、定住が「有機的」な状態を齎したのである。無機質の状態に戻ろうとする死の欲動が現れたのは、その時である。それは先ず、他者に向けられる攻撃欲動として奔出したが、さらに、それを抑えて他者への譲渡=贈与を迫る「反復強迫」が現れた。そして、それは霊の命令として出現した。
95 まとめ
123 Aによって齎される力は、定住化によって抑えられた原遊動性Uの脅迫的な回帰に基づくものだ。そのためAによって原遊動性がある程度保持され、平等性と独立性を保っている。
交換様式B
100 歴史学は、古代に関してしばしば「遠近法的倒錯」を犯す。つまり結果として生じたことを、原因に見出す誤謬である。貨幣や国家の起源を問うときには、そのことに注意すべき。
102 通常、奴隷は強制されたものなのだが、人々は自発的に隷従を求める。ゆえに自発的奴隷こそが国家を可能にする。権力とはそもそも"自発的な服従"に基づくものだ。人が自発的に服従するのは、それによって保護が得られるからである。それによって生まれた交換様式Bは、主権者に、命令する権利を与えるだけでなく、臣民の要求に応じる義務を課する。
103 主権とは、むしろ人ではなく、人がそこに置かれるような場にある。
106 Bはたんに支配ー服従という状態のように見えるが、あくまで交換である。というのは、それは、服従すれば保護されるという関係、あるいは、保護されるので無ければ服従しないという双務的な関係だからだ。
109 社会のありよう(交換様式)が人口数を決める。それは以下のように発展。
・定住以前の原遊動民のバンド 収穫は平等に配分
・定住以降のバンド 「再配分」制度の誕生。Aの誕生
・氏族社会、部族社会 婚姻を含む贈与交換によって共同体が拡大
・首長制社会 外婚制の拡張によって誕生
・国家 Bの確立
Bが出現したのは、Aが十分に機能しえなくなった時点である。
112 贈与の互酬交換は必ずしも友好的・平和的なものではない。それはしばしば競合的であり、戦争に転化する可能性があった。
114 この意味で互酬交換(A)は、そのポジティブな性質(友好)によって国家の形成を妨げるだけでなく、同時に、ネガティブな性質(戦争)によって国家の形成を妨げる。
116 国家が成立するのは、ある者が絶対的に支配し他の者がすべて自発的に服従するという関係が成立する時、言い換えれば首長が王となる時である。それを可能にするのはAに伴う霊的な力をさらに上回るような霊的な力(聖なる王権)である。それはBによって齎される。
117 国家の成立を生産力だけから説明することはできない。また、農耕の発展から専制国家、すなわち、官僚・軍という国家装置が生まれたというような見方も疑わしい。なぜなら実際はその逆であるからだ。
120 聖なる王権が民衆にとって「大きな魅力」となったのは、それが単に服従と奉仕を要求するだけでなく、それとともに保護・救済を与えるからだ。この時生じたのは、被支配者が支配者に服従することによって保護・救済を得るというタイプの交換(B)である。
121 両者は再分配という点で本質的に類似するので、初期の国家は、成立したあとにも首長制社会あるいは部族社会に戻ってしまう可能制をとどめている。
124 Bを齎したのは、人々の隷従化(subjugation)である。国家の成立に必要なのは、奴隷ではなく、いわば"自発的に服従する奴隷"、つまり臣民subjectである。服従するものが自発的にそうするのは、それによって得をするからだ。言い換えれば、それは、支配することと自発的に服従すること、あるいは収奪されることと保護されることの交換である。
126 農耕が発展したのは、国家の下で農耕に従事する臣民がいたところだけである。国家の出現が農業革命を齎した。
・官僚制は上意下達のシステムであり、互酬原理が強い社会では成り立たない。Aにおいて人々は独立心が強く、上の命令に服従させられることを嫌うからだ。ゆえに官僚こそ、自発的に服従する奴隷、すなわち臣民である。
128 エスニックは最初から存在したのではない。多くの氏族・部族が国家の下で統合されたのちに生まれたのである。国家の下で、あるいは神格化されて王の下で統合された人々は、国家や王の消滅後、宗教や言語の共同性(つまり民族性)に依拠した。したがって、むしろ国家が民族を作ったというべきである。
129 国家権力の正当性
まずBによって齎されたカリスマ的支配。次に、カリスマ的支配が齎した「伝統的」な型を踏襲することに正当性を持つ伝統的支配。最後に合理的支配。これは官僚制、法治制度を伴う。ちなみに法治とは、法に服従すれば法によって保護それるという交換に基づいているので、これはBに起源をもつ。
・カリスマとはBによって生じる霊的な力である。
交換様式C
131 そもそも、遊動的段階では、交換を特に必要としなかった。必要があれば、移動して採取したからだ。
132 信用とは、いわば、両者を拘束するような力である。そして、それを齎すのが、贈与ーお返し(A)という交換である。
・そもそもどんな交換も信用なくしてはあり得ない。B, Cの根底にはAがある。
137 マルクスの言葉でいえば、貨幣とは、何らかの物に貨幣形態が付着することである。その意味で貨幣の力は、付着した霊(物神)の力である。
138 国家が貨幣発行に関与するようになったのは、それが利益をもたらすからであった。・・・・貴金属が貨幣となったことは、国家の確立・拡大と切り離せない。言い換えれば、Cの発展はBのそれと切り離せない。
・貨幣に諸物と交換しうる「力」を付与するのは、国家ではなく、そこに付着した何か、つまり貨幣物神である。ただ、国家の保証がなければ、それは貨幣として機能しない。その意味で、貨幣経済、そして貨幣の増殖としての資本の活動が成立するのは、国家の下においてである。
140 古代国家において重要であったのは、管理交易、すなわち、国家によって遠隔地との間においてなされる交易である。それは一種の利益を動機とするものであると同時に、「王の威信」を拡大するために行われた。その意味で、対外交易を推進し、結果的に領域国家や帝国を築く原動力となったのは「聖なる王権」である。
141 都市国家は、いわば交換様式BとCの結合によって成立した。
142 単に武力によって、諸国家を征服し統合することはできない。古代オリエントに帝国が成立したのは、むしろそれを必要とし歓迎するような状況があったからだ。それを齎したのは、交換=交通の発展である。その意味で、帝国を可能にしたのはCとそれに伴う力である。
143 帝国を可能にしたのは、武力による制圧ではなく、むしろ征服された諸民族の自発的な服従である。すなわち、それがBとして成立したということである。のみならず、帝国の成立を必要且つ可能にしたのは、世界交易、すなわちCの発展である。
・帝国に関してさらに重要な点は、多数の地域の文化・言語を受け入れつつ、それらを越えた統一性を生み出したことである。その点から見ると、帝国のシステムの特徴は「世界言語」の創出に見出される。
145 帝国の関心事は、諸部族・諸国家を支配することだけでなく、それらの「間」、言い換えれば諸部族・国家間の交通・通商の安全を確保することであった。したがって、帝国の法は根本的に国際法である。
149 帝国の王は、それまでの王と同格であってはならない。したがって帝国の王の背後にある神もまた、それまでの神々を越えるものでなければならない。こうして世界帝国の成立がかつてない神観念を齎した。
・超越的な神という観点は、世界帝国の成立に伴って生じた。
152 神観念の変化を齎すのは、支配的な交換様式の変容である。
152
交換様式Aが支配的な段階=呪術的段階。 呪術とは、自然ないし人間を、贈与(供犠)によって支配し操作しようとすることであり、それは互酬交換の原理に基づいている。
B=宗教的祈願。神に贈与することで反対給付を引き出そうとする。
C Bとともに世界宗教を形成
D 普遍宗教を形成
155 そこには「社会正義」を実現するのが王の役割だという観念が見られる。また、それは「社会正義」をもたらす神という観念とつながっている。
157 一神教とは、国家の拡大がもたらした産物である。
158 世界宗教がBとCの圧倒的優位によって齎されるのに対して、普遍宗教はそれらに対抗するものとして、交換様式Dによって齎される。そしてDとは、BとCによって封じ込められたAの高次元での回復に他ならない。
交換様式D
159 社会構成体は、ABCの結合体としてあり、どれが支配的であるかによって歴史的段階が区別される。
159 国家が形成されたあとでも、氏族社会にあった、生産物の共有という平等主義と、個人の自由独立性という観念がさまざまな形で残った。
161 帝国は、国家の単なる拡大ではない。帝国を齎したのは、共同体や国家の間での交換とそれを担った遊牧民や漁民である。
161 遊牧民は原遊動民とは異なるが、後者にあった重要な側面、すなわち自由独立性と平等性を保持したのである。つまり遊牧民は、原遊動性の記憶を保持した。
162
・世界宗教とは、イクナートンやハンムラビ王が齎したような帝国を支える一神教である。広大な統治のために今までを越えた神概念が必要だったからである。つまり一神教はBの極大化によって生じた。
・普遍宗教とは、帝国の中心ではなく周辺部に現れたものであり、帝国に対抗するものであった。彼らが唱えたのは要するに、荒野に帰れ、ということである。それは原遊動性の回帰に他ならない。
165 人は自由だから選択するのではなく、選択においてのみ「自由」が齎される。
169 どこでも、遊牧民たちが部族連合体や都市国家を形成するときは、新たな神の下での盟約によってそうしたのである。
170 旧約の預言者らは、遊牧民として荒野にいた頃の純粋さに戻るよう警告した。
・つまり出エジプトとは、イスラエル民のエジプトからの脱出という出来事を指すだけでなく、イスラエルの民がパレスチナで王国として隆盛していた時期を批判的に見る隠喩でもある。
173 預言者がたびたび遭遇する、無自覚的なエクスタシー、つまり神からの強迫的な「力」は、Dに関わる問題である。
174 つまりイスラエルの預言者たちは、国家すなわちBの支配下で失われた原遊動性を回復しようとしたのだ。そのときDが出現した。しかし彼らはそのことを意識して行ったのではない。むしろDは彼らの意志に反して現れた。Dは自己から発するのではなく、強迫的に到来するがゆえに、見通すことも理解することもできない。
175 マルコ福音書は、その後のものとは異質である。一言でいえば、その他の福音書ではイエスが神格化されているのに対して、そこでは預言者としてのイエスの言動が浮き彫りにされている。
176 イエスはAとBを斥けた。
177 イエスにとって隣人とは、社会的諸関係を越えて見出されるような他者のことである。言い換えれば、彼が試査するのはABCを越えて人と交わることだ。それがDの到来、すなわち「神の国」の到来である。そしてそれは原遊動性の回帰であるがゆえに、反復強迫的である。イエスを急き立てる終末論的強迫は、そこから来る。
178 したがって、原始キリスト教は、原遊動性とその回帰(終末)という問題と切り離せない。
179 ウェーバーは預言者を倫理的預言者と模範的預言者の2つに区分した。前者の場合、預言者は旧約聖書の預言者、イエス、ムハンマドのように、神の委託を受けてその意志を告知する媒介者となり、この委託にもとづく倫理的義務として服従を要求する。後者の場合、預言者は模範的な人間であり、仏陀、孔子、老子のようにみずからの生き様を通して人々に救済の道を指し示す。
186 アショーカ王は、アレクサンダー大王の帝国統治を見倣った、というより、大王が見倣ったペルシア帝国のやり方、すなわち、ゾロアスター教を国教としたことを参照した。
188 Dは、それとして意識的に取り出せるものではない。「神の国」がそうであるように、「ここにある、あそこにある」といえるようなものではない。また、それは人間の意識的な企画によって実現されるものでもない。それは、いわば"向こうから来る"ものだ。
第二部第一章 ギリシア・ローマ時代
192 氏族社会が生産力から見て未開の段階にあるにも関わらず、優れた側面を持つこと、のみならず、それが未開性と切り離せない、ということにマルクスは注目した。
195 モーガンは、未来の理想的社会(共産主義)も、氏族社会の「より高度の形態における回復=反復」として見ることができると考えた。
198 ギリシア・ローマの文化が、それ以前のオリエントにあった文明(生産力)を取り入れることで成立したことは確かである。しかし、そこには、アジア的社会にない、そしてそれを超える何かがあった。そして、その秘密は、ギリシア・ローマにおいて保持された"未開性"、あるいは"子供性"にある。それは交換様式で言えばAが強く残っていることを意味する。
199 カール・ウィトフォーゲルの区分
「中心」ー「周辺」ー「亜周辺」
・亜周辺は、周辺と同様に中心から文明、生産力を受け入れたが、周辺と違って選択的にそうしたのである。例えばギリシアは文字、技術を中心から受け入れたにも関わらず、中心の専制国家的官僚制を拒絶した。
・中心はBが極大化してできたが、亜周辺ではAが強く残っていた。
・ウィトフォーゲルは亜周辺の例として、初期のギリシアやローマ、さらにゲルマン、日本、タタールの軛以前のロシアを挙げている。
202 ローマ帝国滅亡後、ギリシア・ローマの特性は主としてゲルマン社会に受け継がれた。というより、それは、ゲルマン的な"未開性"の下で選択的に再生=反復されたのである。それは文化史的にルネサンス、宗教史的には宗教改革と呼ばれている。
203 普遍宗教は本来国家を否定するものであり、だからこそ弾圧されたのだが、それが国教となると国家を支えるBを肯定することになる。これはゾロアスター教や仏教、キリスト教がたどった道である。
206 アウグスティヌスによれば、「神の国」は此岸にある。「地の国」が自己愛に立脚する社会であるのに対して、「神の国」は神への愛と隣人愛によって成立する社会である。
208 アウグスティヌスにとって神の国は、人間の手によって実現されるようなものではない。それは人間が望もうと望むまいと、恩寵として向こうから来るほかないものである。しかし同時に、アウグスティヌスは人間の歴史を、出来事のランダムな連鎖や、天国に至るまでの待合室のようなものとして消極的に捉えるのではなく、地の国と神の国の戦いの場として先鋭化し、そこで人間が果たしうる役割を重視した。
第二章 ゲルマン社会
212 じっさい、未開人だけが、瀕死の文明に苦しむ世界を若返らせる力を持っている。
213 ゲルマン的な封建制とは、生産様式から見れば封建領主と農奴という生産関係だが、交換様式から見れば双務的な主従関係がそこに現れる。
214 封建制は集権的な国家の成立を妨げる。そこでは部族社会にあった原理、すなわちAが濃密に残存し、それがBの決定的な優越を許さない。後者が文明的であるとしたら、前者は未開である。その意味でゲルマン社会には未開性が強く残っていた。
219 中世ヨーロッパの商業・工業都市は、「連合体」である。すなわち国家から独立した盟約共同体(アソシエーション)である。
221 ゲルマン社会ではAが濃厚に残ったため、Bに従属することなくCの拡大が可能となった。
224 ローマ帝国統治の一機構として組み込まれたキリスト教は、西ローマ帝国の滅亡とともにそれまでの政治的基盤をなくした。その後、キリスト教はゲルマン民族の侵入ののちに、社会が全般に農村化するとともに変容せざるを得なかった。その変容を典型的に示すのは修道院の出現である。
226 キリスト教は異教的なものと融合することによってのみ、農民の間に普及した。
第三章 絶対王政と宗教改革
234 ゲルマン社会でBが確立されたと言えるのは、絶対王政が出現したときである。それは王が都市ブルジョワと結託して封建領主を抑えたことによって実現された。言い換えれば、Bの優位を可能にしたのはCの拡大である。
・絶対王政はその名に反して、「絶対的」ではなかった。都市ブルジョワと結託することによってのみ、その地位を確保し得たのだから。
235 絶対王政以前、民衆は中世以来の村落共同体に属しており、彼らにとって王は遠い存在でしかなかった。ところが、絶対王政の段階で王の存在が急激に彼らの身近に迫ってきた。そのことを示すのは「聖なる王権」という概念である。
・この時、王はたんに支配する存在ではなく、同時にそれの聖なる力によって民を治療する存在となった。これはまた絶対王政が厳重に民衆を処罰・監視するとともに、同時に福祉・救貧を行うに至ったことと関連している。
236 絶対王政は、それが育成した市民社会によって倒されることになった。しかし、絶対王政を通して形成された臣民としての共同性は、王政が倒された後も消滅することはなく、別の形で生き残った。それがネーション(国民)と呼ばれるものである。
237 Cの拡大が先に生じると近代国家になりにくい。むしろ近代国民国家の成立は以下のような過程を経て形成される。先ず絶対王政が成立し、その後に、それが市民革命によって倒されることを通して実現されたのだ。
・ベネディクト・アンダーソンの考えでは、ネーションとは共同体が解体されたあとに想像的に再建された観念である。またそれを推進したのは資本主義経済の成立、印刷を通じた情報技術の発展である。
238 絶対王政は倒されたが、その時点で主権者として現れたのがネーション(国民)である。それは絶対王政とともに形成されたものだが、以後、そのような統合体としての共同体が昔からあったように思念されるに至った。
239 宗教改革は意図せず、国民言語の形成を通してネーションを作り出した。
240 宗教改革にはもう一つ意図せざる効果があった。すなわち、共通の文字言語をもち規律をもって集団的に労働できるような労働力商品を作り出したのである。
241
産業資本主義以前
→商人資本は、商品をその価格が安いところで買って、高いところで売る、その差額を利潤として増殖する。金貸資本は、貨幣を貸すことによってその利子を得て増殖する。その時、称賛されたのは王=国家のために働くことであって、個人的な金儲け活動は軽蔑されていた。
269 現代では、商人資本は商社として、金貸資本は銀行として現れている。
246 絶対王政とともに確立された常備軍が傭兵や民兵よりも優れているのは、規律をもつ点においてである。これがのちに規律をもつ産業労働者をもたらした。
249 フーコーの生権力
252 規律をもった労働者の起源を、ウェーバーは「神の監視」から、フーコーは「国家の監視」から説明しようとした。
254 イギリスにおいて、共同体にいた農民が、どこでいかにして賃労働者に転化したか。それは新都市においてである。そこは農民が働きに来て、また、物を買って帰れるような場所であった。このため、貨幣経済が農村共同体の中に浸透するようになった。
256 労働者に支払われた賃金以上の仕事をさせる。それによって生じた利益は、資本家が受け取るものと見做されている。
257 産業資本が発展するために必要なのは、たんに二重の意味で自由な労働者だけではない。それが必要とするのは、消費者となるような労働者である。
第三部 第一章 経済学批判
266 1848年の革命は、社会主義の敗北であると同時に、ある意味で、その実現でもあった。この年の革命以降、ヨーロッパ各地で、資本=ネーション=国家が生じた。
270 物神とは、人と人の交換において生じる、霊的な力である。その変化形のひとつが「信用」である。
271 現代人は物神から解放されたわけではない。恐慌時には、何としても支払手段を確保しようという「信用主義から重金主義への急転回」が不可避である。
273 ホッブズが"怪獣"として見出した国家のありようは、古代の国家にあてはまるだけでなく、また、ヨーロッパにおける絶対王政時代の国家にもあてはまるということ、のみならず、それを倒した清教徒革命によって生じた政体、および、その後復活した王政、すなわち立憲君主体制にも当てはまる。むしろホッブズは、近代の議会制民主主義国家にこそ怪獣を見出したのだ。
Posted by ブクログ
交換様式=最も普遍的で説得力のある歴史区分、という感じ。
普遍的であるが故にそのダイナミズムは追えないが、その事柄の相対的なポジションを意識したいときにはとても役に立つ。
来るべきDは"A=B=Cの、Aの高次の回復に因る揚棄"によって現れるという点には、環境問題に取り組む身としては賛同できないが、Aの高次の回復が必要なのは今至る所で言われていること。
自分自身もそこに貢献していきたい。
Posted by ブクログ
マルクスを中心に、交換様式を通して資本主義や国家・宗教・思想を扱う。交換様式という構造を見抜く力、それを元に世界を説明できる教養の深さと思考の明晰さは面白かった
構造を見抜く力は大切。宗教ですら具体で、宗教「的」や宗教「性」が本質の観念部分にあり、そこが及ぼす影響が分からないといけない。
問いを再構築する本だから、結局のところ交換様式Dは何なのか、だからどう世界は動いてくのかといった、結論部分はあまりない。でも問いの再構成は分かりやすい
Posted by ブクログ
贈与には必然的な信用の概念が伴う。交換様式が発展すると社会が変わる。物事、歴史の動きを交換様式というフレームワークで捉える観点は斬新で面白かった。交換様式はA(贈与と返礼の互酬)、B(支配と保護による略取と再分配)、C(貨幣と商品による商品交換)、D(Aを高次元で回復し、自由と平等を担保した未来社会の原理)として定義。その上で時代によって異なる支配的な交換様式で、社会形態が決まる。Aだと氏族社会、Bだと国家、Cだと資本主義、Dはまだ歴史上ない。
Posted by ブクログ
2023年バーグルエン哲学文化賞を受賞した作品である。唯物史観では社会の発展要因を「生産様式」とするが、それに対して作者は「交換様式」の概念で人類の発展を理解するというもので、作者が数十年にわたって温めてきた思考を集大成する異色の人類発展史観である。
人間の共同性を贈与と返礼の互酬概念から考え始めるものであるが、哲学的で抽象度が高い文章が続き、理解しながら読み進めるのに相当の努力が必要である。
最初に、四つの交換様式の定義から始める。A 共同体における「互酬(贈与と返礼)」、B 国家権力にみられる垂直的な「服従と保護(略取と再分配)」、C 市場における「水平的な商品交換(貨幣と商品)」、D 「Aの高次元での回復」である。これら四つの交換様式を歴史的段階で考え、それぞれの段階が通底したり重なったりして社会は進化する。氏族社会(A)-封建社会(B)-資本主義社会(C)へと進み、「人間の意思を超えて到来する」D段階に至る、そこは「資本主義-国家-ネーションを揚棄する」究極の社会である。この交換様式からみた発展段階説はマルクス主義の経済的下部構造の段階説とは異なり、政治的・精神的なものも含み霊的な力の作用も重視する。Aにはマルセル・モースのいう「ハウ」、Bにホッブスが名付けた「リバイアサン(海の怪獣)」、Cにはマルクスが指摘した「資本の物神(フェティッシュ)性」という霊的観念諸力である。
Dの「A段階の高次元での回復」については、究極の理想である共産主義社会をイメージし「原初への回復・ユートピアの到来」として、それは「向こうから自然にやってくる」という、・・・この辺りまでくると殆どついていけない。何とか喰らい付いてきたのに最後の一番盛り上がった肝心なところで振り落とされる、「もう一回よく読み直してこい」と、そして又読む。
世界宗教は既にDの要素があるということや、アソシエーションなどの概念もD「高次元での回復」のヒントになる気がして頷ける部分も多々ある。箇所によっては論理・論証の凄さに共感し感覚が昂ぶることもある。作者はこの作品で哲学思考の可能性を存分に味合わせてくれる。人類の将来展望も示す。マルクス・エンゲルスをはじめヘーゲル、カント、ギリシャ哲学者や歴史的な思想家の成果をベースに組み立てた密度の濃い論考である。
生煮えながら少しわかりかけてきた気もする。読む毎に刺激的な思考の世界に入りつつあるという実感が満足感を増幅させる。
Posted by ブクログ
恐るべき名著。近年では東浩紀「観光客の哲学」に匹敵するかそれを上回るスケールの哲学書といえるのではないか。
交換様式と「力」について、個々の踏み込みとしては弱いような、もう少し説明がほしいような、また、繰り返しが多いような気はしたものの、世界史を総掴みする壮大な試みには驚いた。
そしてラスト。「向こうから」「Dが必ず到来する」と。その言葉に勇気づけられる。
Posted by ブクログ
呪力(A)、権力( B)、資本の力(C)が結合した資本=ネーション=国家を揚棄する力(D)が、必ず到来する
・・・一冊約400ページを読んでみた(私にとっての)結論が、表紙の内側に記載されていたことばそのまんま、の本でした。
去年くらいから、けっこうまじめに、遠からず、資本主義の次のシステム?社会?が到来する時代を自ら経験することになるのだろうなぁ、、、と考えていて、次にきたるものを考えるヒントになるかも!?と手にしたのだけれど、、、
うーん、私の読解力では、上記キャッチフレーズ?以上の深まりはなかった。
ただ、遠からず資本主義の次の時代が到来する、という思いは、深まりました。
Posted by ブクログ
交換様式Aの高次元での回復であるDをキーワードに、時間や地理を横断しスケールの大きい考察が繰り広げられる。
予備知識として欠落している所もあるので、中々消化するのに苦労した。
Posted by ブクログ
かなり久しぶりに柄谷行人さんの本を読んだ。
最後に読んだのはなんだっけと調べてみると、1994年の「「戦前」の思考」だった。これは出版後すぐ読んだ気がするので、なんと28年ぶりに柄谷さんを読んだことになる。
柄谷さんは、80年代の日本ポストモダーン思想を代表する思想家という印象とマルクスやカントを独自に解釈をする思想家という印象がある。
わたしは、柄谷さんの1978年の「マルクスその可能性の中心」を読んで、それまであまり興味なかったマルクスが「こんなふうに読めるのか!」と驚きファンになった人なので、その発展型ともいえる内容と思われるこの本を見つけ、久しぶりに新刊を買って、読んでみたというわけだ。
が、なんだかスッキリしない。
この本で、柄谷さんは、「資本論」を物神論(フェティシズム)を中心に読むというチャレンジをしていて、それはなるほどの説得力がある。
つまり、経済という下部構造、とくに生産様式が政治や文化などの上部構造を規定するといういわゆる史的唯物論については、その後、ウェーバーをはじめ多くの論者が上部構造が下部構造とは独立して、下部構造に影響することがあるということを指摘してきたわけだが、柄谷さんは、マルクス自身、そんなことはわかっていて、その問題に対するマルクスなりの答えが物神論なのだとする。
柄谷さんは、「マルクスその可能性の中心」において、「生産」ではなく、「交通」とか「交換」という概念の重要性を指摘していたわけだが、その議論を「交換様式」として発展させ、それを「資本論」の物神論につなげるわけだ。
このマルクス読解は、当然に好き勝手にやっているのではなくて、「資本論」の執筆が止まっていた時期のマルクスの関心事などをメモ書きなども参照しながらのもので、一定の説得力がある。(柄谷さんは、マルクスがモーガンの「古代社会」を読み込んでいたことを重視している)
マルクスはこう考えていたかもしれないというここまでの議論は、面白いと思う。(あと、科学的な史的唯物論を一般化した考えられるエンゲルスも、実は宗教的なものをある程度肯定的に議論していたことがあるという話しも面白かった)
が、柄谷さんはここで議論を止めずに、その「交換様式」の議論をベースに、唯物史観の下部構造を「生産様式」から「交換様式」に置き換えて、世界史全体を再解釈していこうという壮大なチャレンジに挑む。
柄谷さんの試みは、人類学などの最近の議論も含めて、さまざまな論者の研究を参照しているのだが、かなり大味なもので、最後は宗教的な予言になってしまうのは、疑問がたつ。(ちなみに、マルクスが参照していたモーガンの議論は、人類学的には、古典ではあるものの、その内容に対する現代の評価はかなり批判的なものであると思う。その辺りのところを柄谷さんは、最近の進化人類学などの研究を使って、補強しているわけであるが、それにしても議論の粗さは否めない)
どうして、晩年のマルクスは、いわゆる唯物史観からは離れた物神論を展開していたという読解をするだけで、話を止めなかったのだろうか?というのが素朴な感想。
つまり、柄谷さんは、マルクスの考えていたことが、ソ連や中国の共産主義とは違うものであることを示しつつ、もう一度、マルクスの原典を読み直し、そこから本当のコミュニズムを生み出そうと呼びかけたいのだと思う。そして、それをカントの「永久平和」と連関させて、未来への希望を打ち立てようということなのだ。
わたしは、いわゆる唯物史観は、キリスト教の黙示録的な歴史観の復活と捉えているのだが、柄谷さんは、それを明らかにつつ、それを批判するのではなく、肯定しているようなのだ。
最近のマルクス解釈としては、斎藤幸平さんが、やはり「資本論」以降のマルクスにエコロジーの思想を見出していて、これも面白かったのだが、斎藤さんもマルクスはこう考えていたのかもしれないというところで止めずに、そこから今の世界への批判に直接に議論を進めているように感じた。(柄谷さんほどではないが。。。)
こうした新しいマルクス解釈が現在の世界に一つの視点を与えてくれるというのはいいのだけど、それ以上のことになるとマルクスはやっぱ昔の人なので、今の時点で、そこから直接的に世界を理解するには、やはり無理あるのではないか、と思うわけである。別に、私はマルクス信者ではないので。
となんだかモヤモヤしたのは、「「戦前」の思考」を読んだ時の感覚に近い。
そして、このモヤモヤは、インテグラル理論やティール組織の社会の文化的な進化というコンセプトへの疑問にも通じる。
なんらかの演繹的な理論をベースに歴史全体を解釈して、それを未来に投影することの危険性を柄谷さんがわかってないはずはないのだけど。。。
と批判的になっているのだが、彼の議論の展開を30年くらいフォローしていなかったわたしは、柄谷さんがなんでこんな議論をしているのかが知りたくなっている。
とりあえず、マルクスとカントを柄谷さんが新たに読解しているらしい「トランスクリティーク」を読んでみようかな?