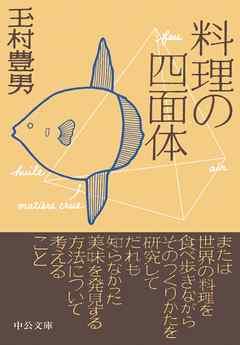あらすじ
英国式ローストビーフとアジの干物の共通点は? 刺身もタコ酢もサラダである? アルジェリア式羊肉シチューからフランス料理を経て、豚肉のショウガ焼きに通ずる驚くべき調理法の秘密を解明する。火・水・空気・油の四要素から、全ての料理の基本を語り尽くした名著。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
これは面白い。
途中途中にあるギャグ的な要素もにやけずには読めない。
そして料理という複雑な変数にまみれた事象を、簡潔に四つの要素にまとめるという試みが素晴らしい。
料理系の本は初だったが充実した時間であった。
複雑な事象を簡略化するヒントにもなった。具体と抽象を行き来し、物事の本質を知るとはまさにこの本である。
Posted by ブクログ
これも素敵な料理本。「火、水、空気、油」を鍵に、料理の成立過程を原則から説くプロセスが、知る歓びにダイレクトに効く。この本質さえ踏まえて臨めば、世界のどこで何を作っても料理。冒険心を抱かせてくれる。それにしても冒頭の羊料理が美味しそう!
Posted by ブクログ
今までに無い切り口で料理を解説している本。レシピ必須で家庭料理をしている人が、レシピを見ずに料理が出来るようになるための一歩を後押ししてくれるような内容です。
Posted by ブクログ
紙面の大部分を世界各地の料理の分析、共通点の探索に割いている。
そう聞くと、淡々とした文章で読み進めるのが苦のように思えるが、そこを筆者の軽い文体とジョークを交えることで気づいたら最終章に辿り着いていたという経験をさせてもらった。
最終章では、それまで紹介された内容が水、油、空気そして火という4要素に還元され、それらの関係性をひとつの図形で視覚的にわかりやすく説明される。
この図形のどこかに点を置くことで新しい料理ができると同時に、すべての料理が(底面変換を繰り返すことで)この図形に詰まっていると考えると、これから料理を食べるのが楽しみになって仕方がない。
Posted by ブクログ
火、空気、水、油の構成要素で世界中の料理が実は語れること、四面体の考えを使って無数のレパートリーで料理が作れること(ただし美味しいかは各自の腕前と味覚による)が語られる。適当な料理でも四面体のあの辺に位置するな…とかなるのでハードルが下がりそう。料理面白い、となる良い本だった。心平粥は家でだらだらしてる日に作ってみたい(米、ごま油、水を1:1:15の割合で混ぜて2時間煮る)
Posted by ブクログ
料理の四面体という理論が出てくるのは最後の章だけ。
それまでは、その理論を演繹法で導いていくのだが、そこがとても面白い。知らなかった知識や、今までの固定概念を覆された。
Posted by ブクログ
料理の事例と分析を行なって共通項を洗い出す。
その繰り返しで最終的には料理の根幹的要素である料理の4面体に辿り着く
明日役に立つようなものではないが、この4面体を念頭に置いておくと4、5年後くらいに何か、蒙が啓かれる体験が出来るかもしれないような気がする
面白かった
Posted by ブクログ
料理の理論を語る本は初めて読んだ
料理の四面体を知ってしまった以上食材に対して色々なアプローチを試したくなる
現在存在してるレシピなどは先人が考え美味い故に残ってる物だとは思うがそこから外れた所に新境地を探検したくなる
例えばきゅうりはあまり火を通す料理がない印象があるがこれを揚げたらどうなるかなどやってみたい
Posted by ブクログ
世界中のありとあらゆる料理は基本的に原理は同じであり、(1)火という中心要素の営みを受けてそれに対応する(2)空気(3)水(4)油という三要素を合わせた四要素から、食材や調理器具などの差異こそあれども、成り立つ調理法の組み合わせだと論じている本書。この抽象的で聞いただけでは理解しがたい概念を、著者が出会ってきた様々な料理の丁寧な説明と共に読み進めていくうち、結論ではっきりとその教えの理解に驚きと共に至ることとなる。料理に於ける哲学書のような一冊。しかもこの原理は過去に存在したであろう料理やこれから未だかつて誕生したことのない料理にも通用するから、魅力的である。必携の名著。
Posted by ブクログ
某Podcastの堀元さんがたびたび本質本として紹介していたので、料理には疎い私ですが興味を引き読んでみた。
肩肘張らないエッセイ本ということで、すらすらっと読み進めることができたし、異国の料理と身近な日本の家庭料理との共通点を、少し無理やり感はありますがユーモラスに論じていき、結局納得されられている私がいます。料理に対するメタ認知の極致であるように思うし、そこまで俯瞰して料理を捉えることができたら、確かに刺身も結局はドレッシングをかけたサラダなのだなーと共感。
火を頂点として、空気、水、油の三点を底辺と置いた四面体が料理の根本原理。ここまで達観した主張を出らための思い付きで述べてるのでなく、最終章に至る諸々の考察がこの論旨を支えている。料理に対する精緻な研究がそこにあるからこそ、一見単純な主張がまっすぐ受け取ることができるのだろう。
個人的にお米の炊き上がりには少しこだわりがありますが、そこは硬くなったり柔くなったりが違う料理への誘いなのかもと、視野が広がったかな。
Posted by ブクログ
料理の本質に注目すれば火、空気、水、油の4要素しかないよねという本。
調理へのハードルを下げつつ、無限の可能性を提示してくれる良質エッセイだった。
Posted by ブクログ
まず何より筆者の文章がとても読みやすく好みだった。ユーモラスでありながら、細かい論理展開しかり、最後に振り返ったときに全てが布石として繋がっている筋の作り方に脱帽。
一つひとつのエピソードが面白く、さながら世界を旅しているような感覚。さまざまな料理、文化と出会える。
そしてタイトルにもなっている四面体の理論をはじめとする、事物の整理の仕方に筆者の恐るべき知性を感じる。
文化人類学に興味がある方には是非手に取ってほしい一冊。