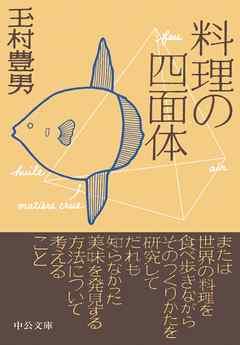あらすじ
英国式ローストビーフとアジの干物の共通点は? 刺身もタコ酢もサラダである? アルジェリア式羊肉シチューからフランス料理を経て、豚肉のショウガ焼きに通ずる驚くべき調理法の秘密を解明する。火・水・空気・油の四要素から、全ての料理の基本を語り尽くした名著。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ゆる言語学ラジオで堀本さんがおすすめしてた本質本ということで読んでみた。目次があんま意味ない、というか、内容とあんまりあってなくて読みにくかったけど、料理の四面体の概念は確かに面白い。
Posted by ブクログ
玉村さんの本を読んでいると料理がしたくなる。四面体理論のような構造としての料理の捉え方は新鮮だしレシピに縛られた料理概念から解放してくれるような気がする。
Posted by ブクログ
2021/10/17 読み終わった
ゆる言語学ラジオで紹介されていたので。堀元見のいう「本質本」を食らってみたかったので。本質本については当該YouTubeチャンネルの#36をご参照ください。
料理のプロセスを分解すると、火、水、空気、油、の4つの要素のパラメータバランスで全てが説明できるというもの。
確かに、という感じ。例外は無さそう?この知識が料理実践に活きかどうかはわからないけど、思考の整理にはかなり役立つと思う。
Posted by ブクログ
料理の四面体とは頂点に火、底面に水、油、空気からなる三角錐であり、どんな料理も三角錐にプロットすることができる。
序盤では世界中の色んな料理・調理法を紹介しながら、帰納法的に火、水、油、空気を用いていることが示され、終盤では演繹法的に左記4つの要素を組み合わせた蓋然性が述べられている。火が加わった食材を再度底面にプロット(底面変換)することで様々な調理方法を説明することができる。
ビジネスでも同様に底面変換を繰り返すことでUSPを云々…的な事は考えずに、中華ってすごいな!今日は青椒肉絲だ!とか思いながら読み進めるのが楽しかった
Posted by ブクログ
料理を創意工夫し楽しむときに役立ちそうな本。
料理の基本要素は(1)火(2)空気(3)水(4)油でこの組み合わせとのこと。フランス料理も怖くない。
Posted by ブクログ
全ての料理を火、水、油、空気の4大要素の配分量に落とし込んだ本。
特に「全ての料理がサラダである。」、「焼くというのは水と油の介在度を極限まで少なくした加熱法」と表現しているのが秀逸で面白かった。
Posted by ブクログ
ずいぶん前にゆる言語学ラジオで堀元さんが本質本として挙げていて、ずっと読みたいと思っていた本。
ようやくポチった。
料理することは、面倒くさいのでそんなに好きじゃないんだが、食べることは好きだ。
毎日なんだかんだ言いながらも食事の時間が楽しみなので、必要に迫られて料理をしている。
例えばサラダを作るとき。
調味料に加える油の種類によって、
中華っぽくも洋風っぽくもなるなー…あ、和食のサラダなら酢の物とか油入れなきゃいいか、その代わり麺つゆ投入!
とか、
汁物もお水に適当な野菜を入れて、出汁のもとや麺つゆにするか、鶏がらスープにするか、コンソメにするかで和洋中が変わるよなー…、
ぐらいのゆるーい認識はもともとあった。
料理の構造をここまでロジカルに説明してくれる本書は確かに本質的。
上記したわたしがふんわり感じていた味と料理カテゴリーの関係のみならず、調理段階で関わる4つの要素がどのように料理に影響し、完成に繋がるかを見事に構造化してみせる最終章は圧巻だった。
それまでの、焼く、揚げる、煮る、などの調理法に沿った各国のいろんな料理の紹介も面白い。
特に冒頭のアルジェリア式羊肉シチュー。アルジェリア南部で著者がご馳走になったそれを、現地の方が作っている描写が本当に美味しそうで、その他にも試してみたくなる料理のレシピが載っていたりして、
…あれ、もしかして私、料理好きなのかも…、と錯覚してしまいそう。
食べたい欲が、作るの面倒くさいを越えたらいつか挑戦するかもしれない。
しかしこれ、美味しそうだし、
そのくせめちゃくちゃ理屈っぽくて、
本当に好みの本だったな。
復刻バンザイ!
Posted by ブクログ
おいしさは、五感だけで感じるものじゃないかも。
このごろ「実用的でない料理本」というのが好きで。料理が自分のライフスタイルや思想に与える影響、原始から続く料理という運動が、どんな歴史をたどって、世界にどんな影響を与えたか等に興味があり、色々本を漁るうちに『料理の四面体』と出会いました。
この本を読んでも、包丁さばきがうまくなるわけでも、火加減の調整が適切になったり、盛り付けセンスが磨かれるわけでもありません。実用的な料理指南書やレシピ集ではないですが、「料理は単純な原理で成り立っていながら、無限の可能性がある」というメッセージを伝えてくれます。
他方で得た知見がまったく無関係の分野と結びついたりする、そんな瞬間こそが私の生きる喜びのひとつ。料理で得た経験がマラソンに活きることや、農業のノウハウが油絵に活きること、暗算がロッククライミングにいきることもあるかもしれないと思うだけで人生は楽しい。だから自分の生活に直接役に立ちそうにない本の方がワクワクします。
本書ではまず世界のあらゆる料理が紹介されます。フィレンツェのビステッカとか、コトゥレット・ド・ムトンとか、いかにも美食家が好みそう料理名が頻出する上にとても文学的な表現もあり、グルメ評論アレルギーがある人にとっては、著者がうっとり自己陶酔しつつ書いたように感じて鼻につくかもしれません。
最初こそ気取ったグルメエッセイのような印象でしたが、少しずつ確実に、私たちは著者が導き出したある一つの論理に一歩一歩と近づいていきます。高級フレンチも、アルジェリアの野外で野蛮に作られたシチューも並列に語り、目玉焼きもスクランブルエッグもオムレツも「卵の油いため」という点で同じ料理だとする大胆さをもって、紙上・世界グルメツアーは展開していきます。スープとシチュー、果てはサラダと刺身の境界線もぼやかせる力技にクラクラしながら読み進めていくと、最終章でついにモノリスにたどり着きます。
それがタイトルの「料理の四面体」です。
食材⇆媒介(水、空気、油)⇆火
という関係性を暴き出したのです。料理の工程を分解し、四面体(三角錐)の立体チャートにあらわす。頂点に火、底面の三点は空気、水、油。この世にある料理をその四面体チャート状の座標ですべてあらわすことで、調理の原理を解き明かしたものです。
逆に言えば火を使い、水、空気、油をどの程度か媒介させれば、それはもう「料理」と言いきれてしまうというコペルニクス的転回が起こるのです(生食は除く)。世界中に料理は数多あるけれど、調理の本質は基本的に変わらないということと同時に、そのチャート上にまだ誰も見つけてない一点の座標、つまりまったく新しいレシピが隠されているかもしれないといったロマンも感じます。
こういった本を読むたびに思うのは、おいしさというのは、五感からのみ感じるものではなくて、その調理の工程などに思いを馳せることからも感じるのかもしれないと思います。その食材の生産地の風土のことを想像したり、生産者の顔を思い浮かべたりすること(野菜コーナーに農家の名前と写真が添えられていますよね)、伝統を感じること、思い出と結びつけることなど、五感以外の「気持ちのおいしさ」があるのだろうと。
Posted by ブクログ
一言結論:料理の構造を解き明かした画期的な本。ここから何を学ぶかが問われると思います。
感想:世界中の色々な料理を実際に食べ、かつ知識を有しているからこそ辿り着く発想でしょう。料理のレシピとしての研究ではなく、料理という行為そのものの本質・構造を扱った本はなかなかないのではと思います。前フリはだいぶ長いですが結論の衝撃たるや!やられた感がすごいです。
復刻版にあたり著者のメモには「料理人からは否定的な意見も多かった」と書かれているように、この本が言いたいことを読者自身が考えなければただの戯言で終わってしまいます。ここから何を学びどう思考や行動に転換させていくのかが大事ではないでしょうか。料理に限らず、様々な分野はある基本法則・原理に基づいて成り立っており、それを理解しようと努めることがひいてはその分野そのものを理解することに役立ちます。物理学は良い例だと思いますが、物理学でなくても日常のあらゆる現象には大小の差こそあれ全て本質があるわけですから、それを構造化しようと努めるべきと個人的には思います。それは生活全体、人生そのものも然りです。
ですから、料理という一見基本原理など見えそうもないものが1枚の図で表されていることは衝撃的なことであり、私たちは自分の人生ひいては他の人の人生を良いものにしていくためにそれぞれの四面体を読み解いていくことを諦めてはいけません。この本は真理を突く点で大切なことを教えてくれています。必読です。
Posted by ブクログ
頭のいい人は、具体と抽象を行き来するのがうまいという。この本で述べられているのは、世界各国の料理から、調理を構成する基本要素を抽出して四面体に落とし込み、その要素の組み合わせによって様々な料理を生み出すということで、具体化と抽象化そのもの。この四面体を知れば、これまで別個のものとして捉えていた料理同士のつながりが見えてきたり、既存のレシピにアレンジを加える発想を得られたりすると思う。新しいアイデアも既存の要素の組み合わせというが、四面体に当てはめれば納得感がある。
Posted by ブクログ
著者のことは全く知りませんでした。
面白いタイトルだなぁと思い、手にとってみると著者の考え方もまあ面白い!
料理の表現がとても素敵でこれは食べてみたい!と思わせる文章が素晴らしいです!
内容も科学やコツとも異なっていて、法則や哲学(?)に近いものを感じます。
レシピを考えるときにはこの思想を取り入れて、作ってみようと思いました。