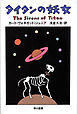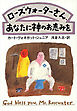カート・ヴォネガット・ジュニアのレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
没落貴族がキャトルミューティレーションされ、仮面ライダーの如く宇宙戦争に巻き込まれるSF小説です
火星、水星、土星と拉致される様は、どの惑星も美しく宇宙旅行気分になれました
ロボトミー手術を受けた没落貴族の、少年時代から老衰するまでを描かれています
ヴォネガット作品を初めて読むのですが、宇宙人のモノローグが上手でした
謎の固有名詞がほぼ出てこず特有の倫理観が伝わりやすかったです
洗脳前後の没落貴族のモノローグも、本当に別人の様子が伝わってきてすごかったです
一番好きなパートは、火星に拉致された人々が指紋鑑定によってどのような地球人だったか答え合わせをする場面です
軍曹がふつうの警備員だった -
Posted by ブクログ
作者が戦時中に体験した事実に基づいた半自伝的SF小説。戦争をはじめとする、作者が直面した目を覆いたくなるほど辛い体験の数々。そこから目を逸らすのではなく、「そういうものだ」と受け止め、それでも楽しかった瞬間を思い出して(あるいは、その瞬間を訪れて)前を向いて歩んでいきたい。そんなメッセージを感じる、とても素晴らしい作品だと感じました。
最近「歌われなかった海賊へ」を読んだばかりだったこともあり、精神的にキツいところもあったのですが、別の視点から戦争を知ることができたことは、貴重な読書体験がでした。
SF作品として見ると、小松左京「果しなき流れの果に」や、今敏の映画「千年女優」に近いかもしれ -
Posted by ブクログ
ネタバレレーベルはSFだけどSFではないんだよね…
ある種問題作かもしれません。
(まあ仮の人物としてがSFか?)
一人の二重スパイがこの状況にまで
至るまでのお話。
結局言ってしまえば、
戦争というものは様々な憎しみの種を植え付け
どこまでも暴走していくということ。
まあそれでもこのキャンベルは
うまく立ち回ったとは思うのよ。
じゃなきゃ最初につかまった時点で
とっくに絞首刑になっているので。
そして一時の幸せであろう生活までもが
途中で暗転してしまう恐ろしさ。
それが彼にとっての「報い」だったのかもしれません。
結局は彼は望んで
延長されていた罪を受けることになります。
そうなるとどん -
Posted by ブクログ
ネタバレ名作と言われる『タイタンの妖女』がさっぱり面白いと思えなくて、疎外感を味わっていたものだ。そこでもっと評価の高いものを読んで、それでダメなら本格的に合わないのだろうと随分前に買ったのをようやく読んだ。SF的な要素はあんまりおもしろいとは思えなかったのだけど、ドレスデン爆撃の現場で地獄を見た人がその様子を描写するためには、こねくり回して形にするしかなかったことがうかがえる。諦観や虚無感が満ち満ちている。相当なPTSDがあるのではないだろうか。こちらとしては平々凡々とした人生を送っており、圧倒的な現実に立ち会ったことなどない。
人が死ぬたびに「そういうものだ」と差し込まれ、村上春樹の「やれや -
Posted by ブクログ
ドレスデン無差別爆撃の話。
ビリーが第二次大戦における米軍爆撃機隊の活躍する深夜映画を逆向きに観て、負傷者と死者を乗せた穴だらけの爆撃機が逆向きに飛び立ってゆき、爆弾や銃弾を吸い込み、新品に戻り、軍需工場で解体され、鉱物になり、それをだれにも見つからない地中深く埋める、という一連の映画逆再生のシーンが切ない。
p. 33大量殺戮を語る理性的な言葉など何ひとつないからなのだ。
p. 44死んだものは、この特定の瞬間には好ましからぬ状態にあるが、ほかの多くの瞬間には、良好な状態にあるのだ。いまでは、私自身、誰かが死んだと言う話を聞くと、ただ肩をすくめ、トラルファマドール星人が死人に -
Posted by ブクログ
普通、物語のはじまりが思い出からだったり、思い出がはさまれたりすると情緒がただようのである。が、この小説は「けいれん的時間旅行者」という思い出の進行、なんとも読者は不思議な気持ちにさせられる。
主人公ビリー・ピルグリムは現在、過去、未来を行ったり来たりしている「けいれん的時間旅行者」。そうなったのは戦争に召集され、襲撃を受け敗退、逃げ出した森の中で死ぬ思いをした時。
そこから過去に行くのだが、その過去が現在や未来へ続き、また現在へ戻るという複雑な経過。夢かうつつかまぼろしかということになるのだが…。
過去現在未来は一瞬、一生は一瞬。つまり、中国のことわざ「一炊の夢」、だから一瞬一瞬を大切 -
Posted by ブクログ
他の多くのヴォネガット作品と共通して、エリオット・ローズウォーターの行動原理は第二次大戦でのトラウマに端を発している。軽く可笑しく展開している物語のなかで、戦争中に誤って少年を刺し殺してしまう述懐だけが異様に生々しく、温度が違っているように感じた。終盤でエリオットが大勢の子どもを持つ、という第三の選択は、唐突なアイデアのようでいて、実は最初から追い求めていた救済のかたちだったんじゃないだろうか。
最後の最後で病んだ資本主義社会が転覆する爽快感を味わった後で、ここのところディストピアな妄想ばかりたくましくして、魅力的なユートピアなんて全く思い描けていなかったことに気づき、なんとなく淋しい気持ち -
Posted by ブクログ
ネタバレ貧しき人々に惜しみなく財を与える億万長者・ローズウォーター氏」を狂気の塊として扱うこの作品。他のヴォネガット作品よりはあっさりしているなあと読み進めていたけど、以下のフレーズは、「生産性」という言葉に揺れる今の日本にとって暗示的な内容だった。
「規模は小さいものだけれども、それが扱った問題の無気味な恐怖というものは、いまに機械の進歩によって全世界に広がってゆくだろうからです。その問題とは、つまりこういうことですよ──いかにして役立たずの人間を愛するか? いずれそのうちに、ほとんどすべての男女が、品物や食糧やサービスやもっと多くの機械の生産者としても、また、経済学や工学や医学の分野の実用的な -
Posted by ブクログ
ネタバレ機械が高度に発達し、コンピュータEPICACによりIQと適性を認められた極小数の管理者と技術者が支配する未来のアメリカ。大多数の人間は職を失い、自尊心をも失いかけていた。
第三次世界大戦中に人手不足のため機械への依存が高まると、機械は飛躍的に進歩し、EPICACと呼ばれるコンピュータにより全てが決定されることとなった。この組織を作り、発展させたジョージ・プロテュース博士の息子、ポール・プロテュース博士は高い地位にあったが、このような世界を徐々に疑問に感じ始めた。ポールより出世が早かったがその地位を投げ打った旧友フィナティー、夫を出世させることにしか頭に無く、何事に関しても口出しする妻のアニー -
Posted by ブクログ
序盤、エリオット・ローズウォーターがなぜこのような慈善の人になったのか、また彼を取り巻く貧しく不運な多くの人々の描写などが、まるで演劇の舞台を基礎から創っていくかのように細かく丁寧に描写される。この状況説明を読みこむのに時間がかかり、「この作品はタイタンの妖女みたいに自分には向いていないのか?」と思いきや、中盤から愛すべきエリオットという人が掴めるようになる(それまでの丁寧な描写がここで効いてくる!)と、どんどん面白くなっていき、最後高みに飛び立って、ストンと終わる。
でも。
私にはエリオットのような人間愛はきっと寂しく思えてしまうだろう。彼の妻が、彼を愛していても寂しかったように。彼の父が -
Posted by ブクログ
ヴォネガットの小説はいつも話の筋になかなか掴みどころがない。
そしてこの作品は今までにましてストーリーが掴めなかった。
読んでいて、いるのかいないのかも分からない透明のウナギを捕まえろ!と命令されている気分。
狂った登場人物たちによる、でたらめな事実が箇条書きで続いていく。
訳者のあとがきによると、“ヴォネガットが書いた最も直接的なアメリカ批判の書”なのだという。
確かにその通りで、“ヴォネガットらしい”宇宙を感じさせられる途方もない視点から見たアメリカという国を、
かなり痛烈な言葉で批判したり皮肉っている文章が多く目に付いた。
例えば、コロンブスがアメリカ大陸を発見した“1492年”について -
Posted by ブクログ
もしも完全に利他的な人間が、働かなくてもお金の手にはいるような大金持ちだったら?
これはヴォネガットのいつものユーモアと皮肉と笑いをまじえて大金持ち、エリオット・ローズウォーターの生き方を描いた小説。
エリオットの周囲にいる人間たちを同じ人間とも思わないような俗物らしいエリオットの父親は、誰をもを愛していると言っているエリオットに対し、特定の人間を特定の理由で愛する自分たちのような人間は、新しい言葉を見つけなければいけないと嘆く。
エリオットが「役立たずの人間」に奉仕するときの「愛」とはどんなものなのか?
住民たちのもとを離れ、もう戻りたくないと思いながらも、まだ見もしらぬ子どもたちのために