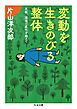検索結果
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
4.0藤本さんは私の釣友達で昔から羆のことは追いかけていた。 そしてついにこんな本まで。これは読むべし。――夢枕獏(作家) 2019年夏、北海道東部で、牛を次々と襲う謎のヒグマが確認された。付けられたコードネームは「OSO18」。 捕獲に乗り出した地元の男たちの数年に及ぶ闘いを描く。 <目次> プロローグ 第一章二〇一九年・夏 襲撃の始まり 第二章 二〇二一年・秋 追跡開始 第三章 二〇二二年・残雪期 知られざる襲撃 第四章 二〇二二年・夏 知恵比べ 第五章 二〇二二年秋 咆哮 第六章 二〇二三年・春 異変 第七章 二〇二三年・夏 「OSO18」の最期 「OSO18」とは何だったのか? あとがき
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 自覚がなくても、肩こりの人はたくさんいます。 実は、ほとんどの人は、肩こりなのです。 でも、残念……。 肩こりは、いくら肩をマッサージしてもよくなりません。 どうすれば、肩こりはよくなるのでしょう? その画期的な方法は「脇」にありました。 カギを握るのは「脇」にある前鋸筋(ぜんきょきん)という筋肉。 これが、ものすごく大事。 前鋸筋のある脇に注目したワーク、 それが『脇もみ』です。 もむといっても、 マッサージでもストレッチでもありません。 簡単な動作で、運動が苦手な人でも大丈夫! 『脇もみ』は、肩こりに効きます。 肩だけでなく、腰もすっきり、頭もすっきりします。 この本は、『脇もみ』で肩こりをすっきりさせて、 全身の不調や悩みも改善させる 『脇もみ』ワークガイドです。 大げさではありません。 『脇もみ』で人生が変わります!! 第1章 世の中の人は、みんな肩がこっている 世の中、みんな肩こりで悩んでいる どうしてマッサージを受けても、すぐ元に戻ってしまうのか? そもそも、肩こりとは? 現代社会は24時間肩こりの原因にまみれている 肩を下げても、こりはゆるまない 腕の支え方が変わると、肩は楽になる 肩こりは快適な体を蝕んでいく 第2章 「脇」をもめば、肩こりは消える 肩こり解消の救世主「前鋸筋(ぜんきょきん)」 あなたの「脇」は大丈夫? チェックテスト 脇は全身をつなぐ“力の橋渡し役” 現代人の「前鋸筋」は眠っている 「脇もみワーク」をやってみよう 「脇もみワーク」基本編 脇もみ肩回し 「脇もみワーク」で肩こりのない体になる 「脇もみワーク」なら努力しなくても肩はゆるむ 第3章 全身すっきり「脇もみワーク」 脇もみワークで全身がしなやかになる +αの効果を生む「脇もみ」応用ワーク 「脇もみワーク」応用編1 脇もみウォーキング 「脇もみワーク」応用編2 脇を押さえて小指ペンワーク 「脇もみワーク」応用編3 脇タオル 「脇もみワーク」応用編4 肩甲骨枕 第4章 肩こりがなおると、人生もうまくいく 「脇もみワーク」で猫背はなおる 「脇もみワーク」で腰痛・ひざ痛が改善 第5章 肩こりが消えると、人生もうまくいく ストレスからくる肩こりに注意
-
4.6
-
-秘伝、公開! 本来備わっている「自己調整力」(自らが整う力)を引き出す方法、「間合い」の全容とは。三人のボディワーク施術者=「間法(まほう)使い」による、数十年の年月をかけた探求が明らかに。 ・リラックスできない ・漫然と不調 ・朝から疲れている 「からだの力」を取り戻し元気になりたい、すべての人へ届ける智慧とメッセージ。 【目次】 ▼1:からだの深みを見つめていたい――片山洋次郎(聞き手: 藤本靖) 近代社会の限界と日本人の身体/息苦しさはどこから来るのか 日本人の胸はなぜ固いのか/「困った…… 」が発動している日本社会 施術は問題を解決するのか/「内臓感覚」と「覚醒状態」を取り戻す方法(他) ▼2:交流するからだ――田畑浩良(聞き手: 藤本靖) 日常生活で「最初の場」をどう探すか/「逃げる」ということ 「イールド」とは何か/体内における情報の伝達とボディワーク コントロールしない呼吸を迎える/グラウンディングとイールディングの違いとは(他) ▼3:鼎談 空間から身体と感覚を考える――空間身体学宣言 空間の緊張も共鳴する/身体があることで空間が生まれる 動的感覚が流れる空間へ/物理的距離を超えてからだは共鳴する 重力方向と水平方向から身体を考える/根源的な安心感をもたらすもの ――イールド原論/「何も起きないポジション」を探して(他)
-
-深い呼吸は気分のいいことであり、よく生きることそのもの。身体、心、人づきあいと呼吸の関係など、整体の現場から、身心を整えなおす、心地よい呼吸について解きほぐしていく。 深い呼吸とは、 よく生きることそのもの。 太古から先人たちが 身心の安定の中心的課題としてアプローチしてきた呼吸。 身体、心、人づきあいと呼吸の関係など、 整体の現場から、 身心を整えなおす呼吸の仕方について解きほぐしていく。 呼吸を自然と、長く深く導く「脱ストレッチ」なども紹介。 真の脱力を体感できる本。 【Contents】 序 章 呼吸の中に整体がある 第1章 呼吸と身体 第2章 呼吸とこころ 第3章 人と人のあいだの呼吸 第4章 呼*吸の極意
-
3.3心地よいかどうか。それが、本当の「良い姿勢」を教えてくれる。姿勢の思い込みを手放し、身体が持つ回復力を引き出すためのヒント。姿勢をほぐすメソッド、寝相別・体癖一覧も紹介! 【背筋をピンっと伸ばすのが、本当に正しい姿勢?】 心地よいかどうか。 それが、本当の「良い姿勢」を教えてくれる。 背筋をピンッと伸ばすのが正しいわけではない。 姿勢の思い込みを手放し、 身体が持つ回復力を引き出すためのヒント。 姿勢をほぐすメソッドも イラスト入りで紹介! 【疲れをためず、 持続可能 な身体で生きるために】 Contents i あなたにとって 本当に良い姿勢 とは? ii 姿勢と心の関係をひもとく iii 疲れない姿勢をつくるセルフメソッド 自分の姿勢の癖がわかる 「寝相から読みとく体癖」一覧も収録! * * * 気持ちよく寝て、気持ちよく座り、立ち、そして歩く。 そこに一人ひとりの良い姿勢があります。 それぞれの身体の内側から湧き上がるような、 生き生きとした、自前の姿勢を見出していきましょう。
-
4.0正しい姿勢、正中線、丹田、etc.... 自分の身体の正解を、外に求めてばかりいませんか? 外の知識を無理失理自分に当てはめても、本当に自分のものにするのは難しいものです。 スポーツ、武道、ダンス、日常、本当に自律した、自分の身体が好きになれる「正解」は全部、あなたのなかにあります。 この本ではそんな方法を紹介しています。 ロルファー・能楽師 安田登氏のコメント 「一読するとからだが変わる、世界も変わる」―― 身体感覚とか身体意識とか、よく言われているけど、じゃあ、それって本当は何なんだ、具体的にどうするんだ。ちゃんと書いてある本はほとんどない。が、この本はすごい。なるほど! こんなアプローチがあったのかと驚かされる。やられた!って感じです。
-
-
-
-
-
4.0疲れる、疲れがとれない、それは身体のセンサー(目・耳・口・鼻)の使い方がまちがっているからです! 疲れた身体がたちまちよみがえる、藤本式「疲れゼロ」のボディワークの方法。 聞きたくない話や騒音に耳が、ガマンすることで口が、イヤな思いをすることで鼻が固まっている! さらに、パソコンで疲れる、人に会うのが疲れる、マッサージでほぐしてもすぐ元に戻る……などなど、日々つきまとう疲れを感じている方に朗報です。 本書では「立ち続けても疲れない方法」から、「緊張しないですむ視線の合わせ方」、「話し上手になる声の出し方」、「ストレスや不安を感じたときにおすすめのストロー呼吸」まで、すぐにできるシンプルなボディワークを紹介。
-
3.0
-
-朝・昼・夜 自分でできる片山整体(身がまま整体)の決定版!! 3・11以降、疲れがとれない身体のままストレスにさらされ、「なんとなく不安な日々」を生きてきた方は多いはず。 そうした中、「野口整体」の思想をベースにしながら、独自のメソッドで新しい整体法をつくりあげてきた著者が、自分でできる「一日の整体プログラム」を本書で提唱。 朝、起きたときに何をするか?通勤時に気をつけることは?退社後、夕食後にやることは何か?――など、疲れたとき、頭が煮詰まったとき、片山式メソッドで身体が生まれ変わり、疲れやストレスから解放されるのです!
-
-