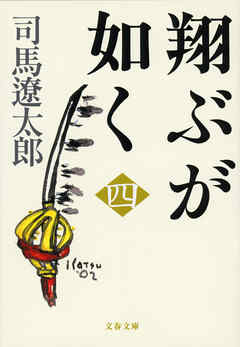あらすじ
西郷に続いて官を辞した、もとの司法卿・江藤新平が、明治七年、突如佐賀で叛旗をひるがえした。この乱に素早く対処した大久保は、首謀者の江藤を梟首に処すという苛酷な措置で決着をつける。これは、政府に背をむけて隠然たる勢力を養い、独立国の様相を呈し始めている薩摩への、警告、あるいは挑戦であったのだろうか。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
佐賀の乱での江藤新平の暴発、晒し首から、征台に至る国内外の駆け引きまでの4巻。作者が文中に記しているとおり、西郷隆盛という存在が本人の意思とは無関係に周りに与えた影響を描いており、知識欲を満たすものと考えれば良書であるが、読み物といえば話が進まず退屈すると思われ、後者をやや重視する自分としては読後はなんだかホッとする気持ちになる。
Posted by ブクログ
グダグダの台湾出兵。第二次大戦の軍部の暴走はこの時に倣っているようだ。歴史に学ばないとこうなるのだ。
台湾出兵は秀吉の頃とあまり変わらない海外遠征で、つくづく征韓論は時期尚早だったとわかる。
学校の教科書だと、台湾出兵なんて2行程度で、薩摩士族への申し訳程度の出兵だとしか書いてない。もちろん興味もわかない。こんなにもグダグダだったなんて、この本を読まなければ一生知ることはなかっただろう。サンクス。
______
p28 佐賀の乱は大久保の餌食になった
江藤新平の起こした佐賀の乱は、政府の根幹を揺るがすどころか、却って政府の結束を強めることになった。この乱のために、臨時的に明治政府の権力が集中し、来る西南戦争へ予行演習になった。
p35 独裁官だな
佐賀の乱において、大久保は独裁のごとくになった。軍事統帥権のほか、行政権・司法権の一部を委任された。その結果、佐賀の乱の戦犯の裁判は大久保のために厳粛に行われ、明治新政府の独裁性が強まった。
p38 大久保の戦略
大久保は佐賀の乱に対して驚くほど迅速な対応をした。その結果、佐賀の乱を挑発して導くことができた。実質、大久保の掌の上で踊らされた形になった。
p53 庭役
西郷は斉彬のもとで、藩士としてではなく、庭役として雇われた。それは、当時の封建制のしきたりで藩士は格式ばった形でしか面と向かって話すことができなかったからである。庭役だからこそ自由に話し合いができ、斉彬の教育を受けられるというわけである。
当時の庭役は庭の手入れだけでなく、密偵などの役も仰せつかったある種特別な存在だった。
p68 実話
佐賀の乱で配送した江藤新平が西郷のもとに救援を求めにやってきた。しかし、西郷はこれを拒否する。
この密談は西郷が宿泊していた宿で行われたが、そこのおかみさんが長命で、当時の西郷の声を聴いている。
「わたしのいうようになさらぬと、当てが違いますよ。」と西郷が怒号をあげたらしい。西郷はあくまで反乱を起こす気はなかった。なのに勝手に佐賀では反乱を起こし、それが破れたら私を担ぎに来るなんて、当てが違うということである。
p102 私学校を作ったわけ
佐賀で沸き立っている壮士たちの怒気を抑えるために、収容所のようなものか?
p125 集成館
薩摩の最新式工場。当時すでに薩摩は小規模な産業国家を形成するだけの力があった。ガラス工場や反射炉による製鉄工場もあった。が、斉彬の死後、これらは廃止された。藩財政の圧迫ということだったが、斉彬ほどの人物がいなければ運営できない代物だった。
p130 兵農不分離
西郷は商業志向を嫌い、あくまで農業志向の国家観を持っていた。「武士は百姓になっても商人にはなるな」
武士の源流は平安時代の農民である。商業は武士の精神を失わせるという。
p138 ビスマルクの器
西郷曰く「西洋人と言っても何も違ったことはあるわけではありません。聞くところによると、ドイツのビスマルクなる者は豪傑で、何の技能もない男であると申します。」西郷は君子器ならずという。君子は道具ではない。道具のような技能はない方が良い。君子は偉大なる徳だけがあればいい。そういう意味でビスマルクを喩えている。
p140 小人は…
小人ほど才芸があって便利なものである。これは大いに用いなければいけない。しかし、長官に据えて重職を授ければ、必ず邦家を覆す。これは薩摩藩の斉彬の後継者争いで感じたことだろう。
p142 斉彬の家督騒動
斉彬は42歳まで藩主でなかったのは、父である斉興が家督を譲らなかったからである。それは斉興のブレーンであった調所笑左衛門の手回しによる。笑左衛門は茶坊主あがりで、藩財政の立て直しのため家老に大抜擢された男である。彼は大阪の借金凍結やサトウキビ貿易と中国密貿易など無理をして財政を立て直した有名な男である。
西郷に言わせれば、調所に家老という役職の褒美を与えたのがいけなかったという。褒美は物の褒美を与えればよかったのだ。
調所は財政力という技能を持っていたため、政治にそれを用いて失敗したという。調所は斉彬の開明的政策を財政ひっ迫になるとして強く反対した。それゆえ斉彬はなかなか藩主に慣れなかった。しかし、時勢を見れば斉彬が正しかったはずである。技能があると小手先に囚われ、対局が見れなくなる。そのため、政治には不向きなのである。
これが西郷の理論。斉彬が藩主になれなかった理由。
p156 沖永良部
おきのえらぶ島は西郷が二回目の島流しにあった場所。1862年に西郷は久光に「浪士を煽って武士社会の転覆を腹に含んでいる」という嫌疑で島流しにされた。
p171 空っぽの西郷、春日潜奄を訪ねる
大隈重信は西郷や板垣を馬鹿と思っていた。実際西郷は維新後の世の中で路頭に迷っていただろう。
西郷の新時代観は「堯舜のようなもの…」ていどのふわふわしたものだった。だから、勉強のために部下の村田新八を遣わした。
p173 横井小楠
この時代の新国家観の持ち主は、横井小楠、勝海舟、福沢諭吉、この程度だった。横井小楠は有名でないから調べたい。
p178 薩長の対比
長州は江戸時代から藩主を端に機関として扱い、君臨すれども統治せずを実施していた。
対して薩摩は、藩主がすべてを仕切っていた。「島津に暗君なし」といわれる奇跡の国家だった。
ゆえに西郷には天皇の存在がうまくつかめなかったようだ。
p191 西郷VS大久保 対立の原点
廃藩置県がその原点。大久保は廃藩置県を推奨したもののそれを決して表には出さないようにした。薩摩藩士でそれを唱えれば、殺されることは必至であった。木戸孝允ら長州人たちにこれを推進させ、島津久光の怒りはほとんど西郷にかぶってもらった。
このやり方から、二人の決別は始まった。
p222 台湾出兵
「薩摩の沸き立つ壮士たちが喜ぶであろう」という子供だましのために起こした対外戦争。
沖縄の漁船2隻が難破して台湾南部に漂着した。漂着者たちは高砂族に襲撃され66人中54人が虐殺され。残りの12人は中国の福州に逃れた。これに対する報復戦争である。
p224 尚氏は源氏、対馬氏は平氏
日本の武家らしく、源流を名乗っていた。
p229 鄭成功
鄭成功は日本の平戸藩の藩士の娘を母とする混血児で、明が清(ヌルハチら遊牧民族)に滅ぼされそうになった時に抵抗を続けた武将である。その対清の拠点としたのが台湾である。この当時の台湾はオランダの東インド会社に占拠されていた。鄭成功はゼーランディア城を奪取し、拠点を得た。
鄭氏の台湾は21年間続いたが、清の追討軍により破れ、清の植民地になった。
p233 グラント大統領はだめだった
アメリカ南北戦争の北軍の将軍グラントはアメリカ大統領になった。しかし、グラントは史上もっとも無能と言われるほどだった。
p243 客家
中国でも不思議な存在である客家。唐末の黄巣の乱の際に華北から南下した連中を祖先に持ち、そのうち全土に散った。常に反政府的気分を持っており、太平天国の乱なんかも彼らの仕業で、洪秀全なども客家だった。
p252 革命のエネルギー
革命のエネルギーは正義とか人権擁護とかキレイごとは並べていても、結局は殺意と反逆心のエネルギーでしかない。このエネルギーは革命が収束したら消えるというものではない。歴史ではしばしばそのエネルギーは外国に向けられる。
中国がいい例である。中国で国号が変わる革命が起きたのち、その強大な軍隊を解散させるわけにもいかず、北方遊牧民族などの外征や防衛などに用いられ、中央から遠ざけられることも多かった。ナポレオンの対外戦争もフランス革命のエネルギー発散だったということもできよう。
p254 台湾へぶつける
台湾出兵の理由。①出兵の兵を募れば、薩摩藩士の気も紛れるだろう ②台湾に出兵することで政府が外国に対して弱腰ではないということを示すため
結局、台湾はとばっちりを受けただけなのである。
p257 清ならまぁいっか
征韓論はダメで、征台論が良い理由。挑戦を打倒した後に出てくるのはロシアである。しかし台湾ならその後に出てくるのは清である。この時期、日本はロシア帝国に勝てる軍事力はない。しかし、清ならまだ何とかなるという希望があった。
p261 毛利元就から始まる長州の気質
元就は輔佐政治という家憲を残した。元就亡き後、輝元を支えるため、二人の叔父である吉川元春と小早川隆景が「毛利の両川」として本家を護るために補佐官に徹した。
この精神が長州藩の法人的国家観を生んだ。
p285 西郷の台湾出兵の反応
木戸孝允は「政府は征韓論を押した江藤新平を処した。それなのに、台湾出兵をするという。これは理に合わない。本来ならば、江藤をして台湾出兵の総大将にすべきである。」といって矛盾をついた。
しかし西郷は、「それはよろしい」と従道に言った。
p317 当時の明治政府軍の程度
台湾出兵と言っても猪狩りのようなものだった。日本の持つ銃器は火縄銃で、高砂族の者たちは日本軍が追えば山林に逃げ、それを追い落とす程度のものだった。
日本軍はマラリアでひどい被害を出し、それを含めれば日本人の方が被害が大きかった。
p319 台湾出兵の異常さ
台湾出兵は日本史上の珍事件と言える。兵三千以上の軍隊を国民に開示することなく、夜盗のようにこっそりと出兵するという近代国家にあるまじき一大事であった。そして、それは現代に至っても日本人に馴染むことのない不思議な事件である。
この台征に際する大久保の所業は詐欺まがいと言っていい。太政大臣の三条実美と岩倉具視の勅命だけで出兵の許可を得て、早々に西郷従道に出発させて既成事実として作戦を進行させた。ゴリ押しにもほどがある。
このやり方はのちの軍部のクセになる。このせいで昭和の大失敗が起きた。その起源とも言えそうである。
_______
この巻の中心は台湾出兵であるが、ここにも昭和の軍人の思考を絡めてくるところがさすが司馬遼太郎だ。
しかし、まだ4巻。半分いかない。スゴイ読みごたえを実感している。
Posted by ブクログ
p.219
「文明が極まれば神なきに至る。開化がきわまれば、戦争なきに至る。必ずそういう日が来るであろう。」
そういう日への道のりは、まだまだ遠そうですね…。
Posted by ブクログ
西郷隆盛がいかに、明治維新の中で英雄だったかという点が事細やかに書かれている印象。この巻では、主に薩摩藩の志士の不満を解消するために、台湾に出兵する過程の話がかかれていた。幕末~明治維新の歴史の流れが頭に入っていないとちょっと文章中の事柄を理解するのは辛いかな。逆にその部分に興味を持ったりもする。こうして文章を読むといろんなことが知りたくなってくる。(そんな時間はあまり無いけれど)。感想はこんなところです。
Posted by ブクログ
後半、にわかに征台論がクローズアップされ、西郷従道により強引に実行される。西郷どんは鹿児島に篭もり、政府に無言の脅威をあたえつづける。大久保利通とは征韓論で袂を分かち下野したのだった。この西郷兄弟について、長州人は全く理解できないとあきれ果てるばかりなのだ。薩摩人にも理由はある。江戸幕府が無血開場したことにより、江戸を焦土にすると振り上げたこぶしの下げ場所が無くなってしまった。この有り余るエネルギーのはけ口にされる隣国はたまらない。
行動があまりにもストレートすぎはしないだろうか。思考では理解できても感情が抑えきれないという場面は確かにある。確かにあるのだが、それでいいのかと苦笑せざるおえない。彼らの不満が政府に降りかかることを恐れ、大久保もこの案を了承するのだった。