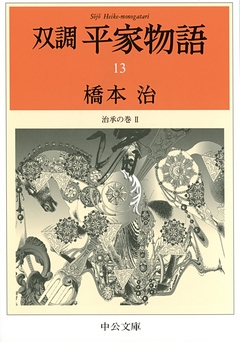あらすじ
中宮徳子の懐妊──待望の男子(後の安徳天皇)誕生に、平氏一門は湧き返る。だが、摂関家の北政所である白河殿盛子、さらに、病を得ていた重盛が世を去ると、後白河院と摂関家は再び反平氏を明確にした。これに対し、重盛という歯止めを失った清盛は、関白基房を逐い、院を鳥羽の離宮へ幽閉する。父院を救うため、高倉帝は中宮の皇子に御位を譲り、この暴挙に対して、異母兄である以仁王は源頼政に平氏追討を要請する。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
重盛が死んじゃった。宮仕えをしている今の身としては重盛に一番共感。変人と呼ばれていても、いなくなってその人の働きがわかるって目指したいところですね☆
(大河ドラマは見ていないけど)あー、ちょうど同じくらいのところですね。重盛の病状悪化から後白河法皇の幽閉までほぼ1巻でした。エピソードもだいぶ違うみたい。
たしかにこれを映像にしたら、室内の会話・駆け引きがすべてなので、演技のうまい人たちでないとね。派手ではないけどおもしろいと思うけどね(でも人気ないんでしょ?みんな録画してみたいんだろう)。
Posted by ブクログ
途中で源氏物語とか読んでいたらしばらく双調を放置状態になってしまいましたが、ようやく続きを読み始めました。重盛死にました(涙)しかしこれだけ複雑な源平ドラマを一年間大河で取り上げようと思ったNHKさんはたいしたもんです。最後の方、正に今(2012年11月)大河でやってるところでした。以仁王の令旨が出てどんどん盛り上がって行くのがたまらないです。佐殿はまだ活躍していませんが…続きが楽しみです。
Posted by ブクログ
清盛の先を頼もしく思った。清盛のためにならどんなことでもやってやろうと思い、そのようにして来た邦綱である。今更の他人行儀はおかしい。二十数年前も昔の話を持ち出して、無理なこじつけをする必要はない。清盛は、そのような人物ではなかったはずだ。しかし、清盛は変わった。
盛衰は、起こっては消え、消えてはまた起こる。御世の表の波頭。咲く花は、やがて散るためにこそ咲き誇る。盛りの華に降りかかる雨の滴を、風雅と見るか、無惨と見るか。治承二年の春、その一門の栄華の時は、盛りの蕾を開かせんとして息づいていた。
なにがどう絡み合っているのかは分からない。
しかし、重盛は面を動かさない。かつて勇んで敵に立ち向かって行った平氏の若武者は、今では何事にも動ぜぬ人物と成り変わっていた。それが慶事であれ、凶事であれ。
教盛は、理解出来なかった。まさか、そこに「絶望の表情」があるとは思えなかった。重盛自身さえ、そのように理解してはいなかった。まさか、一門の繁栄を推し進める中宮の懐妊に対して、自身が絶望の色を示しているなどとは。重盛はただ、一門を巡る人の思惑の中に、処理しきれぬ煩わしさだけを感じていた。「中宮の懐妊はよし。しかし、その先は――」と思うと、重盛にはどのような展望もなかった。「よし」と思うその先には、ただ『無』しかない。教盛は、「中宮ご懐妊」の慶事に不安を見、重盛は無を見ていた。なぜなのかは分からない。重盛には「その先」が見えなかった。
俊寛の一族は消え、これに仕える者達も四散して、今や、有王と俊寛の間を隔てるものは、ただ青く広がって続く海だけとなっていた。
人臣位を極めて身を退けた清盛は、すべてが自分の思うままになりうるものと、信じ込んでいた。しかし、重盛は違う。俗世を離れた父から一切を委ねられた重盛は、自身の一族が、藤の一族によって占められた大海に浮かぶ小島のようなものであることを、よく知っていた。
盛子によって、清盛は「摂関家」という格式を手に入れた。盛子があればこそ、高倉帝の立太子も御即位も可能になったーー摂関家の北政所たる盛子は、高倉帝の御生母滋子よりも先、遥かに高い身分を得ていたのであるから。…平氏一門の栄華の礎は、まだ年若い盛子によって築かれたのだ。
盛子は、栄華の女だった。そして、父に孝なるこの娘は、ひそやかな女だった。…11歳で「摂関家の後室」となった盛子には、愛する夫も、愛する子もなかった。ただ義務として、「母」の役割を勤めさせられたーー「在る」という以外になにもする必要のない「母」の役を。盛子にとって、その後の人生は、ただ「在る」ばかりで、実質のないものだった。盛子は、ただ待った。なにを待つとも思わず、ただ待った。待つ以外、盛子にはなすべきことがなかった。なにを待つとも分からずに待ち続けた盛子は、ついにその年になって、「待つべきこと」のなんたるかを知った。その年、盛子は二十四歳になっていた。夫の基実は、二十四歳で死んだのだ。盛子は、基実のそばへ行きたいと思った。盛子が愛し、盛子が「愛された」と思いうるただ一人の男ーー…基実の享年と同じ二十四歳の春を迎えた盛子は、ひそかに食を断った。その年まで生きて、盛子は、十分に自身の役割を果たしたと思ったのだ。…夫基実の命日より、一月ほど早い死だった。「故摂政殿よりも一日も若く」と、盛子は、それもまた望んでいたのである。
一門は、鳴りをひそめていた。八月になると…知盛が、嫡宗の兄重盛の喪に服して、官を辞した。殊勝な心懸けではあるが、これを見習う弟達はなかった。見習おうにも、辞するほどの官を持つ者は、まだない。
邦綱の支えるべき相手は、既に重盛であって、清盛ではない。その重盛が病み衰えて、幾許もない――邦綱は確かな頭脳で時代を読んだ。…彼が支え実現させた「伊勢平氏の栄え」は、既に先のない、散り始めた万朶の桜も同然のものだった。
「花は、咲き誇ってある。しかし、幹は折れた」
邦綱は、負けるわけにはいかなかった――清盛を、負けさせるわけにはいかなかった。
瞬く内に清盛は、人の世の階梯を登りつめた。登りつめた「先」はない。清盛は、栄華を達成した。達成することは許された――清盛一代に限って。…栄華の高みに駆け上った清盛は、栄華の高みに追いやられ、退けられたのである。…清盛の去った一門は、既に「栄華の一族」ではなかった。
清盛の生涯で最も輝かしくあったのは、栄華の頂で俗世を去るその日だった。…栄光と歓喜の中で、清盛は世を捨てた――それが当然のありようと、誰もが思っていた。であるならば、清盛に全き栄達を与えれば、清盛を朝廷から逐うことも出来る――
院が、清盛を「疎ましい者」と思し召されていたのなら――。「疎ましい者を逐い払わん」と思し召された院が、清盛に「身に過ぎるほどの栄達」をお与えになられたのなら――。清盛は、身に過ぎる栄を畏んで受け、歓んで朝廷を去った。…「逐われる」という自覚なくして、清盛は逐われた――その後の一門の不協和は、すべてこのことに由来する。
「夜討同然の、”官打ち”などという兵法が、この世にはあるのか?」
…しかし、それはあるのだ。昇進の矢を次々と放たれ、見事清盛は、人の世から退いた。昇進の矢に「射られた」と知らぬまま。
清盛と邦綱が「栄華への道」と信じて歩んだものは、「奈落への道」でもあった。
父の忠通はない。兄の基実もない。舅の公教もない。兄の遺領を奪って平然としている伊勢平氏の一族との縁もない。「殿下」を称される摂関家の長が、後盾のなさを嘆く時代が来ていた。
院にとっては、御自身のご勢威を瑕つけ奉る者のすべてが「敵」であられるのである。院のご勢威に拠り奉って力を得ようとする者のすべてが、疎まれ悪まれ、退けられてしかるべき者輩なのである。
十九年前、平治の乱の翌年、…一門は、院のおそばに一人の女を奉った――ひそかに、院のお胤を得るため。院は、奉られた女を寵され、同時に、一人の男をも寵された。女は、後の建春門院――平滋子。男は、世を去った平重盛。重盛へ賜わされた越前一国の知行権は、その一門へ賜わされた、院の初めてのご恩寵であった。院は、その初めへ戻られて、平氏一門へのお心を根こそぎお奪いになられようと思し召されたのである。
越前の国にあった重盛の知行権は、効力を失っていたのである。除目の席にいた公卿は、誰一人として、この決定に異を唱えなかった。唱えようがなかった。…席に姿のあった平氏一門の公卿は、清盛の義弟である公家平氏の時忠と、清盛とは微妙に距離を置いた異母弟頼盛。そして、喜界ヶ島から戻った婿の丹波少将成経を迎えて精魂の尽き果てた、人のいい門脇の宰相教盛の三人ばかりだった。…小松の内府重盛を欠いた平氏の一門は、いつの間にか、朝廷での勢威を失っていたのである。
(院を幽閉した時)
入道の声は落ち着いて、静かだった。季貞はなにも疑わず、これを静憲に告げた。しかし季貞は、清盛が涙を堪えていたことを知らなかった。清盛は、静憲の来訪に感謝していた。「したくてしたことではない」と思う清盛は、自縄自縛の嘆きの中にいたのである。
清和源氏の棟梁としてあった老将為義は、嫡男義朝と戦って、敗れた。我が子を思う為義に、義朝を憎む心はなかった。父に弓引いた義朝にも、その心はなかった。仕える主に「戦え」と命じられれば、戦わねばならない。それが、王朝の世に走狗としてあった、清和源氏の宿命である。
(頼政の、平治の乱の回想)
頼政の一党が固める橋を、既に自身が制したもののように心得て、義平は突進してきた。義平が何を叫んだか、頼政は覚えていない。しかし、軍神が乗り移ったかのような義平の形相を、頼政は忘れることが出来ない。それは、「戦う」ことがいかなることであるかを熟知し、それを己が性とした者の顔だった。そんな顔を、頼政は初めて見た。頼政にとって、「戦う」ということは、攻めることではなかった。まず、守る―― …第一になされるべきことは、戦いを回避すること―― …このことを第一とする都の武者達にとって、戦いの場から逃げ出すことは、卑怯でも怯懦でもなかった。
「ようぞや兵庫頭!清和源氏の一統ながら、なにゆえ伊勢平氏の麾下につく!臆したか!怯んだか!二心を恥じる心はないか!兵庫頭の二心、我が一族の恥として、末代までも語り継がん!」
…何をもって「二心」などと言い放てるのか。…しかし、頼政は、その言葉が忘れられなかった。聞き捨てにしようとして、その言葉が胸に食い込んだ。
「日本一の不覚仁、信頼卿に一味同心したることこそ、我が一族の恥となる!恥を唱えて恥を知られい!」
――そう義朝に怒鳴ったことを誤りとは思わない。しかし、「恥」の一語が、頼政の胸に深く突き刺さった。なにを「恥」とし「二心」とするのか――その根本が、頼政と義朝とでは、大きく違うのだ。
頼政が人となって行く時期は、清和源氏と伊勢平氏の勢力が交替して行く時期であり、院の御所がお主上の朝廷の上に立たれて、御世のありようが不思議に揺らぎ始める時期でもあった。
戦うことは、死ぬこと。王城の地の平安を守って、「戦いを回避する」という術は、もうない。守るべき王城の平安は、既に、頼政の知るものではなくなっていた。「生きるべき時は生きた」と、頼政は再び思った。「俺は、長く生き過ぎた」と。戦うということは、己の尊厳を賭け、己の尊厳を守り通すことであるのだと、その生涯の最後の時に至って、頼政は悟った。
(以仁王に挙兵を求められる)
「我が身は今、なにを陳べているのか」
――それを思うと、腹立たしかった。偽りを陳べ、「偽りにはあらず」と断じて、危うい状況に突き進む。覚悟のこととはいえ、自身の生の最後に訪れるのがこの空しい弁舌かと思うと、頼政は、腹立たしく、悲しかった。
++++++++++++++++++++++
邦綱はめっちゃ頭いいですね。どんだけ清盛のこと好きなんだ。こういう右腕がいるトップは、強くなります。参謀。
盛子ちゃんはとにかく幸薄です。摂関家に嫁がされた運命。「生きて居るだけ」の大切な存在だから出家もできず、再婚もできず。
そいてやっぱり黒い後白河。こいつは…嫌いだ…!清盛が疎ましくて、さっさと身を退いてほしくて、高い位をあげたってことですね。清盛の片思いかわいそうです。
しかも、この時期って「平家の栄華」とか言われる時期だと思うんですが、意外とそうでない。除目の席にいる平氏公卿は3人ぽっち。越前知行権の奪還を阻止することもできませんでした。全然力ないじゃんね…。
最後のほうは、頼政にスポット。平治の乱で義朝義平親子に「恥」と罵られたことが胸に残っているんです。恥とは何か。そしてとうとう、平氏と戦うことを決意します。勝てる見込みの無いことを知って。以仁王に勝てるか強く問い詰められたときには、仕方なく「勝つ見込みはある」と言い、己の不甲斐無さに悲しくなります。為義とかぶる部分が多いですね。上の人間の言葉で動かされるつらさ。
Posted by ブクログ
新興の一族の周りには、目に見えぬ標が結い渡されている。己が分際を忘れ、その境から一歩でも踏み出しさえすれば、ひそやかな嘲りがたちまちに襲いかかる。栄華の大海に乗り入れた一族には、この攻撃に対処する術がなかった。新興の一族を呑み込もうとして盛りあがる大波をかわし、進むべき航路を指し示す者はなかった。この哀れな一族を導きうるお立場にあられたのは、御世の頂の更にその上の高みにましまされる、法皇ただお一方ばかりだった。法皇がどのようなお力をお持ちであられるのかを、哀れな浄海入道は、わきまえずにいた。であればこそ入道は、摂関家に抗することも恐れず、法皇に対し奉っても抗そうとした。その父の哀れな振舞が、ごうがんなる人の世を残された嫡宗の子重盛に、心労を積もらせ、回復の余地のない疲弊へ誘っていった。