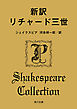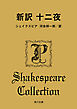河合祥一郎のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
ミルドレッドに失恋した主人公フィリップは、新しい恋も始まり立ち直りつつあったが、そんな彼の前に恋人に捨てられたと言ってミルドレッドが現れる。彼女を見てフィリップの感情はまた揺さぶらるのだが、果たして二人の間はどうなるのか、といったところから下巻は始まる。
そして、フィリップが親しく付き合い、その言動に目を見張ったり、才能に憧れたりした友人たちが、ある者は病に倒れ、また別のある者は夢をあきらめたりして、かつての親密な関係が失われていく一方、医局員として研修をしていた病院で知り合ったことがきっかけで、アセルニー一家との交際が始まり、フィリップは人生の新たな一面に目覚めていく。
そんな中、フ -
Posted by ブクログ
沼むっつり、読んでる間ずっと石田彰さんのボイスで音声が再生されてた…
沼むっつり今巻で1番好きかな笑
逆に今作のヒロインのジルちゃん、ちょっと苦手かも
虐められる設定だけど、なんか地味にわがままな感じが、そこが原因じゃない?って思ってしまって笑
悪い子ではないんだけどなぁと思ったり
3巻が個人的にドンピシャだったからか、面白かったけど4巻はなんかワクワク感が物足りない気分だったなぁ
ネガティブな言い合いしてる事多いのも関係していそう
ユースタス、ジル、沼むっつりの3人で旅をしている間、喧嘩していること多くて……
旅している間の出来事はとても楽しいんだけどなぁ、なんかワクワク感よりどんより気分 -
Posted by ブクログ
マクベスと並ぶか、たぶんそれ以上に暴虐を繰り返す悪の権化みたいなリチャード三世の物語。王であるお兄さんの死をきっかけに、いかにして自分が王に登り詰めるか、という話。
シェイクスピアの作品でおれが初めて読んだ歴史劇。オセローとかマクベスみたいなその場で始まってその場で完結する物語とは違って、この前の時代にも話があり(「歴史劇としては『ヘンリー六世』三部作の続編」(p.227)らしい。)それを背景として話が進んでいくというのが難しかった。薔薇戦争、とかよく分からない上に、何といっても公爵とか騎士とか登場人物が多くて誰が誰なのかよく分からないし、しかもエドワードとか何人かいたり、場面に応じてリチ -
-
-
-
-
-
Posted by ブクログ
今年は古典を読もうと思っていて、古典と言えばこの人でしょ…、ということで手に取ったシェイクスピア。
COTEN RADIOでジャンヌダルクの百年戦争を聴いたあと、そう言えば完全に穴だな、と思っていた薔薇戦争にも興味があったので、一石二鳥とばかりに選んだのがこちら、リチャード3世です。
翻訳の戯曲なんか読んだこともないし、ましてや自覚のある通り知識の穴であるところの中世イギリスが舞台のこの作品。何度か最初に戻って登場人物を整理したり、読みながらスマホで人物相関を調べたり…いやぁ、苦労した。
内容を私なりに要約すると、
容姿に恵まれないが血筋には恵まれていたリチャードが、清々しいまでの悪巧み -
-
-
Posted by ブクログ
原題 Much ado about nothing
(往年のTV番組「恋のから騒ぎ」は Much ado about love が副題だった。)
アラゴン大公のおかしな動機と、付人の聞き間違いと、大公への嫉妬に基づくドン・ジョンの悪意と、ベネディックとベアトリスの意地の張り合いと、いろんなものが相互に影響しあって、訳の分からないドタバタ劇となるも、最後は大団円、という喜劇のお手本の様な内容。
注釈を読む限り、細かいところでは、いろいろと辻褄が合っていないところが多いようで、大御所作家が年月を掛けて書き上げた名作というよりは、当時の売れっ子脚本家(宮藤官九郎のような)が短い時間で書き殴った即