無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
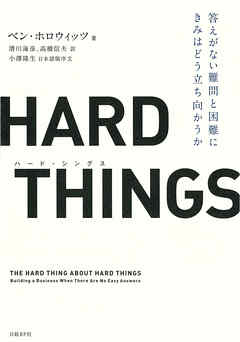
シリコンバレーのスター経営者に慕われる最強投資家からのシンプルなアドバイス
起業家時代のホロウィッツには、これでもかというほどの困難(ハード・シングス)が次々と襲った。
上場してもパーティさえ開けないような状況でITバブルが弾け、株価は35セントまで急落。
最大顧客の倒産、売上9割を占める顧客が解約を言い出す、3度にわたって社員レイオフに踏み切らざるを得ない状況に――。
しかし最終的には、困難を切り抜け続けて、1700億円超で会社を売却するという大成功を収めた。
壮絶すぎる実体験を通して、ベン・ホロウィッツが得た教訓とは何なのか?
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。