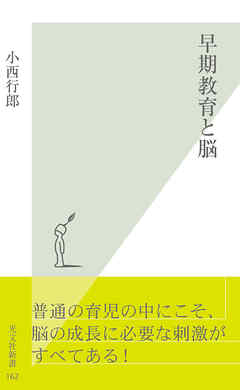あらすじ
「三歳児神話」と相まって過熱する早期教育。しかし、乳幼児の脳について科学的に解明された部分は少ない。行きすぎた早期教育に警鐘を鳴らし、「普通の育児」の重要性を説く。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
乳幼児期の習い事や教材は、あくまでも遊び感覚で親子のコミュニケーションの一つとして、体験を共有するくらいでよいのではないでしょうか。臨界期(△歳までなら××が身につく)にこだわらずに「あなたの得意分野をゆっくり探そう。これをやってもできなかったけど、他のものがあるよ。」とおおらかな気持ちで子どもの成長を見守る方がいいように思うのです。
Posted by ブクログ
子どもをもち、習い事をさせているにもかかわらず、
早期教育には懐疑的な私。
考え方も分かれるが、親自身がしっかりと考えなければならない、と改めて思う。
この手の本は何冊か読んだが、冷静に分析されていて面白かった。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
脳の発達に必要な刺激は、普通の育児の中にこそある!
本当に早期教育は効果があるのか?
赤ちゃん研究の第一人者が様々な視点から検証する。
さらに育児不安やテレビ視聴問題、虐待問題などにも触れ、親と子どもにとって最も幸せな育児とは何かを考える。
[ 目次 ]
第1章 早期教育と脳(過熱する早期教育 「臨界期」と脳の発達 ほか)
第2章 乳幼児と英語教育(乳幼児から英会話ブーム 日本語を追放した家族 ほか)
第3章 育児不安と孤独な親(心身ともに不安定な産後 育児不安とは ほか)
第4章 地域社会と子ども集団(限界にきた「母親ががんばる育児」 地域の保育力を奪った学校 ほか)
第5章 障害児教育から子育てを考える(障害児のノーマライゼーション 福子、福虫、宝子 ほか)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
以前この方の著書を読んだ際、赤ちゃんへの愛情のもと論拠に基づいた説明がなされていて好感を持ったので、この本も手に取ってみたのだけど、今回は「早期教育はよくない」という主義主張が先行しすぎているように感じられて、少し残念…
そもそも「早期教育」とはどのようなことを指すのか定義づけがなされないまま論が展開されるため、いまいち具体性がなく、説得力に欠けるように思えた。
あと、これは確認しなかった私の責任なのだけど、発行年が古いので、注意が必要。
Posted by ブクログ
誠実な著者であり本だと思う。
しかしまあ、この著者にして、ちょいと無理のある仮説や持論を唱えちゃってるところはあるんだよね。
育児とか教育とか、純粋に科学的に何か証明することが不可能な分野って、なかなか難しいなと感じた次第。
Posted by ブクログ
早期教育への疑問が出発点。◆人間の脳は確認しながら成長する。◆だから一方通行の教育システムは片手落ち。◆教育の深化より横展開。◆臨界期はやっても出来ないボーダーライン。◆◆まだ、人間の脳についてよく分かっていないと言う現実。
Posted by ブクログ
少子化の現在、子供に対してかけられるお金が増え、早期教育をふくむ教育熱が高まっていると思う。
著者は障害児教育を専門とする立場から、一般的な早期教育に対しての提言・批判をしている。
頭ごなしに早期教育に反対するのではなく、現在あるデータを挙げつつ、自身の研究や体験を含めて、精緻に考察していく。
「こうすれば必ずうまくいく!」「これはやってはいけない!」といった一本調子な本が多い中で、その慎重な姿勢はとても好感が持てる。三歳児神話や幼児からの英語教育にも、「ちょっとまってくださいよ」と言いながら検証が始まるような流れ。
おおまかに流れている思想は、あまり極端なことをして偏りのあることをするよりも、こどもと親があり、家族があり、地域があるという状態を改善していく必要がありそうだ、ということ。
そんなにすぐに変わらないよ、と言われるかも知れませんが、なにごともできることからコツコツと。じっくりと書かれる著者の考え方から学べることがたくさんあります。