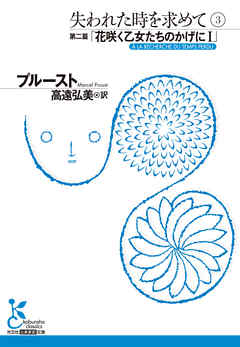あらすじ
若者になった「私」はジルベルトへの恋心をつのらせ、彼女の態度に一喜一憂する……。19世紀末パリを舞台に、スワン家に出入りする「私」の心理とスワン家の人びとを緻密に描きつつ、藝術と社会に対する批評を鋭く展開した第二篇第一部「スワン夫人のまわりで」を収録。〈全14巻〉
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
451P
失われた時を求めて 3~第二篇「花咲く乙女たちのかげにI」~ (光文社古典新訳文庫)
by プルースト、高遠 弘美
多くのブルジョワが保守的な人たちとだけつきあおうとして重ねる努力、将来意義ある結果を生み出すはずもなく、結局は当たりさわりのない意見だけを口にすることにしかならない努力など、自分に何かをもたらすものではないがゆえに避けて通っていいことを知っているからである。
しかし私として言っておかなくてはならないことがある。それは、ノルポワ氏の会話は、ある種の職業や階級や時代──といっても、その職業や階級に属している人たちからすれば、完全に過去のものとなったわけではない時代かもしれないのだが──に特有の、いまでは時代遅れに感じられる言葉遣いの完璧な目録のようなものだったから、この耳でせっかく聞いた彼の言葉をどうしてただその通りに覚えておかなかったのか時々悔やまれてならないということだ。
というのも、私たちは何か貴重な発見をしたいと思って自然や藝術から何らかの印象を受け取ろうとするのだが、そのとき、そうした印象の代わりに、美の正確な価値について私たちの判断を誤らせるかもしれない低次元の印象を、魂がそのまま受け取りかねないことにいささか不安を感じないではいられないからで
アンドロマック』[ラシーヌ作]『マリアンヌの気まぐれ』[ミュッセ作]『フェードル』のラ・ベルマは、私の想像力がつよく望んでいた特別な存在と言ってよかった。ラ・ベルマが以下のように朗誦するのを聞けば、私は、ゴンドラに乗って、フラリ教会のティツィアーノやサン・ジョルジョ・デッリ・スキアヴォーニ同信会のカルパッチョの作品( 25) の足もとに運ばれてゆく日に感じるような陶酔感を味わうことだろう。
いずれにしても、見ていて不思議なのは、あれだけ社交界、それも超一流の人びととつきあいのあるスヴァンが、せいぜい雑多なとしか言えないような人たちの集団に格別の好意を示していることです。昔の彼を知っている私としては、あれほど育ちがよくて、えり抜きの人びとの間でもてはやされた男が、郵政大臣の官房長が訪ねてきてくれたといっては喜色満面で礼を述べたり、自分の妻が官房長夫人に会いに行ってもよろしいでしょうかと訊いたりしているさまを目の当たりにしてびっくりするやらおかしいやらでしたよ。
そう、モリエールの言葉( 98) をご存じでしょう? あれだということくらい多少は意識しているとは思うのですけれど、それでも、そのことを『 都と世界にあまねく( 99)』知らしめるべしとは誰も求めているわけではない。ただ自分の妻はすばらしいとまで言うと、それは言い過ぎだろうと思うのですね。ところで、それは他人が思うほど間違ってはいないのです。
しかし、結局のところ、ただそれだけです。たいしたものではありません。瘦せこけた彼の作品にはきちんとした骨格というものがあったためしがない。筋立てがない、あるいはあってもごくわずかしかなく、とくに広がりというものに欠けています。ベルゴットの本は根柢となる部分に欠陥がある、というより、そんな根柢がまったくないのです。生活そのものがますます複雑になって読書する時間もほとんどなく、ヨーロッパの地図が根本的な改変を余儀なくされ、さらに大きな改変もおそらく目前に迫り、深刻な問題が新たにこれだけ起こっている今のような時代に生きている私たちは、作家に対して要求してもいいのではないでしょうか。純粋なる形式が如何に優れているかについて暇に飽かせて無意味な議論を繰り返し、内と外から二重に押し寄せる野蛮な連中の波にいまにも侵略されるかもしれない状態を私たちに忘れさせるような、そんな頭でっかちの教養人ではない別の存在であってほしいと。こんな言い方が、そうした方々が『藝術のための藝術』と呼ぶ神聖不可侵の流派に対する 冒瀆 であることは承知しています。
実際、私たち一人一人にとって、自らの言葉や行動を他人がどこまで把握しているものなのかを正確に知るのは難しい。私たちは自分の重要性を過大評価してはいけないと思っているし、他人の全生涯にわたるさまざまな記憶が必然的に占める領域は途方もなく大きくなってゆくものなので、私たちは自らの会話や振る舞いのどうでもいい部分は、おしゃべりをしている相手の意識にほとんど入ってゆくこともなければ、ましてやその記憶に残ることはないと想像する。
父がもはや私を「外交官」にする可能性を考えなくなったことに母はあまり満足してはいないように見えた。母は変調を 来しやすい私の神経が規則正しい生活によって律せられるのではないかということに何より心を砕いていたから、私が外交官の道を諦めることより、私が文学に専念しようとしている姿を見るほうが残念だったのだと思う。「でも、好きなようにさせておやり」と父は大きな声で言った、「自分がすることに楽しみを見出すのが一番だ。それにこの子はもう子どもじゃない。自分が何が好きかわかっている。この先変わることはまずないと思うね。人生で何が自分を幸福にしてくれるのか理解できるんだよ」。
人生における「時間」もそれと似たようなものだ。過ぎゆく時間を感じさせるために小説家は、時計の針の動きを極端に速めて、読者に二分間で十年、二十年、三十年といった時を超えさせる。あるページの冒頭で、希望に満ちた恋人だった青年が姿を消したと思ったら、次のページの最後では八十歳の老人になっていて、養老院の中庭で苦しそうに日課の散歩をし、昔のことを忘れているので何か訊かれてもろくに答えられないというように。
レディは、その甥ほどには 優雅 な人びとと親交がなかったし、スワンのほうも、その叔母のことが好きではなかったので、おそらく自分が遺産相続人になるはずであるのにさほど頻繁に叔母と会うこともなかった。だが、スワンの親戚のうちで、スワンが社交界で占めている地位について認識していたのはこの叔母だけだった。
十二時半になると私は意を決して家のなかへ入る。この家は 降誕祭 の大きな靴と同じで、私に超自然的な喜びをもたらしてくれるに違いないと思われた(スワン夫人とジルベルトは「ノエル」という名称を知らなくて、英語のクリスマスという言い方にしていたので、クリスマスのプディング( 226) とか、クリスマスに頂いたものだとか、クリスマスには留守にするなどとしか言わず、私は苦痛で発狂しそうになったものである。一方、家にいるとき「ノエル」などと口にするのは名誉に関わると考えてもはやクリスマスとしか言わなくなったのだが、父はそんな私をひどく莫迦にしていた)。
たぶん、地平線上のものをすべて一様にとらえてしまうのにも似た錯覚のなかで、以下のように想像するのはたやすいことだろう、すなわち、今まで絵画や音楽の世界で起こったあらゆる革命は、それでもある種の規則は尊重してきたものだが、今私たちの眼前にあるものは、印象主義も不協和音の探求も支那式音階( 234) の単独使用もキュビズムも未来派もみなすべて、旧来のものとは激しく異なっていると。
というのも、今まであったものについて考えるとき、人は長い同化作用の結果、それが私たちにとって確かに多様ではあるけれど結局は同質のもの──そこではユーゴーとモリエールが隣り合わせになっている──に変わってしまったことを考慮しようとしないからである。もし私たちが未来と未来がもたらす変化のことを考慮しないとすれば、十代の青春期に、三十代の分別盛りの年頃になったときの運勢を占ってもらった星占いがどれほど不愉快な食い違いを呈することになるか考えるだけでいい。
真の多様性というものは、現実の思いがけない要素のこうした充実にある。あるいは、すでにぎっしり密生しているかに見えた春の垣根から出るとは誰も予想しなかったのに青い花を咲かせて伸びてゆく枝のうちにある。反面、多様性をただ形だけ模倣したものは(文体の他のすべての美点についても同じことが言えるだろうが)空っぽで画一的である。それは多様性とは正反対のものであり、模倣しているだけなのに、あたかもそこに多様性があるという錯覚を抱いたり多様性を想起したりしているのは、巨匠のうちに存在する多様性を理解できなかった者だけである。
厳しい審美眼、あるいは自分で「穏やかだ」と言えないことは絶対に書かないという意志のようなもの──それゆえに彼は長年、不毛で気取り屋の、些細なことに気を配りすぎる藝術家だと見なされてきたのだが、じつはそれこそが彼の力の秘密だった。というのも、習慣は人間の性格と同時に作家の文体をも作るからである。自らの思考を表現するのに、ある程度魅力的に見えるところまで達したというだけで何度か満足してしまった作家は、かくして才能の限界を永久に定めてしまう。それは、しばしば快楽や怠惰や苦しむことへの不安に負けてきた者が、もはや修正がきかなくなった性格のうえに、自らの悪徳の姿や美徳の限界を浮かび上がらせるのと似ている。
パリに恋人がいて、それはぞっこん惚れていたわけですが、彼は何とか工面して週に二回パリに来ていたんです。二時間、女に会うためだけにね。きわめて知的で、その頃はほんとうに魅力的な女性でした。いまでは遺産で裕福に暮らしている貴婦人( 310) ですよ。
つまり、何年も前から(長い孤独と読書の時間を通じてまさに彼は私自身の最良の部分となっていたから)ベルゴットに対しては誠実さと率直さ、それに信頼をもって向かう習慣ができていたせいだろう、初めて言葉を交わす相手の時ほど臆することがなかったのである。しかし、同じ理由から私は、自分がベルゴットに与えた印象がどうなのかひどく心配になっていた。
知的な人間には愚かな人間とは別の健康法が必要だということも大いに疑問だった。私は必要とあらばいつでも愚かな人間の健康法を採用するつもりでいた。「いい医者が必要な人間はと言えば、私たちの友人、スワンでしょうな」とベルゴットが言う。スワンは病気なんですかと問うと、「うん、そう。あれは娼婦と結婚した男だから、妻を自分の家に招きたくない女たちとかつて妻と寝た男たちから一日に五十回も投げかけられる侮辱をじっと堪え忍んでいますからね( 320)。すぐわかりますよ。
あら、あなた、菊の活け方、ご存じないのね」と帰り際にヴェルデュラン夫人は、玄関まで送ろうとして立ち上がったスワン夫人に言った、「これは日本の花なのだから、日本人がするように活けないとだめです
仕事をするのもこの部屋です(もっともその仕事というのが絵を描くことなのか、あるいは、何かをしたい、役立たずでいたくないと考える女性たちの間で 流行り始めた趣味として、本を書くことを指すのかについて彼女は明言を避けたのだが)」と言っていた部屋のなかで、彼女はマイセン磁器( 382) に囲まれていた(この種の新しい磁器が好きだったので、英語式に発音しながら、どんなものについてもその言葉を使った。たとえば、「まあ、きれい。サクス磁器の花みたいね」というように)。
不幸になると人は道徳的になる。ジルベルトが現在私に対して感じている嫌悪感は、その日私がしたことのせいで、人生から与えられた罰であるかに思われた。道を横切るときに車に注意を払っているからとか、危険なことは避けているからといった理由で、人は罰を免れることができると信じ込む。
モーリス・バレス(一八六二~一九二三年)。作家。右翼の論客として活躍した。一九〇六年、アカデミー会員。
第一次大戦が終わり、フランス文壇の中心も世代交代の時期に入っていた。アナトール・フランスやモーリス・バレスらに代わって、コクトー、ジイド、クローデル、ヴァレリーなどが新しいフランス文学の中心的存在になり始めていた。プルーストも彼らと同じく、ガリマール書店の出版部NRFに拠る一人として、戦後の読者の支持を集めてゆく。
プルーストは最も偉大な巨匠達の一人としてわれわれの知性にも、われわれの感性にもせまる。」アメリカ人達はこの作家の詩的な、そして深い、ユーモアの味を理解する。
プルーストを読まない、あるいは読んでも心惹かれない知識階級のフランス人は確かにいて、彼らはしばしば、バルザックは「人間の社会」( un monde) を描いたのに、プルーストが描いたのは「社交界」( le monde) にすぎなかったなどと異口同音に言う(果ては私に対して、時代も国も文化も違う日本人のあなたがどうして、そんな第三共和政下の社交界を描いた作家であるプルーストをそれほど愛して、かつその翻訳までしようと思うのかと訊いてくることすらある)。そういう「反プルースト派」の人びとに対してモーロワはプルーストの魅力を説いた。これは、「長い」と思いながらも、プルーストを読んでみようと思われた方々(「プルースト派」あるいはこれから「プルースト派」になりうる方々)にも有益だと思われるので、以下、章を変えて、モーロワの主張するところをできる限りモーロワの言葉を用いながら略述してみる。
いかなる小説家でもすべてを描きつくすことはできない。バルザックにしても、その時代の社会全体を描いたわけではない。どんな天才であっても、書物のなかにひとつの社会の全要素を入れることは不可能である。すぐれた小説家は、たとえ小さくても自らが描き出す社会の深層まで見つめることで、個を超えた普遍に達する(たとえば『源氏物語』が今もなお読まれているのはそれゆえである)。プルーストは貴族社会とそこに生きる貴族や使用人だけでなく、それを囲むさまざまな 階梯 に位置する貴族を含めた人々や、ブルジョワの姿を、彼らの欠点を含めて冷徹に、あるいはユーモアや皮肉を込めてまざまざと描き出す。一方、教会の彫像に写し取られた今も変わらぬ「永遠のフランス人」の姿を、女中のフランソワーズや、食料品屋の青年やアルベルチーヌその他の人物のうちに見いだす。貴族と同様に民衆にも見られる歴史的性格をプルーストは見逃さないからである。
プルーストは、人間性に関する一般的な法則を発見しようと努める。ここからはモーロワの言葉を二つ挟みながら続けよう。 すべての人間は、その根本において同一性をそなえているから、任意の一人を厳密に分析すれば、すべての人間にわたっての最も貴重な文献を得ることになる。《一つの》頭蓋骨、《一つの》皮剝ぎ屍体が、解剖学の指針となるように、《一つの》魂、《一つの》心があれば、愛情や虚栄心、人間の偉大や悲惨を知るに十分である。スワンの味う嫉妬や、ヴェルデュラン家の人々のスノビスムや、母に対する苦痛にみちた 話者 の愛情は、あらゆる空のもとで、同一ではないまでも、似通った形のもとに見出されるものであることを、経験が教えたのだ。
プルーストは、抽象的で 勿体ぶった、中身のないあまたの思想家よりも社会的な作家である。と言ってそれは、プルーストが労働運動や群衆を描こうとしたという意味ではない。プルーストは大袈裟な文学理論や社会参加を叫ぶのではなく、沈黙のうちに確乎たる藝術を完成させようとした。第一、描かれた事件の大小で作品の偉大さが決まるのでは
プルーストはフランスのモラリストの系譜に立って、人間について一般的な真理を追究し、それを作品中に描こうとした。一方、多くの読者が抱える苦悩をともに分け持ち、彼らを藝術による 慰藉 へと導く、というのもプルーストの特徴の一つだと言っていい。
チャプスキはプラハに生まれ、少年時代をベラルーシで過ごし、サンクトペテルブルクで法律を、クラクフで美術を学んだ。一九三九年九月一日、ナチス・ドイツ軍とスロバキア軍がポーランドに侵攻。十七日にはソビエト軍も侵攻。予備役の将校だったチャプスキはクラクフで軍に合流。部隊とともに東に向かった。同月二十七日、ソビエト軍の捕虜となり、コジェルスク(コゼリスク)、オスタシュコフ(オスタシコフ)と並ぶ、スターリン時代の強制収容所の一つスタロビエルスクに送られた。一九四〇年の四月から五月にかけて、同胞が列車で運ばれ、カティンの森事件で知られるように、次々に虐殺されるなか、五月十二日にはチャプスキも列車に乗せられ、最終的にグリャゾヴェツの収容所へ移送される。そこにはソビエトに有用と思われた四百人あまりのポーランド将校と兵士が集められていた(彼ら自身はその理由を知らされてはいなかった)。四千人がいたスタロビエルスクから来たのはわずか七十九名。残りの圧倒的多数の人びとは消息を絶った。
パリに来たチャプスキがプルーストの本をたまたま入手したのは一九二四年のことだった。ラディゲの遺作『ドルジェル伯の舞踏会』が評判を呼び、コクトーやサンドラールやポール・モランが文名を上げ、「電報のように簡潔で乾いた文体」がもてはやされていた。だが、その一方で、レオン・ブロワの忘れられた小説『貧しい女』(一八九七) やシャルル・ペギーの作品集が刊行されている時期でもあった。ペギーやラディゲに魅せられたチャプスキも、最初に手にしたプルースト(「たぶん『ゲルマントのほう』だったか?」と彼は書く)の、何百ページも社交界の話が続く展開と文章に辟易したらしい。だが、プルーストはどこかで彼を捉えて放さなかった。引用する。
プルーストの本は、極度に洗練されていて、あふれんばかりに豊饒で、当時の私たちには時代の精神と思われたものとは対極の位置にあるものだった。そんな精神ははかなく過ぎ去るものだったのに、若い頃の愚かしさのなかでは、いつまでも続くものに違いないと思い込んでいたのである。限りない「脱線」、およそかけ離れたもの同士を意想外に結びつけるさまざまな連想、序列化されない錯綜した主題を扱う不思議な手さばき──そうしたものを伴う、無限とも思われるプルーストの文章。私はプルーストの文体の価値、その極度の正確さと豊かさをかろうじて察することができたくらいだった。
プルーストは朝になって、ベッドで死んでいるのが見つかった。ナイトテーブルの上には、薬の瓶が倒れていて、洩れた薬液が小さな紙片一面に黒く染みこんでいた。その紙片には、神経質そうな彼の筆跡で、夜のうちに記された文字があった。それは、『失われた時を求めて』のさして重要ではない人物、フォルシュヴィルの名前だった。
マルグリット・ジャンヌ・ジャピー(一八六九~一九五四年) は、ドイツとスイス国境にほど近い、フランス東部の町ボークールに生まれた。地方のブルジョワの出身で、ジュリアン・ソレルのような気性を備えた女だった。父はホテルの主人として働いたが、引退後はもっぱら三番目に生まれたマルグリットの養育に力を注いだ。父の意向でマルグリットは、四歳の頃からヴァイオリンを習い、花の摘み方を覚え、礼儀正しい所作を身につけ、階段を優雅に下りたり馬に巧みに乗ったりする術を我がものとしたのである。やがて、ピアノや絵画、数学、宇宙論、美術史、歌曲を習い、モーツァルトやラモーやグルックなどの作品を演奏するようになった。十四歳の頃は芝居に夢中になっていた。
だが、当時、離婚した女性はもっとも軽蔑される対象だった。公式の離婚を避けるとすれば、パリでの評判を高める必要がある。そう考えた彼女は父のつてをたどって、さまざまな藝術家にサロンを開くことを知らせた。十五区の彼女の館はたちまち多くの客が訪れる人気のサロンになった。グノーやマスネ、ゾラやロティも常連客だった。 そのサロンには道徳的に評判のよくない者たちも来れば、いわゆる社交界の人々も通い始める。スノッブにも外国人にも事欠かなかった。金持ちのコレクターや有力な政治家も集まってくる(このあたり、オデットのサロンを思わせる)。
マルグリットに自由をもたらし、社交界への扉を開く助けとなったのである。マルグリットは著名な人物と関係を持つだけでなく、女同士の同性愛をも拒まなかった。 要するに、育ちが決して悪いわけではなく、最初から娼婦だったわけでもない。結婚生活の失敗と二十歳も年上の夫の歪んだ嗜好、サロンを通じての交遊、もともとの性向、性的な自由さ。それでいて、信心深いピューリタン。生来の美貌。優雅な身のこなし。教養。英国への憧れ。押し出しの立派さ。そういうマルグリットを愛する貴族や有力政治家たち。その上で生まれたのが「ココット」マルグリット・ステネーユ夫人だった。
この本には彼女たちの同性愛の例が数多く引かれているだけでなく、リアーヌ・ド・プジーをはじめ、オデットの人物造型に──のみならず、じつはアルベルチーヌの人物造型にも──重要な役割を果たした「ココット」たちの姿が溢れている。「サロン」とともに「ココット」は『失われた時を求めて』の世界を根柢から支えていると言えるだろう。
春、ブーローニュの森への散歩の帰途、最初の喘息の発作に襲われる。喘息は生涯の 宿痾 となる。 一八八二年
Posted by ブクログ
スワンは、オデットに恋心を抱き頻繁に逢うようになる。
やがて、スワンは、オデットの言動に疑いを持ち、強い嫉妬に駆られる。
だが、幸福な時は短い。
スワンの中にもう一つの疑念が生まれ、追うほどに彼の前にオデットの新たな相貌が現れる。
この辺りのプルーストのメスさばきは、氷のようだ。/
スワンの孤独な横顔に惹かれる。
彼は、田舎娘を貴婦人と見間違うドン・キホーテのようだ。
彼がオデットの中に見ていたボッティチェリのチッポラは、跡形もなく打ち砕かれる。
やがて、スワンにも結晶解体の時が訪れる。/
彼はまた、自らの意見を昂然と口にするがゆえに、ヴェルデュラン夫人の不興を買い、サロンから追われる。
だが、住み慣れた社交界も、彼にとっては、もはや異邦の地なのだ。/
『しかし、スワンのことが気にくわないと発言したヴェルデュラン氏はそのとき、自分の意見を表明しただけではなく、妻の考えも見抜いていたのだ。
—中略—
だが、もっと深い理由がほかにあった。スワンのうちには他人が入っていけない固有の空間があることに夫妻はすぐに気がついたのである、そこではスワンは相変わらず、口に出さないまでも、内心では、たとえばサガン大公夫人は粗野ではないし、コタールのジョークは面白くないと言い続けていることに。
そして、
—中略—
そんなスワンに教義を押しつけたり、全面的に改宗させたりするのが不可能だということにー
—中略ー
されど異端抛棄の誓いをスワンから引き出すことはできない。それを夫妻は理解していた。』(第二部「スワンの恋」)
空気を読まないスワンには、孤立への道しか残されていない。/
『スワンの想念は初めて、かのヴァントゥイユー同じように大いに苦しんだに違いない、卓越した能力に恵まれた未知の同志へと向かってゆき、深甚なる同情と愛情が澎湃として湧き上がるのを感じた。彼はどんな人生を送ったのだろう。どんな苦悩の底からこの神のごとき力、限りない創造力を汲み取ったのだろうか。
ー中略—
小楽節が模倣し、再創造しようとしたのは、内面の悲しみが放つ魅力だった。』/
『吉田秀和がいみじくも指摘しているように、(略)プルーストを読むとは、畢竟、私たち自身の経験や過去を読み直すことでもある。』(「読書ガイド」)/
確かに、プルーストを読んでいると、自分の人生のいろいろな場面が走馬灯のように甦ってくる。
怖ろしいほどに。
この物語が何回もの再読に耐える所以だろう。
Posted by ブクログ
語り手の初恋、スワンの娘・ジルベルトとの恋についてあれこれと語り手が考えを巡らせるが、ジルベルト自身の印象は薄く、スワン一家、特に第一部のタイトル「スワン夫人のまわりで」が最初から最後まで通底している印象の第3巻。
ジルベルトは語り手の中のこうあってほしいと思う理想のジルベルトが描かれ、スワン夫人(オデット)については、服装、趣味、会話が事細かに描かれている。
話の筋としては単純なのに、その情景も空気も心情も丸ごと作品に閉じ込められている。
流麗な文体の中に語り手の若さが出ていて(憧れの作家に会いその風貌に落胆したり、相続した壺を売って「毎日ジルベルトに花を贈ることができる」とウキウキする)クスっとしたり、うろたえたりしました。恋は怖い。
スワン夫人と女性たちのサロンでの会話もぞわぞわします。上流階級に生きるというのは心が休まらなさそう。
注釈が丁寧で助かっています。これがなかったら私には手の届かない作品です(;´∀`)
巻末の「読書ガイド」のユゼフ・チャプスキ『精神の荒廃に抗するプルースト』やココット(高級娼婦)の詳細な説明、馴化園(ジャルダン・ダクリマタシヨン)の説明も興味深いものでした。
Posted by ブクログ
恋についてプルーストの触れ方は私にとって異質で興味深い。ジルベルト、アルベルチーヌの2人への思いが違ってみえる。恋をなくしても、悲愴ではない。プルーストの紡ぎだす連綿とした、章立てしてない文は読みにくくもあるが、「私」の語りは慣れてくると心地いい。 私も若いころ「乙女たち」とひとときを会話したり、散歩して過ごしたかった。 また絵画、訳者撮影の建築物、ネットへの参照など、とても親切で多くの注は読書をより深く楽しめた。
Posted by ブクログ
第二篇の上巻は光文社で。
今まで自分にぴったりの訳を追い求めてちくま文庫、岩波文庫、集英社文庫…と色々読んできたけれどやっぱり古典新訳に関してはさすが安心と信頼の光文社、読みやすかった。
個人的な読みやすさ指標としては、
集英社>光文社>岩波>>>>ちくまという感じかな。(左に行くほど読みやすい)
そんなことは置いといて、相変わらず主人公のジルベルト愛が溢れてたなあ。
と同時にちょいちょい挟まれる芸術への批評も読んでいて面白かった。
Posted by ブクログ
スワンも語り手である私もすごく一方的な自分勝手な片思いしてる印象を受けたけど、スワンのがまだなんとなく読んでて楽しかった。どっちもなよなよしてたけど。それに語り手はジルベルトのことを好きなはずなのにオデットに魅了されすぎじゃない。
Posted by ブクログ
読み始めは、「かなり読みやすくなってきたかも♪」と思ったのに結局すごい時間かかってしまった…社交界のなんちゃらとか当時の文化とかこの本を楽しむポイントはたくさんあるんだろうけど、スワンの恋からの流れで、やっぱり恋って病気なんだなぁ(´・_・`)と思う一冊でした…
Posted by ブクログ
「源氏物語」と「失われた時を求めて」は誰の翻訳でもこれくらい面白い本は無いから、次々に目を晒すのだが、いずれも翻訳によってその文学世界が完全に異なってしまうので、面白いというより恐ろしい。だから本当の読書とは、やはり原書・原文に直接当たるべきなのだろう。
実際に今までにそうしてみたこともあったが、源氏よりもよく頭に入ったのはプルーストで、この重層的複合文てんこもりの牛のよだれのような羊腸の小径を辞書を頼りにおぼつかなく分け入る辛気臭い作業は、しかし微分積分的読解の快楽というものを与えてくれたのである。
かというて文庫本で10数冊に及ぶこの膨大な著作をそのまま読み切る自信はまるでないから、次々に出版される翻訳につい手が伸びるのであるが、最初に触れたように翻訳のテーストはこんにゃく同様十人十色であるから、いろいろ読み比べて自分の感覚に合致したものと仲良く付き合えばよろしいかな、と思うのである。
光文社から出ている高遠訳は今回がはじめてであるが、語学的に正確であろうと努めるあまり、井上訳で成功していたプルーストの独特の文学的香気がまったく感じられない点に不満を覚えた。こういう文章なら別にプルーストでなく、ジッドでもアナトール・フランスでもおんなじことではなかろうか。
全体のトーンとしては岩波の吉川訳に似た現代文の平明さを基調にしているのだが、訳者としては完全にその調子になり切っては困ると考えたのか、ときおり「されど」といういささか古めかしい接続詞を節目節目で投入する。
「されど」は私も嫌いではない言葉であるが、3ページに1回の割合でそれが繰り返されては迷惑千万。さながら平成のビジネスレターに明治の候文が闖入してくるような違和感が付きまとい、今度はいつ出てくるのだろうと比叡山のお化けの出現に身構えてしまうようになり、とても主人公とオデットの娘ジルベルトの恋物語の透徹した心理分析に身を委ねるどころの騒ぎではなかった。
今宵また我が家のチャイムを鳴らすのはおそらく風の又三郎ならむ 蝶人