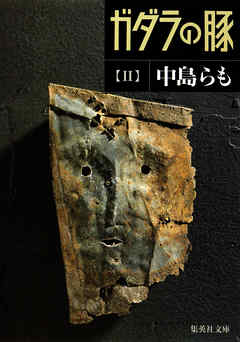あらすじ
研究助手、スプーン曲げの青年、大生部の長男、そしてテレビ局のスタッフ6名を引き連れて、大生部はアフリカへと旅立つ。目指すはスワヒリ語で「13」を表わすケニアとウガンダの国境近くの町クミナタトゥ。そこで大魔術師バキリの面会に成功するが、最大のタブーを犯してしまう。バキリの呪具(キジーツ)である少女を攫ったのだ。バキリの手下たちに追われ、危機一髪、ケニアを後にするのだ。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
前巻の『ガダラの豚1』を「今まで読まなかったのが本当にもったいない」と紹介したが、結論から言うと、2巻もやっぱり面白かった!
1巻で登場した多彩なキャラクターたちは、今度は呪術の本場・アフリカの大地で大暴れすることになる。
映画やドラマの続編は、スケールアップに失敗すると一気に失速しがちだが、本作はその点がとにかく上手い!
舞台は小さな日本から、スケールの大きなアフリカへ。
一介のマジシャン崩れが行っていた奇術まがいを暴く物語だった前作から、今作では「村全体が呪術師」という、より奇怪で大掛かりな話へと転じていく。
人員も、今回はTV撮影という設定上、撮影スタッフや流暢な関西弁を話す現地案内人、さらにはアフリカで活躍する本物の呪術師まで加わり、舞台・登場人物・物語のすべてがオーバーに拡張されている。
しかし、ただ派手になるだけでは終わらない。
現地の呪術は、亡くなった神父の残した日誌を読み解くことで少しずつ明らかにされ、登場人物たちもこれまでの経験を経て精神的に成長している。
派手さと地に足のついた描写の緩急が、非常にいいバランスで構成されていると感じた。
また、1巻で回収されなかった伏線――教授の娘の死についても、ここで見事に回収される。
一方で、教授の家系の謎や道満君の「目覚め」など、新たな伏線も張られており、3巻でそれらがどのように回収されるのか、続きを読まずにはいられない。
Posted by ブクログ
すっごく面白かった。
前半の面白さは笑える面白さで終わりがけは、手に汗握る面白さだった。
前半の雰囲気で、ちょっとおちゃらけた感じで行くのかと思ったら真面目な感じになっていって引き込まれた。
納と清川のコンビがとても良かった。
大生部もIの方ではアル中の大して権威のなさそうな教授だなと思っていたけど、Ⅱになってから、頼りになるアル中教授になっていたのも読んでいて心地良かった。
Posted by ブクログ
テレビの企画で大生部一行はケニアへ。
そこは呪術が生活の一部として存在する社会。
住民全員が呪術師の村クミナタトゥで一行は強力な呪術師バキリと遭遇する。
現代ホラー小説を知るための100冊の一つだがホラーのジャンルに収まらないジャンルミックス的なエンタメ大作。しかしかつて村に住んでいたスコット神父の日記の箇所は紛うことなくホラー。登場人物たちのやり取りの多くがユーモラスなだけにこのシーンの怖さが際立つ。
タイトルの意味を忘れていたがこの巻に記述がある。聖書からの引用。イエスが人に取り憑いた悪霊に出ていけと命じ、悪霊たちは人から豚へと移動したあと崖から海へ飛び込んで死んだ。その出来事があった土地がガダラだった。
Posted by ブクログ
ここから、話がどんどん展開していき
出てくるキャラクターも一人一人個性的で面白く、
ハラハラドキドキな要素もあり、
どんどん引き込まれて一気読みしました。
中島らもさんの独特の言い回しも本当にセンスが良くて笑ってしまうほどでした。
わたしはⅡが一番好きかもです。
Posted by ブクログ
一気に読み進めてしまったから、星5
ケニア部族の、自分の周りの生活には全くなかった考え方を覗かせてもらった気分。
神父とオニャピロの会話が印象的だった。
Posted by ブクログ
深夜特急にも似た雰囲気が好き。
そんなこと感じるの私だけかな?
人は自分の魂を千切って投げる。それが言葉だ。
矢を放つ。が「話す」の語源。
水面は物理的に存在しない。そこには水と空気があるだけだ。だが水面は認識できて、そこに確かに存在する。
Posted by ブクログ
呪術パワー、超能力ブーム、新興宗教など盛り沢山の背景✨
ある大学教授と周囲の人々がTV局をも巻き込んでいく呪術の戦いとラストまで面白かった。アフリカと日本を舞台に魅力的な登場人物✨3巻目は阿鼻叫喚でした
Posted by ブクログ
(2025-09-29 3h)
移動の合間に読んだ。
第1巻と同様に、単行本でまとまっていたとは思えないくらい文庫本で綺麗に章が分かれているような印象で、次巻が気になる引きが良い。
第2巻は呪術師の村「クミナタトゥ」の話。
民族学の未知の楽しさ、軽やかに惹き込まれる。
やっぱり感染症や食中毒やらが怖くて、アフリカに行くことはハードル高く感じるものの、ウガリは食べてみたい。
一気におどろおどろしさがやってきて、不穏になってきた。
Posted by ブクログ
おもしろい!!
すぐ3にとりかかる!!
前半なんて舞台がアフリカに移って
アフリカとは何ぞやという話をしてるだけなのに
わくわくが止まらないのとテンポの良さ
テレビを見ているように映像が脳内にポンポン入ってくる。
最後はバタバタと物語が動くし死人も出てくる。
新興宗教から呪術最後はどうなる!!
Posted by ブクログ
めっちゃ面白い。
文章が巧みなのとテンポの良さで飽きずにどんどん読める。
中島らもさんの他の作品も読もうと思う。
自分には派手な展開や設定の方が今のところは合ってる気がする。
Posted by ブクログ
まさかの急展開で、3巻をすぐに読みたくなりました。
シオリが生きていたとは想像していなかった。
マジックにトリックがあるように、呪術にも裏が
あるということ。
呪われたという人間の思い込みで衰弱することも
なきにしもあらず。
病は気からという言葉もあるので気の持ちようって
大事というか、生命すら左右してしまうのかと。
Posted by ブクログ
舞台はアフリカへ。今回のテーマは呪術。
現地の風土、民俗学、文化人類学を丹念に読みこんだ跡が滲み出ているディテールの深さ。主人公たちと旅を同行している気分になる。
終盤の呪術師からの逃走劇。手に汗握るね。
続きが気になって爆速読み。次巻へノンタイムでご-。
Posted by ブクログ
2巻で大生部一行がアフリカに着いてから、物語が一気に加速してページをめくる手が止まらなかった。
呪術といえば胡散臭いはずなのに、科学的に立証されることだと物語の中でもエピソードが登場するのに、逆にそれによって呪術の気味の悪さが引き立って妙な納得感が出てくるという変な感じ。
アフリカに魅了されてしまう。
Posted by ブクログ
大生部教授とその仲間たち?
アフリカでのTV撮影の旅
楽しい旅かと思いきやあれやこれや‥‥
大騒ぎ!もう読まずにはいられない!
ドタバタだけではなく、なんだか考えさせられる
こともたくさん。呪術を学びたくもなる
「言葉こそすべてじゃないか!ひとは自分の魂をちぎって投げるんだ!それが言葉だ!」
byオニャピデ
Posted by ブクログ
ちょっと人離れし過ぎた知識を持ちすぎじゃないかラモさん...序盤“いいねいいね”なんて思ってたけどあれこれちょっと資料ってどこから...”って恐怖が勝っちゃったよ。なんせ専門用語のため検索エンジンを使用しても画像を示さないからね(全てラモ氏の本で埋まっている)こりゃ徹夜確定で3冊一気するってレビューに書いてたわけだ。本書と顔が離れないや
Posted by ブクログ
ケニアの情景がよく浮かび、ケニアって不思議な国と思った。。いや、違う。日本もどこの国も、案外同じで、占いや呪いってとても身近にあることに改めて気がついたら。卑弥呼もそうだった!3へ続く。
Posted by ブクログ
ガダラの豚 中島らも
壮絶。スリリング。
読み始めたとき、こんなに夢中になると思ってなかった。2022年は宗教絡みの事件やウクライナ戦争もあったり、昔の本だけど通じるものが多々あった。
呪術はアニメがあったりするほどポップになっているが、そんな甘いものじゃない。呪術だけでは微力だが、物理や心理学など他分野と掛け合わせることで強力で何千年と宗教や呪術がこれ程長い期間生きている証拠なのかもしれない。
文章は簡潔、短文で読むスピードを落とさない。
1巻は難しく、展開もゆっくりだったが2巻3巻と重加速的にどんどん読み進めたくなるような構成。
巧い。会話のやり取りが多いのも特徴か。
一方、ふるみが亡くなるシーンは描写が細かく恐ろしさをリアルに伝えてくる。
1巻大生部の日常。2巻アフリカにロケ。3巻東京帰国後。
Posted by ブクログ
アフリカ呪術編。予測不能のすごい展開。傑作。
旅行ドキュメンタリーを見ているような生々しさ、科学と非科学、宗教、大多数の日本人の持つアフリカ観の表層さ、沢山の要素が混ざりあってスピーディーに駆け抜ける。さらに後半であっと驚く展開に。
ガダラの地で悪霊にとり憑かれた男が言った。なぜここに来て私どもを苦しめるのか。私どもを追い出すなら、あの豚の群れの中につかわしてください。豚の群れは崖から海に飛び込み死んでしまった。
Posted by ブクログ
いや~~~~面白い!!!
アフリカには絶対に行きたくないという気持ちを強く抱いた。
呪術が当たり前のように存在していることがおもしろい。
呪いの根本的なものは「妬み」だと知って納得。
怒涛の展開でまたもや一気読み。面白い!
Posted by ブクログ
シリーズ第2作となる本作では、舞台を日本からアフリカ・ケニアへと移し、呪術師取材の旅が描かれます。前半はほとんど観光紀行のような趣で、食事、治安、宗教観、経済格差など、日本とはまったく異なる価値観や生活様式が、コミカルな登場人物たちを通して丁寧に語られていきます。その情報量は圧倒的で、読みながら自然と「異文化を理解していく楽しさ」に引き込まれていきました。
後半から物語は本格的に動き出し、呪術師への取材が核心に迫っていきます。特に印象的なのは、呪術が人々の生活に深く根付いている点です。
日本的な感覚では呪術は禍々しいものに映りますが、ケニアでは攻撃だけでなく、魔除けや治療、さらには犯罪への抑止・処罰といった役割も担っています。抽象的でありながら、医療と警察の両面を内包した社会システムとして機能しており、直接的な報復ではなく、呪術師を介した調停によって流血を避ける構造が成立している。この社会の在り方は非常に興味深かったです。
もしかしたら平安時代もこんな感じだったのかもしれませんね。
そんな呪術社会の歪みを最大限に利用するのが、本作の悪役・バキリです。
面白かったエピソードとして、バキリに対して挑戦してきた青年の飼牛が無残に死ぬと呪いを掛け、その通りとなりました。実際は呪殺ではなく、嵐の夜にヘリで牛を吊り上げて殺すという身も蓋も無いオチでしたが、しかし、採算度外視で突飛な凶行であるがゆえに、誰もその可能性に思い至らず、「得体の知れない力による奇跡」が肯定されてしまう。
文明の利器と信仰によって育まれた“魂の力”を同時に操り、理屈では太刀打ちできない恐怖を生み出すバキリの存在は、純粋に恐ろしく、そして非常に面白い悪役でした。
バキリから見れば、人間は湖へ追い立てられる豚の群れであり、落ちるその瞬間まで自分の運命に気づかない存在なのでしょう。一方で、他者から見た彼は、湖に沈んだ悪霊の群れのような存在——人を死へ引きずり込む悪意の総体として映る。
タイトルである「ガダラの豚」は聖書由来の言葉ですが、本作では、水面は「この世とあの世の境」という形で例えられています。その為、「"死"と生者」、すなわち「バキリとそれ以外の人間たち」の関係を示しているように感じられました。
奇跡とエンターテインメントを、圧倒的な知識量で融合させた本作は、舞台をケニアに移すことで、宗教と人生が密接に結びついた新たな宗教観を描き切っています。ケニアという土地に呼応するかのように活力を増していく清川や道満、そしてアルコール中毒に苦しむ大宇部といった人物描写も見応えがあり、シリーズとしての厚みを確実に増しています。
第1作を楽しめた読者なら、スケールもテーマも大きく広がった本作を、間違いなく堪能できる一冊だと思います。
Posted by ブクログ
「呪術」に関するお話
2巻は、アフリカに来てから帰るまで
まさか、こんな展開になるとは思わなかった
あと、テンポが早い
重厚な小説だったら、アフリカを脱出するまでにさらに1冊くらいの分量が追加できそう
詳細な感想は3巻の方でまとめて
Posted by ブクログ
本書って、かなり面白かったという記憶があったんだが、再読してみるとそうでもなかった。
最初読んだ時は20代だったからなあ。
あれから、「やりすぎ都市伝説」とか、YouTubeとか、オカルトの情報は、溢れんばかりだったからなあ。
なんか盛り上がりに欠けるんだよなぁ。
第2巻はアフリカの冒険行なはずだけど、単なる日常風景という印象。
面白かったけどね。
可もなく不可もなくというところか。
Posted by ブクログ
アフリカに呪術師を探しに行く第2巻。ストーリー展開はエンタメ路線だが細かなところまで相当な調査に基づいての記述だろうと驚く。アフリカのことを何も知らない私ではあるけど。宗教やら呪術やら全く気にしないと思っていても、深くアフリカの現地民族の中に進んでいくに連れて恐ろしく感じるところが多くなってきて、楽しく読み進めるのが辛くもなってきた。
主人公一家がどのようにアフリカの厳しい旅を乗り切るのか、テレビ局のロケなんてどうせまともに成功はしないだろうか、呪術の怪しげなところを現代科学で否定してしまうのか、いろいろと先のストーリー展開を予想しながらも先が楽しみ、不安もありありで気が抜けない。さて急展開の第2巻からどうなる大生部一家とその一行。
Posted by ブクログ
かなり現地の調査をされたのか、細かな描写がとてもリアルです。予想外な展開にちょっとハラハラドキドキしながら一気に読み進めました。3巻ではどんな展開になるのか楽しみです。
Posted by ブクログ
大生部教授一家とTVマンらは、アフリカの地へ
前半は、アフリカの当時の現状なのか、風土や呪術を含めた文化をコミカルに読ませてくれる
あまりにも旅行記部分がリアルなので らもさんアフリカ行ったのかなと思うほど
実際は、かなりの文献からの創作のようですけど
大呪術師パキリの「バナナのキジーツ」が、この作品のミステリー、1巻で亡くなったと思われていた教授の娘となり なるほど!
日本からの一行は彼女を救い、逃げる逃げる
アフリカ旅行に「道祖神」というツアー会社を使うのだけど こちらは実在する会社らしい
HPによると 今もアフリカのオーダーメイドタイプの旅にも対応しているみたい
らもさんの洒落れなのかな