無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
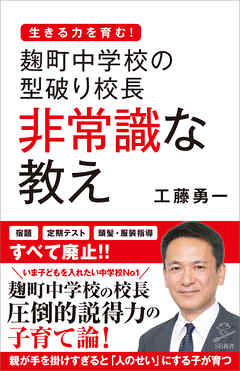
東京のど真ん中に「学校の常識」をひっくり返している公立中学校長がいます。
宿題は必要ない。固定担任制も廃止。中間・期末テストも廃止。
多くの全国の中学校で行われていることを問い直し、本当に次世代を担う子どもたちにとって必要な学校の形を追求しているのが、
千代田区立麹町中学校の工藤勇一校長です。
大人が手を掛けすぎて、何でも他人のせいにする…。
そんな今の教育に反し、改革を断行し、話題を呼んでいます。
一部始終を表した『学校の「当たり前」をやめた。』はベストセラーに、朝日新聞、NHKなどメディア出演も昨年後半から急増。
文部科学省など視察は後を絶たない。
現役ビジネスマンであっても関心の高い、日本の教育問題。
それを根底から変える、稀代の教育者が初めて親向けに子育て論を出版!
「子どものために」が自立をはばむ――。
名門と呼ばれる麹町中学に赴任するやいなや、課題を200も挙げ、次々と改革に着手されていった工藤校長。その視点には、教育界にどっぷりつかった者や親が思考停止してしまっていて、気づかない「気づき」が多くあるのではないでしょうか。たとえば、宿題をとにかくやらせる、運動会で結束をうたって組体操をさせる…などなど、大義名分の名のもとに慣習を変えられない教育関係者は大勢いるはずです。
そこで本書は、「その教え方は本当に正しいのですか?」と投げかけることで、多くの親の教育への思考をクリアにできるのではないか、と企画いたしました。「子どものため」を思いながら、逆に自律を妨げてしまっている規制やルールや思い込み。そこから自由になることで、真に現代に合った子育てを標榜する、そのための1冊をめざします。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。