無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
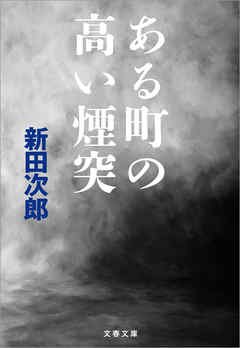
映画「ある町の高い煙突」
2018年春撮影開始。
2019年春公開予定。
明治38(1905)年、買収によって茨城の地に開業した日立鉱山。やがて鉱山の宿命ともいえる煙害が発生。亜硫酸ガスが山を枯らし、農民たちの命である農作物までも奪っていく。
そこで、立ち上がったのが地元の若者・関根三郎(モデルとなった実際の人物は関右馬允)である。郷士であった名家に生まれ、旧制一高に合格、外交官という夢に向かって進んでいた。しかし、祖父・兵馬が煙害による心労で倒れ、人生が変わる。
こうして、地元住民たちと日立鉱山との苦闘のドラマが幕を開ける。
試行錯誤の末、1914年、当時としては世界一の高さを誇る155.7mの大煙突を建設し、危機を乗り切るのであった。
足尾や別子の悲劇がなぜこの日立鉱山では繰り返されなかったのか。
青年たちの情熱と今日のCSR(企業の社会的責任)の原点といえる実話を基にした力作長篇。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。