無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
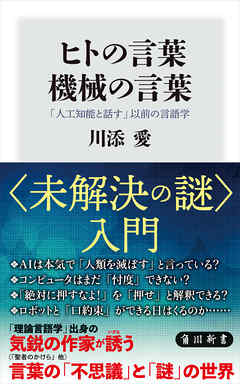
AIが発達しつつあるいま、改めて「言葉とは何か」を問い直す――
AIと普通に話せる日はくるか。
人工知能と向き合う前に心がけるべきことは。
そもそも私たちは「言葉の意味とは何か」を理解しているか。
理論言語学出身の気鋭の作家が、言葉の「不思議」と「未解決の謎」に迫る
(目次)
第一章 機械の言葉の現状
第二章 言葉の意味とは何なのか
第三章 文法と言語習得に関する謎
第四章 コミュニケーションを可能にするもの
第五章 機械の言葉とどう向き合うか
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。