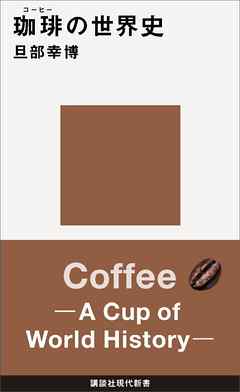あらすじ
カップ一杯のコーヒーの中には、芳醇なロマンに満ちた「物語」の数々が溶け込んでいます。その液体を口にするとき、私たちはその中の「物語」も同時に味わっているのです。コーヒーの歴史を知ることは、その「物語」を読み解くことに他なりません。歴史のロマンを玩味するにせよ、知識欲の渇きを潤すにせよ、深く知れば知るほどに、その味わいもまた深まるというもの。一杯のコーヒーに潜んだその歴史を、一緒に辿ってみましょう。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
1001
旦部 幸博
1969年、長崎県生まれ。京都大学大学院薬学研究科修了後、博士課程在籍中に滋賀医科大学助手へ。現在、同大学助教。医学博士。専門は、がんに関する遺伝子学、微生物学。人気コーヒーサイト「百珈苑」主宰。自家焙煎店や企業向けのセミナーで、コーヒーの香味や健康に関する講師を務める。著書に『コーヒーの科学』(講談社ブルーバックス)、『コーヒー おいしさの方程式』(共著、NHK出版)がある。
珈琲の世界史 (講談社現代新書)
by 旦部幸博
我々が普段何気なく飲んでいるコーヒー。それは、コーヒーノキというアカネ科の植物の種子(コーヒー豆) から作られる飲み物です。お茶やココアと同様にカフェインを含み、単においしい飲み物としてだけでなく、仕事や勉強の合間の気分転換や、眠気覚まし、ストレスの緩和などの効果──専門的な言い方をすれば、精神薬理的作用──を持つ嗜好品としても、世界中の人々に親しまれています。
国別で見ると北欧諸国の消費が最も多く、第 1 位のフィンランドは 1 人あたりの平均で 1 日 3・3 杯。アメリカは 1・2 杯で、日本は 1・0 杯……つまり、平均すると日本人全員が毎日 1 杯ずつ飲んでいる計算になります。
それは、アラビア語の「カフワqahwah」に由来します。この言葉がトルコ語の「カフヴェkahve」になり、その後、ヨーロッパにこの飲み物が伝わるとともに、coffee(英語)、café(フランス語)、Kaffee(ドイツ語) など、各国語に派生していきました。日本にはオランダ人が最初に持ち込んだため、オランダ語のkoffieから、「コーヒー」という呼称が生まれています。なお「珈琲」という漢字は、江戸時代の蘭学者、宇田川榕庵 が最初に用いたと言われ、おそらく中国語表記の「咖啡」から独自に考案したと思われます。
中世アラビアの辞書編集者によれば、アラビア語の「カフワq-h-w-」はもともと、「食欲を消し去るq-h-y」という言葉から派生したもので、その語義から、ワインを意味する古い言葉の一つだったとのこと。それが、アラビア半島でコーヒーが飲まれだした 15 世紀頃から、この「睡眠欲を取り去る」飲み物を指す言葉として定着していったようです。 カフワの語源についてはもう一つ、コーヒーノキの原産地であるエチオピア西南部の「カファKaffa」という地名が由来だとする異説もあります。ただし、アラビア語の「カフワ」は飲み物としてのコーヒーだけを指す言葉であり、コーヒーノキやコーヒー豆(アラビア語ではブンbun) を意味しないことから、研究者の多くはこの説に懐疑的です。
コーヒーの原料となるコーヒーノキは、アフリカ大陸原産の常緑樹です。熱帯産で寒さに弱く、通称「コーヒーベルト」と呼ばれる南北回帰線の間の、熱帯から亜熱帯にかけての国々で栽培されています。ただし「熱帯産」とは言っても、もともと標高が高い山地の森の中で、背の高い樹々の陰に生える植物のため、強い日差しや暑さにも割と弱く、年間を通じて気温が 15 ~ 25 ℃になる標高 1000 ~ 2000 mの高地が、良質なコーヒー作りにはもっとも適しています。
世界のコーヒー豆の総生産量は、現在、年間約 900 万トン( 60 ㎏入り麻袋で取引され、それで換算すると約 1 億 5000 万袋)。最大生産国であるブラジルが世界の約 3 分の 1 を占め、以下、ベトナム、コロンビア、インドネシア……と続きます。その大部分はアメリカ、ヨーロッパ、日本などの消費国への輸出品です。輸出総額は多い年で 200 億ドルにも上り、熱帯地方産の一次産品の中では石油に次いで第 2 位の、重要な取引商品だと言われています。なお、近年では生産国の国内消費も増えつつあります。
コーヒーノキの仲間(アカネ科コフェア属) は、現在 125 の植物種が知られていますが、主に栽培されているのは、アラビカ種とロブスタ種(植物学上の正式名称はカネフォーラ種) で、これにリベリカ種を加えた 3 種類を「コーヒーの三原種」と呼んでいます。 このうちアラビカ種は、エチオピア西南部のエチオピア(アビシニア) 高原が原産です。優れた香りと適度な酸味で、もっとも高く評価されていますが、病虫害に弱いのが玉にキズ。これが現在、世界の生産量の 6 ~ 7 割を占めています。 残りの 3 ~ 4 割を占めるのがロブスタ種。中央アフリカの西部が原産で、香味の面ではアラビカ種に比べて低評価ですが、病虫害に強くて収量も多く、比較的低地でも栽培できることから、耐病品種として広まりました。酸味が乏しく、きつい苦味と独特の土臭さ(ロブスタ臭) があり、通常は深煎りにしてブレンドの材料などに用いられます。またカフェイン含量が多いため、インスタントコーヒー…
コーヒーノキは、年に 1 回~数回──国や地域によりますが、通常は雨季のはじめに──ジャスミンのような芳香のある真っ白な花を咲かせ、そのあと 6 ~ 9 ヵ月かけて「コーヒーチェリー」と呼ばれる、赤い(品種によっては黄色の)サクランボ大の果実が熟していきます。果実の中には通常、半球形の大きな種子が 2 つ、向…
精製された生豆は、保管や輸送中に有害なカビが生えるのを防ぐために、水分量 12%以下まで乾燥させてから消費国に輸出され、次の加工処理である「焙煎」が行われます。
焙煎とは、一言で言うと「生豆を 乾煎りにする」こと。焙煎機という機械を使って、 180 ~ 250 ℃くらいまで生豆を加熱します。その過程で水分が蒸発し、生豆は次第に褐色、黒褐色に変化し、香ばしい匂いと苦味を持った「焙煎豆」に生まれ変わるのです。
焙煎の度合い(焙煎度)が「浅煎り→中煎り→深煎り」と進むに連れて、豆の色が黒くなっていくだけでなく、味や香りも大きく様変わりします。一般に浅煎りは苦味が弱く、焦がし砂糖やナッツのような香ばしさや酸味に秀でます。その後、深煎りになるにしたがって酸味は弱まり、苦味が強まるとともに、ビターチョコレートやスコッチウイスキーを思わせる重厚な香りや、複雑で奥深いコクのある味わいへと変化していきます。
焙煎された豆は、コーヒーミルで小さく砕いた後、その中の成分をお湯(または水)に溶かし出します。この工程が「抽出」です。ペーパードリップやネル(布) ドリップ、コーヒーサイフォンやエスプレッソなど、さまざまな種類のコーヒー抽出器具があり、そのどれを使ってどう淹れるかでも、コーヒーの味わいは変わります。
現在、世界中の人々が飲んでいる嗜好飲料の中で、お茶には 5000 年、カカオには 4000 年の歴史があると言われています。一方、コーヒーが確実に飲用されていたと言える最初の時代は 15 世紀頃……お茶やカカオに比べて、なんだか随分、歴史が浅いもののようにも感じられます。しかし、じつはコーヒーのほうがお茶やカカオよりも遥か昔に、人類と巡り合っていた可能性が高いのです! その最初の出会いは、いったいどんなものだったのでしょうか? この章では、さまざまな手がかりから、その謎に迫ってみます。
1・「ヤギ飼いカルディ」発見説 カルディという名のヤギ飼いの少年が、自分のヤギを山に連れて行ったとき、あまりに興奮して騒ぐので様子を見てみることにしました。すると、茂みに実っていた赤い木の実を食べていることに気づき、さっそく自分でも食べてみたところ、なんだか楽しい気分になって、ヤギと一緒に飛び跳ねて踊ったという話です。 さらに、それを目撃した(あるいは話を聞いた)修道僧が、夜間のお祈りのときに利用するようになったという、「眠らない修道院」の伝説として紹介されることもあります。
2・「シェーク・オマール」発見説 無実の罪でイエメンにあるモカの街を追放された、シェーク・オマール(シャイフ・ウマル。シェーク/シャイフは長老や族長の意) というイスラームの修行者が、空腹に苦しみながら山中をさまよいつづけていました。そのとき、赤い木の実がなっているのを発見し、それを食べたところ、疲労が回復したという話です。 このとき、小鳥に導かれて発見したとか、その後、この実から作ったスープでモカの街を疫病から救って罪を許されたとか、いろいろなバージョンの話があります。
ヤギ飼いカルディの伝説は、イタリアでアラビア語教師をしていたシリア人、ファウスト・ナイロニが 1671 年に著した『コーヒー論』が初出です。ときどきエチオピア高地の話だと誤解されますが、場所はオリエント(中東) のどこかで、時代は不明。「カルディ」はアラブ系の人名ですが、原典に少年の名前はなく、飼っていたのもラクダかヤギと書かれており、一緒に踊ったという話もありません。
さて、この 2 つの「発見説」、単なる伝説伝承の類いとはいえ、 3 つの共通する要素が 窺えます。それは、 ①主人公(おそらくアラブ系の人物) が山の中に人知れず生えていたコーヒーを発見した ②最初から飲み物だったのではなく、果実を食べたのがはじまり ③神経興奮や疲労回復などの薬効が発見につながった という点です。果たして、本当のところはどうだったのでしょうか。
「コーヒーノキの故郷」であるアフリカ大陸は、我ら人類の故郷でもあります。ヒト・ゴリラ・チンパンジーの共通祖先とオランウータンの祖先が分岐したのが、コーヒーノキ属が出現したのと同じ時期( 1400 万年前頃)。やがてその後、約 700 万年前の中央アフリカでヒトの祖先にあたる「猿人」が分岐し、さらにその仲間から約 200 万年前のタンザニアで「ヒト属」、すなわち現生人類の共通祖先が生まれたといわれています。なので、地球上ではコーヒーノキのほうが人類よりもはるかに「先輩」だったといえるでしょう。
先に述べた 2 つのコーヒー発見説は「山の中に人知れず生えていたコーヒーを発見した」というストーリーでしたが、こうしてそれぞれの誕生の歴史を辿ってみると、本当の「最初の出会い」はそうではなかった可能性が高いと考えられます。コーヒーノキは、じつは人類が地球上に生まれたそのときから、すでに身近に存在する植物だったのです。 改めて考えてみると、お茶には 5000 年、カカオには 4000 年の歴史があると言いますが、それらの植物との出会いは、人類がユーラシア大陸やアメリカ大陸にそれぞれ移住した後のこと。人類誕生のときまで遡れるコーヒーノキとの出会いのほうが、お茶やカカオよりも、はるかに早かった可能性は高いと言えます。
もっとも、「コーヒーが人類の進化に手を貸した」は大げさですが、逆に「人類の祖先がコーヒーの進化に手を貸した」可能性は十分あります。果実を食べた小動物が、流木に乗って海を渡るなどしながら各地に移動し、その糞によってコーヒーノキを運んだと考えられているからです。我々の遠いご先祖様もこうした「運び手」だったのかもしれません。
ジャック・ニコルソンとモーガン・フリーマンの二大名優が競演した、『最高の人生の見つけ方』という映画をご存じでしょうか? 癌で余命半年を宣告された二人の男が「死ぬまでにやりたいことリスト」を作って実行していくという、笑いあり涙ありの感動作です。この作品でジャック・ニコルソン演じる余命半年の億万長者は「最高級のものだけ飲み食いする」というポリシーから、「コピ・ルアク」というとても高価なコーヒーだけを飲んでいて、これがこの映画の小道具になっています。
「汚い」と思われるかもしれませんが、腸の中では果肉だけが消化され、コーヒー豆は丈夫なパーチメントに覆われたまま排泄されますので、パーチメントを外してやれば中身は 一応 汚れていませんし、万一何かしらの菌が付いていても焙煎すれば全部死ぬので、これまた 一応 衛生的にも問題ありません──もちろん、気分的にどうかは人それぞれなので、無理にはお薦めしませんが。
コーヒーノキが自生する森の中で誕生したホモ・サピエンスは、その後、エチオピアからユーラシア、そして世界へと旅立ちました。今から約 7 万年前のことだといわれています。こうしたアフリカからの移住は何回かにわたって起きており、また最近の遺伝子研究の結果からは、辿り着いた先で、すでにアフリカから巣立っていたネアンデルタール人やデニソワ人とも一部交わりながら生まれたのが、現代に暮らす我々「現生人類」のルーツであることが明らかになりました。
また、歴史背景からも比較的新しい時代に作られたと推定されます。エチオピアの歴史の中心は、北部~中央高地のアムハラ人やティグレ人を中心とするキリスト教徒(エチオピア正教徒) たちの国、つまりエチオピア帝国( 1270 ~ 1974) で、彼らにはもともとコーヒーを飲む習慣もなければ、コーヒー生産にもあまり関わりがありませんでした。
日本のコーヒー本には何故かあまり見かけないのですが、欧米のコーヒー本にはしばしば、コーヒーの歴史の始まりとして「 5000 年以上前から、エチオピアのオロモ族(オロモ人) が戦争に赴くときにコーヒーを携帯食にしていた」という話が出てきます。煎って潰したコーヒー豆を動物の脂(バター) と混ぜて大きな団子に丸めたもので、カフェインによる興奮とバターの高いカロリーで気分がハイになって戦闘のときに大活躍したとか、あるいは人類初のコーヒーはエナジードリンクならぬこの「エナジーボール」だったなどと言われます。現在も西南部との州境付近に暮らすオロモ人の一部に「ブナ・カラー」という名前で、この風習が残っています。
じつはオロモ族がエチオピアに侵攻する以前からアラビア半島でコーヒーが飲まれていたことを示す文献がありますし、オロモ族がもともと暮らしていた南東部のソマリア国境付近の山地は、コーヒーノキの自生域から外れているからです。
エチオピア西南部ではコーヒーの呼び方だけでなく、その利用法もじつに多種多様です。葉や豆を飲み物にするだけではなく、薬にしたり、新鮮な果実をそのまま野菜代わりに、あるいは干した果肉をバターで炒めて食べたりもします。さらに、新しい土地に移住したときに人々の体にコーヒーを塗って身を清めたり、子供が生まれた家でコーヒーを口に含んで四方の壁に吹き付けたり、結婚を申し込むときに男性から女性の両親への贈り物にしたりと、人生にとって重要なさまざまな場面で行われる儀礼に用いています。
こうした生活儀礼との密接な結びつきは、エチオピア西南部の人々が古くからコーヒーを利用してきた証拠だといえるでしょう。また同時に、単に食用としてではなく、特別な使い方をするということは、彼らがコーヒーに何か特別な「力」を感じていたからかもしれません。コーヒーは、果実や若葉にも若干のカフェインを含んでいます。それを食べた人々がカフェインの持つ覚醒や疲労軽減作用という「力」を知り、儀礼に使うようになったのではないでしょうか。
人類の祖先がアフリカから旅立った後、エチオピアの山中に取り残されたコーヒーノキ。どのようにして両者が再び巡り合い、コーヒーという飲み物が生まれたのか……これまで多くの研究家がその謎に挑んできましたが、情報に欠落が多く、十分に解明されていませんでした。しかし、一見コーヒーとは無関係な、当時のエチオピア周辺の社会情勢を、過去の研究知見と重ねていくと、パズルのピースが埋まるように、エチオピアからイエメンへとコーヒーが辿った道筋が浮かび上がってきます。
7 世紀にはアラビア半島でイスラーム教が興りますが、 615 年に預言者ムハンマドの最初の信徒たちがマッカ(メッカ) で迫害されたとき、逃れてきた彼らを匿い庇護したため、アクスム王国はキリスト教国家ながらイスラーム教徒らとも友好関係にありました。
また最近になって、この仮説を補強するもう一つの証拠が見つかっています。 1996 年、ドバイの北東に位置するクシュという遺跡で、 1100 年頃に中国やイエメンで作られていた陶片と一緒に、炭化したコーヒー豆が 2 粒、出土したのです。この豆は後から紛れ込んだものではなく、この時代に炭化したものだと推定されていますが、偶然火の中に落ちたものか、人為的に焙煎されたものかはわかっていません。
10 ~ 11 世紀になってやっと姿を現したと思ったのも束の間、コーヒーに関する記述は、どういうわけか、その後 400 年以上にわたって文献から消えてしまいます。その次にコーヒーが姿を現すのは、 15 世紀のイエメンです。この空白期間にいったい何があったのか……その手がかりを得るために、少し視点を変えて、コーヒーとは直接の関係はないのですが、イエメンの歴史の流れを辿ってみたいと思います。
イエメンでは、 1021 年にザビードを首都とするナジャーフ朝( 1021 ~ 1158) が成立しました。その中心になったエチオピア系住民は、人数こそ多かったものの、身分の低い奴隷出身で、イスラームに関する知識や教養を持たない者が大半でした。ところがイスラーム世界では、本来、優れた宗教指導者がイスラームの教えにしたがって国を治め、人々を導くという考えが根幹にあります。
ラスール朝末期、アル゠ラーズィーから 400 年の時を経て、イエメンに再びコーヒーが姿を現します。この時代に、改めてエチオピアからイエメンにコーヒーが伝来したともいわれており、どうやらエチオピアにも手がかりがあるようです。少し時間を遡って、今度はエチオピアの歴史の流れを駆け足で辿ってみましょう。
それほど古い産地でありながら、ハラーのコーヒーが有名になったのは 20 世紀初頭。エチオピア帝国が積極的にコーヒーを輸出するようになってからです。それまでエチオピアのコーヒーはイエメンに集められ、すべて同じ「モカ」の名で輸出されていました。現在も「イエメンモカ」「エチオピアモカ」「モカ・ハラー」などの銘柄を見かけるのは、こうした歴史が背景にあります。
そしてその後、 15 世紀にイエメンのアデンで、コーヒーから作るカフワが発明されました。ちょっとややこしいですが「コーヒーノキとカフワはどちらもエチオピア発祥だが、『コーヒーのカフワ』はイエメン発祥」ということです。
彼が広めたカートの葉には「カチノン」という、覚醒剤(アンフェタミン) と似た成分が含まれており、覚醒作用や食欲抑制、多幸感、陶酔感をもたらします。しかし生のカート葉は保存が利かず、鮮度が落ちると効き目がなくなってしまうという欠点がありました。これが「コーヒーのカフワ」が生まれるきっかけになったのです。
カフワの普及に大きく関わったのが、「スーフィー」と呼ばれるイスラーム神秘主義者たちの一派です。イスラーム教には本来、神官や僧侶のような職業としての聖職者は存在せず、万人が俗世の生活の中で信仰するという考えを採っていますが、 8 世紀頃に俗世を捨てて、粗末な毛布(スーフ) だけをまとって生活する初期のスーフィーが現れました。
彼らの儀式には異端すれすれのものがあり、例えばイスラーム教では娯楽のための音楽や舞踏は禁忌ですが、一部のスーフィーは「サマー」という楽器を奏でて歌い踊る儀式を行います。また、アヘンや大麻、タバコなどのドラッグを儀式に使うスーフィー教団もあり、正統派の学者から非難されることもありました。こうした中でエチオピアやイエメンのスーフィーたちがズィクルの儀式に取り入れた飲み物が「カフワ」だったのです。
人々の相談を受けたザブハーニーは、アジャムの地の人々がいろいろなものからカフワを作って飲んでいたことや、コーヒーの赤い果実を食べていたことを思い出しました。また彼はアデンで病気にかかったとき、薬にしてコーヒーを取り寄せて使った経験があったようで、身をもってその覚醒作用を知っていたと思われます。 その効果は実体験済み。何より果実を干して乾かせば保存が利き、山から運んでくるのも可能です。そこで彼は「コーヒーの果実や種子にもカートと同じような働きがあるから、それでカフワを作ればいい」という考えに至ったのです。
前者は「キシル(=殻) のカフワ」で「キシリーヤ」、後者は「ブン(=コーヒーの果実) のカフワ」で「ブンニーヤ」とも呼ばれます。私たちが飲んでいる「豆だけを煎って作るコーヒー」は、この時代の記録にはありません。しかし、イエメンのカフワが世界に広まる過程で、キシルは姿を消してブンだけになり、ブンのカフワが豆の部分だけを使う現在のコーヒーに姿を変えたので「カフワがコーヒーの起源」ということは間違いありません。 イエメンには、今でも「キシルのカフワ」と「ブンのカフワ」の両方が残っています。ただし、現代の「ブン」は豆だけで作るアラビア式のコーヒーで、古い記録のものとは異なります。キシルはカルダモンなどのスパイスや砂糖と一緒に煮出して飲むのが一般的で、ブンに比べて値段も安く、イエメン人にはこっちが人気のようです。
こうして見ると順風満帆だったかのようなコーヒーの普及ですが、それほどすんなりと受け入れられたわけではありません。もともとアルコールや豚肉など飲食にまつわる宗教的タブーが多いイスラーム教で、コーヒー飲用の是非が問われたのは当然のことでした。 1511 年にマッカの市場監察官ハイール・ベグ(カイル・ベイ) がコーヒーの販売や飲用を禁止した、いわゆる「マッカ事件」を皮切りに、 1534 年カイロの反対派によるカフェハネ襲撃、イスタンブルでも正統派の学者らがカフェやコーヒーを批判し、為政者によるコーヒー禁止令やカフェ閉鎖命令も各地でたびたび出ています。 どの禁止令も長続きせず、すぐに解除されるか形骸化したものの、コーヒーの歴史全体を見渡しても、これほどいざこざが多かった時代は他にないでしょう。
当時から現在に至るまで、コーヒー反対運動の 表向きの理由 は、①宗教上の戒律に触れる、②人体に有害である、③カフェハネなどにおける風紀の乱れ、の 3 点にほぼ集約されます。イスラーム教では、クルアーン(コーラン) や預言者ムハンマドの言行録に基づく「慣行(スンナ)」に従って物事の是非を判断するのが基本で、コーヒーのように預言者の没後に新しく生まれた習慣に対する見解は分かれがちです。
伝統を重んじるスンニ派の一部の学者からは「そもそも慣行からの逸脱(ビドア) だ」「精神に作用するのだから、酒の同類だ」などの批判が何度も出ましたが、そのたびに反論され、 16 世紀後半になるとコーヒーはイスラームの法に照らして合法な飲み物だという考えが学識者の多くに支持されるようになりました。アブドゥル゠カーディルの『コーヒーの合法性の擁護』(2章) も、この時期に書かれたコーヒー擁護側の代表的な書物です。
当時のコーヒー反対運動の中でもっとも過激だったのは、何といってもイスタンブルのコーヒー禁止令でしょう。 1633 年の禁止令では「 1 ストライク・アウト」で、見つかったら即、死刑。 1656 年では若干甘くなったとは言え「 2 ストライク・アウト」で、 1 回目は杖で酷く叩かれ、 2 回目は袋詰めにして海に沈められる(!) というから、かなり強烈です。 「何もそこまでしなくても……」と思われるかもしれませんが、コーヒー禁止を口実に当時の皇帝の政敵を排除すること、つまり最初から政治利用が目的だったのです。
さらに「女子禁制だが男性は誰でもOK」というコーヒーハウスのスタイルもマンネリ化してしまい、女性同伴可でメリーゴーラウンドなども庭園に備えた、紅茶主体の「ティー・ガーデン」や、完全会員制の「クラブ」など、新しいコンセプトの店に取って替わられていきました。
フランスは、出だしこそイギリスに後れをとりましたが、途中で衰退したコーヒーハウスとは異なり、カフェ人気がずっと持続しつづけた、安定したコーヒー消費国だといえるでしょう。消費の大半はパリの中産市民階級が中心で、個人消費量に換算するとパリっ子がフランス人平均の 10 倍近くを飲んでいた計算になります。
特に惹き付けられたのは、上流階級に憧れる富裕層や中流階級の人々でしたが、貴族や知識人、コメディ・フランセーズの俳優たち……プロコップは、じつに多彩な人々で賑わいます。 18 世紀には当時最高の知性と称されたヴォルテールをはじめ、ディドロ、ダランベール、ルソーらが集い、『百科全書』の編集会議を行ったのもこの店でした。 ソリマン・アガのときといい、このプロコップといい、パリっ子たちは、どうも味や薬理作用より、この手の「高級感のあるスタイル」から、コーヒーにはまってしまう人が多かったようです。いずれにせよ、他のカフェもすぐにこのスタイルを取り入れるようになり、まさにパリのカフェの歴史はプロコップから始まったといえるでしょう。
レジャンスを一言で言い表すならば「チェス喫茶」。啓蒙思想の時代を迎えた 18 世紀のフランスでは、知的遊戯としてチェスが大流行し、カフェでも客同士でチェスを打ったり、試合を観戦したりするようになりました。なかでも、その中心地になったのが、このレジャンスだったのです。多くの知識人やチェス名人が集まり、黙々と勝負を繰り広げる様子は「プロコップは談論が、レジャンスは沈黙と緊張が支配した」と語られています。
この当時のドイツ女性の間でのコーヒー人気を謳ったものの一つが、バッハの名曲『おしゃべりはやめて、お静かに』……通称『コーヒー・カンタータ』です。 1 日 3 杯コーヒーを飲み、コーヒーなしではいられないと歌う娘に、父親が何とかやめさせようと、食事や洋服などを取り上げると脅します。娘は全くこたえませんが、最後に「コーヒーをやめなければ婿探しはしてやらない、結婚させないぞ」と父親が脅したところ、娘は動揺し、「恋人を見つけてくれるならコーヒーを諦める」と父親に誓います。
この時代、ヨーロッパではコーヒーが健康に悪いのではないかという問題がたびたび議論を呼びましたが、それを「人体実験」で確かめようとした人物がいます。スウェーデン国王グスタフ 3 世(在位 1771 ~ 1792) です。この国王、「コーヒー有害論」の支持者でコーヒー禁止令を布告していたのですが、隠れて飲む人が跡を絶ちませんでした。
ところが皮肉なことに 1792 年、国王は暗殺されて囚人 2 人よりも先に亡くなってしまいます。王の死後も実験は続けられ、 2 人とも大変長生きしましたが、紅茶を飲んでいたほうが 83 歳で先に亡くなりました。コーヒーを飲んでいたほうが何歳まで生きたかは伝わっていません。
当時、イエメンではコーヒー栽培を独占しようと、種子や苗木の持ち出しを禁じていたと言われています。真偽は不明ですが、わざわざ豆を煮て発芽しないよう加工してから輸出したと噂されるほど。
1658 年、オランダがポルトガルに代わってセイロン島(スリランカ) を植民地化したときには、すでにイスラーム教徒が移入していたコーヒーノキが生えていたといいます。だからそれを栽培したというのが、イエメン以外でコーヒーが栽培された最初の記録です。このコーヒーノキは、一説にはインドやインドネシアにも伝わったとも言われていますが、その真偽は不明です。
リオとサンパウロ、この 2 つの産地の明暗がはっきり分かれたのは 1888 年、 2 代皇帝ペドロ 2 世が奴隷解放令を出したときのことでした。依然として奴隷労働に頼りきり、これといった対策を講じていなかったリオでは、解放令がでるや否や、奴隷たちが文字通り「一夜のうちに」都会へと逃げ出してしまったのです。農園には赤々と実ったコーヒーの実だけが残され、誰に摘まれることもないまま腐っていってしまいました。こうして長く隆盛を極めたリオのコーヒー栽培は一気に破綻し、それと入れ替わりでサンパウロがブラジルのコーヒー生産をリードします。
ブラジルではかつてコーヒーのことを「オウロ・ヴェルデouro verde」とも呼びました。ポルトガル語で「緑の黄金」という意味の言葉です。ポルトガル植民地となったブラジルでは当初、砂糖栽培が主要な産業でしたが、 17 世紀末に南東部のミナスジェライス州で金鉱脈が発見されたことでゴールドラッシュに沸き立ち、 18 世紀中はミナスジェライスのオウロ・プレト(「黒い黄金」の意) 地区で採掘された金がリオ・デ・ジャネイロから輸出されました。その後、 1808 ~ 1821 年の間、リオがポルトガル・ブラジル連合王国の首都になり、フルミネンセ(ヴァソーラス近郊) 地区でのコーヒー栽培がさかんになります。
コーヒー立国を目指した当時のコスタリカにとって、最大のライバルだったのはブラジルです。しかし国土の狭いコスタリカではブラジルのような大農園が作れず、移民もより好条件の国に流れていったため、小地主や家族労働による小・零細農園が主流になりました。アメリカ市場向けではブラジルの生産量と価格に 敵 わないと早々に見切りを付けたコスタリカは、主にイギリス経由でヨーロッパ向けの高品質なコーヒーを輸出します。その後も薄利多売路線のブラジルとは対照的に、狭い土地を有効に使える品種や栽培法の改良、そして 19 世紀半ばに開発された水洗式精製もいち早く取り入れ、コスタリカは中南米屈指のコーヒー先進国に成長します。
そして 18 世紀末、南インドのマイソール地方とスリランカを植民地化したイギリスは、そこでもコーヒー栽培を始めました。この努力は 19 世紀半ばに実を結びます。特にスリランカはパルパーによる水洗式精製を取り入れ、 1868 年のアンリ・ヴェルテール『コーヒーの歴史に関するエッセイ』でも高品質で将来有望だと、期待が寄せられていました。 ところが皮肉なことに、この本が出版された直後、スリランカは最大の脅威に見舞われます。それまで全く知られていなかった「コーヒーさび病」という新しい病害が蔓延したのです。 その名の通り、この病気に罹ると葉の裏側に「赤さび」のような病斑が生じます。赤さびはやがて樹全体に広がって樹自体を枯らしてしまうだけでなく、樹から樹へと伝染して、畑、地域へと広まり、数年後にはスリランカ全土に蔓延しました。翌年にはインドにも伝わりますが、こちらはスリランカよりもさらに激しく、発生後まもなくインド中のコーヒーが壊滅的被害を受けました。
1880 年にイギリスからスリランカに招聘された植物病理学者のマーシャル・ウォードは、この病気が「コーヒーさび病菌(ヘミレイア・ヴァスタトリクス)」という新種のカビによる伝染病だと突き止めました。そしてコーヒーのモノカルチャーをやめて、他の作物と混植して蔓延を防ぐべきだと進言します。 ところが農園主たちの多くは、別の学者が唱えた「遺伝病の一種で、新しい樹に植え替えるだけで収まるはず」という、自分たちに都合のいい説を信じ込んでしまい、彼の提言に応じませんでした。結局ウォードは周囲の理解を得られないまま、イギリスに帰国してしまい、スリランカはさび病に 蹂躙 されて、コーヒー栽培を断念することになりました。その後、 1890 年に廃農園を訪れたトーマス・リプトンが自社で販売する紅茶を栽培することを思いつきます。スリランカが紅茶の産地として有名になったのはここからです。
ただしインドネシアのコーヒーは、悪名高い「強制栽培制度」の下、低賃金で酷使される植民地の住民に支えられたものでした。 1860 年、植民地官吏だったダウエス・デッケルが「ムルタトゥーリ」の筆名で著した小説『マックス・ハーフェラール』で現地の惨状を訴えると、オランダ本国で強制栽培に対する反対世論が高まります。その結果、 19 世紀後半には強制栽培制度が順次廃止され、官営大農園から中小農家での栽培へとシフトしていきました。なお、現在「フェアトレードコーヒー」( 10 章) を認証しているマックス・ハーフェラール財団( 1988 年設立) の名前は、この小説から採られたものです。
こうした社会的な動きの中、インドネシアのコーヒー生産が最大の危機に見舞われます。コーヒーさび病です。スリランカとインドのコーヒーを壊滅させた最悪の疫病が、 1888 年、とうとうインドネシアでも発生したのです。瞬く間に広がるさび病に対して、人々は対抗策を模索します。インドネシアでは官営農園時代に生産性向上を目的に、いろいろなコーヒー品種の試験栽培が行われていたため、その中からさび病に強いものを見つけようとしたのです。
19 世紀末、ベルギーのジャンブルー農業研究所(現ジャンブルー農業大学) の教授、エミール・ローランは、中央アフリカのコンゴの植物を研究していました。当時のアフリカは未知の植物資源の宝庫で、薬の原料や作物になる有用植物を、先を争って探索していた時代です。ローランはベルギーの園芸会社をスポンサーに付けて資金援助を得る代わりに、発見した植物を提供する契約でコンゴに現地調査に赴きました。
1895 年、 2 度目の調査旅行のとき、彼はコンゴの奥地でこれまで見たことのないコーヒーノキ属の植物を見つけます。彼はその植物を採集してベルギーに持ち帰り、自分の弟子であったエミール・デ・ウィルデマンと、園芸会社にそれぞれ渡しました。
20 世紀初頭、さび病に苦しむインドネシアを尻目に順風満帆に見えた中南米の国々には、さび病以上に厄介な難敵が迫っていました。その正体は「市場経済」。コーヒー普及になくてはならないものながら、隙あらば思い通りに操ろうとする「怪物」です。この頃から「 2 つのコーヒー大国」、生産大国ブラジルと消費大国アメリカの間で、コーヒー価格を巡る主導権争いが激化します。 1960 年頃までの流れを追っていきましょう。
しかし、当初ドイツの銀行から受けた 100 万ポンド(現在の約 160 億円) の融資も、大量の生豆を前に、すぐ底をつきました。返済の見通しも立たぬまま、追加援助を求めた銀行には次々断られ、困り果てたサンパウロの生産者が最後にすがった相手──彼こそハーマン・ジールケン。後に世界のコーヒー取引を牛耳って「アメリカ最後のコーヒー王」と呼ばれた人物です。
ジールケンは、 1847 年、ドイツ・ハンブルクの小さなパン屋に生まれました。 21 歳を目前にコスタリカを経て渡米し、職を転々とした後、語学力を買われてニューヨークのW・H・クロスマン兄弟商会(後のクロスマン・ジールケン社) に雇われます。それから彼は、南米を駆け回って数々の大口取引を成功させ、翌年には共同経営者に就任。「人間発電機」ばりの活躍で商会を大躍進させますが、同業者の不幸に付け入って儲ける容赦ないやり口でも有名で、しばしばドイツの「鉄血宰相」ビスマルクにも喩えられました。
こうして「コーヒー王」となったジールケンですが、本人は「歴史上、没落しなかった王は存在しない」と言って、そう呼ばれることを嫌っていました。その言葉どおり、 70 年の生涯で──鉄鋼業や鉄道業界の「王」たちとも渡り合いながら──一度たりとも事業で失敗することはなかったのです。そして 1914 年、毎年恒例だったドイツの別宅での滞在中に、第一次大戦が勃発して帰国できなくなり、 1917 年にその人生を終えることになりました。
需要が激減したコーヒー豆の価格は、かつてない大暴落を起こします。特に損害を被ったのはヨーロッパ向けに高級品を輸出していた中米でした。一方、恩恵を受けたのがアメリカです。大戦特需による好景気に加えて、それまで安いブラジル産ばかり買っていたアメリカに、行き先を失った中米産の高級品が安価で流入したからです。さらにアメリカの業者は、アメリカ同様に中立を表明していた北欧に、北海を迂回してコーヒー豆を再輸出し大儲けします。連合国への手前、表向きは北欧での消費用でしたが、実際はドイツにかなりの量が横流しされました。
また第一次大戦のときに、アメリカではじめて普及したものがあります。インスタントコーヒーです。 1917 年、連合国側で参戦したアメリカからヨーロッパに赴く兵士たちに、グアテマラ在住ベルギー人、ジョージ・ワシントンが考案したインスタントコーヒーが支給され、手軽さが受けて戦場で愛飲されます。 なおアメリカ初のインスタントコーヒーの特許は、シカゴ在住の日本人化学者、カトウ・サトリが、ジョージ・ワシントンより先に取得しています(アメリカ以外ではそれより早く、 18 世紀中にイギリスで試験的に作製した人や、 1889 年にニュージーランドで特許取得した会社があったことが最近判明しています)。
このとき宣伝に活用されたのが、当時最新の「科学」です。彼らは休憩時間のコーヒーで仕事の能率が向上するという論文を引用し、労働者向けにコーヒーの利点をアピールしました。また健康への関心が高いインテリ層には、医学論文の引用などで、C・W・ポストが広めたコーヒー有害説(6章) に反論するとともに「じつはコーヒーは体に良く、知識人向けの飲み物だ」とアピールしました。家庭向けに「科学的でおいしいコーヒーの淹れ方」を紹介したりもしています。
科学だけでなく、当時の社会情勢もフル活用されました。当時、社会進出をはじめた女性向けに「インスタントコーヒーこそ忙しいキャリアウーマンの味方」とアピールしたかと思えば、保守層向けには「家族のためにおいしいコーヒーを淹れることは主婦の嗜み」とアピールしました。中南米の貧しいコーヒー生産者を支援することは、新しい世界の主導者になる自分たちの務めだとアメリカ人の善意や自尊心に訴えかける一方で、経済界には彼らが裕福になればアメリカの工業製品を買う「良き消費者」になって、投資した分は戻ってくると主張します。
戦時中はどの国でもコーヒーは軍に徴用されて、前線の兵士に支給されました。覚醒や興奮など、コーヒーの持つ薬理作用が、戦地での眠気防止や疲労感の軽減に役立ちましたし、その香りや、温かいものを飲むという行為そのものが貴重な安らぎとなり、ストレスの軽減にもつながったのです。
1959 年、価格低下とロブスタの台頭に頭を悩ます中南米の生産者にとって、思わぬところから事態が好転します。キューバ革命の勃発です。中南米を「アメリカの裏庭」と呼んで、経済的にも政治的にも睨みを利かせ、反米勢力が生まれるたびに力ずくでねじ伏せてきたアメリカにとって、カリブ海での社会主義国家の誕生は大きな危機感を生じさせるものでした。 アメリカは、中南米に「第二のキューバ」を作らないためにも、また冷戦時代の西側諸国のリーダーとしても、中南米はもちろん世界のコーヒー生産国の経済や政情を安定化して、共産主義や反米ゲリラ勢力の台頭を防ぐ必要にかられます。そこで、第二次大戦時の「環アメリカコーヒー協定」と同じことを、今度は世界規模で行おうと考えたのです。
1930 年代までは、アメリカのコーヒーには地域ごとに多様性があって、南部は極深煎り、ボストンと西部は比較的浅煎り、東部は深煎りだったのですが、恐慌以降の買収合併で焙煎会社が大規模化するとともに全国的に浅煎り化します。短時間で焙煎できて燃料代の節約になる上、深煎りにすると揮発や燃焼ガスとして失われる成分だけ重量が減るので、「 100 gいくら」で売るコーヒーは浅煎りのほうが儲かるからです。中には大型焙煎機で冷却用に散布する水の量を増やして重さを増やす、不届きな業者もいたようです。
さて、ここで少し目線を変えて、日本でのコーヒーの歴史を見てみましょう。お気づきのように、これまでの世界史に日本が登場するところは、ほとんどありません。欧米と比べてコーヒーと出会ってからの年月も浅く、また国際コーヒー協定で「新市場国」という、コーヒー需要の発展途上国に認定されてきた国なので、当然といえば当然です。 しかし、じつは日本は、戦後から 1980 年代頃までの間に、焙煎や抽出の技術を国内で研鑽していった結果、まるでガラパゴス島のように独特の進化をとげたコーヒー文化を持つ国だったのです!
いつ誰が日本ではじめてコーヒーを飲んだのか、その正確な記録は残っていません。 17 世紀末~ 18 世紀頃、出島のオランダ商人たちが飲んでおり、それを商館に出入りしていた通訳、遊女、役人らも飲んだのが最初だと考えられています。
1776 年、出島に赴任したスウェーデンの植物学者で医師のカール・ツンベルクは 2 ~ 3 人の通訳がかろうじてコーヒーの味を知っている程度だと記していますが、その 20 年後に、遊女が出島でオランダ人から貰って持ち出した物品記録に「コヲヒ豆」の文字が見られます。
ギリシア神話の 放埒 な牧神、パンの名にちなんで「パンの会」と名付けられたこの集まりは、耽美派の新しい芸術運動の拠点になりました。彼らはいくつかの西洋料理店で会合を重ねますが、そんな彼らが集まった店の一つが、 1910(明治 43) 年に日本橋で開業した「メイゾン 鴻の巣」でした。最初は酒場、後にフランス料理屋となったこの店を、木下杢太郎は詩集『食後の唄』( 1919 年) の序文の中で「まづまづ東京最初のCaféと 云 つても 可 い家」と記しています。それくらい食後のコーヒーにも力を入れていた店だったようです。
1911 年 3 月、こうした文人たちの活動から生まれたのが銀座の「カフェー・プランタン」。パンの会に啓発された洋画家の松山省三が、画家仲間の平岡権八郎とともに、芸術家たちの語り合うサロンとして開業した店です。フランス語で「春」を意味するプランタンという名は、松山の親友だった小山内薫の命名です。コーヒーの他、洋酒や軽食も提供し、給仕係に女性、すなわち「女給」を置いたのが特徴でした。当初は会員制を導入し、松山や平岡の師である黒田清輝をはじめ、森鷗外、永井荷風、北原白秋など当時のインテリ、文化人が集まりました。このためか、一般客には敷居が高い店だったようです。
続いて 1911 年 8 月、銀座に開業したのが「カフェー・ライオン」。こちらは料理が中心で、コーヒーや酒類も提供し、やはり女給を雇っていました。現在の「銀座ライオン」や「ビヤホールライオン」などのはじまりとなる店です。
パウリスタ最大の武器は、原価ゼロの生豆が可能にした「安さ」でした。値の張る洋酒や洋食でなくコーヒーがメニューの中心で、女給ではなく男の給仕(ボーイ) を雇って、チップ不要、コーヒー一杯だけの客も歓迎したため庶民や学生客が集まります。芥川龍之介や慶應義塾の文芸誌『三田文学』の久保田万太郎ら、平塚らいてうの 青鞜 社 の女流作家たちが集まり、文化の発信地にもなりました。
1970 年、いざなぎ景気の終了でサラリーマン生活に見切りを付ける人々が現れました。この「脱サラ」が流行語になり、社会現象化したのが 1971 年。彼ら「脱サラ組」の中から、一国一城の主を夢見て、喫茶店を独立開業する人々が大勢現れたのです。 彼らはなぜ他の商売ではなく喫茶店を選んだのでしょうか。その大きな理由は喫茶店がもっともお手軽な自営業だと思われていたからです。洋食屋などの本格的な飲食店を開くには、それなりの料理の腕が必要だと尻込みしても、純喫茶のような「コーヒーと軽食を作って出すだけ」なら何とかなると考える人がほとんどでした。 こうした風潮から「でもしか喫茶」なる言葉が生まれたのもこの頃です。「脱サラして喫茶店 でも 始めようか」「私には他の業種は無理だから、喫茶店くらいしか できない」という軽い気持ちで始める喫茶店への 揶揄 が込められた言葉です。
『喫茶店経営』の編集長を務めた嶋中 労 は、著書『コーヒーに憑かれた男たち』の中で、当時を代表するコーヒー人たちの系譜を描いています。同書では、終戦後まもなく開業して自家焙煎を広めた人物として、銀座「カフェ・ド・ランブル」の関口一郎と、大阪で「リヒト」「なんち」などを営んでいた 襟 立 博 保 が紹介されています。さしずめ、終戦直後の「東西の両巨頭」といったところでしょうか。 さらに嶋中は、ランブルの関口に加え、襟立を生涯の師と仰いだ吉祥寺「もか」の 標 交 紀、合理的思考に基づき、独力で焙煎技術を体系化した南千住「カフェ・バッハ」の田口 護 の 3 人を、 70 年代以降の東京を代表する「自家焙煎店の御三家」として挙げています(もちろん、ほかにも多くのコーヒー人が日本各地で活躍していたことは言うまでもありません)。
コーヒーを中心にする店では原価が比較的安いので「利益率」はそこそこ良いのですが、客が「コーヒー 1 杯でテーブル 1 つ占める」ことから、時間当たりの客単価が安く「利益高」はあまり高くなりません。バブル時代の地価高騰によって、テナントとして他の建物に入っている店などでは家賃も高騰したため、売り上げが追いつかなくなっていきます。また、原料を輸入に頼るコーヒーでは、バブル時の円安も原価の上昇に繫がりました。
そして 1986 年、スペシャルティ業界を一転させる「あの会社」が登場します。そう、皆さんもご存じの「スタバ」ことスターバックスです。「あれ? 思ったより遅いな?」と感じたかもしれませんが、じつはスターバックスの創業自体は 1971 年。ピートの「深煎りの高品質コーヒー」に魅了されたジェリー・ボールドウィン、ゴードン・バウカー、ゼヴ・シーグルの 3 人がシアトルで始めた店です。しかし当初は、我々が知る現在のスタイルとは別物で、自家焙煎豆の小売りがメインの店でした。 それが現在のようなスタイルになったのは、敏腕経営者ハワード・シュルツの手によるものです。 1981 年に彼らの店を訪れ、その可能性を見抜いたシュルツは、翌年に入社して優れた経営手腕を発揮しました。しかしまもなく彼の興味は、エスプレッソを使った飲料販売に向かいます。 1984 年、彼の発案で店舗の一つに併設したバール(エスプレッソ・バー) が大当たりし、こちらを本業にすべきだと主張するシュルツと、あくまでピートの自家焙煎店を理想とするボールドウィンとの間に見解の相違が生じます。結果的にシュルツは独立し、 1986 年にエスプレッソの店「イル・ジョルナーレ」を開業しました。 一方でボールドウィンは、売りに出ていた元ピートの店「ピーツ・コーヒー&ティー」を買い取りますが、その借金が 祟って 1987 年に資金繰りが悪化します。ピーツとスタバ、どちらを手元に残すかの選択に迫られたボールドウィンが選んだのは、憧れていたピートの店でした。このときスタバがシュルツに売却されて「スターバックス」の名の下にイル・ジョルナーレと合併しました。現在のスターバックスのスタイルは、 1986 年にイル・ジョルナーレでシュルツが確立したものなのです。
アメリカで生まれたスペシャルティコーヒーの波は、 5 ~ 10 年ほど遅れて日本にも上陸します。 1987 年、高品質なコーヒーに注目する企業連合が設立した「全日本グルメコーヒー協会」が、その日本における先駆けになりました。本格的に注目されるようになったのは、 1990 年代のカフェブームの到来後。「自家焙煎の御三家」の中で、以前から生豆の品質の重要性を唱えていたカフェ・バッハも、スペシャルティの動きにいち早く目を付けた店の一つで、この頃から自分たちのスタイルにうまく取り入れて融和させ、進化させていく自家焙煎店が現れます。 ただ、その最大の転機になったのは、 1990 年代半ばの、スターバックスの日本上陸だったと言えるでしょう。北米で社会現象にまでなったスターバックスが、世界に進出する足掛かりとして最初に選んだ国──それが日本だったのです。
日本に白羽の矢が立った背景には、日本のコーヒー文化が「ガラパゴス化」していて、海外に知られていなかったことも関係したと思われます。特にアメリカ人にとっては、コーヒーは自分たちがヨーロッパから教わり、日本に教えたというのが一般的なコーヒー観でした。日本独自に「こだわり文化」が進化しているなんて、当時は誰も──当の日本人たちですら──はっきりとは認識しておらず、 与し易いと思ったのかもしれません。
この成功を受けて「シアトル系」と呼ばれる、カフェラテなどを含めたエスプレッソメニューが、日本でも一気に市民権を得ます。タリーズコーヒーやセガフレード・ザネッティなどの海外企業も上陸し、ドトールコーヒーなどの国内チェーンもエスプレッソ中心のカフェを開設。個人営業のカフェでもエスプレッソを取り入れるところが増え、その中から、より本格的なイタリア式のエスプレッソを志向するバリスタたちも現れました。
また、アメリカのときと同様、日本でもスターバックスで初めて「スペシャルティ」の存在を知った人も多く、スタバの普及とともに、スペシャルティコーヒー自体の知名度も上がっていきました。日本のコーヒー関係者は前にも増してアメリカの動きに注目するようになり、ジョージ・ハウエルのように浅煎りをプレス式で抽出したコーヒーなど、シアトル系以外のアメリカのスタイルを取り入れる人々も現れます。こうして日本でもスペシャルティコーヒーの波が広がっていったのです。
その一つがフェアトレード(公正取引) コーヒー。一言で言うと「わずかな賃金で働かされているコーヒー生産者たちに、その労働に見合った公正な賃金が支払われるようにしよう」という活動理念から生まれたコーヒーです。 歴史的に見てコーヒーは、戦前は奴隷や植民地住民、戦後は発展途上国の住民から、労働力を搾取して生産されてきた作物です。そして、その現状を知った消費者の中には、生産者の窮状を解決したいと思う人々も、各時代に現れました。 19 世紀には、それがインドネシアの強制栽培への反対運動や、ブラジルでの奴隷解放につながったわけです。
当時の中米では親米派の軍事独裁政権による民衆の弾圧や搾取が横行し、それに抵抗する反政府ゲリラをソ連が支援していました。その結果、 1979 年にはニカラグア革命、 1980 年にはエルサルバドル内戦が勃発。これに対し、 1981 年に就任したタカ派のレーガン米大統領は徹底した反共主義を掲げ、ニカラグア革命政府への経済制裁、ニカラグア反共ゲリラ組織やエルサルバドルの親米政府への軍事支援などの介入を行います。
この二度目の暴落を招いたもの、それは先ほどのACPCに非加盟だった「伏兵」、ベトナムの増産です。元々は生産量も少なく目立たない産地だったベトナムは、 1986 年のドイモイ政策以降、フランスや国際通貨基金(IMF) などの資金援助も受け、気候に適したロブスタ栽培に注力していました。これが 1999 年にはブラジルに次ぐ生産量世界 2 位になるほどの急成長を見せます。
また 21 世紀以降は、国際協定の破綻にともなう未加盟国への輸出増加や、ブラジルのような生産国の経済発展に伴う国内消費の増加など、それまであまりコーヒーを飲んでいなかった地域での消費が拡大しました。顕著なのが、韓国と中国での急激な消費拡大です。 もともと茶の文化が根付いていた東アジアでは、日本のコーヒー消費が突出して多く、生活の欧米化が早かった台湾がそれに続き、韓国と中国での普及は遅れていました。
また、アメリカでは 2000 年代後半から徐々に、それまでまったく見向きもしていなかった、日本のコーヒーに注目が集まりはじめます。「サードウェーブ第二波」以降の人々が、日本製のコーヒー抽出器具を使い始めたのです。
私は典型的な「理系人間」で、じつは子供の頃から、社会科──歴史、地理、政治経済──には、今ひとつ関心を持てずにいました。大学時代にコーヒーにはまるようになってからも、まずはコーヒーの化学、生物学的な面に興味を抱いたのですが、コーヒーノキの品種についての植物学的な資料を調べていたとき、歴史や地理の知識の重要性に気付かされました。それぞれの品種が、いつ、どこで生まれて、どの地域に持ち込まれたか、その来歴や経緯を知るには、当時の時代背景を知らないと理解できなかったからです。
今は非常にありがたいことに、インターネットの普及によって、一昔前なら信じられない数の文献が……それも 18 世紀のド・サッシーのフランス語文献やユーカースの原書ですら、簡単に入手可能です。またフランス語やラテン語で書かれた原書もネット経由で英訳して、他の訳本と照らし合わせて自分でも中身が検証できる時代になりました。そうして歴史を追いかけていくうちに、生産国側だけでなく消費国との関係や、政治・経済情勢など、いろいろな事象が頭の中でやっと有機的につながってきました。知れば知るほど奥が深く、自分の勉強不足を痛感しつづける毎日です。
Posted by ブクログ
今までコーヒーの歴史については、さほど興味を持てなかったのが正直なところだったのだが、様々な珈琲豆を飲み比べするうちに、素人ながら地域ごとの特徴というべきか、共通項のようなものが感じられるようになった。だが、どうも例外が多いような…と気になって本書を紐解いた。
コーヒーの世界史というにふさわしく、原産地から貴族や庶民などへ普及していく過程や、宗教的な問題など、多くの困難が待ち受けていたことに、「たかがコーヒー」などとは口が裂けても言えなくなってしまった。
読み疲れたタイミングでコーヒーブレイクが挟まっているのも気が利いている。
コーヒー好きなら是非てにとってほしい一冊になっている。
Posted by ブクログ
カフェがメインの小説を読破していくうちに、ふと、コーヒーの歴史について気になり、この本にたどり着きました。
コーヒーという嗜好品から背景の歴史を見る。
この厚みでこの内容。くどくもなく読みやすくて良かったです。もう何回か読み返して頭にいれます。
ゲイシャ。最近の新種。どっかで聞いたことがある名前だなあと思ったら、ドラマ『遺留捜査』でした!!
Posted by ブクログ
コーヒーを主人公とした、世界の移り変わりを見ることができた。
今ではネットで意見の交流ができるが、それがない時代、コーヒーの存在と場所によって、集う場所になっていた話が面白かった。
今飲んでいるコーヒーも、より美味しく感じてくるだろう。
コーヒー好きな方へ。
コーヒーの『植物としての歴史』や『飲み物としての歴史』を著者の視点から分析した本です。
植物としての歴史は古く、大陸がまだ一つだった頃の話まで遡っています。どんな経緯で世界中にコーヒーが広がっていったのか、詳しく記述しています。
飲み物としての歴史は、人間との関わりや貿易での役割などです。個人的にはこちらの話がとても面白かったので、ぜひ。
Posted by ブクログ
コーヒーの歴史をここまで丁寧に追って新書にする著者のコーヒー愛に脱帽。前著に引き続きとても面白かった。
コーヒーの語源はアラビア語のカフワというのは知ってたが、語根から考えると睡眠欲を消し去るものを指している言葉というのは知らなかった。アラビカ種、ロブスタ種、リベリカ種の三原種。人類とお茶の出会いは5000年前、カカオは4000年前だそうだが、コーヒーノキはアフリカにあったのでもっと早い可能性は高い。イスラーム世界でのコーヒー反対運動で30000人以上が殺された。ナポレオンの大陸封鎖で絶えていた待望の本物のコーヒーが復活しヨーロッパで起きたブーム。さび病。日本での1920年代の純喫茶、70年代の自家焙煎店、90年代のスタバやスペシャルティコーヒー専門店の出現。経済動向に応じたコーヒーの価格の上下。
Posted by ブクログ
著者が前書である『コーヒーの科学』に載せることのできなかった文化的背景についてをこれでもかとばかりに詰め込んだ本。『コーヒーが廻り、世界史が廻る』よりも近代史に詳しく、政治史も絡めた内容なのでかなり歯ごたえがある。
『コーヒーの科学』を先に読んだ方がよかったかなあと……ちょっとだけ後悔した。
理系である著者の文面はちっちりとしていて、ひとつひとつを積み上げている感覚がある。事実を淡々と記載しているところもあるので、かたい印象があるもののコーヒーブレイク的なコラムが差し挟まれていて、そちらはかなり気軽に読めるし、読んでいて楽しい。
地理と歴史の知識がないので、戸惑うことも多い本だったけれど、良い勉強になったと思う。
Posted by ブクログ
読み応えのある内容。胃癌(多分)のナポレオンが死ぬ直前までコーヒーを飲みたがっていた話と、ベートーベンが毎日60粒数えてコーヒーを入れてた話に人間味を感じた。ブラジルからの豆が止まったことで、豆をうっすく使ってアメリカンが生まれた話も面白かった。サードウェーブコーヒーとゲイシャ、飲んでみたいな。
Posted by ブクログ
コーヒー好きなら頭の片隅にでも入れておくべきコーヒーの歴史。
アメリカンコーヒーとか代用コーヒーとか純喫茶とか物事とは訳在って生まれた。
同一著者による文系的?歴史な話は本書で理系な話はブルーバックスとのこと。
ということでブルーバックス「コーヒーの科学」も読んでみたい。
Posted by ブクログ
喫茶店でゆっくりする時に、この本を思い出しながら一杯頂けたらどれだけ幸せだろうか。
「プラセボ効果」とはまた違った、知ることにより美味しさの本質に迫ることが出来るんじゃないだろうか。そんな感覚を与えてくれました。
国ごとや地域ごとに歴史が述べられており、細かかったり前後したりで少々の読み辛さを感じます。
海外の戦争や革命などが関わってくるため、世界史の基本がないと大変で、図や年表などがあればもっと読みやすいかもと思いました。
日本史から短いながら面白くなり、全体的に大変興味深く読むことが出来ました。
コーヒー通史
ほぼ毎日欠かさずコーヒーを飲む私にとって、身近で親しみがあってわかりやすいコーヒー通史である。この様な本は往々にして、単にトピックス トリビアを寄せ集めただけのものが多いのだが、本書は生物 農作物としての歴史や、飲まれ方 飲む店などの文化史など複数の切り口から書き出されている所がなかなかに良い。
Posted by ブクログ
コーヒーは、戦前は奴隷や植民地住民、戦後は発展途上国の住民から、労働力を搾取して生産されてきた、とあるけどどうしてなのだろう。それだけ、コーヒーの地位が低かったということか。ビジネスとしてしかみられなかったからか。今の日本は恵まれてるけど、それもつい最近。歴史に翻弄されてきたコーヒー。コーヒーの味わい深さを感じる。
Posted by ブクログ
コーヒーに関する書籍を少しずつ読む。
世界史の中でコーヒーという文化でもあり、作物が多くの人と経済を回している。
今日の世界は何で回されているのだろうか?
Posted by ブクログ
科学の本よりも読みやすかった。しかし、理系の用語や考え方にも慣れる必要があるなと感じたのと、コーヒーという側面からそれが与えた影響を通じ的に学べたことは面白かった。
Posted by ブクログ
茶とカカオに比べるとコーヒーの歴史は浅く、はっきりと認識されたのが15世紀だという。エチオピアから中東イエメンに伝わり、オスマン帝国を経て、17世紀に本格的にヨーロッパに普及し爆発的な需要が生まれた。今後コーヒーを飲むたびにコーヒーの歴史に思いを馳せながら飲みたい。
Posted by ブクログ
歴史の勉強になればと買ってみた。
著者の博識っぷりに舌を巻く。流れは解りやすいですが、あまりの情報量に半分も飲み込めていない気がします。
珈琲を飲みながら何回か読みたいと思います。
珈琲の科学の方も読んでみます。
Posted by ブクログ
1章と2章は退屈で挫折しそうになりましたが(笑)、3章以降はすごく面白かったです☆特に一番面白かったのが、「イギリスのコーヒーハウスはイギリスの人々にとってはじめてのしらふで語り合える飲食店だった」という点。当時のコーヒーハウスは、一見さんでも常連でも貴賤貧富の別なく入店出来、中で交わされる様々な会話に参加が出来るため、1ペニー払えば大学のように何でも学べるとの評判から「ペニー・ユニバーシティ」とも呼ばれていたそうです。僕は10年前から読書会というイベントに参加していますが、生活空間の異なる様々な人たちと貴賤貧富の別なく対等に会話出来るってホント素晴らしい事だよなと改めて感じました♪
世界史と書かれていますが、京大卒の医学博士が書いただけあって非常にロジカルで説得力のある本で、ただ単に珈琲の歴史を学ぶだけでなく、その背景にある当時の世界史の勉強にもなりました♪「どこそこのコーヒーが美味しい」とか、「こうやって淹れたら美味しいよ」とかそういう情報は一切載っていないですが、単純に読み物としても楽しめますし、コーヒー好きなら是非☆
Posted by ブクログ
歴史を知れば、おいしさが変わる。
まさにその通りの一冊!
昔から世界中の人々を虜にしたコーヒーの魅力。
その小さなコーヒー豆が、世界と時間を旅して味わってきた物語。
その歴史的背景を知ることで
産地の特徴、各国のスタイル、人物のエピソードなどの知識が高まり、いつも飲むコーヒーの味がどんどん変わる。
いつもの一杯から、お気に入りのコーヒー探しの旅に出たくなる!
Posted by ブクログ
ビックリするぐらい、すごく詳しく書かれている。アラビカ種とロブスタ種ね…。コーヒーの科学も読みたいと思います。
ただ、自分には少し難しい気もしたので、5点ではなく、4点です。
Posted by ブクログ
コーヒーの発見から世界中への拡散、今日の姿までコーヒーの歴史的発展に絞って記述した本。
そういう視点で歴史を見たことが無いので新鮮。但し、古代から中世にかけての発展は少し冗長。ただ、大航海時代との絡み、植民地戦争との関係、ナポレオンの大陸封鎖令によって却って流通が促進された話、第一次大戦で北欧にコーヒーが集まった話など自分の知っている世界史にコーヒーが絡んでくると俄然話が面白くなる。つまり、ベースラインの歴史知識がある程度無いと理解が中途半端になってしまうところがある(中世のアラブでの発展の話などはイマイチピンとこない)。
その意味で日本の珈琲史は本書の珠玉。大正〜昭和前期の隠微なカフェー文化とこれに対する純喫茶、戦争でほぼ供給が途絶えたせいで戦前の文化が保存されたこと(アメリカは下手に供給があったため、薄く入れるアメリカンが発展)、スペシャリティコーヒーとスタバの攻防、アンチテーゼとしてのサードウェーブなどこれまで中途半端な理解だった用語の意味や発展の流れがよくわかる。
古代〜中世の箇所はあくまで自分の不勉強の問題なので、総じてよく纏まっている面白い書籍だと思った。
Posted by ブクログ
新書本のあるあるタイトルで一番のブームは「~の世界史」と、個人的に思う。読んだ記憶をたどると、砂糖の世界史、帳簿の世界史、傭兵の世界史、奴隷船の世界史などなど。で、珈琲だ。
著者は医大教授でありながら、コーヒーにハマりすぎて、多くのコーヒーに関するセミナーを開催し、書籍も発表している。そんなオタク教授が最初に断言。コーヒーの歴史を知っていれば、コーヒーをおいしく感じるのだ、と。
そんな前フリの本書でまず語られるのが、世界最初のコーヒー。10世紀のエチオピアで存在していたことが確認できる。やがてコーヒーはイスラム世界で拡散され、トルコのオスマン帝国やヨーロッパでアルコールの代替嗜好品としてもてはやされる。そして、コーヒーを飲む場所、カフェが作り出され、人々の憩いの場となる。
また、コーヒーの流通拡大にはフランス革命や産業革命、ナポレオン治世が密接に関わっていたことも本書では紹介される。最後はスタバ、サードウェーブなどの現代の最先端コーヒー事情について。
総じて、アルコールや食物と違い、コーヒーには世界を変えるほどのパワーはなかった。が、世界の大きなうねりにうまく乗っかって、自らの存在感を高めてきた。歴史におけるコーヒーとはそんなイメージだ。
Posted by ブクログ
ゴリゴリの遺伝・微生物学の研究者がコーヒーに惹かれて記した珈琲の歴史や地理を探る本。エチオピアのカッファ、イエメンのモカあたりから始まった珈琲が壮絶な移動を得て、様々な歴史要因、それは戦争や革命、植民地支配、ブルジョワジー、市民の台頭、工業化の中で、動き、飲まれ方も変わってきた旅を描く。すこし説明がつまらないが、とてもいい本。
Posted by ブクログ
『カフェの世界史』が物足りなかったので、そちらで紹介されていた『珈琲の世界史』を読んでみました。
・エチオピアからイエメンへ、紛争から逃れた人々がコーヒーの伝播に関わっていたのではないかという説
・イスラーム圏からヨーロッパへのコーヒー伝播ルート
・ボストン茶会事件はアメリカ独立だけでなく、紅茶からコーヒーへの転換となった
・イエメンのコーヒーノキの苗木や種子は密かに盗み出され、世界各地で栽培が始まる
・イエメンのモカ港は現在は廃墟となり、ブランド名の「モカ」が残っている。
・コーヒーの増産を支えたのは植民地や奴隷制
・奴隷解放後、ブラジルのリオのコーヒー栽培は破綻し、サンパウロは移民による労働力で栄えた
・さび病によってスリランカのコーヒー栽培は崩壊し、廃農園をリプトンが紅茶栽培に転換した
・ブラジルとアメリカのコーヒー価格をめぐる争い
・「コモディティコーヒー」の品質低下に対する「スペシャルティコーヒー」の誕生
・スターバックスに対するアンチテーゼとしての「サードウェーブ」
などなど。
コーヒーの歴史とは略奪の歴史であり、イギリス、フランスなど先進国のコーヒーブームを支えたのは植民地だったという史実がなかなか重い。大航海時代がなかったら、現代までコーヒーが飲まれることもなかったのかも。
ブラジルとアメリカの市場経済がコーヒー豆の品質を低下させるとともに、スペシャルティコーヒーを産み出したというのも興味深い。
特に、日本のコーヒー文化が独特で、「味にこだわる一杯淹て」が世界的にもめずらしいものだったというのがおもしろかったです。
以下、引用。
73
カフェハネは基本的に男性の集まる場所であり、この当時の女性同士の交流の場は公衆浴場(ハンマール)だったそうです。この「アルコール禁止・男性だけ」というルールは、カフェハネをモデルにした、イギリスのコーヒーハウスにも踏襲されています。
75
オスマン帝国の首都イスタンブルでコーヒーが本格的に普及したのは、1554年に2人のシリア人、ハキムとシャムスがカフェハネを開いたのがきっかけだと言われています。
円筒形の手回し式焙煎機やコーヒーミルなどのコーヒー専門器具も、この時代のイスタンブルで考案されたと言われており、その後のコーヒー文化や技術の発展に大きな影響を与えました。
89
恩賞として、金と家、そして敗走したオスマン兵が塹壕に残していた大量のコーヒー豆をもらったコルシツキーは、ウィーン初のカフェ「青い瓶の下の家(ホフ・ツア・ブラウエン・フラシェ)」を開いたという物語です。
「青い瓶の下の家」は彼の死後まもなく無くなりましたが、この逸話から名前を取ったのが、アメリカの「ブルーボトル・コーヒー」なのです。
92
イギリス初のコーヒーハウスは1650年にジェイコブというユダヤ人が、オックスフォードで開いた店だと言われています。ただしこの店は長続きせず、本格的な流行は1652年にアルメニア出身のパスカ・ロゼがロンドン初のコーヒーハウスを開いてから。
94
イギリスのコーヒーハウスは、イスラーム圏のカフェハネがモデルの、(少なくとも流行初期は)酒を出さない店でした。じつはイギリスの人々にとって、はじめての「素面で語り合える」飲食店だったのです。
98
1672年にアルメニア人パスカルが、サン・ジェルマンの定期市でオリエント風のコーヒー店を出したのが、パリ最初のコーヒー店だと言われています。
157
20世紀になってから、タンザニアとケニアの境にあるキリマンジャロ山の南麓、モシ地方で栽培されたコーヒーが、有名な「キリマンジャロコーヒー」のルーツです。日本では、1953年に公開されて大ヒットした、ヘミングウェイ原作の映画『キリマンジャロの雪』がきっかけで、一大ブランドになりました。
159
スリランカはさび病に蹂躙されて、コーヒー栽培を断念することになりました。その後、1890年に廃農園を訪れたトーマス・リプトンが自社で販売する紅茶を栽培することを思いつきます。スリランカが紅茶の産地として有名になったのはここからです。
160
1860年、植民地官吏だったダウエス・デッケルが「ムルタトゥーリ」の筆名で著した小説『マックス・ハーフェラール』で現地の惨状を訴えると、オランダ本国で強制栽培に対する反対世論が高まります。
現在「フェアトレードコーヒー」を認証しているマックス・ハーフェラール財団(1988年設立)の名前は、この小説から採られたものです。
171
1917年、連合国側で参戦したアメリカからヨーロッパに赴く兵士たちに、グアテマラ在住ベルギー人、ジョージ・ワシントンが考案したインスタントコーヒーが支給され、手軽さが受けて戦場で愛飲されます。
なおアメリカ初のインスタントコーヒーの特許は、シカゴ在住の日本人化学者、カトウ・サオリが、ジョージ・ワシントンより先に取得しています。
174
ブラジル政府はスイスのネスレ社に長期保存可能なインスタントコーヒーの開発を依頼しました。その後、8年の歳月をかけて完成したのが「ネスカフェ」です。
178
この消費者離れを食い止めようと、1952年、汎アメリカコーヒー局が宣伝のために作った言葉が、「コーヒーブレイク」なのです。
192
1888年、上野黒門町で鄭永慶という人物が開業した「可否茶館」が最初とされます。上流階級の社交場であった鹿鳴館に対抗して庶民の社交場を目指し、文房具室やビリヤード、トランプ、クリケット場まで備えた、欧米最先端のカフェさながらの先進的な店でした。
193
1911年3月、こうした文人たちの活動から生まれたのが銀座の「カフェー・プランタン」。
194
1911年12月開業したのが「カフェー・パウリスタ」。ブラジル移民の父と呼ばれた水野龍が開いた店です。
皇国殖民会社の社長だった水野はサンパウロ州政府から、日本からの移民の輸送に貢献した見返りに、コーヒーの無償提供を受けることになりました。
197
銀座のカフェー・ライオンの近くには「カフェー・タイガー」という店が開店し、美人ながらも素行の悪さでライオンを首になった女給が雇われて、お色気路線の営業が行われます。
198
健全路線の店、特に変な客が寄り付くことを避けようとした店は、もともと洋菓子店や台湾喫茶店が用いていた「喫茶店」を名乗るようになりました。1925年頃には、酒や女給を置く「カフェー」、これらを商わない「普通喫茶店」、そして中間的な「特殊喫茶店」という分類があったようです。
199
1930年代に日本で最初の喫茶店ブームが到来しました。この時期、1929年からの世界大恐慌でコーヒーの原料価格が低下していたことも後押しして、酒や女給を置かない喫茶店ではコーヒーがそのメニューの中心でした。このような喫茶店が1930年前半には「純喫茶」と呼ばれるようになります。
201
戦前から風俗店化していた「カフェー」のほうは、GHQによる公娼制度廃止時に多くの遊郭がカフェーや料理店に看板を付け替えたことでそれらと同一化していき、1957年の売春防止法施行でその幕を閉じました。
204
1981年にその数は個人、法人を併せて全国で15万軒を超えました。うち13万軒が個人事業主によるものです。日本で最大の喫茶店ブームの頂点にして「黄金期」と呼ぶにふさわしいのがこの時代です。
喫茶店数の急増は激しい競争を生み、一部の喫茶店主は「コーヒーのおいしさ」で他店と差別化しようと考えました。彼らが最初に力を入れたのは抽出です。ペーパードリップやネルドリップ、サイフォンなど、それぞれ自分の店に合った抽出技術に磨きをかけ、たくさんの銘柄のコーヒー豆を常備して、注文を受けるたびに1杯分ずつ抽出して提供する、いわゆる「一杯淹て」が常態化していきました。
このような「コーヒー自体のおいしさを売りにする専門店」が流行するのは、じつは歴史的に見て、とても珍しいことでした。
245
サイフォンはもともと1910年代にアメリカで大流行したのですが、とっくに廃れてしまって、器具を作りつづけていたのは日本のガラス器具会社、HARIO社などの数社だけ。そこで日本のコーヒー抽出器具がアメリカ向けに販売されるようになったのです。
246
世界からの日本への注目は、2012年、メリー・ホワイトの著書『Coffee Life in Japan』で、日本独自のコーヒー文化と喫茶店が紹介されたことで、ますます高まっています。
なかでも、この本で紹介されたダッチコーヒー(滴下式の水出しコーヒー)は「キョート・コーヒー」や「コールド・ブリュー」の名で2015年頃からアメリカで流行し、新しいトレンドとして世界に広まっています。
90年代初頭に創業
堀口珈琲(世田谷)、丸山珈琲(軽井沢)
Posted by ブクログ
本書は「珈琲の歴史を知っているのと知らないののとでは、珈琲のおいしさの感じ方が違う」、「情報のおいしさ」を楽しむためのものだという。
15世紀ごろから薬や活力剤的に飲まれ始めたコーヒーが、歴史が進むごとに味の追求されていったこと、その最先端がサードウェイブといわれるものであったりスペシャリティコーヒーであること、そして日本で、ハンドドリップなどのコーヒーが世界的に特異的であったことなど新鮮な驚きを感じた。
スペシャリティコーヒーの言葉は知っていたが、それが何を意味するのか本書を読んで知ることができ、これから、より楽しめるようにおもった。
Posted by ブクログ
思っていたより歴史の本。軽くウンチクを求めるような気持ちで読むと振り落とされます。文章自体はわかりやすく書かれており、読みやすくはあります。なんとなく知識がついた気がしました。
Posted by ブクログ
どちらかと言えばコーヒーよりも紅茶の方が好きだと思う。
そんな私が、チャイの美味しいカフェを併設する本屋さんで見つけたのがコチラの本。
あまりにも気になる本が多すぎて、いろいろ目移りしているうちに、このぐらいの新書ならまだ本棚に置けるだろう…、という理由で購入した。
いやぁ、面白かったー!
自分的世界史ブームは続いているんだが、コーヒーを軸にした世界史がこんなに面白いと思えるなんて。
そしてそんなに興味のなかったコーヒーについても、認知が変わったので口にするたび特別な感情を持ちそう。
とは言え、コーヒーの味とか全然わからないので、多分気分の問題ぐらいなんだろうけど。
この本の中で1番グッときたのはフランス革命の口火を切ることになった(のかもしれない)カフェの話。
フランス革命の後に7月王政にも繋がってくるあのオルレアン家が、当時民衆に解放していたパレ・ロワイヤルの一角で、コーヒーと共にフランス革命への種火が点けられ、大きくなっていったんだなと思うと…なんかたまらん。
さらにその後に現れたナポレオンによってもたらされた影響で、ブラジル産コーヒーがひろまる契機になったということにも、めちゃくちゃ歴史のロマンを感じた。
それにしても「〇〇の世界史」ってタイトルなら、どんな〇〇がきても楽しめるのではないか?
いまちょっと積読が増えてきたので、ひと段落したらまたこんな感じの出会いを探しに本屋さんへ出掛けよう。
Posted by ブクログ
最近自分でコーヒーを淹れることにハマっている。こんなに準備をするのが面倒くさい飲み物が、そもそもどのような経緯で飲まれるようになったのが気になり本書を手に取った。何百年からも前から存在はしていたようだが定かではないようだ。そんな話が半分ほど続き、読むのが辛くなり、読破を諦めかけた。しかし、19世紀のあたり、ファーストウェーブの話からなるほどと思える記述が増え、楽しく読むことができた。これからコーヒーを飲むとき、一味違ってくるかもしれない。
Posted by ブクログ
序盤「世界史むずかしい……」とめげそうになったけど、近世に入ってからの部分は面白く読めた。
基本はやっぱり侵略と植民地ありきの歴史ではあるけど、生産国側もただ搾取されるだけじゃなくちゃんと儲けるための考えを巡らせていたんだなぁ。
スリランカのコーヒー産業のエピソードが、特に印象に残った。
ラクで都合のいい説を信じて病害を防ぎきれずに壊滅、今の世の中では決して他人事ではないですよねー……。
それで農地が空いたからこそ多種多様で美味しいスリランカ紅茶が生産されてる今があるっていうのは歴史の妙だなぁと思いつつ、当時スリランカで作られてたコーヒーってどれだけ美味しかったんだろうって想像を巡らせるのも楽しい。
あとはやっぱり日本のコーヒー事情。
質の高いコーヒーが輸入しにくい時代から技術を磨いて美味しいコーヒー出してた昔ながらの喫茶店のマスターたち、リスペクトしちゃうよね……。
そんな昭和の自家焙煎コーヒーを飲みに、老舗の喫茶店に行きたくなってきた!
Posted by ブクログ
コーヒーの起源からその伝播の歴史、国ごとの特徴、コーヒーの品種、生産地の推移などが分かりやすくまとめられている。
起源の話では、コーヒー・ルンバという曲が「昔アラブの偉いお坊さんが~♪」と歌っていたなあ、なんて思い出した。
「ネルドリップ」とか「スペシャルティコーヒー」とか、聞いたことはあるけどよく知らなかった言葉が理解できて良かった。
Posted by ブクログ
珈琲の在り方が歴史の中で様々に変化しているのが知れて良かった。
日本で発祥した時はキャバレー的な所でお酒と一緒に振る舞われていたことは意外だった。
Posted by ブクログ
コーヒーが誕生して世界中に広まっていくまでの歴史を記した一冊。エチオピアの山中にあったコーヒーの木が周辺に伝播していくところからコーヒーの歴史はスタート。世界中に広まっていく過程では宗教や戦争の影響が色濃くみられる、特にナポレオンとコーヒーの関係が深いことには感銘を受けた。そのほかコーヒーの日本史も紹介されており、最初は「焦げ臭い」ということで敬遠されていたようだが、明治維新あたりから受け入れられて、日本独自の純喫茶文化を構築するまでに至る過程は面白かった。