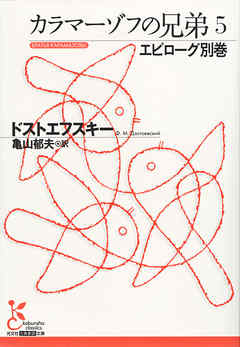あらすじ
「エピローグ」では、主人公たちのその後が描かれる。彼らそれぞれに、どんな未来が待ち受けているのか……。訳者・亀山郁夫が渾身の力で描いた「ドストエフスキーの生涯」と「解題」は、この至高の名作を味わうための傑出したすばらしいガイド=指針となるにちがいない。【光文社古典新訳文庫】
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ドストエフスキーが常に監視や検閲の元で執筆をしていたと知り、文体がとても回りくどく感じるのは本当に伝えたいことをチェックに引っかからない程度に含みをもたせた結果だったのかなと思った。
Posted by ブクログ
それぞれのその後が描かれる最終巻! →
エピローグの終わってない感もすごい。本当なら第二部があったはずなので、おそらく第二部のプロローグに繋がるんだろうな、という終わり方なんだけど……けど!!
カラマーゾフの兄弟って、未完なんですよ!私知らなくてびっくり(←下調べせずに読み始めるタイプ)続きが読みたいー!!!
Posted by ブクログ
第1巻前半は登場人物の前史のような話でつまらない。
カラマーゾフ兄弟に絡む二人の女性が登場してそのあとは俄然面白くなる。これほどプロットのある長編とは思わなかった。事前の想像より面白い。
未読の方は、世界屈指の評価を受ける小説がどんなものか、読んでみることをお勧めする。
この古典新訳文庫の5巻目は訳者亀山氏の解説が長い。
小説部分(エピローグ)が60頁、訳者解説等が300頁ほど。
エピローグは4巻に含め、5巻は解説書として販売した方が読者に親切だった。
ちなみに解説中の「ドフトエフスキーの生涯」100頁程は未読。
解題(200頁程)は、批判的に読んだ。
この作品のどこが・なぜ、過去から現在まで世界中で高く評価されているのかをまず簡潔に説明してくれた方がわかりやすい。
Posted by ブクログ
ここで終わるんだ。がまず最初の感想
3巻ぐらいから、グルーシェンカのことを可愛いなと思い始めていた私はその対局のようなカテリーナがヒステリーっぽくなるたびに、よりグルーシェンカと比べてしまった
けれどこの5巻ではアリョーシャに素直に、今の彼女の気持ちを話しているところで、少し見方が変わった。
まだイワンと、しなくていいような嫉妬や言い合いしそうだけど
幸せになってほしいなとおもえた。
私はあの、どうしようもないフィヨードルが一番好きだったから
(途中からグルーチェンカに変わった)早々の退場で残念だった
Posted by ブクログ
文学史上の最高傑作を読みたくて購読。
長く、難解なため読むのに非常に時間がかかった。
本作のテーマは、神は存在するかという点である。様々な場面で神の存在を信じる者と信じない者との対比が描かれており、その様子を楽しむことができた。
私はカラマーゾフの兄弟以外にも『罪と罰』を読んだことがあるが、当時のロシアの様子、キリスト教的価値観の揺らぎを感じることができ、非常に面白い。
全体的に理解できたとは言い難いが、各巻の後書きの解説を読みながら進めることで、理解が深まった気がする。その解説の中でも、カラマーゾフの兄弟は四楽章仕立ての交響曲的構成になっているという指摘は、フィナーレに向けて盛り上がる様子からまさにその通りだと感じた。
Posted by ブクログ
とても、面白かった。
でも振り返ってみると「大審問官」が全然理解できていなかったことがわかった。
もう一度、キリスト教について学びなおし、読み返してみてこういうことが書いてあったのかと、やっと少し理解。
ドストエフスキーの厳しいカトリック批判だなんて気が付きもしなかった
Posted by ブクログ
エピローグで何かあるかと思ったがこれもあっけなかった。
それより全体解説の「ドストエフスキーの生涯」約100ページと「解題」約200ページがわかりやすくてすばらしい。ロシア皇帝権力に対するテロ事件に影響を受けていた様子がよくわかった。単なる芸術家ではなく祖国を何とか良くしたかった。
だから第2の小説は13年後のアリョーシャやコーリャが皇帝暗殺を目指すという説に説得力がある。ドストエフスキーがもう少し長生きして執筆してくれてたら・・・。でも若い頃国家転覆の罪で銃殺刑に処されかけたのが恩赦で助かって第1の小説を書いてくれただけでも良しと考えよう。ドストエフスキー万歳!
Posted by ブクログ
「カラマーゾフの兄弟4」
「カラマーゾフの兄弟 5 エピローグ別巻」
※4.5の感想です。
これで、亀山郁夫訳のカラマーゾフの兄弟全巻を読み終えた。
長くて苦しくて楽しくて、、今まで読んだどの本にも無い読後感だった。
それはこれが、未完の大作であるからということも大きいのかと思う。
ドストエフスキーは、このエピローグまでを第一の小説とし、その13年後を描く第二の小説を念頭に置いて書いていたが、亡くなってしまったから。
にもかかわらず、この完結性の高さという、他に比べようがない(少なくとも自分が読んだ中では。)「人類の奇跡のような」作品。←訳者、亀山郁夫氏の言葉
まずは、第4巻から。
第4巻は、第10編「少年たち」という話から始まるのだけど、これが個人的に素晴らしく良くて、ドストエフスキーの、反抗的でありながらも、少年のもつ純真さや繊細さ、故の暴力性を台詞回しや出来事によって描き切る才に驚愕した。特に、後々まで重要になるコーリャという少年の描写が本当に良くて、、どことなく、スティーブン・ミルハウザーの「エドウィン・マルハウス」の世界観を思い出させた。(これも傑作中の傑作)
イワンの内面が徐々に浮かび上がる中盤、スメルジャコフとの対話のシーンは不穏で不気味、グロテスクで、なんだか自分自身の内面を暴かれているようでどきどきした。
その流れからのミーチャの裁判。
世の中の残酷な事件や、戦争、虐待。
「父殺し」という作中での直接的表現にそれらをあてはめてみると、更に先ほどのイワンの内面描写が他人事ではなく思えて今度はゾッとするのである。
そしてそれらを見つめる「わたし」の俯瞰的目線、それによって台詞の意味が補完される。
5巻にある訳者による解題での「ポリフォニー(多声)性」という手法の巧みさ!読み手により如何様にも読めるという面白味に加えて、最大の主題「神はあるのか」についてもまた、登場人物の言動や行動や、それに伴う結果のそれぞれの違いによって複雑に絡み合って、決して白か黒かでは分つことができない。
その「複雑さ」がリアルで惹きつけられる要因のひとつなのかもしれない。
またしても「二項対立の脱構築」的思考だなと、、
第5巻エピローグは、僅か63ページ。
これで本編自体は完結する。
最後のアリョーシャのスピーチを読んだとき、本当に自然に、ハラハラ涙が出て、心が動くということは多分これのことなんだなと実感した。
これまで積み上げてきた長い物語世界の、一つの側面であり大きな主題でもある、先述した「神はあるか」についての、人間としての最適解というか、本当は全ての人間がこうありたいと願っていると「思いたい」と思える、素晴らしいものだった。
143年前のロシア古典文学が、今もずっと読み継がれている理由が身に染みてよくわかった。
訳者違いで、また何度も読みたい。
素晴らしい読書体験だった。
Posted by ブクログ
カラマーゾフ万歳!
兎にも角にも続きが気になります。。
ロシア文学は苦手意識が強かったんですが、こんなに楽しめるとは想定外でした
新訳が良かったのか、亀山さん訳が自分に合ってたのか。。時間があれば原さん訳にもチャレンジしようかと!
Posted by ブクログ
日本列島が最強寒波におおわれている頃、この凍てついたロシアの地で繰り広げられる物語もまた、クライマックスへーー。
昨秋から4か月におよんだ読書の旅も、ついに完結。
いやあ、それにしても長かった。
まずはおつかれ、私!!
3巻から徐々にスピードアップしていた展開は、4巻でさらに凄みをまして、5巻のエピローグまで一気読みでした。
ミーチャ、有罪になってしまったのか、うわあ……。
そしてイワンはこれからどうやって生きていくんだろうか。
それにしても話が長くて読むのが辛くて、途中で何度も投げ出しそうになったけれど、なんとか最後までたどりついたいま、この作品と出会えて本当に良かったと思っています。
なんとなく、最近は自分の経験のなかで、小説ってこういうものだ、というイメージをもっていたのですが、それを根底からくつがえすような構成と世界観。
はじまりがあって、事件がおこって、結末をむかえて、という流れに加えて、登場人物が話すごとに、頭の中に万華鏡のような球体が形づくられて、切り取り方や光の当て方でいくらでもキラキラと見え方が変わる。
人の心の、とらえどころのなさや危うさが、あますところなく表現されている。
運命のあやで無実の罪人になってしまったミーチャに、アリョーシャがかける、
「兄さんは苦しみを受けることで、もうひとり別の人間を自分のなかに甦らせようとしたんです。ぼくに言わせれば、一生どこへ逃げようとも、そのもうひとり別の人間のことをつねに忘れずにいるだけでいいんです……それだけで兄さんは十分なんですから。」
という言葉が好き。
苦難に巻き込まれた人の、怒りや絶望を絶ち切って、人生の主導権を自分自身に取り戻す意味が込められていると思う。
5巻は、約半分が訳者の亀山郁夫による解題でしめられているけれど、本編を読み終わってから読むと、これがまためちゃくちゃ面白い。
今回は途中で挫折することをさけるために、とにかく先へ進むことを優先して読んだけど、再読の際はもっとディテールに着目して読めたらいいなあ。
細部の描写で個人的に印象に残ったのは、最後の裁判でカテリーナやラキーチンの、風俗を生業にするグルーシェニカに対する差別心がむき出しになる場面。
ドストエフスキーの冷静な観察力に驚いてしまった。
それにしても、この重量の作品を読み通すには、2020年代に生きる身としては、学生時代に読むか、社会人の場合は生活上の何かの優先順位を下げて時間をつくらないと、かなりむずかしいと感じる。
私は学生時代(はるか昔)にカラマーゾフを読まなかったので、たまたまとはいえ、人生の中でこの作品に向き合う時間を与えられたのは幸運だったと思う。
めぐり合わせに感謝しよう。
そして同じく最後までたどり着かれた皆さまも、おつかれさまでした!!
さようなら、カラマーゾフの兄弟たち、また会える日まで。
Posted by ブクログ
最終巻はエピローグが数十ページ。残りの大部分は解説となり、ドストエフスキーの生涯、解題、訳者あとがき。
エピローグのみ別巻とする配分は初めてらしい。気になる登場人物たちのその後は、アリョーシャと少年たちの未来を予感させて終わる。続編が予定されていた本作だが、刊行直後に作者が亡くなってしまい執筆されずに終わった。13年後のアリョーシャを見てみたかった……。
エピローグ部分は短いのですぐ読み終わる。その後の解説などは必ずしも読む必要はないのかもしれないが、読み飛ばす人は意外に少ないのではないか。圧倒的なエネルギーを持つ本作を読み解くには、何がしかの思考補助が有用で、訳者・亀山郁夫先生の「解題」は非常に大きな助けになった。
とても長い小説でありながら、多くの人に読まれ続ける『カラマーゾフの兄弟』。圧巻のラストを目の当たりにして、やはり人類の至宝といえる文学のひとつなのだと強い確信を抱いた。
Posted by ブクログ
最後は泣けた。
アリョーシャが、人間の、人生の真実を子どもたちに語ったその言葉は、この小説の核として奥の方で輝いていたものだ。
今までの長い物語があったからこそ、アリョーシャの言葉は胸に響いて鳴りやまない。
心が洗われるような思いのする最後だった。
Posted by ブクログ
ひとこと、重厚。
多くの人が何度も読み返す理由がわかる気がした。初回は大筋だけつかめただけだった。理解しきれなかった細部が、より気になった。
淘汰されずに、大作として読み継がれていることに納得。
Posted by ブクログ
長い物語の中で、いくつもの父と子の関係が描かれている。
ヒョードルと実子たちと私生児
二等大尉とイリューシャ
血のつながりだけではなく、「父=教え導く者」としての関係性も散見される
長老とアリョーシャ
アリョーシャとコーリャ(コーリャに父がおらず、偏った考えで突き進むところも印象的)、こどもたち
そして、ロシア正教に基づく神と登場人物たちの関係
勤めを果たさない父を持った4人のカラマーゾフの兄弟のうち、外の世界に父を求めたアリョーシャだけが、精神の安寧を、救いを得たようにみえる。
最後のシーンでアリョーシャは、両親の元で幸せに過ごす幼少期の尊さを少年たちに説くが、今後の自分たちの繋がりを強調する。
両親に恵まれなくても、求めれば導きを得られ、精神を貶めず引き上げていくことはできる、という思いが込められているように読めた。
…しかし、面白かったけど長かった!
普通の会話でも登場人物が軒並み「!」と叫んでいて、エネルギー過剰、、とやや当てられて(嵐が丘でも同じ印象を受けた)さらにイワンの1人語り問答のわけのわからなさもあって、途中ちょっと停滞しました。
でもモームが紹介している中で「冗漫で読み飛ばすこともある(大意)」と書いていたので、そっか〜理解しきれなくても一度読み通してみよう、と少し気楽に付き合えました。
ロシア正教について予備知識があった方がより面白いかな、と初心者向けのキリスト教の本を併読したことで、ドミートリーの罪の意識などが多少理解しやすくなって良かったです。
Posted by ブクログ
ずっと読んでみたかった名作。めちゃくちゃ長くてめちゃくちゃ時間かかったけど読んで良かった!
あとがきにあった、四巻+エピローグという形式は交響曲の形式と似ているっていうのにすごく納得。
第一部がアレグロ・コンブリオ(速くいきいきと)。登場人物が多い割に、時系列や人物関係、キャラクターが分かりやすくまとめられていて、さほど苦労せずに読めた印象。カラマーゾフとは何たるかを知る場面。
第二部がアダージョ(ゆっくりと)。ここが長くて辛かった!あとがきにここで挫折する人が多いとあったけど、それも頷ける。神がかり的な力を持つゾシマ長老に傾倒する無垢な三男アリョーシャと、「神がいないことで全てが許される」と説く次男イワンの対立が軸となって、ロシアの社会情勢や作者の無神論者的な考えが反映される。話の大筋には関係ないようなことが長々と語られて、交響曲であれば確実に寝てしまうところ。長ったらしい和音の中に時折魅力的なメロディや衝撃的な異音が混ざったりして、物語全体に深みをもたらす部分。特にゾシマ長老の「腐臭」の場面はかなりの衝撃だった。
第三部はスケルツォ(諧謔的に)。ここから話が一気に進み、本作のテーマである「父親殺し」に向かって話が展開していく。無類の女好きであり道化的な性格をもつ浪費家の父フョードルの性質がそのまま「カラマーゾフ」となって三兄弟にも受け継がれる。対極的な2人の美人、カテリーナとグルーシェニカ、そしてカラマーゾフ家の使用人グリゴーリーとスメルジャコフを巻き込んで、フョードル殺害をめぐる事件が起こるまでを描く。ドミートリー・イワン・アリョーシャの三兄弟がそれぞれ絡み合いながら行動し、それぞれが別の目的を持って一つの事件へと向かっていく。
第四部はモデラート・マエストーソ(ほどよい速さで厳かに)。カラマーゾフを語る上でポリフォニー(多声)的な視点というのはよく言われるが、第四部はまさにこの視点が多用される。登場人物たちの視点によって見えなかったものが見え、意味のなかった行動が意味付けされ、事件が一つの結論へと集約していく。対話によってその人物自身気付いていなかった心情に気付かされる場面や、「父殺し」の真相が明かされる場面は圧巻。そして最後の裁判シーンは最初から最後まで目が離せない急展開。陪審員の判決もまた、ドミートリーの「カラマーゾフ的」な性質を裏付けるものとなっている。
別巻のエピローグをもって完結となる本作だが、序説にもあった通り、これは「第一の小説」であり、本来は第二の小説に続くのだという。第二の小説が書かれることなく終わってしまったのは残念だが、むしろ第二の小説がないからこそ、最後の「カラマーゾフ万歳」がある種不穏で狂気的な印象を与えるのかもしれない。父親殺しの事件が一つの解決を見せ、これからアリョーシャと町の少年たちを中心とした話が始まるのだという兆しを見せるが、その未来は果たして明るいものなのか?ミーチャの脱獄が仄めかされ、カテリーナとグルーシェニカの関係も曖昧なままである。「カラマーゾフ」は女好きで道化で浪費家の象徴であった。父は殺され、長男は服役囚となり、次男は精神を病み、私生児とされるスメルジャコフは自殺した。三男のアリョーシャだけが万歳と祝福されるわけにはいかないだろう。
個人的には、カラマーゾフの血を受け継ぎながら、世間の人々やゾシマ長老、2人の兄、そして自分本位な父からも天使のようだと一目置かれていたアリョーシャの、カラマーゾフ的な一面を見てみたいと想像を膨らませてしまう。
Posted by ブクログ
エピローグは、明るい未来を感じさせるものでした。「カラマーゾフ万歳!」と青年たちが叫ぶのはよくわからなかったですが。
ドストエフスキーの生涯や解説は興味深い内容でよかったです。作品を振り返ることができました。
Posted by ブクログ
訳者による解題がとても興味深く、解題を踏まえたうえでもう一度読み直したくなりました。引っかかりを覚えた一文や、何気なく通り過ぎた箇所にそんな意味が込められていたのか、と驚きました。
謎がたくさん残る小説でしたが、とても読みごたえがありました。最後まであきらめずに読めてよかったです。でも理解しきれている自信はないので、いつかまた復習したいな。
Posted by ブクログ
まずは約2週間かけて読破できた自分を褒めたい。非常に充足した気分。
振り返ると、第一部は非常に苦しかった。正直面白くなかった。全く知らない登場人物の詳細がないまま会話ベースに話が進んでいく。誰が、どんな気持ちで話しているか読み取るのが非常に困難だった。
第二部の大審問官は実は読み飛ばしてしまった。が、これから頑張って読み直そうと思う。
第三部からは打って変わって手が止まらなくなった。少しずつ各キャラの性格や、物語の向かう先がわかってきたのと、ドストエフスキーの文章(と、訳者の亀山さんの文章)に慣れてきたのもあり、一気に読みやすくなった。
第四部は終着点。正直最後は、えっ、これで終わり?と思ってしまった。
そしていよいよエピローグ。最後、子供達とアリョーシャのやり取りを読んでいて、ふっと気持ちが軽くなった。少し、未来に希望が持てそうな気持ちだった。
そのうえで、亀山さんの解説を読むと、いろいろ納得できるところも多く、もう一度読みたいと思ってしまうのが不思議なところ。また落ち着いたらカラマーゾフの兄弟の世界に足を踏み入れてみようか。
もっと面白い本は世の中にたくさんあると思うが、それでも傑作と名高いカラマーゾフの兄弟を「読破」した側の人間になれたことが嬉しい。
万人におすすめはできないが、読書好きな人にはぜひ、読んで欲しい作品です。
Posted by ブクログ
5巻ってほんのちょっとなんだね…
ドミートリーやイワンがその後どうなったか、知りたかった
アリョーシャは宗教とどう関わっていくのだろうか。
全体を通してみると、まぁ緻密な物語。
カラマーゾフたちの性格が、最後の裁判にどう繋がっていくのか、いつか再読してたしかめたい。
Posted by ブクログ
読書として長い旅だった。数十年前は分からなかったことが少しはうなづけるようになり、ドストエフスキーの生涯と解題を読んでさらに理解が進んだ。
キリスト教と社会主義、農奴解放後の混乱という19世紀のロシア特有の空気と、著者が実生活で持つ背景が作品に及ぼす強い影響。ミーチャ、イワン、アリョーシャという3兄弟と父親、スメルジャコフやコーリャ、女性たちとの会話など、どんなに分かりやすい翻訳でも、おそらく原語が理解できないとその面白さは半分以下なのだろうと、訳者の解説を読みながら実感。それでも他作品を間に挟みつつ3か月で読み通せたのは、活力ある言葉での翻訳に徹した訳者のおかげだ。
著者が予定していた第二小説が永遠に読めないのは残念だが、ここまで5冊でも十分に体力の要る読書だったし、読み方によっては十分に完結している物語でもあった。
Posted by ブクログ
読み終わった。この本は、何をテーマにしていたのだろう。多くのことが思い起こされるが、人生と同じく、一度は考え、悩むことがたくさん盛り込まれている。そこに、裁判という小説としてのエンターテイメントも加えられている感じがした。
伝えたいのは、ドストエフスキーの思想。それをエンタメ作品にのせて吐き出した?
あまりにも評価が高いだけに、どう言っていいのかわからないが、素直に言うなら、もう一度読みたい。訳もわからず読み進めた部分、得に登場人物の深層心理を理解を深めつつ、状況の進み具合を把握しつつ読んだら、もう少し物語に没入して楽しく読めそうだ。
Posted by ブクログ
何が起きたのかは何とか理解できたが、そこから宗教や心理学、哲学に繋げることは非常に難しかった。もう一度読んだらもう少し深く理解できるのかもしれないが、そんな元気はもうない…(゚∀゚)
Posted by ブクログ
暫く間が空いたが、今日5巻を読み終えた。感想は?と聞かれると少し躊躇する。あまりにも表現が、気持ちが、そして神とのつながりや断絶が強すぎ、理解できない部分が多い。作者の神経の繊細さと激しさ、愛への狂おしいほどの猛進。兎に角もう一度読まないと理解は半分かもしれない。ロシアの人名や地名の難しさ。特に人名は下を噛みそうだし、相性と正式な呼び名の違いに混乱する。また、いつか読み直してみようとは思う本だ。
Posted by ブクログ
エピローグ。
ドミトリーとカテリーナの和解。
(引用)こうして二人は、ほとんど意味もなく、狂おしい、ことによると真実とかけはなれた言葉をたどたどしく交し合っていたが、この瞬間にはすべてが真実であり、ともにひたむきに自分の言葉を信じていたのだった。
この二人はその場の情熱で自分にも嘘を吐くし、似たもの同士なんだろうね。裁判でのカーチャの虚偽発言が有罪に導いたのは間違いないし、ミーチャは甘んじてそれを受け入れようとしているということか。
そして、イリューシャの葬儀で幕。書かれなかった第2の小説に繋がる箇所。
その後は亀山先生の解説。ドストエフスキーの生涯と評論「解題」。
ドストエフスキーはギャンブルが止まらなかったり、かなり破滅型の人だったんだな。恋愛についても(闘争の中で、奪われるという予感の中かでしか人を愛することのできないマゾヒスト)とあり、大作家はかなり問題のある性格と知った。
亀山先生の解題には、自分の読みの浅さを思い知らされた。全部書いていると限がないので、心に留めておくところを幾つか記す。
・記述のポリフォニー性。登場人物を光と影から交錯させ、作者の一方的なまなざしを許さないとある。
・破天荒なミーチャの行動に目が行ってしまうが、事件の罪人イワンの隠れた悪魔性が主題だったと思う。実行犯スメルジャコフが彼の深層心理を体現したばかりでなく、少女リーザの変身はイワンの関係性に起こっている。これは完全に読み落としていた。スメルジャコフとリーザと彼の幻影である悪魔もイワンの分身ということなんだろう。
・大審問官の説話は教会批判でキリスト批判ではないと思ったが、キリストと思しき「彼」は言葉を発していない。悪魔と手を組んだと自白する大審問官に接吻するだけ。この接吻とこの話の後にアリョーシャがイワンに与えた接吻の意味を亀山先生は注目する。アリョーシャの意味とイワンの受け取った意味が同一でないとの示唆。
・イワンは、神がなければすべてが許されている、という。スメルジャコフはそれに従う。では、神がいたならば。これがイワンの精神病を引き起こす。エピローグではイワンの命が尽きようとしていることが告げられるが、第2の小説での登場は想定されていなかったのだろうか。
・この長編の自伝性についてドストエフスキー自身の内なる父殺しについては、NHKの100分de名著でも亀山先生レクチャーしていた。それから考えても、やはりイワンを一番の主役なんだろうな。ミーチャは父の死について、特段の感情持たなかったようだし、アリョーシャには長老ゾシマの死の方が重要だったろうし。
面白かったけど、かなりの難物。いつかは再読しようと思う。
Posted by ブクログ
名作を読もうシリーズ。とっつきやすさから光文社の新訳文庫で。5巻はエピローグと訳者解説などおまけのような感じ。これで一応は、『カラマーゾフの兄弟』を読んだことがある人間になった。ほかの訳でじっくりいつか少しずつ読み直したい。
Posted by ブクログ
正直咀嚼しきれていない部分も多いが、物語全体を貫く宗教価値観・ドストエフスキーの自伝的要素等、精緻に論じられた解題のおかげで解像度が上がったと思う。振り返るとサスペンスとしての面白さは圧巻のものであった。読み返すことは当分ないかも。でもこの1ヶ月の読者体験のことはまた思い出しそう。
年内に読み切れた。来年も活字には触れ続けないと。
Posted by ブクログ
カラマーゾフの兄弟エピローグとドストエフスキーの生涯と解題と。
訳者のドストエフスキーに対する造詣の深さに驚かされる。これぞプロのお仕事。自伝的要素を含む三層構造。
未完の小説
Posted by ブクログ
読んだ本 カラマーゾフの兄弟5 ドストエフスキー 20240602
最終巻は、本文60ページで残りは「ドストエフスキーの生涯」と「解題」。なんか感想が変わっちゃうんで解説とかは読まない方なんでありゃって感じ。
エピローグっていうだけあって後日談って感じ。
しかし、読み終わって思うのは、これだけ神の在不在なんかを描きながら、奇跡らしいことが全く起こらない。死ぬ人は死んで、誰も救われない。聖人も死ねば腐臭を出すし、父殺しの裁判でも客観的事実のままに裁かれ、読者の知る事実は無にされる。ある意味身も蓋もないお話なんだよな。
神はいない。だけど必要だから人間が作った。ってのがイワンだったっけな。宗教法人はともかく、神は必要ですよね。それがどんなもんだとしても。信じたものが誰かの利益のためとか、利用されてたとかって突きつけられる残酷さって考えさせられるもんがあるんですよね。ちょっと本とは関係ないんだけど。