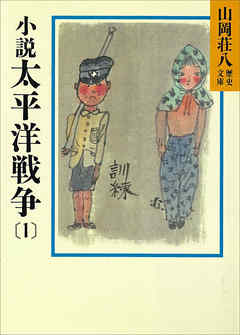あらすじ
昭和16年、日米両国は最悪の関係に陥っていた。前年の日独伊三国同盟に徹底対抗を宣するアメリカ。大統領ルーズベルトは、すでに対日戦争の肚を固めていたのだ。日本は打開策を模索し、再三交渉の特使を派遣するが……。太平洋戦争全史を描いた唯一の大河小説、今よみがえる! 全9巻。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
これは小説なのか……。
あえて、小説と銘打っているのであれば、真実に近くともそうではないことを肝に銘じて読まねばならない。
それを踏まえてでも、開戦前の外交の緊張感、東条の苦悩……
近衛のひどさに、震える(笑)
なんか近衛は現在の政治家たちに通じるものがあるので、いろいろな意味での震え。うーむ。
Posted by ブクログ
まず,本書を読み始めるのは非常に腰が重たかった。9冊というボリュームだし,歴史小説と言うには余りにも近代は近すぎたためだ。しかし,前書きを読み始めたとたんにそんな考えは吹き飛んだ。現在の太平洋戦争についての常識は,アメリカ人がこしらえたものだ。日本でそのときに何が起こっていたのか,日本人が何を考えて戦争へと突入したのか。現在の日本人として当然知っておくべきことであり,間違った見解を他人・他国の人が言った場合,それはきちんと正して行くことが,日本のことを思い散って行った人たちに対する,残された我々の義務なのだと。それがないと,やりきれない。私の祖父の兄弟2人も太平洋戦争で亡くなった。海軍と陸軍でだ。そんなに近くに戦争の犠牲者はいるのだ。戦争で亡くなったおじいちゃんの兄弟に対し,戦争の真実を知ることが私にとっては義務である,そんな思いに駆り立てられた。通常,私の歴史小説備忘録は,数巻の長編でも一つの備忘録に集約するが,今回は,1巻ずつ丁寧にまとめていこうと思う。
殺人は平時において最大の悪行である。が,戦争では,それが堂々と行われる。それも,殺しあう人々の間では直接何の怨怨もないと言うのに国家の名で堂々とだ。その殺人の量が功績となり,忠誠心を計るバロメーターとなって勝利者が決まってゆく。そのような不思議なルールの現実について,従軍経験のある著者の山岡氏は納得が出来なかった。日支事変を泥沼へ追い込んでいるものは,近衛首相や東条首相でもなければ蒋介石でもない。日支の代表者である両者が握手しそうになると,列強の間の見えざる手が動いたり,原因不明の不思議な事件が突発したりして戦線は思わぬ方向へ拡大する。前者の主役はアメリカとイギリスであり,後者は世界の赤化を目指すコミンテルンの手が動いている。それを解決して行くということは,そのまま,アメリカ,イギリス,ソ連を敵に回して戦わなければならないということと同義であった。
山岡氏は三十四歳の時,徴用令書を受け取っている。家を出るときは,自分の位牌を仏壇の隅に隠して行ったらしい。自分で自分を殺してゆけば気が楽だとでも思ったのだろう。そんな山岡氏が復員した中で一番辛かったのが,占領軍が日々ラジオで語りかけてくる「太平洋戦争の真相はこうだ!」という独善放送だった。日本国民がいかにして巧妙に大本営や軍部に欺かれ,踊らされていた愚民であったかという放送が,これでもかというほど続けられた。連合軍側は全て正しく,日本の散華者はみな犬死という,ありえないような戦争が日本民族の手で強行されたと言っても誰も信じるものはないが,しかし,それに関する反論の仕方さえわからないのではこの独善放送や戦後の誤った史観に対し,批判の仕様がない。山岡氏が十年間に渡りこの小説を連載していったのは,何のためにこの戦争は起こり,どのような結果を辿って敗れたのか,その粗筋だけでも読みやすく書き残しておくことが従軍した責任でもあったと綴っている。
日本と蒋介石が提携し,緊密化して行けば一番困るのは自由主義世界の諸国ではなく,アジア赤化を目指す勢力のはずであった。両者の間に紛争を起こさせるのは赤色革命の常道であった。盧溝橋の最初の撃ち合いは日本側の発砲でも蒋介石側の発砲でもなく,赤化勢力の仕業だった。にもかかわらず,日本側は蒋介石に挑戦されたと勘違いし,蒋介石側は日本軍に挑まれたと誤解した。近衛内閣の外相松岡洋右は,日支事変の解決には3つの大きな障碍があると近衛に語った。一つはコミンテルンの日支赤化方策,一つは日本にも蒋介石にも適当に干渉し適当に威圧を加えながら双方へ軍需物資を売っている米英両国の商人たち,そしてもう一つは,日本の内部における少壮軍人の下克上であると。
ただ,松岡外相も,今となってはアメリカの仲裁によるほか支那事変の解決の手段はないと考えた。アメリカがその気になれば,援助物資を断たれるのを恐れて,蒋介石もいやとはいえないだろうということだ。そして,日本もアメリカに首根っこを押さえつけられている。日本が今まで支那で戦い得たのは,アメリカの供給するくず鉄と石油のおかげだったからだ。松岡の目的の全ては,アメリカの仲裁による日支の和平であり,日米戦争の回避であった。
そんな日本の周りには,ソ連のスターリン,ドイツのヒットラー,アメリカのルーズベルト,イギリスのチャーチル,支那大陸の蒋介石がおり,世界の勝負は5人の男に握られていると言っても良かった。この5人の動向をいち早く・確実に掴むことが,国を存続させていく最低で最大の条件であった。米英は既に,支那事変からはっきりと日本の敵に回っている。米英が蒋介石を援助しなければ,とうに事変は解決していることを誰よりもわかっているのも彼らだ。その意味では,当時の支那軍は,米英とソ連の傭兵のようなものだ。支那軍は,ソ連と白欧主義の武器を持たされて,彼らの戦略のために同種の日本人と殺しあいを演じている。ソ連は日本と支那を戦わせ,双方を疲労のどん底に突き落とし,そこに共産政権を樹立して支那も満州も日本も一挙に赤化併呑しようというのが狙いだった。米英もそうしたソ連の方針は悉知しているし,やがてソ連が米英の前に立ち塞がる敵ということも分かっている。だが,彼らは白欧文明の支配者意識におごりきり,日本がやがて彼らの大切な協力者に育つのだと言う一点に目を塞ぎ,思い上がっている軍部を懲らしめるために正義感を燃やしていたのだ。もし,日本が滅び去ったら,ソ連の赤化は成功し,米英の自由は最大限に脅かされるということを見落としていた。
ルーズベルトの懸念と言えば国内の戦争反対の圧倒的な世論であった。彼は3選という異例の大統領選挙中に,皆さんの子供は戦争に引き出さないと公約もしているのだ。だが,当選後は彼は蒋介石に武器援助を開始した。こんな彼が日本に好条件で握手しようと言う提案を持ってきた。これを松岡外相は,アメリカにそんな意志はなく,単なる時間稼ぎで,出来れば会戦の口実を日本に作らせようとする罠であろうと,提案受け入れに前向きな近衛首相につっかかった。結局彼は更迭され,日本はまんまとアメリカの策略にはまって行く。戦時の指導者と国民ほど皮肉なものはない。誰が巧に国民を欺いて駆使し得るかにかかってゆく。ただ,この場合の国民欺瞞はそれを”勝利”に繋ぎ得れば救国の英雄とされ,”敗北”の側に回ると,哀れな最期を遂げざるを得なくなるのだ。
日本はアメリカに欺かれた。日本はアメリカに屈服すること無しに何事もなしえない属国のようなものだとアメリカはたかをくくっている。彼らはただ日本を激昂させ,日本から開戦の口火を切らせ,アメリカ国内世論を戦争に向かわせれば良いと考えているのだった。
そんな中,ドイツがソ連へ侵攻する。ドイツ軍の快進撃に,陸軍の少壮分子は世界中をドイツに取られてしまうと声を上げる。そんな声に押されて,南部仏印(第二次世界大戦下におけるフランス領インドシナ)に侵攻する。それをきっかけに,アメリカは日本の在米資産を凍結し,石油輸出もストップした。これで,戦争になれば1年から1年半で石油貯蔵がなくなるという事態に陥ったのだ。アメリカと戦って勝算があるのか,天皇が軍令部総長の永野にご下問した。永野は,座して屈服するわけに行かず,ほかに活きる道はないと言ったようだ。天皇も,それではこれは捨て鉢の戦ではないかとおっしゃられたという。天皇は日米開戦に絶対反対なのは明白な事実だった。日本人にとって,天皇と皇室は絶対であり,道徳そのものだった。御前会議でも天皇の意志は戦争に反対なのは明白であったが,専横を恐れ,小心で律儀な政務家の近衛の決断力のなさが,戦争を止めることが出来なかった一因でもあるのだろう。
そんな公卿首相に東条は『人間はたまに清水の舞台から目をつぶって飛び降りることも必要ですよ』と言った。この言葉が,後々まで開戦の決意を促したとして,東京裁判でも問題になったが,東条は,必ずしも開戦の決意を迫ったのではなかったのではないか。天皇の意を汲み取り,戦争してはならないときっぱり言うべきだと言いたかったのではないか。
東条は,総理の煮え切れなさに腹を立てて言う。日本軍が満州から退き,防共駐兵を譲ると,支那全土は瞬く間に共産軍に占領される。これはアジアを赤化するかもしれない重大な問題だ。防共駐兵を譲れば交渉が妥結する確証があるなら別だが,確証はないと。東条はここで,開戦も止むを得ずと思うとも発言した。東条は確信していた。開戦を回避することは困難であると。アメリカ側に有色人種も含めて真に平等にものを考えていく習慣はまだ全くない。地球は白人のためにあると。日本がどれだけ良心的であろうと,戦を避けようとしても無駄であると。
その東条は,元首相7人で構成される重臣会議で首相に推薦される。陛下の意志には身を挺して主旨に沿うし,軍部の信用もあり,外交交渉の折に陸軍の少壮分子の主戦論を抑えることが出来ると。東条が首相に推薦された理由は他にもある。それは,責任回避の空気だ。みなが戦争は回避したいと思っている。でも戦争は回避できそうもない。その責任者にはなりたくないのだ。そんな感じだから,政府はあっても無政府状態となり,結局は責任ある行動がとれず,戦争に流れていったのかもしれない。これも開戦となった大きな理由の一つだろう。
しかし東条は天皇の意志が戦争回避にあるなら,それを貫こうとする。首相指名を受け,閣僚の人選に移るが,陸軍内の戦争へ向かって付き進むような閣僚推薦名簿には目もくれず,自分で人事を決めた。そして,陸軍の発言を抑えるために陸軍大臣と,警察権を手中にしておくため内務大臣を兼任した。
アメリカの思いは,日本もまたアジアのヒットラーであるということだ。その中心勢力は軍部であり,最後にはこれを叩きのめして懲らしめてやることが彼ら白人の言う正義のために絶対必要だと言うことだった。従って,日本が絶対服従の答えを出すのでなければ無意味と言うことは明らかだった。日本は様々な外交を駆使し,また,譲歩案も持参し,平和に努力した。中国における日本の地位さえも犠牲に共しかねまじき態度を示した。しかしアメリカは日本を許さず,またただ許さないだけ出なく,まず日本に最初の一発を発砲させることのみに苦心した。こんな状況下におかれて,日本人はどうすればよかったのだろうか。現に,インド,ビルマ,マレー,ジャワ,カンボジアなどは米英の支配の下で見るも無残な奴隷生活を強いられている。日本人はそんな現実を知っており,座してそうなるか,一縷の望みを胸に戦うのか,ぎりぎりの選択を迫られた。そんな極度の緊張を強いられることで,明治人の性根が再び頭を出してきた。日本国内では,直ちに開戦せよという声が国民大衆の声にまで膨らんできていた。
日本が開戦することを決意したのは,ルーズベルトの世界政策であったが,日本側で天皇はじめ,東条,などの平和の希望を一挙に吹き飛ばしてしまったのは,実は白人支配の地上の不合理に気付いて,外交交渉を行う前線と一つになって激怒した民衆の声であった。
ここで,山本五十六という,現連合艦隊司令長官の登場である。山本は日本海軍の使い方としては,独伊への奉仕に使うのでは,米英への奉仕に使うのとなんら変わりはない,白人利己主義から人類解放という全有色人種のために日本海軍は使うべきなのだというのが持論があった。ただそんな思いももはやこんな段階になって言っても仕方がない。挑みかかられれば,職責を果たすのみであった。
黒船来航以来,明治維新の根本には和魂洋才の思想が根を下ろしていた。独立を保持せんがために彼らの文明を吸収するのだと言う強い意志があった。それに対し,はじめはアメリカも同情の念があった。しかし,ロシアの抑え手である日本は好もしいが,アジアの強国になる日本は好もしくなかったに違いない。日露戦争の折にはアメリカは日本を応援したが,日本海海戦における日本軍の大勝利を見たとたん,急にこれを恐れて大西洋艦隊を回航してまで日本海軍を威嚇したりしたことでもそれはわかる。これを見た山本は日米対立は遠からずくるものと想定し,大艦巨砲時代から航空兵力の充実を提唱した。それに伴って飛行機の国産に乗り出し,上昇力・戦闘力ともに世界の目をみはらせた零式戦闘機が開発したのである。ただ,これらが悪循環し,アメリカは日本を,日本はアメリカを仮想敵国とし,太平洋での熱戦を展開しなければならなくなった。ここはしっかりと歴史の教訓として覚えておかなければならない。
一旦開戦となれば,日本陸軍はまず東南アジアに進出して,アメリカの売らなくなった石油の入手を計らなければならない。そのためには,陸軍の策戦海域にアメリカ海軍の出動を許してはならず,それを許さぬためには真珠湾に出てきているアメリカの太平洋艦隊主力に壊滅的な打撃を与えておかなければならない。これは小学生でもわかるようなことである。それをアメリカは予想できず,真珠湾を奇襲されたと言う。おかしなはなしではないか。
1941年12月8日の決戦前夜はどのようであったか。11月27日のアメリカのマーシャル参謀総長は,ハル・ノートに示した白人第一主義とも言うべき要求を日本が受諾する可能性はほとんどないこと,そして,その結果日本から先に敵対行動に出る事を期待していること,その際のアメリカ側の策戦計画も出来上がっていることをカリブ海の基地司令官宛に発していた。また奇襲の2時間余り前にも,ハワイ・フィリピン・パナマその他の前哨基地に特に警戒するよう打電している。これは,もはや奇襲とはいわない。アメリカ側から挑発した戦であり,彼らが日本にまず第一発を打たせる事によって自国の民衆を第2次大戦に参加させようとして,営々と苦心を重ねてきた結果なのである。日本が平和に解決せんがために様々な妥協案を提示したにもかかわらず。
そしてその時はやってきた。まだ世は明け放れず,月も落ちきってはいない時間に戦闘ラッパは鳴り響いた。有色人種の最初の反撃だ。ここ数百年,思うままに地球支配を続けてきて,次第に良心を麻痺させていった白人たちへの最初にして最大の警告だった。ただし,どんな場合にも非戦闘員に銃撃を加えたり,一般市民の頭上に爆弾を落としたりして日本人の名誉を損ずることのないようにという訓示は徹底されていた。結果として,真珠湾攻撃では,真珠湾の隣のホノルル市街地には何の被害も無い。後のアメリカの日本都市の無差別爆撃や原爆投下のような一般市民を巻き込みはしなかった。日本人の誇りとして。
なお,備忘中の言葉は小説の記載によりました。