無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
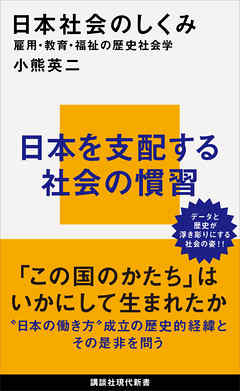
いま、日本社会は停滞の渦中にある。その原因のひとつが「労働環境の硬直化・悪化」だ。長時間労働のわりに生産性が低く、人材の流動性も低く、正社員と非正規労働者のあいだの賃金格差は拡大している。 こうした背景を受け「働き方改革」が唱えられ始めるも、日本社会が歴史的に作り上げてきた「慣習(しくみ)」が私たちを呪縛する。 新卒一括採用、定期人事異動、定年制などの特徴を持つ「社会のしくみ」=「日本型雇用」は、なぜ誕生し、いかなる経緯で他の先進国とは異なる独自のシステムとして社会に根付いたのか? 本書では、日本の雇用、教育、社会保障、政治、アイデンティティ、ライフスタイルまで規定している「社会のしくみ」を、データと歴史を駆使して解明する。【本書の構成】第1章 日本社会の「3つの生き方」第2章 日本の働き方、世界の働き方第3章 歴史のはたらき第4章 「日本型雇用」の起源第5章 慣行の形成第6章 民主化と「社員の平等」第7章 高度成長と「職能資格」第8章 「一億総中流」から「新たな二重構造」へ終章 「社会のしくみ」と「正義」のありか
...続きを読む※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。