無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
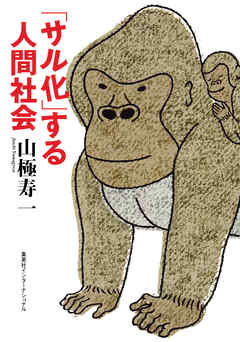
「上下関係」も「勝ち負け」もないゴリラ社会。厳格な序列社会を形成し、個人の利益と効率を優先するサル社会。個食や通信革命がもたらした極端な個人主義。そして、家族の崩壊。いま、人間社会は限りなくサル社会に近づいているのではないか。霊長類研究の世界的権威は、そう警鐘をならす。なぜ、家族は必要なのかを説く、慧眼の一冊。 ・ヒトの睾丸は、チンパンジーより小さく、ゴリラより大きい。その事実からわかる進化の謎とは? ・言葉が誕生する前、人間はどうコミュニケーションしていたのか? ・ゴリラは歌う。どんな時に、何のために? その答えは、本書にあります。
...続きを読む※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。