無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
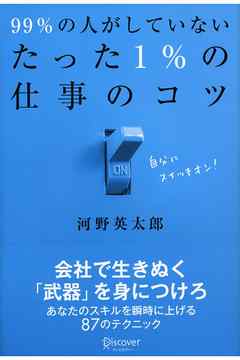
「まじめ」と「みじめ」は紙一重!?
はきちがえた「まじめ」さは、「みじめ」な結果を招きます。仕事を効率的に進め、着実に目標を達成するための今すぐできる仕事のヒント、教えます。
こんなことはありませんか?
・とにかく仕事がたまる
・上司によく無視される
・命がけでつくった書類を見てもらえない
・「言ってることがわからない」と言われる
・会議で反対ばかりされる
・自分にだけ、メールの返信がこない(遅い)
・いつもあら探しされる
・いつもあとまわしにされる
・いい仕事は全部他人にもっていかれる
・やり直しばかりさせられる
まじめにやっているのになぜか報われない……
そんな人は、その「やり方」を見直す必要があるかもしれません。
まじめさとパフォーマンスは決して正比例ではありません。
悪い意味で「まじめ」すぎると、パフォーマンスは逆に下がるのです。
デキる人とは、このまじめの「力のかけかた」を知っています。
そこにはちょっとしたコツがあります。
このコツを知っているか知らないかは、あなたのパフォーマンスをとても大きく左右します。
実は99%の人がしていない、ちょっとした、でも効果絶大な仕事のコツを、本書では紹介していきます。
読後すぐ実行いただければ、突然、そして飛躍的に仕事がうまくいくことに、あなた自身、驚くでしょう。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
たくさん線引いた
全般的に線を引いたが、特に目標達成の章のマインドには、少し救われた気がする。
ストレスがかかった時に、必ず読む本がある、というのも相性が良かったな、この本、と思えました。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。