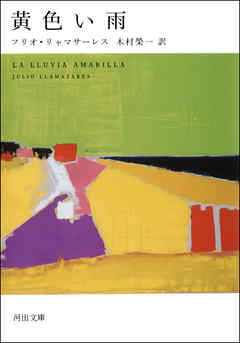あらすじ
比類なき崩壊の詩情、奇蹟の幻想譚。スペイン山奥の廃村で朽ちゆく男を描く、圧倒的死の予感に満ちた表題作に加え、傑作短篇「遮断機のない踏切」「不滅の小説」の二篇を収録。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
物語を語っているのは何者なのか?
生きた者なのかそれとも死んだ者の記憶が語っているのだろうか?
物語はピレネーの山にある小さな廃村の話だ。
しかし、はじめのうちは何が書かれているのかを手探りのように読み進めていくことになる。
必然的にじっくりと辛抱強く読むことになるのだが、やがてその内に少しずつその背景が、全貌が明らかになってくる。
村からは人々が消え去り、自らの子どもや妻さえも。そこで、老人はただひとり、唯一の友である雌犬とともに記憶と時間の中をさまよいながら過ごすのだ。
圧倒的な哀しみのテンションで書き綴られ、ラテン文学の特徴なのか、時間が行ったり来たりして迷宮をさまよっているような感覚にもなる。
冬には雪が果てしなく降り積もり、秋にはポプラの雨が降り注ぐ。常に死の予感とともに。
強さと弱さ、深い愛情が自ずと感じ取れる、哀しくも美しい物語だった。
Posted by ブクログ
スペインに実在し、廃村となった消滅集落に1人最後まで残り、崩壊していく村、去っていく人や死んでいく人や家族、自分の死を回想し、詩情溢れる文章で綴られた小説。黄色い雨は、秋の落ち葉の色であり、時間の経過であり、村の淀んだ空気の色でもある。救いのない暗い話だが、美しい詩的な文章が際立っていて憂鬱な気分にはならない。現実の問題だけに考えさせられる小説である。
哀愁ある作品
淡々と進んでいく。故郷の村も自分も死へと近づいていく。読んでいくうちに時間の感覚がなくなる。この歩みに委ねて、本を楽しんだ
Posted by ブクログ
たったひとりで、過疎化した村の終わりを見届けた男の話だった。孤独に死に向き合う語りが胸を打つ。
主人公は死ぬまでの果てしなく思える年月を過ごしたあと、死んでからの真に果てしない時をも過ごしている。荒廃した村に流れる時間が、まるで止まっているような錯覚を引き起こし、不思議な体験ができた。
主人公の生まれ育った土地であるし、戦争から息子が帰ってくる、娘の墓があると思えば移住が選択肢に入ってこないのもやむを得ない。生活があったかつての村の姿を知るだけに孤独感は増すと想像できる。サビーナの自死、雌犬の最期は特に深い悲しみが襲ってきた。
現在と過去と未来のすべてが主人公の記憶の中で一体となり、最後はただ安らかに眠りたいという思念が土地に残っているかのよう。まるでゆっくりとした走馬灯。人間は死後もこんなふうに考え続けているのだとしたら、救いがない。
Posted by ブクログ
①文体★★★★★
②読後余韻★★★★★
こちらは廃墟、廃村が主な舞台となっている小説で、一人の男の死を村の消滅にかさねて描かれています。
語り手はその男による死者の視点。これが不思議な設定で、彼の回想や死に行く過程が語られています。その孤独のなかで生と死の境界が淡くなり、昼と夜の境が無くなっていくのが読んでいて感じます。季節の移り変わりとともに朽ち果てていく家や村、はなれていく人、死に行く人。ポプラの枯葉とともに降りしきる黄色い雨。深い沈黙の中に消えていく記憶。
この何とも退廃的な状況を詩人である著者の透明感溢れる文章で綴られているのがとても印象的でした。そこには死が漂っているのにもかかわらず、なぜか美しさを感じます。
Posted by ブクログ
・文体の美しさ。
・簡素な舞台と、奥深さ。
・不吉さ。
・幽霊。
・雌犬の存在。
・悲しくも優しいまなざし。
・異文化。
出会えてよかった本。
@
以上は、2012年、ヴィレッジブックス単行本初読時の、きれぎれの感想。
以下は、10年経って2022年5月、河出文庫で再読しての感想。
文庫版では短編をふたつ(「遮断機のない踏切」「不滅の小説」)収録。
まずは、初読後10年、本書を思い出すたびに脳裏に描かれていた、カバーイラストの美しさについて。
ニコラ・ド・スタール(露: Сталь, Никола де、仏: Nicolas de Staël、1914年1月5日 - 1955年3月16日)という画家の作品らしい。
ロシアで生まれたがロシア革命を逃れ欧州方々に移り最終的には自殺したんだとか……。
ただ黄色い絵ということではなく、ちゃんとした文脈がありそうだ。
古屋美登里が豊崎由美との対談で類推していわく、訳者である木村榮一が某新潮社や某白水社に持ち込んだにもかかわらず門前払いされたあと、ソニー・マガジンズの海外文学に積極的な編集者に辿り着いた結果、出版にこぎ着けたのだろう、と。
その(想像の中の)編集者に感謝。
このカバーイラストを選んだもその編集者なんじゃないか(と勝手に想像を重ねてしまう)。
また今回は連想を拡げながら読み返せたのもよかった。
・2014年に読んだ、フアン・ルルフォ「ペドロ・パラモ」1955。墓の下からの語り……コマラという町そのものの……と、いつ死んだか判然としない語り手の一人称と、は重なり合っている。生者と死者の境界は曖昧なのだということ。
・幽霊の語りという点で、2017年デヴィッド・ロウリー「A GHOST STORY ア・ゴースト・ストーリー」も。
・ビクトル・エリセ「ミツバチのささやき」などの風景。
・やや無理矢理だが、押井守「天使のたまご」の、窓のこちらと向こうという構図も。
・前回読んだときは読後ネットで探すことをしなかったが、今回いろいろ検索してみて、なんと作者自身が(本当に実在した)アイニェーリェの跡を訪れた動画を見つけて……胸塞がる思い。それこそアナ・トレントが成人して「ミツバチのささやき」の舞台を訪れたときの映像に近い。
ポプラの枯れ葉がまるで雨のように。
落ち葉をサクサク踏んだり、戯れに蹴り飛ばしながら歩いたりする季節があるが(いや、銀杏並木だった)、あれは死の上を歩いていたのだった。
死を目前にしたとき……たとえば癌で入院して余命数年というときに……必ず読み返したいと決めた、筆頭作品。
Posted by ブクログ
寂れゆく村に一人取り残される老人。
圧倒的な孤独と寂寥感が漂う、散文詩のような幻想譚。
木村榮一の訳が素晴らしく、硬質で乾いた文章と絵画的な世界観に魅了された。
Posted by ブクログ
すとん、と、心が落ちていきます。
周囲にひたひたと、孤独が満ちていきます。
黒い闇のようで、でもそれは黄色い雨です。
スペインの山奥の棄てられつつある村で、最後の男はどこから、この世のものでは無くなったのかわかりません。
自分の最期も、こんな風にひとりで、じわじわと彼方側との境がわからなくなるのかな。
とてつもない空気でした。孤独と哀しみは、近いようでそうではない気がします。
後編ふたつの狂気も好きでした。列車の通らなくなった線路で、踏切に遮断機をおろし続ける男。創作に没頭して妄執にかられる男。
小説だけど詩のようでした。
これからも読んでいきたい作家さんです。
Posted by ブクログ
何と美しい退廃であろうか、と、読後に本を閉じたまま、暫し呆然としてしまった。
まるで叙情詩のような手触りだったと思う。文章の流麗さということがまず一つ、その要因として挙げられるだろう。
それから、語り手が自らの心象風景を一人称で独白する文体である、ということも効果的だと感じた。読み返して気付いたのだけれど、会話文のカギカッコが一つもない。語り手以外の人物のセリフというものがそもそも一つしかないのだけれど、それも語り手の内言語にいつしかすり替わって、その独白の一部になってしまう。つまり外言語を排除することで語り手の内面に焦点が向くように仕掛けられているのかもしれない。
「彼ら」という言葉の暗喩的な響きや、次第に明かされていく「私」の正体、そして象徴的に繰り返される「黄色い雨」というフレーズが幻想さを強めている。それから段落ごとに一行空けて文頭を一文字上げるという独特なスタイルも、この文字列がただの小説ではないことを物語っているように見える。
また、読中にアンナ・カヴァンの『氷』を思い浮かべた。あれを、私は「ヘロイン中毒患者の死際の幻覚」と解釈したのだけれど、それに似たものがあったように感じる。
語り手である「私」が既に死んでいることは文中で次第に明らかにされるが、実際のところ「私」はまだ死の直後か、あるいはまさに死ぬその瞬間か、彼岸と此岸の境目のところを漂っている状態なのではないだろうか。
死ぬ間際に見る幻覚、もしくは死の直後の意識、彼岸と此岸の境目で見る景色というのはこのようなものなのかもしれない。
Posted by ブクログ
表題作を読み進めると季節的に今がぴったりだなと思いながら読んでいた。孤独や過去、亡霊と向き合い、側にいる雌犬と黄色い雨が降るこの村で死を待つお話。一人語りが続き、声帯を震わせた言葉は出てこない。静まり返り、朽ちていく村で言葉を発したところで誰かに(読んでいる自分のところにも)届くわけではないのだから。というような感じでずっと地の文が続きます。
終盤では私(父)が語り手だと思っていたのに、急に息子のアンドレスが語り手かのようにふるまう所でかなり混乱した(妻はサビーナってまだ言っているし)。語り手の私の命が尽きようとして全てが混沌としていく中で色んな境界が曖昧になっていき、このような語り口になったのかななんて考えてみたり。あとは訳者あとがきで驚いたのは舞台となるアイニェーリェ村は実在していたこと(すでに廃村)。他に短編が2つあるのだけどどちらも面白かった。
Posted by ブクログ
花ちゃんに出会ったばかりの頃におすすめして貰った本を、六年越しに見つけた。snowdropに売っていた。時間はかかるけれど、僕は忘れない。
黄色のことを真剣に考えたことがなかったと気付かされた。見過ごしてきた。この作品では、死に近しいものとして描かれている。そこに付随する懐かしさや風化してゆくさまなどと共に。
黄色というと、稲穂の実りや夕暮れのきらめきなどを想像する。黄色とは僕にとって一瞬間の光景であったのかもしれない。だからこそこの作品で段々と黄色に染まってゆく村の景色が新鮮で、それが死という永遠に向かってゆく道程がうつくしかった。
Posted by ブクログ
朽ちていく村に一人残った男。彼が生きているのか死んでいるのか、境目が曖昧に溶けていく。音もなく降る雪のような感触の文章にいつの間にか引き込まれていった。
Posted by ブクログ
百年の孤独の舞台マコンドを想起させられる。
嵐のように畳み掛けるが如く滅び去るマコンドではなく、
じりじりと時間を費やして滅ぶマコンド。
時間を費やすというとうよりも
無時間、時間感覚の不確かさ。
男は、いつ死んだのか定かではない。
生と死の境もあやふやであり、
たしかなことは村が滅びること、家も人も土に帰ること。
短い小説だが、言葉の密度と緊張感を徹頭徹尾、
維持している事が素晴らしい。