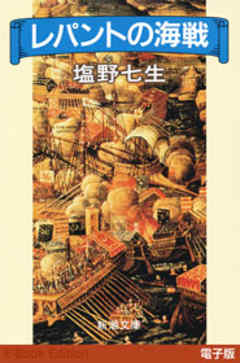あらすじ
西暦1571年、スペイン王フェリペ二世率いる西欧連合艦隊は、無敵トルコをついに破った。コンスタンティノープルの攻略から118年にして、トルコの地中海世界制覇の野望は潰えたのだ。しかし同時に、この戦いを契機に、海洋国家ヴェネツィアにも、歴史の主要舞台だった地中海にも、落日の陽が差し始めようとしていた――。文明の交代期に生きた男たちを壮大に描く三部作、ここに完結!
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
地中海三部作の完結編。塩野さんのヴェネチア愛が溢れる最後の輝きのレパントの海戦。前も書いたのだが、スペイン無敵艦隊がイスラムの大国オスマントルコを倒したという教科書的なまとめは、あまりにもおこがましいと、感じる内容。アドリア海の女王ヴェネチアを抜きには勝利はなかっただろう。コンスタンチノープル陥落が最新兵器・大砲が勝利の決め手であったように、レパントではガレアッチァという砲撃ができる最新兵器が大きな意味を持っていた。アルマダの海戦が1588年だから、17年しかスペインの海軍の栄光は続かなかったんだなぁ。
Posted by ブクログ
1571年西欧連合艦隊は無敵トルコを打ち破った
コンスタンティノープルの陥落から118年
同時に地中海の時代から大西洋の時代に変わっていった
戦闘は西欧軍の圧勝 日本海海戦のよう
ベネチアの地中海覇権を辛くも守れたが
もはや単独ではなく、スペイン王が主体である
これも世界史の変遷の一コマ
Posted by ブクログ
西暦1571年、スペイン王フェリペ二世率いる西欧連合艦隊は、無敵トルコをついに破った。コンスタンティノープルの攻略から118年にして、トルコの地中海世界制覇の野望は潰えたのだ。しかし同時に、この戦いを契機に、海洋国家ヴェネツィアにも、歴史の主要舞台だった地中海にも、落日の陽が差し始めようとしていた。文明の交代期に生きた男たちを壮大に描く三部作、ここに完結。
「コンスタンティノープルの陥落 」「ロードス島攻防記」から続く一作。
迫りくるオスマントルコ帝国の脅威に立ち上がったヴェネツィア共和国を中心とした地中海世界。
レパントの海戦は、ガレー船が主力を成す大海戦としては最後の海戦となったが、十字架を先頭にして闘われた最後の戦闘にもなった。
キリスト教勢が一枚岩にいかないのは相変わらずではあるが、薄氷を踏むような勝利を収めたにも関わらずその影響力を次に活かすことが出来なかった。
ヴェネツィア共和国もトルコ帝国もレパントの海戦を機に衰亡の一途をたどることになる。両国の力の衰退だけが原因ではなく、その後、西ヨーロッパ地域が世界の中心になり、地中海世界は歴史の主人公の座を降りた。
Posted by ブクログ
ヴェネツィア共和国を中心としたキリスト教国家と、強大なイスラム教国家トルコとの海戦です。
十字の旗を掲げての最後の海戦であり、地中海覇権の分水嶺と言えます。
ヴェネツィアとトルコは地中海での貿易経済に依存していましたが、スレイマン没後のトルコでは反欧が盛り上がります。
血を流さない戦争、血を流す政治、血を流さない戦争を駆け抜けた二国ですが、経済を停滞させたことで自ら首を絞める結果に終わります。
地中海世界全体の緩やかな衰退が見える一冊。
Posted by ブクログ
塩野七生の「コンスタンティノープルの陥落」「ロードス島攻防記」「レパントの海戦」三部作の最後の一つ。
強大なトルコがキプロスを攻略して我が物とし、その後クレタ島を攻略してクレタ島は陥落寸前であった。トルコは東地中海の覇権を確保しつつあり、ベネチアは支配地域だったキプロスを失い、その上クレタまで失い、海洋通商国家としてトルコと通商関係を破棄ししてでも対決せざるを得ない状況にあった。
しかし、東の超大国トルコに対してヨーロッパの結束は心許ない状況であり、ローマ法王の権威は低くヨーロッパ各国が領土争いをしていたため、ローマ法王が対トルコの十字軍をなかなか結成できない状態だった。そういった中で、ベネチアが対イスラムの十字軍としてヨーロッパ各国をまとめ、トルコと対決するのは並大抵の努力ではなかった。
そのベネチア外交によるヨーロッパ各国の政治的駆け引き、そして決戦となるレパントの海戦がベネチアの男たちの活躍を通じて描かれている。
手こぎのガレー船が主体であった時代に、ベネチアの最新兵器である浮かぶ砲台とも言える重装備船からの砲撃はベネチアの海軍力の技術力と強さを見せつける。
結果的にガレー船による最後の大海戦となったレパントの海戦は、ヨーロッパ・キリスト教国連合艦隊の勝利に終わり、超大国トルコが負けるという歴史的転換点になる。特に負けることがなかった超大国トルコが負けたと言うことの精神的な側面は大きかったようである。
戦闘もさることながら、外交交渉も興味深い。ベネチアの外交官がトルコからの帰国報告で、「相手にどう思われているかよく考え、相手が強大だからといっても怯むことなく相手の弱点を突き、毅然とした態度を取ること。そして、こちらの強みを生かして、なめられないように交渉するということが重要である。しかしながら対トルコ外交は穏便に済まそうとして外交交渉が不十分であったために、トルコに野心を抱かせ領土拡張を許してしまった。」と述べている。
何とも現代の日本が二重写しとなり、時と場所は違えども何も変わりがないように思える。
Posted by ブクログ
『海の都の物語』シリーズの続きであり、ヴェネツィア共和国の衰退の一歩を描く海戦シリーズの最終巻。どのシリーズでもそうであったがヴェネツィア共和国の人たちの祖国愛の深さに感嘆されるばかりであった。イタリア本国や島々で活躍する人、コンスタンティノープルに残りトルコ相手に交渉する人、教皇を説得する人と様々な人々の模様を描きながら海戦本番に載せていく構成は流石であり、とても面白かった。
一度は失敗していても、次には成功させる。そのような粘り強い外交がヴェネツィア共和国繁栄の一因であったのであろう。そんな共和国がこの戦の後に衰退の一途をたどっていったというのは信じられないが、歴史であり国家というのはそういうものなのであろう。
Posted by ブクログ
1571年、スペイン王フェリペ2世率いる西欧連合艦隊は、無敵のオスマン帝国を破り、地中海世界制覇への野望を阻止した。無敵のトルコ神話を打ち破ったことで、西側諸国の精神的重要性は圧倒的であった。逆にトルコは地中海支配の喪失と陸の支配に動揺をもたらした。この戦いを契機に文明の交代期が起こり始め、海洋国家ヴェネツィアにも、歴史の主要舞台だった地中海にも、落日の陽が差し始める。本書は、文明の後退期に生きた男たちを壮大に描いた3部作の完結編である。
Posted by ブクログ
塩野七生さんの代表作を久しぶりに読みました。もう20年前の著作。地中海のキプロス島を巡る領土問題ですが、いつの世の中も領土問題の解決は難しいんだなあと、妙に切実な気分になりました。
Posted by ブクログ
『コンスタンティノープルの陥落』から続くキリスト教VSイスラム教の戦いも第3ラウンド、ついに完結です!
地中海で勢力を誇っていたヴェネチアと大西洋に勢力を拡大していたスペインの連合艦隊が、レパントの沖でオスマントルコの艦隊を撃破します。
強大なオスマントルコを前に敗戦を重ねてきた西洋世界にもついに勝利の瞬間が訪れました。
海戦の模様や戦略上の解説もとても面白かったです。
Posted by ブクログ
オスマントルコとヴェネツィア、西欧諸国連合によるガレー船同士の戦い”レパントの海戦”をテーマとした、『地中海戦記』三部作の第三弾。時間を忘れて読んでしまった。
Posted by ブクログ
地中海の戦さの三部作、完。今回は短期間での海戦でら前の二作とはまた趣かが違っていて面白かった。あとがきにもき記載があったが、塩野さんのヴェネツィアの民への愛情を強く感じました。自分は正直一作目が1番ワクワクしたけど、二作、三作目のロマンスもまた素敵でした。
Posted by ブクログ
ヴェネツィアをはじめとしたキリスト教国が勝利を収めつつも、地中海世界の時代の終わり、十字軍の終焉、ヴェネツィアの落日を止めることにはならなかった、オスマン帝国とのレパントの海戦を描く。
海洋国家の栄光と落日というテーマは、やはり面白い。
人々の個性にもおおきくよって織り成されるダイナミックな文明と歴史のなかにおける国家を描きつつ、そこに生きる人間のことも忘れない、壮大でありつつも暖かく細やかな目配りが感じられる素晴らしい作品。
読みながら、翻って我が国は、私は、と考えたときに、歴史のなかの今、歴史のなかのわれわれということを意識させられる、歴史観の涵養にまさにふさわしい作品を書かれる作家であると思う。
Posted by ブクログ
西欧の連合艦隊がトルコを破った歴史的海戦。
この一戦で大きく歴史が転換したわけではないが、西欧がトルコに一矢を報い、結果として歴史のキーポイントとなった。
Posted by ブクログ
塩野七生さんの海戦三シリーズで、これは最終回。歴史小説は苦手だったけど、その意識をすっかり覆してくれた。
時代は1570〜71年、最後の大海戦がレパントで起こった。その戦争が起こるまでの動きや人物像は戦争がいざ始まる前の高揚感を高める。とにかく描写が素晴らしくて、映画のようなスペクタクルな場面を想像した。戦闘が始まる瞬間や各重要人物の動きなど、小説の最高潮に達する。
Posted by ブクログ
大帝国トルコと海洋国家ヴェネツィアを軸にした、地中海世界中心の世の中が終わり始める大海戦:レパントの海戦。これをきっかけというように、地中海を中心にした経済・政治が衰退し始め、と同時にトルコ・ヴェネツィアも力にかげりを見せ始める。
世の中が移り変わる様を、多くの登場人物の目線で描き出す三部作の締めくくりです。
おもしろい!読み出したら止まりません。。。歴史は物語。いい作品でした。
Posted by ブクログ
トルコが西欧に負けたという程度の知識しかなかったレパントの海戦。戦争の発端がキプロスを巡るトルコとヴェネチアの争いであったが、ヴェネチアがローマ法王とスペイン王フェリペ2世を味方にした事で、戦いの姿はキリスト教VSイスラム教という宗教戦争の様相を呈してくる。
この作品は主にヴェネチアの視点で描かれている。バルバリーゴ、ヴェニエル、ソランツォ、ベルバロといった人物を中心に話が展開する。 スペインとヴェネチア、法王の間で「誰が総裁となるか」で意見がまとまらなかったが、最終的に総裁に決まった、若きドン・ホアンという人物の事もとても気になるところだ。
Posted by ブクログ
キリスト教世界vs.オスマン帝国の3部作の第3弾。前の2作と違って本作はヴェネツィアからの視点が強調されている。戦闘が始まるまでのキリスト教陣営の迷走っぷりと決戦の海戦シーンが見所。
Posted by ブクログ
ローマ人の物語の作者でもある、塩野七生によるレパント海戦を描いた歴史物。小説タッチに近い。レパントの海戦に至る経緯と登場人物の動きと併せて描いている。キリスト教国(スペイン・ヴェネツィア・教皇)が一枚岩でなくいがみあっていたのが面白かった。確かに、スペイン的には北アフリカを攻略したいし、ヴェネツィア的には東地中海を攻略したいってのがあったからそらそうだわなぁwwと感じた。レパントの海戦を復習・整理するにはいい本だった。ただの事実の羅列になってしまいがちだけど、この作者にはなんか躍動感や物語チックな描写が出るので読みやすい。
Posted by ブクログ
最後のガレー船艦隊対ガレー船艦隊の海戦となったレパントの海戦を、西洋側の視点、特にヴェネツィアを中心とした視点から描く。海戦以前の様々な政治情勢から、実際の戦闘に及ぶまでを、鮮明な描写で丹念に再構成している。平易な文章で読みやすく、かといって情報量が少ないわけではない。一気に読んで余韻に浸れる。
Posted by ブクログ
塩野七生の三部作と言われるキリスト世界とイスラム世界の対決を都市国家ヴェネチアから見た連作歴史小説の完結編。双方合わせて400隻を越す歴史上最大の海戦が幕を開けます。200隻を越す船団はどんなに壮観だった事でしょう。ガレー船の旋回、激突、甲板になだれ込んでの白兵戦、もう頭の中は妄想で一杯です。
Posted by ブクログ
三部作の中では、戦い自体はすぐに決する。コンスタンティノープルの陥落が五十日、ロードス島が六か月に対して、レパントの海戦は5時間。
今回もバルバリーゴはじめ魅力的な登場人物たちで一気に読み終えてしまった。
面白かった
面白かったけど、海戦(白兵戦)を一回戦っただけなので
いまいち盛り上りに欠けるとも思う。
地中海に馴染みのない身としては
ものめずらしさを感じて、
それなりに楽しめた。
Posted by ブクログ
前二作ですっかりヴェネツィア共和国推しになったのち、連合艦隊結成までの各国の足並みの揃わなさにキレ散らかしながら読んでいた。
バルバリーゴ死んじゃ嫌だ〜〜〜(;∀;)
Posted by ブクログ
中世の地中海を舞台にした空前絶後の大海戦の物語。
コンスタンティノープル陥落、ロードス島攻防記に続く作品で、中世バトルの3部作の最後を飾る。
争うのはキリスト教の連合軍 VS イスラムのトルコ。
著者の視点は完全にヴェネツィア側に立脚していて、かなりヴェネツィア贔屓に描かれている。
人間模様もかなり踏み込んで描かれており面白いが、物悲しさが漂う作品になっている。
塩野七生ファンにおすすめです。
Posted by ブクログ
オスマントルコとキリスト教世界の攻防を描いた3作目。昔の海戦は人間どうしの白兵戦だったみたいです。この戦いののち、歴史の舞台は地中海から大西洋へ。歴史物はスケールが大きいね。
Posted by ブクログ
~裏表紙より~
西暦1571年、スペイン王フェリペ二世率いる西欧連合艦隊は、
無敵トルコをついに破った。
コンスタンティノープルの攻略から118年にして、
トルコの地中海世界制覇の野望は潰えたのだ。
しかし、同時に、この戦いを契機に、海洋国家ヴェネチアにも、
歴史の主要舞台だった地中海にも、
落日の陽が差し始めようとしていた。。。
文明の交代期に生きた男たちを壮大に描く三部作、ここに完結!
~感想~
第二部の『ロードス島攻防記』を読み終えたのが、
実に10数年前、やっと完結できました(*`д´)b
最近イタリア住みの人と仲良くなったせいか、
イタリア人に対しての評価が著しく落ちている今日この頃です。
ただ、この小説に出てくるヴェネチア共和国。
歴史上最も長く続いた共和国であり、
「最も高貴な国」と呼ばれてたそうな。
その高貴さを示す、トルコから戻ってきた外交官が言う、
『国家の安定と存続は、軍事力によるものばかりではない。
他国が我々をどう思っているかの評価と、
他国に対する毅然とした態度によることが多いものである。』
ってセリフに要約されている気がした。
この言葉、今の日本の政治家に聞かせたいもんだわ。
おしまい。