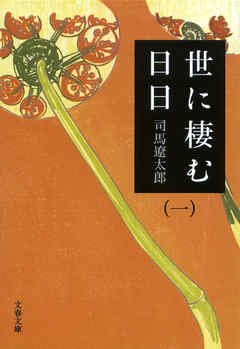あらすじ
2015年のNHK大河ドラマ『花燃ゆ』の主人公は久坂玄瑞の妻、文(ふみ)。文の兄であり玄瑞の師である吉田松陰こそ、『世に棲む日日』前半の中心人物です。「人間が人間に影響をあたえるということは、人間のどういう部分によるものかを、松陰において考えてみたかった。そして後半は、影響の受け手のひとりである高杉晋作という若者について書いた」(「文庫版あとがき」より)
嘉永六(1853)年、ペリー率いる黒船が浦賀沖に姿を現して以来、攘夷か開国か、勤王か佐幕かをめぐり、国内には激しい政治闘争の嵐が吹き荒れていた。この時期、骨肉の抗争を経て倒幕への主動力となった長州藩には、その思想的原点に立つ松下村塾主宰・吉田松陰と、後継者たる高杉晋作がいた――。維新前夜の青春群像を活写した怒濤の歴史長編、ここに開幕。
感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
吉田松陰と高杉晋作の物語。
松陰は、その師である玉木文之進から、私情を一切捨てて、公のために尽くせ、と教えられ、それを頭の中で考えるだけでなく、実践に重きをおいて生きたひとである。実行の中にのみ学問があるという、陽明学的思想である。孟子的といってもいい。
それが必要だとなれば、武士たるものは断乎行うべきだ。それが成功するかどうかということを論ずるべきではない。こういう思想で松陰はペリーの乗ってきた軍艦に漕ぎ寄せるのであった。
攘夷、攘夷と念仏のように国中の志士がとなえているが、ことごとく観念論である。空理空論のあげく行動を激発させることほど国を破ることはない。世の事に処するや、人はまずものを見るべきである。実物、実景を見てから事態の真実を見極めるべきだ。
松陰は、松下村塾で教育をするつもりはなかった。松陰は書いている。一世の奇士を得てこれと交わりを結び、我の頑鈍(がんどん。わからずやなとこ)を磨かんとするなり、と。平凡な者でも松陰を磨いてくれる特質を持っている。百人やってくるうち、一人ぐらいは凡質からはるかに突き出た奇士がいるにちがいない。それを待っていると。松陰は知人に書き送っている。
そして、松陰は晋作という可燃性の高い性格に火をつけた。
松陰は思想家であった。思想とは要するに論理化された夢想または空想であり、本来は幻である。その幻を実現しようという狂信・狂態の徒がでてはじめて虹のような鮮やかさを示す。思想が思想になるには、それを神体のように担ぎ上げてわめきまわるもの狂いの徒が必要なのであり、松陰の弟子では久坂玄瑞であった。狂信しなければ思想を受け止めることができない。が、高杉晋作は狂信徒の体質を全く持っていなかった。晋作は思想的体質ではなく、ちょっかんりょくにすぐれた現実家なのだ。現実家は思想家と違い、現実を無理なくみる。思想家は常に思想に酩酊していなければならないが、現実家は常に醒めている。晋作と松陰のちがいはここであった。もちろん、坂本竜馬も晋作の部類である。ただ坂本竜馬とか他のいわゆる勤王の志士と違っているところは、藩主に対する異常なまでの忠誠心であった。ここで間違ってはいけないのは、長州藩はどうでもいいのである。つぶれようが。藩主は大事だということだ。高杉家が上士という家庭であり、また、晋作がいくら無茶なことをしてのけても、藩主は常におおめにみてくれて、寛大な措置を施した。世子の小姓にもなったこともあったであろう。だから、晋作は、藩が幕府と戦争して敗れたら、藩主を担いで朝鮮へでも亡命するとまでいったのである。勤王の志士の多くは藩主のお目見え以下の者が多かったため、藩主への忠誠心は薄く、脱藩して活躍していくが、晋作は違った。
晋作は開国し国を富まさなければならないと考えていたが、ただ開国するのではダメだとも考えていた。じゃあどうするか、それは、攘夷をやたらめったらおこない、外国と戦争をする。日本中をあげて浸入軍と戦う。山は燃え、野は焦土になり、流民はあちこちに増える。それとともに、規制の秩序は全く壊れ、幕府も何もあったものではなくなる。その攘夷戦争をやってゆく民族的元気の中から統一がうまれ、新国家が誕生する。それが革命の早道だと。海外から敵を迎えて大戦争をやってのける以外、全ての革命理論は抽象論にすぎないと。しかしそれは、民族そのものを賭けものにするという、極めて危険な賭博だった。負ければ侵入国の植民地になってしまうのだ。できると思った。アメリカもイギリスと戦い、独立した。七年も戦ってである。ただ、晋作は論理というものがなかっな。戦略であった。藩が討幕に立ち上がらないのであれば、立ち上がらせるだけた、と。
イギリス公使館への放火、松陰の遺骨の掘り出しと将軍しか通ることを許されていない御成橋の通行、白昼堂々の関所の無手形通行(関所破り)と、晋作のこの頃の行動は、゛狂゛の一字である。 動けば雷電の如く、発すれば風雨の如しである。
おもしろきこともなきよをおもしろく
全四巻
Posted by ブクログ
~全巻通してのレビューです~
冒頭、「長州の人間のことを書きたいと思う。」という書き出しで始まっています。
長州の人間は理屈好き、議論好きということで、尊王攘夷運動にも熱を上げました。
主人公は吉田松陰と高杉晋作です。
どちらかというと吉田松陰の話の方が中身が濃くて面白かったですね。
読むまでは松下村塾の人ということくらいしか知りませんでしたが、後々の長州にこれほど大きく影響を与えた人ということは知りませんでした。
高杉晋作は私の好きな言葉「おもしろき こともなき世を おもしろく」が辞世の句ですが、どちらかというと若い頃に久坂玄瑞と松下村塾に通った頃の話が面白かったです。
他に伊藤博文(俊輔)、井上馨(聞多)、山県有朋(狂介)など後々明治政府で活躍するメンツが登場します。
本当にすごい藩だったんだな、と実感しました。