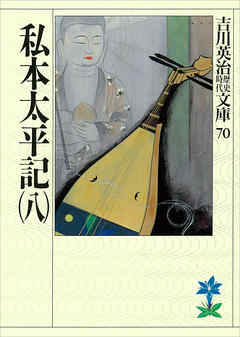あらすじ
※本作品は 2011年1月31日~2014年8月31日まで販売しておりました『私本太平記』全13巻を、全8巻に再編成した作品です。
巻の切れ目が違うのみで、本編内容は同じとなりますので予めご了承下さい。既に同作品をご購入されているお客様におかれましてはご注意下さい。
湊川に繰り広げられた楠木軍の阿修羅の奮戦。さしもの正成も“敗者復活”の足利軍に制圧された。正成の死は、後醍醐方の大堤防の決壊に等しかった。浮き足立つ新田義貞軍、帝(みかど)のあわただしい吉野ごもり。その後の楠木正行、北畠顕家の悲劇。しかし尊氏も、都にわが世の春を謳うとは見えなかった。一族の内紛?勝者の悲哀?彼は何を感じていたか。終章「黒白問答」が、その解答である。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
7巻まではものすごく面白いのですが、8巻から急に駆け足になります。というか、作者の体調の問題でやむを得ないのでしょうが、義貞なんかいつのまに舞台を去ったの、というあっけなさ。
湊川後もとても面白い(混沌とした)展開があるのでそれを最後まで読みたかった気がします。
それでもとても楽しい作品でした。
Posted by ブクログ
佐藤優が獄中で読んでいると知ってよみたくなった本。この本のお陰で、鎌倉時代末期から室町までの歴史を初めて知ることができた。最後の観応のじょう乱を読んでやるせない気持ちになった。尊氏たちにお前らなにやってるの?何のために立ち上がったの?と説教したくなった。この物語の中で唯一真っ直ぐなのは楠木正成と吉田兼好だけだった。この物語で一番出世したのは佐々木道誉だったな。
Posted by ブクログ
西上する足利軍は怒涛の進撃を見せ、ついに京都を奪回。楠木正成の自刃など宮方軍は瓦解を見せ、後醍醐方の勢力は吉野に篭ることとなる。
復活を遂げた尊氏だったが、喜びに浸っているとは見えなかった。未だ続く南北朝の血みどろの争い、志を共にした者とすら殺しあわなければならない現世。その中に彼が見たものはなんだったのか―。
無常を感じずにはいられないこの作品にあって、最期の「黒白問答」が一つの救いとなっています。
「長い戦乱は、みなを苦しめたには違いはないが、庶民の生活はいつともなくずんと肥えていましょうが。外へこぼれ出た宮廷の文化。分散された武家の財力、それらも吸って」
血でこの世を変えねばならない時代でも、次代の希望は必ず地中に萌えている―。この希望こそ、戦乱に散っていった哀れな武士たちのなぐさめとなるのでしょう。
私本太平記、おそらくなじみのない時代でしょうが是非一読あれ。お勧めです。
Posted by ブクログ
日本史の授業で習った複雑な南北朝時代の動乱が改めてよくわかり非常に面白かった。足利尊氏、後醍醐天皇、新田義貞、楠木正成、佐々木道誉、北畠顕家…個性豊かな登場人物と波乱の歴史。大河ドラマがさらによくわかる。
Posted by ブクログ
正成の湊川の戦いから、尊氏が没するまで。まあ、ムチャクチャに戦ばかり続く時代で、敵味方、本当に入り乱れる。これでこの太平記は完結するが、尊氏の死後も34年後まで南北朝は続く。この時代のことを初めて理解した。中高校時代、日本史、全く興味なかったしなあ・・・
Posted by ブクログ
湊川の戦いで、楠木正成らは壮絶な最後を遂げる。
その後、足利尊氏、足利直義、高師直、などなど足利一族、南朝方との権力に取り憑かれた抗争が続いていく。
Posted by ブクログ
尊氏にとってのライバルとなる正成や義貞を倒して、後醍醐天皇も亡くなり、足利の時代になったにも関わらず、弟直義との骨肉の戦いになるとは。いつの時代になっても際限のない争いをする生き物なのだと強く感じた。
Posted by ブクログ
この作品もようやく読破。約4ヶ月であるから、月に2冊のペースで読みきったことになる。日本史好きな私ではあるが、もともとこの時代は好きでもないし詳しくもなかったのだが、職場の同僚SYUくんが「くちゃくちゃで訳わからなくなるから」と半ば強制的にくれたため読み始めたのである。
読んでみると、彼が言っていたほどはくちゃくちゃでもなく、訳が分からなくて方向性を見失うことはなかった。最終盤において、足利直義と高師直のナンバー2争い、尊氏と直義の兄弟喧嘩などが畳み掛けるように勃発しているさまを言っていたのだろうが、もともとこの辺りは高校時代の大河ドラマで観ていたし、先に読んだ「日本の歴史 第8巻 南朝と北朝(小学館)」において予習済みだったので、余裕で飲み込むことができたのである。
おしなべて言うと、あまり楽しい時代ではない。それが、二つの皇室が乱立していたから、という高尚な理由ではなく、魅力を感じたキャラクターが少ないからである。足利尊氏は言うまでもない。つまり、本作品でも凡庸でどこかのんびりしたキャラクターという設定であるので格好いいとは思えない。彼を見習って現代のビジネスに投影しようとも思わない。まあ多少、仁義に熱い楠木正成が格好良いといえば格好良いのだろうが、本作品においては彼もどこかつかみどころのないキャラに仕上がっている。なので、いつかまた機会があれば北方謙三あたりの南北朝モノを読んでみて、吉川太平記との違いを感じながら魅力あるキャラクター探しをしてみようかなと思っているところ。
正直、今の感想は「やっと、無事に終わった」ということ。ようやく私の大好きな戦国時代に戻れる。
Posted by ブクログ
▼本を読んだ理由(きっかけ・動機)
もともと吉川英治氏の作品は全て読破したいと思っていたため、いずれ読むつもりであった。
このタイミングで手をだしたのは、山岡荘八氏の『源頼朝』を読んで、鎌倉~応仁の乱を経て戦国に到るまでの歴史を改めて知りたいと思ったから。
「足利尊氏」という人物をぼんやりとしか知らなかったのも動機のひとつ。
▼作品について
室町幕府を起こした足利尊氏を主人公に南北朝動乱の始まりから鎌倉幕府崩壊後の泥まみれの戦模様が描かれている。
これを読めば、室町幕府が早期に瓦解し、応仁の乱を経て戦国に突入した理由がよくわかる。
▼感想を一言
切なくなった
▼どんな人におすすめ(気分、状況)
日常に疲れ、厭世観に付きまとわれている人。
「足利尊氏」の晩年の悲しさも最後の「覚一法師」の琵琶問答に救われる。
▼作者について
歴史・時代作家としては吉川英治氏が描く作品は司馬遼太郎氏のリアリティとは違い、人間愛に溢れている。
作品は最後に”救い”があり、現実の厳しさの中にも一輪の花(希望)を咲かせるような
読む人を励まそうとするような一面があるように思える。
Posted by ブクログ
・完結編。楠木正成の最後となる湊川の決戦は、ある意味で本作品のクライマックスでもある。正成の武士でありながら、生きながらえることの大切さを諭す人間性、美談の象徴となるべき史上人物であることが頷ける。無秩序な世の中にあって、揺るがない価値観、自己を貫く信が際立つ。
また、尊氏を描く上でも正成との人間関係が重要になっているのだろう。
・その後の展開は、「京都は、彼(尊氏)が幕府を置いてからでも、猫と猫の間の鞠のように、奪ったり奪い返したりをくり返してきた。」
・最後の「黒白問答」にて、この時代の歴史上の意義を総括している。
「源平、鎌倉、北条と長い世々を経てここまで来た国の政治、経済、宗教、地方の事情、庶民の生業、武家のありかた、朝廷のお考え-までをふくんだ歴史の行きづまりというものが、どうしてもいちど火を噴いて、社会の容をあらためなければ、にっちもさっちも動きがとれない、そして次の世代を迎えることができない、いわば国の進歩に伴う苦悶が何よりも因からと思われまする。」
「曙の兆しが地の下、つまり庶民の中に萌えかけている。長い戦乱は、みなを苦しめたには違いないが庶民の生活はいつともなくずんと肥えていましょうが。外へこぼれ出た宮廷の文化。分散された武家の財力、それらも吸って。」
・全巻を読み、混乱の世の中にあって尊ばれる者があり、文化の萌芽がある。そのような歴史を学ぶ意義はあると改めて考えさせられた。
Posted by ブクログ
読み終わった時の感情は、「やっと終わったァ」って感じだった。太平記の時代、特に鎌倉幕府滅亡後、室町幕府の成立ごろっていうのは、日本史上最悪の暗黒時代だったと思う。信じる物が意図的な人の欲望によって分裂することの怖さ。親子、兄弟、君臣、家臣同士、律する物がなくなり裏切りに次ぐ裏切りで信じる物がなくなる絶望感。あの時代の人でなくてよかったと思うけど、こんな人の生き方はどこまでも続くのだろうか?
Posted by ブクログ
尊氏の死をもって物語は終わる。
この時代をどう捉えるべきかを、黒白問答で展開しているのだけど、もう少し観応の擾乱に突っ込んでくれればと無い物ねだりをしてしまう。
敗けても敗けても、結局人心を掌握する尊氏の力はどこからくるものなんだろう? ことに高師直をはじめ高一族抹殺後におこる尊氏と直義間の逆転劇が、どうしてそんなことになったのか、どうもしっくりこない。もっと勉強が必要です。