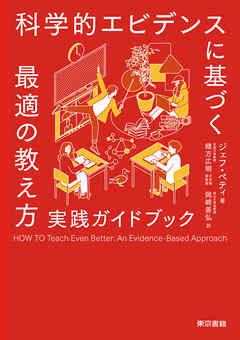あらすじ
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
授業づくりに革命を! 優秀な教師に必要なのは、才能ではない。効果的な「教え方」だ! 学習成績を向上させるだけでなく、生徒たちを楽しませ、意欲を高め、自信を与える。それが効果的な「教え方」。学術研究と教師の経験の蓄積から導き出されたエビデンスをベースに、授業で実践する方法を視覚的に解説。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
多くの研究を実践にどのように利用するかについて詳しく説明した本であるので、教員養成学生に最適である。受け取る、適用、再使用という段階で説明しているのでわかりやすい。参考文献についても各文献に2行以上の説明があるので、助かると思う。
Posted by ブクログ
最近「科学的根拠(エビデンス)」がホットワードの自分にとって、ぴったりの本だと思い、少々値は張るが思い切って購入&読破。
400ページを超えるボリュームがあるが、そこまで難しいと感じる部分はなく、全体的に読みやすかった。
本書から得た学びは多くあるが、9個に厳選して自身の考えとともに紹介する。
①示された教え方の効果があるかどうか見極めるのに5回、体得には25回行う必要がある。←具体的な数値が示されているのが印象的であった。しかも「25回」という多さが体得の難しさを表していると感じた。
②グラフィックオーガナイザー最強←いわゆる思考ツール。現在日本では、デジタル活用とともに思考ツールの普及も進んでいるので、ここに日本の教育のレベルの高さが表れているのかも…と思った。
③RARモデル←受け取る・適用する・再使用するという3段階構造で学習をつくる形。これは1時間の授業単位でなく、単元を通して、また何度も繰り返して…といった探究のプロセスと似たような形で推奨されている。
④アサーティブな質問は効果的←お互いを尊重する質問というニュアンス。もう少しわかりやすく言い換えると、子どもの考えを大切にした質問ともいえる。「なぜそう考えたの?」「どうしたらいいかな?」と、正誤や教師の考えではなく、子どもの考え中心で学習を進める。これは基本。ここで再確認できた。
⑤スプーフィング課題を設定する←教師が用意した不十分な作品を見せて、子どもに評価してもらうというもの。これは自身も作文指導で行ったことがあるが、子どもも細部まで作品をチェックするし、その過程でポイントについても理解できるので効果的学習につながると思う。
⑥学習の転移に効果的な活動として、類似点/相違点探し・一般化・経験想起等がある。←教科に関わらず、共通する方法。転移こそ、学習の最上目標。ぜひ意識してこのような活動を取り入れたい。
⑦成長型マインドセットをもつことが重要←完全同意。これは、コントロール可能なもの(努力・時間・方法など)に原因を求める考え方のことで、言い換えれば、「自分のやり方変えれば絶対成功する!」という自己効力感にもつながる。
⑧ジグソー学習最強←ハッティさんの調査より。たしかに学必要感は持ちやすいと思う。これはぜひ教室でも試したい。25回。
⑨実践コミュニティをもつことが大事←これは自身も実感しているところ。他者と関わる中で学びが深まる。
レビューが本書並みのボリュームになったが、それだけ得た学びが多かったということ。
体重を測りつづけても、牛を太らせることはできない。
本を読み続けても、教育力を上げることはできない。(諸説あり)
実践あるのみ!