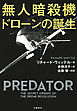赤根洋子のレビュー一覧
-
-
-
-
Posted by ブクログ
「医学の歴史は、人類のために自分の健康やときには命までも犠牲にした研究者らの英雄的行為によって飾られている」
現代当たり前と思っているようなことにも先人たちの涙ぐましい努力や驚くようなドラマがあり、当然ながら試行錯誤を繰り返して初めて実用化されたものだ。19世紀から20世紀にかけて病気やその治療法、毒ガスや爆弾、深海や成層圏などの謎を解明するために、科学者たちは自らの身体で人体実験を試みる。そのエピソードを紹介している。
本自体は面白おかしく書かれているわけではないが、人体実験の事実自体が凄まじく、笑うと言うより恐怖すら感じる。
梅毒と淋病の感染経路を把握するために自らの性器に性病患者の -
-
Posted by ブクログ
ネタバレ読みやすい訳で良かった…。特に印象深いのは出産のために広い骨盤だと言われていたが実は赤ちゃんを抱いて歩くのに適した骨盤にしたからだ。という説は驚いた。
通説を覆したり新しい説が出てくるのを知れるのはすごく嬉しいし楽しくてそうだったのか〜!と思えてありがたい。刺激的。
常に情報はアップデートされていくから追いかけるのは大変だし前読んだ本にはこう書いてあったからそうだろうと思い込むのは良くないなと反省した。
確かに女性はお産があるから二足歩行が苦手説は言われれば納得しちゃう話だなぁ。
お産関係や赤ちゃんのハイハイは興味深かった。
ハイハイせずに立ち上がったりするんだ…産後の成長具合の話は親にと -
-
Posted by ブクログ
【感想】
かつて「マッドサイエンティスト」と糾弾され、医学の表舞台から姿を消した医者がいた。その医者の名は『ロバート・ヒース』であり、彼を主人公として本書は展開していく。
ヒースが施した治療のもっとも有名なものが、同性愛者を異性愛者に矯正するための電気治療である。被験者の脳の快楽中枢に電極をつなぎ、娼婦にお誘いを受けながら同時に脳内に電流を流していく。これまで女性に欲情を抱かなかった患者は娼婦との「セッション」のあいだに初めてオーガズムに達し、実験は大成功に終わった。
現代の視点からすれば、こうした治療はまさに「闇の脳科学」に見えるだろう。実際、彼が活躍した1950年代当時でも、こうした「 -
Posted by ブクログ
痛みや苦しみや悲惨さに目を伏せたくなる様な人体実験の数々だが、興味深い話ばかりだった。
医療技術はもちろん医療に関する法律も定められていない時代。イギリスでは当時、死刑囚の死体が解剖に利用することが認められていた。その死体は、度々遺族と解剖をしたい医者との死体の奪い合いが起きて、その奪い合いの激しさから死刑囚が生き返ったこともあったという。
医学生に必要な遺体が足りないために、メスを入れるのが初めての患者だということも。そのため、遺体が高値で取引され、埋葬屋が医者へ遺体や臓器を横流ししたり、遺体を採掘盗掘する輩がはびこった時代も。
生きた被験者としては主に、医者自身・死刑囚などの犯罪者・ -
-
Posted by ブクログ
科学的
この言葉をつけるだけであらゆる理論は尤もらしくなる。ビジネスの世界でも、特に文系の人を黙らせる、或いは思考停止に持っていくキラーワードだ。
では科学的とは何か?
これは科学哲学の問いだが、この本の著者はホンモノの物理学者。しかもノーベル賞受賞者。彼が言う科学的とは、実際に世界を理解することに貢献するかどうかである。科学哲学では、もっと正確に定義しようとするが、著者は物理学者なので、そんなことはどうでも良い。むしろ、科学哲学の議論を小馬鹿にしている。そうではなく、歴史を振り返り、どうやって理解が進んだか?どんな方法、思考が科学の進歩に役立ったのか?を冷静に分析する。そこには、当時だ -
Posted by ブクログ
シナの台頭、もしくは拡張と、米国の覇権。
様々な問題を提起して、それを各々考察する展開で本は進む。
結果的には、武力衝突の可能性が極めて高く、もしそうなった時には、シナがある意味、覇権を握る可能性が高い。
憂鬱。
単に覇権が米国からシナに移るというわけではない。英国から米国に移った、そんなことではない。
今の世界秩序が、新しいシナのルールに取って代わられるってことだ。それは、全世界が中共のために搾取されるってことと意味するような気がする。
地理的に近い我が国が、とんでも無い状況に陥ることは間違いない。
憂鬱。
シナ製の商品を買うことは、そうした覇権に資金提供するようなもんだってのは、 -