無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
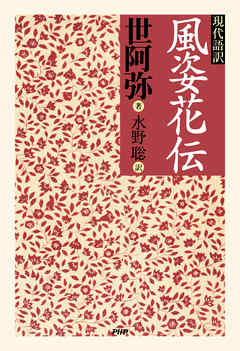
『風姿花伝』は能の大成者・世阿弥が著した、日本最古の能楽論である。『花伝書』の名称でも知られる本書は、「花」と「幽玄」をキーワードに、日本人にとっての美を深く探求。体系立った理論、美しく含蓄のある言葉、彫琢された名文で構成される、世界にも稀な芸術家自身による汎芸術論である。原文の香気が失われぬよう、かつ自然な現代語としてスラスラと読めるよう、工夫を凝らした現代語・新訳として提供する。七歳から年代順に具体的な稽古要領を記した「年来稽古條々」、物真似の本質を把握し表現する「物学條々」、Q&A形式の「問答條々」。そして、「花」の本質を説いた「別紙口伝」。章立て・語り口はあくまで明快、シンプルである。大陸伝来の文化から袂を分かち、日本人自ら育て、咲かせた最初の美しい「花」――。風姿花伝は700年を経た今日でも、広く表現に携わる方々はもちろん、人生訓としても読める懐の深い名著である。
...続きを読む※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。