無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
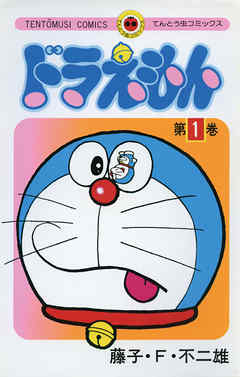
●日本を代表する漫画家藤子・F・不二雄先生の傑作作品『ドラえもん』。未来の国からやってきたごぞんじ、ネコ型ロボットのドラえもんが親友のび太とともにくりひろげる友情ファンタジー。四次元ポケットから取りだされる不思議な道具で日本じゅうを笑いに包みこむ。しずちゃんやスネ夫、それにジャイアンも元気いっぱい。大きな夢をあたえてくれるワクワクドキドキ素敵な道具でキミを心温まるドラえもんワールドにご案内。
▼第1話/未来の国からはるばると▼第2話/ドラえもんの大予言▼第3話/変身ビスケット▼第4話/秘(丸囲み)スパイ大作戦▼第5話/コベアベ▼第6話/古道具きょう争▼第7話/ペコペコバッタ▼第8話/ご先祖さまがんばれ▼第9話/かげがり▼第10話おせじ口べに▼第11話/一生に一度は百点を▼第12話/プロポーズ大作戦▼第13話/◯◯が××と△△する▼第14話/雪でアッチッチ▼第15話/ランプのけむりオバケ▼第16話/走れ! ウマタケ
「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」
2026年2月27日公開
声の出演:水田わさび、大原めぐみ、かかずゆみ
「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」
2025年3月7日公開
声の出演:水田わさび、大原めぐみ、かかずゆみ
「映画ドラえもん のび太の地球交響楽(シンフォニー)」
2024年3月1日公開
声の出演:水田わさび、大原めぐみ、かかずゆみ
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※期間限定無料版、予約作品はカートに入りません
「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」
2026年2月27日公開
声の出演:水田わさび、大原めぐみ、かかずゆみ
「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」
2025年3月7日公開
声の出演:水田わさび、大原めぐみ、かかずゆみ
「映画ドラえもん のび太の地球交響楽(シンフォニー)」
2024年3月1日公開
声の出演:水田わさび、大原めぐみ、かかずゆみ
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。