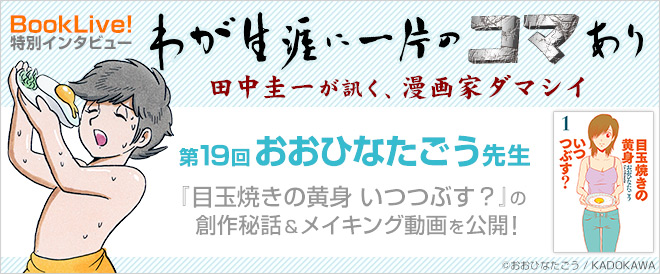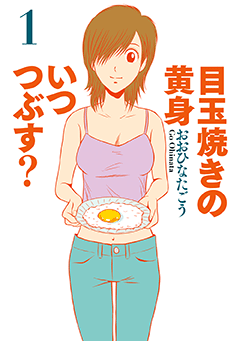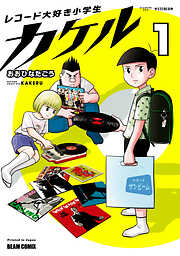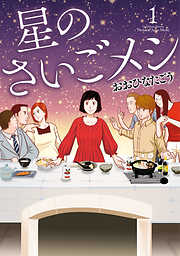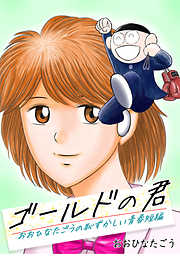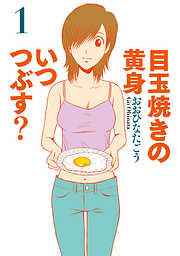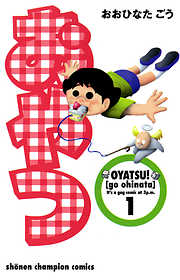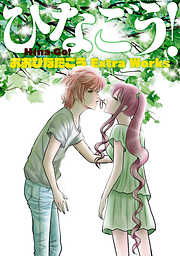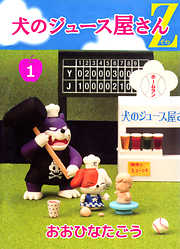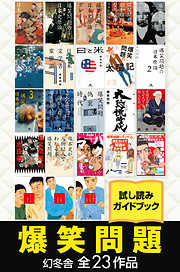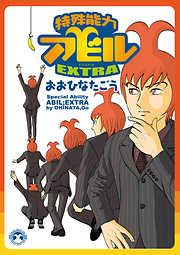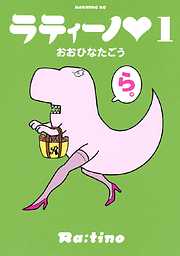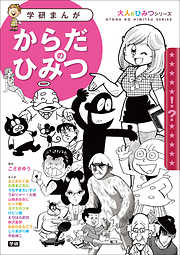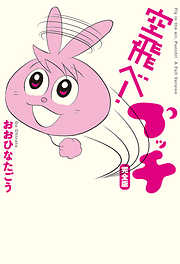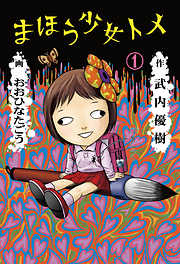田中圭一×『目玉焼きの黄身 いつつぶす?』おおひなたごう先生インタビュー

手塚治虫タッチのパロディーマンガ『神罰』がヒット。著名作家の絵柄を真似た下ネタギャグを得意とする。また、デビュー当時からサラリーマンを兼業する「二足のわらじ漫画家」としても有名。現在は京都精華大学 マンガ学部 マンガ学科 ギャグマンガコースで専任准教授を務めながら、株式会社BookLiveにも勤務。
おおひなたごう先生のメイキング動画を、田中圭一が解説!
おおひなたごう先生に『目玉焼きの黄身 いつつぶす?』の主人公・二郎さんを色紙に描いていただきました。ここではその作画動画を大公開! 田中圭一がおおひなた先生のキャラの魅力を解説します!
インタビューインデックス
- 『目玉焼き』誕生秘話! 売れる漫画を目指したコンセプト
- 「この人たちと飲みたい!」不純な動機(?)がデビューを後押し
- 初めてキャラが「勝手に喋った」一コマ!
- 「表に出る機会があれば、とにかく笑わせてやろう」という気持ちで
- さまざまな才能の「組み合わせ」が新しいギャグを生む!?
『目玉焼き』誕生秘話! 売れる漫画を目指したコンセプト

――今回の「一コマ」では『目玉焼きの黄身 いつつぶす?』のコマを選んでいただいたんですが、まずは『目玉焼き』の連載に至るまでの経緯も興味があるんです。それまでのおおひなた先生のタッチやテイストとは、ガラッと変えてきましたよね?
一時期、連載もなくなって、単行本も全く売れなくなった時期がありまして……。「売れないことにはどうしようもない」ということで、とにかく「売れる漫画」を目指して考えたのがこの作品なんです。
当時からグルメ漫画は流行ってましたし、「美味しく料理を見せる漫画」や「料理対決」などいろんな切り口がありましたけど、「食べ方の違い」を描いている漫画は意外と少ないんじゃないかと思ったんですね。
僕はごはん時に、悶々とした疑問を抱えながら食べてたんですよ。「果たしてみんな、僕と同じように食べてるのかな?」と。例えば、僕は白米とおかずを一緒に口に入れて“口内調味”して食べるんですけど、ふと嫁を見たら、別々に食べてるわけですよ。おかずを食べて、飲み込んだ後に白米を食べて……。
「ちょっと待てよ!」と。「それずっとそうやってたの?」って(笑)。
――それ、まんま『目玉焼き』の世界じゃないですか(笑)。
嫁は「おかずを一緒に口に入れるのははしたない」と躾けられたから、食べられないんですって。でも、丼ものとかお寿司は「おかずとごはんを一緒に食べるもの」だからOKらしいんです。
それで「あれ、僕の食べ方っておかしいのかな?」と思ったんですよ。それで当時mixiで、マイミクに「みんなはどうしてる?」って聞いたら、口内で混ぜて食べる人が圧倒的で、しかも食いつき方が尋常じゃなかったんですよ。みんな「俺はこうする」「私はこうする」と自己アピールしてくれたんです。それで、これを漫画にしたら面白いんじゃないかって思ったんですよね。
――まさにSNSでリサーチをしたわけですね。確証を持てたというか。
当時から「僕の漫画がきっかけで、ネット上で食べ方論争になったら面白いんじゃないか」というイメージが頭にあって、それを形にしてみた感じですね。
――mixiでそういう話をしてから、連載が始まるまで時間はかかったんですか。
どうだったかな。でも1年以内ぐらいだったと思います。
――最初は食べる順番や食べ方だけじゃなく、もうちょっと色々やろうという提案もあったんでしたっけ?
僕は、「食べ方」自体は見せ方の一つとして使ってるんだけど、本当に描きたいのは、「そこで怒って彼女と喧嘩になってモメて、それで自分の至らなさに気づいて直していく……」みたいな気持ちの変化の部分なんです。
最初に持っていった出版社では、「面白いんだけど、16Pを4Pにできないか」と言われました。食べ方にクローズアップして、小ネタ的に描こうよっていう感じになっちゃったんですね。
それじゃダメだと思いました。僕は変な食べ方を描きたいんじゃなくて、そこにある人間模様を描きたかったんです。それで、『コミックビーム』に持っていったら、逆に4P増やそうと言っていただいた。「もっとこのコマ大きくしよう」とか「見せ場は1P使ったほうがいい」とか。4P増やして20Pにして、来月から連載しようという話になって、すぐに決まりましたね。
――『目玉焼き』は、一コマがでかいじゃないですか。それは担当さんの意向もあったんですね。
そうなんです。持ち込み先が違うと、これだけ真逆なことを言われるものなんだなと、少し驚きましたね。でもすごくありがたかったです。
――担当さんがこちらの狙いを理解してくれる時はやりやすいし、成功しやすいですよね。
まだ一話しかできてないのに連載が決まった時は、あまりのスピードにちょっと戸惑いましたけどね(笑)。
――担当さんの中でも確信があったんでしょうね。でも目論見通りヒットして、アニメ化もされたじゃないですか。してやったり! って感じだったでしょ? ヒットを出そうと思って企画を考えて、その作品がヒットした。さらにアニメ化って、漫画家にとってはひとつの到達点ですよね。
増刷という言葉を聞いた時、「ふふふ、思い通り」というよりは「よっしゃ!!!」というのが大きかったですね。何年、増刷という言葉を聞いていなかったか(笑)。ずっと不景気な時代でしたから、本当にジャンプしたいぐらいの気持ちだったし、同時にホッとした感じでしたね。
――ヒットの頃って、ちょうど京都精華大学で教えることが決まる直前ですよね。学生にも、ヒットの経緯を含めてレクチャーできる。
ちゃんと『目玉焼き』を連載している最中に先生になれて良かったなと……(笑)。講師が連載のひとつもやってなかったら説得力がないじゃないですか。自分が描いてないのに、学生に描けとは言えませんからね。
――もう一つ気になったのは、『目玉焼き』で絵柄を一気に劇画風に持ってきたじゃないですか。これはどんな意図が?
今までは『おやつ』や『犬のジュース屋さん』で、いかにもギャグタッチな、赤塚不二夫を踏襲したような絵で描いてきましたけど、あれだと記号を描いてるみたいで、あんまり絵を描いてる実感がない。それで徐々に頭身を上げていくんですけど、『まほう少女トメ』というホラー作品で作画を担当した時に、普段描かないようなタッチに挑戦したりして、劇画タッチとストーリー漫画のコマ構成を練習して慣らしていきました。それで、リアルな絵でギャグ漫画もいけるかもしれないと思って。ギャグタッチの絵だと。、ちょっとズレたぐらいだと面白くなくて、突き抜けないと面白くない。でもリアルな絵だとちょっとずらすだけでギャップで笑えるという、展開のしやすさがあると思いました。
――『目玉焼き』はギャグでゲラゲラ笑わせるタイプの漫画じゃないから、この絵でギャグ要素が入ってくる方が映えるんでしょうね。反面、二郎の気ぐるみアクターのかぶり物はギャグテイストで、今までのおおひなた作品の雰囲気がありますが。
主人公は役者の田宮二郎をモデルにしてるんですけど、これはギャップを狙ってますね。田宮二郎みたいなやつが目玉焼きのことばっか考えてたり、ゆるキャラやってたりしたら面白いだろうなと。あと付き合ってる彼女(みふゆ)が、一見OL風なのにお笑い芸人をやってるとか、そういう「やってなさそうなこと」をあえて与えて緩急をつける。物語部分は深刻なところもあるので、ゆるキャラの絵を出してホッとさせるというのは、狙いとしてありますね。
「この人たちと飲みたい!」不純な動機(?)がデビューを後押し

――おおひなた先生に「漫画家になるきっかけ」として持ってきていただいた、この『COMIC麒麟様』(※1)の話を聞きましょう。90年発行の雑誌ですが、このメンツは豪華ですよ。中川いさみさん(※2)と吉田戦車さん(※3)も、ちょうどブレイクしている最中ぐらいですよね。
たしか『伝染るんです。』(※4)が89年ぐらいなので、そこから一気に不条理系ブームになって、みたいな時代ですね。
この『COMIC麒麟様』を見つけたのは、漫画家を目指しながら会社勤めもしている時期でした。「もし漫画家になれなくても会社がある」という、どっちつかずの状態で、漫画家になれるという確信もなくやっていたんですね。
この中に、まついなつきさん(※5)のコラムがあるんですけど、どういう内容かというと、ここに載っているような人たちが、夜な夜な集まって飲み会をしているんです。それがめっちゃ羨ましくて、「俺もその中に入りたい!」と強く思いました。それが漫画家になりたいと思った動機です。
――その気持ちはすごく分かります。描くこともさることながら、「漫画家というカテゴリー」の中に入りたいという気持ちね。
そう。「これを描きたい!」とか、「世の中にこれを問いたい!」とかじゃないんですよね(笑)。ちょっと不純な動機なんです。
――いや、それを不純とは言いにくい。僕も『COMIC CUE』(※6)の創刊号に載った時に、「あ、このメンツの中に入れた」というのがすごくありました。漫画家の中でも、ちょっと別室にいるような人たちじゃないですか。ある種の憧れの場所に行けたというか、だから余計に嬉しかったですよ。
当時、主婦と生活社の『コミックGiga』に持ち込みをしていたんですけど、どうもパッとしなかったんです。担当さんにも「いつまでこういうことを続けるつもりなんだろうね」なんて言われてしまい、もっと真剣に笑いのことを考えなきゃいけないと思いました。
それまでは深く考えずにノリで描いてたんですね。「発想だけでなんとかなるんじゃないか」とか「1コマ目を変なコマにしたら、あとはオチがなくてもいいんじゃないか」とか。そういう風にちょっとナメてたみたいなところがあって、ギャグをちゃんと理解してなかった。
そこで、自分の4コマ漫画を見直してみたら、「このオチ、前フリを全然活かしてないや」って気がついたんですね。本当に単純なんですけど、それが分かった途端、つまらなかった4コマが面白くなったんですよ。担当さんに見せても「面白くなったじゃん」と言ってもらえて、自分でも手応えを感じました。そこでやっとギャグの構造が分かった感じで、そこからデビューさせてもらってという流れですね。
――最初に載ったのは『コミックGiga』ですか?
ですね。『コミックGiga』の別冊で、8Pぐらいの4コマ漫画でした。
――ギャグの描き方に開眼してからは、一気に描けた感じなんですね。
でも、おおひなた先生は、いろんな漫画を読んで知っているからこその蓄積があるじゃないですか。そういうものがある人は、フタが開いた瞬間に一気に弾けるところがあるのかなという気がします。自分も大学で教えて分かってきたのは、天才と言われている人は、蓄積したものを瞬時に組み合わせて出せるから天才であって、秀才・凡才の人たちは、それをゆっくり組み合わせているからそうなんだということ。結局、自分の引き出しとその蓄積の量の絶対数がなければ、いくら才能があっても難しいんじゃないかと思うんです。
何も知らないのに描けちゃう人は稀でしょうね。手塚治虫先生の言葉で「いい漫画を描くためには、いい映画を観ろ、いい小説を読め、いい音楽を聴け、いい演劇を観ろ」という一言があるじゃないですか。要するに、良い漫画を描くためには漫画だけ読んでても描けないぞっていう。
京都精華大学で教えている学生にも、最初にそれを言うんですが、学生の中には漫画の構造をちゃんと理解していないような奴がたまにいて、「あっ、こいつはちゃんと漫画を読ませないとだめだ」みたいなことがあります(笑)。手塚先生の言葉を鵜呑みにして、漫画の知識もろくにないまま漫画を描こうとしてる奴がいるので、これは訂正しなくちゃいけないなと。「とりあえず漫画を読んでからの話ね」っていう。
――『コミックGiga』の次は、ほかの漫画中心の出版社に行きましたよね。
『コミックGiga』の担当さんが、タナカカツキさん(※7)の担当もやっていたんです。当時のタナカカツキさんは、演劇、テレビなど多方面に活躍してたんですね。それでぜひお会いしてみたくて、担当さんに紹介していただきました。
その後、タナカさんと飲む機会があって、そこで仲良くさせてもらったんですが、後日「漫画家の飲み会があるから来い」って呼ばれたんです。
それが『COMIC麒麟様』にいるようなメンツが集まった飲み会だったんです。夢が早々に叶ってしまったような形で、「意外と早くこの場に来れたな!」って(笑)。
――漫画で言うと、単行本5巻ぐらいかけていかなきゃいけないものが、1巻の途中あたりでいけちゃったんですね(笑)。
若林健次さん(※8)、とがしやすたかさん(※9)、ロビン西さん(※10)、天久聖一さん(※11)、朝倉世界一さん(※12)、吉田戦車さんもいて。僕はまだ『コミックGiga』でやり始めたぐらいのペーペーだから、そこで色々仕事を紹介してくれるんですよ。
天久聖一さんが『TV Bros.』を紹介してくださって、特集で4コマを描いたら好評で、連載をいただくことになりました。それが僕の2つ目の連載で、91年から始まって今でもずっと続いています。そうやって漫画家さんに紹介してもらってだんだんと広げていったんです。とがしやすたかさんにも『まんがくらぶ』を紹介していただいたりとか。
――漫画家は、意外と活発にそういう交流をされますよね。
当時はそんな感じで、ギャグ漫画家が集まって、面白い奴がいたら呼び出すなんてこともよくありました。そんな空気でしたね。
――赤塚不二夫さんの時代から伝統的に、「面白い奴と会って飲みたい」という意識が、ギャグ漫画家には強いんですかねえ。
あと、おおひなた先生がデビュー前後によくやっていたという「サイン色紙交換」、あれは人脈作りに有効だったんですか?
はい。最初にタナカカツキさんにお会いする時も、まず漫画家仲間をたくさん作らなきゃと思って、タナカカツキさんにサインをもらおう、その時に自分のサインもあげようと思って、あらかじめ準備してたんです。それでサインをいただいた時に「お返しです」と言ってド新人の自分のサインを渡したら、「面白い奴だ」って言われて。そのおかげで飲み会に誘ってもらえました。これはかなり役立ちましたね。
これを大学で学生たちに話したら、学生の一人が真似し始めてるんです。ゲスト講師の人とかとサイン交換をやってるんですよ。俺は漫画家としてデビューしてたからいいけど、お前まだ学生じゃん! ってヒヤヒヤしてます(笑)。まあでも、これが後々「あ、あの時の」ってなればいいと思ってやらせてますけどね。色紙はオーバーですけど、人脈作りのためにも名刺ぐらいは持っておいたほうがいいと思います。
1990年に双葉社より発行された漫画雑誌。佐々木望都子が編集長を務め、多彩な作家陣が名を連ねた。続刊はなく、この1号のみとなっている。
神奈川県出身の漫画家。1985年に「うわさのトラブルマン」でデビューし、2003年には朝日新聞広告賞を受賞。ナンセンス・不条理ギャグを得意とする。代表作に『クマのプー太郎』など。
岩手県出身の漫画家。1985年に『ポップアップ』誌(VIC出版)でデビュー。代表作に『伝染るんです。』など。中川いさみ、朝倉世界一、榎本俊二、和田ラヂヲらとともに1990年代前半の「不条理ギャグ」ブームを担う。同作で第37回文藝春秋漫画賞を受賞。
1990年から1994年まで『週刊ビッグコミックスピリッツ』(小学館)で連載された吉田戦車の代表作。「かわうそ君」「かっぱ君」「斎藤さん」などのシュールなキャラクターと世界観が人気となり、「不条理ギャグマンガ」の礎を築いたともされる作品。
東京都出身の漫画家、ライター。高校在学中より出版社に出入りし、『ぱふ』(雑草社)にてデビュー。サブカルチャー誌を中心に活動する。90年代からは出産、育児をテーマにした著書を多数発表。2002年以降は占い師としても活動中。
1994年にイースト・プレスから創刊された漫画雑誌。vol.3まで漫画家の江口寿史が責任編集を務めた(vol.4以降はイースト・プレスの堅田浩二が担当)。各号にテーマを設定し、掲載は基本的に短編のみなど、作家性を強く打ち出す路線で知られる。2003年を最後に実質休刊中。
大阪府出身のマンガ家、映像作家。1985年「ミート・アゲイン」でデビュー。代表作に『オッス!トン子ちゃん』『バカドリル』(天久聖一との共作)など。「うたばん」「ここがヘンだよ日本人」などで映像制作も手がける。現在、自身の母校でもある京都精華大学デザイン学部客員教授を務める。
福島県出身の漫画家。1987年に『ドトウの笹口組』でデビュー。現代社会を舞台にしたスラップスティック調の作風で知られる。おおひなたごう先生とバンドを組んでいた時期もある。
東京都出身の漫画家。劇画村塾3期生で、1985年に『青春劇場−海−』でデビュー。代表作に『青春くん』、『竹田副部長』、『男のいろは』など。下ネタを扱った4コマ作品を多数手がける。
大阪府出身の漫画家。高校在学中にデビューし、楳図かずおのアシスタントを務めながら自身も作品を発表。1995年に発表した『マインド・ゲーム』は、2004年に湯浅政明によって映画化され、文化庁メディア芸術祭アニメーション部門受賞をはじめ、高い評価を得た。
香川県出身の漫画家、アニメーション監督。1989年に『やんちゃブック』(宝島社)でデビュー。代表作にタナカカツキとの共作『バカドリル』や『バカはサイレンで泣く』など。電気グルーヴとの親交もあり、楽曲のPV制作も手がけている。
東京都出身の漫画家、イラストレーター。1988年にデビュー。代表作に『フラン県こわい城』『地獄のサラミちゃん』など。書籍やCDのイラストも数多く手がけている。
初めてキャラが「勝手に喋った」一コマ!
――では、本題の「一コマ」についてお伺いしましょう。『目玉焼きの黄身 いつつぶす?』の第4巻の第21話「焼肉で白メシ 食べる?(後篇)」のワンシーンを挙げていただきました。
焼肉を食べている時に主人公の二郎が白飯を食べたら、同席していた社長が焼肉の時に白飯を食べることを否定する人で、二郎にダメ出しをした。それを近藤は横で黙って見ていて、後から二郎が、なんでかばってくれなかったのかを責める。そこで近藤は「わざと言わなかったんだ」と。
正直、「このコマなの?」と意表を突かれた感じもあるんですが、そのココロは?