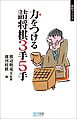趣味・実用 - マイナビ出版作品一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 河口八段の珠玉の観戦記を書籍化 本書は、自らも棋士でありながら、将棋ライターとして多くの素晴らしい観戦記を遺し、2015年に亡くなった河口俊彦八段の観戦記を書籍化したものです。日経新聞紙上に掲載された王座戦の観戦記から51局を厳選して収録しています。 天才といわれる棋士たちの才能を愛し、彼らの指す一手一手を礼賛しながらも、一方でトップだけでなく、全ての棋士を優しい視線で描き続けた河口八段。 随所に大山、升田、中原、米長といった歴代の大棋士のエピソードを散りばめられているのも河口八段にしか書けない観戦記の特長です。 本書には2001年以降に書かれた観戦記から、タイトル戦を中心に51局を収録しています。渡辺明19歳の挑戦、久保、森内、中村太、豊島といった歴代挑戦者を次々に連破する羽生善治。そして、羽生―渡辺戦で現れた将棋史に残る名手△6六銀。 将棋の内容はもちろん、河口八段が名局、名場面をどう綴ったか、その描き方も含めてぜひ読んでいただきたい一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 オリンパスOM-Dの使い方をわかりやすく紹介。最新のE-M5 Mark IIをはじめ、E-M1、E-M5、E-M10に対応 この本は、オリンパスOM-Dシリーズの使い方をわかりやすく紹介しています。あなたにとって、OM-Dが初めてのデジタル一眼カメラだとしてもきっと、すぐに使い方を覚えて、写真を楽しむことができるはず。日々の暮らしの中にOM-Dがあるだけで、なんとなく過ぎていた1日や見慣れた近所の道が新しく感じるでしょう。 それから、むじゃきに遊ぶ子どもやペット、お気に入りのカフェでいただくランチ、キラキラと美しく彩られた夜の風景……。そんな、これまでうまく写真に撮るのが難しかった、たくさんの大好きなシーンもOM-Dなら、その魅力をぐっと引き出して写真に残すことができるのです。ぜひ、OM-Dと一緒に自分らしく写真を楽しんでみてください。 もし、うまくいかないことがあっても大丈夫です。きっと、この本の中に素敵なアイデアが浮かぶ、ヒントがあるはず。それを見つけることができれば、もっともっと、OM-Dとの生活が楽しいものになるでしょう。 【本書 はじめにから】
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ノーマル三間は戦い方はこれ一冊でOK! 将棋の各戦法を指す上で必ず知っておきたい知識をやさしく丁寧に解説する「これだけで勝てる」シリーズ。第3弾となる本書は三間飛車編です。 三間飛車はプロではスペシャリストのみが指すイメージがありますが、その攻撃力の高さと、さばいたときの爽快感から、アマチュアには根強いファンがたくさんいる戦法。そういう事情もあって、求める声が多かった割に、なかなか本格的な戦術書がありませんでした。 そこで今回、三間飛車の基礎からしっかり学べる戦術書ということで、大平六段が書いてくださいました。 第1章の三間飛車の三つのコツから始まり、急戦対策、居飛車穴熊対策、左美濃対策と、この一冊で三間飛車の指し方が全て分かるようになっています。 本書で三間飛車で勝つために必要な知識と感覚を身につけてください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 何切る問題で手筋を覚えよう! 本書は日本最大の麻雀プロ団体、日本プロ麻雀連盟が贈る、麻雀に勝つために必要な手筋を解説した一冊です。 まず、それぞれの手筋に関する何切る問題を解いて、その解説を読み進めることで次々に手筋が覚えられる構成になっています。 第1章で最も基本的な部分である牌効率の手筋を学びます。それを踏まえた上で、第2章で打点も考慮した手筋を解説し、さらに第3章でチー、ポンといった仕掛けの手筋を学びます。一冊を通して読むことで、自分の手のプラスをどうやって最大化すればよいかが身につく内容になっています。 今よりさらに上のレベルを目指したい初・中級者の方には特に読んでいただきたい一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 勝負を決める妙手を探せ! 本書は将棋世界付録で好評を博した沼春雄七段による次の一手問題「ささやかなトリック」から210問を厳選し、書籍化したものです。 次の一手問題を解くことは将棋で最も大事な「読む力」をつける上で非常に有用です。 また、勝敗を決める終盤の場面で、急所を見極める力もつくので、勝率アップにもってこいのトレーニング法といえます。 沼七段の次の一手問題の特長はなんといっても解いたときの爽快感にあります。 難解な次の一手問題では次の一手を正解したとしても、なお複雑な手順が要求される場合があります。しかし、本書に収録された問題はいずれも正解手がわかれば、その「好手性」がひと目でわかるものばかりです。 勝ちを決める快感を何度も味わえるので、どんどん読み進められますし、自然に力がついてきます。 沼七段が仕掛けたささやかなトリックに挑戦して、ぜひ棋力アップに役立ててください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 新藤井システム+△5四銀型四間飛車穴熊 本書は、四間飛車が天敵の居飛車穴熊を破るための2つの有力な戦法、「藤井システム」と「四間飛車穴熊」の最新研究を披露したものです。振り飛車を牽引する若手棋士の一人、宮本広志五段が最先端のテーマ図を使って、詳細に解説していきます。 第1章は藤井システム。 居玉で穴熊を粉砕する破壊力抜群の戦法ですがここ数年は居飛車の対策も進み下火になっていました。それがここ最近になって新しい手順が編み出されたことで、見事に復活しました。本書では藤井システムの基本的な狙いから始まり、旧システムの進化と衰退の理由、さらに新システムの最前線の攻防までを詳しく解説しています。 第2章は四間飛車穴熊。 四間飛車穴熊の中でも居飛車穴熊に対しては△5四銀型が最も優れていると宮本五段は言っています。相手の陣形に応じて自在に駒組みを変化させられるのがその特長で、本書では△5四銀型優先の理由から、先手が左美濃、▲6六歩型穴熊、▲6六銀型穴熊にしてきたときのそれぞれの指し方を解説しています。 四間飛車は今も昔も将棋ファンに最も人気のある戦法ですが、これを指したいなら居飛車穴熊対策は絶対に避けて通ることはできません。 本書で最先端の定跡を学べば、ライバルより一歩も二歩も先をいけることは間違いないでしょう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 囲碁を始めて、多くの方が直面する悩みのひとつが「生きる形」と「死ぬ形」の見分け方です。本書では、林漢傑七段がその見分け方を基本から丁寧に解説します。 石の死活の基本は「欠け眼」と「中手」の考え方を理解するのが一番の早道です。「眼」と「欠け眼」の区別や、「五目中手」の形、中手とセキの見分け方など、苦手とする方が多いテーマを本書でも取り上げます。 林七段が伝授する、形でパターン化して実戦に役立てる考え方をぜひマスターしてください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 世界一上達に役立つ定石の本! 囲碁には、「定石を覚えて二目弱くなり」という格言があります。手順だけを覚えて、手の意味や使い方まで理解しておらず、実戦で正しく使えないことに対する戒めです。また、「定石だから・・・」と周りの状況を考えずに、手順だけ定石の通りに打ってしまうのもアマチュアの代表的な失敗です。 本書で紹介する定石は、「簡明であり互角以上の分かれになること」がテーマ。読者が正しく身につけすぐに実戦で使えるように、解説や紙面の構成も工夫しています。 定石は「弱くなるなら、覚えなければいい」というものではありません。手広い序盤を打つ上で、どのレベルでも大きな指針となるものです。つまり、「実戦ですぐに使える定石」はひとつ覚えるだけで、大きな戦力になるのです。 本書で、実戦的な定石を覚え確かな序盤力をつけましょう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 バビィが問う!現代麻雀の常識問題 「上級者は、推理(読み)を働かせ、相手や局面に対応して最善手を導いています」(まえがきより) 本書はバビィこと馬場裕一プロが問う麻雀の次の一手問題集です。 見えている牌はもちろん、伏せられた牌をどのようにとらえるかが中級者と上級者を分ける境界線です。 本書では捨て牌や仕掛けなどの情報を元にどんなことが考えられるか、その基本的な推理の仕方を例題を使って説明しています。 その推理の正確さが増せば増すほど、現代麻雀において重要視されている「対応力」がついてくるのです。 リーチへの対応、仕掛けへの対応、点棒状況への対応。 なんとなく「この辺が危なそう」といった曖昧な判断ではなく、切り順や仕掛け方、あるいは点棒状況から相手の手牌や判断を論理的に解き明かすことは、ワンランク上の麻雀を打つためには必須事項といえます。 まずは問題を解き、間違えたところは解説を読んでください。あなたの雀力をさらにアップするためのヒントがそこに書かれているはずです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 メディア別だからよくわかる! 魅力的なキャラクターの作り方・描き方! 創作物を作るうえで欠かせないものにキャラクターがあります。キャラクターの体格や衣装などの外見を作り上げることがキャラクターデザインですが、見た目のキャッチーさだけではなく、キャラのキャラクター性が感じられることが重要になります。本書では、キャラクターをデザインするうえでの基礎的なことから、見た人の印象にいかに残るようにするかの方法を解説していきます。 スマホゲームやポスターイラスト、ラノベ表紙など、メディアによって異なるキャラクターデザインの特徴についても解説、それぞれの読者に合った方向を見つける本としても活用できるようにします。 <章立て> 1章 キャラクターデザインとは ・キャラクターの役割 ・キャラクターデザインの流れ ・要素の発想法 2章 スマホゲーム用のキャラクターデザイン 3章 イラスト用のキャラクターデザイン ・漫画の扉イラスト ・ポスター ・一枚絵 ・ライトノベル表紙 Appendix 二次創作用のキャラクターデザイン【東方Project】
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 勝つために覚えておきたい死活の形と手筋が満載! 互先から置碁まで、幅広く登場する星の定石。そこから派生する死活は、みなさんにとって身近な存在なのではないでしょうか? 本書は、実戦に頻出する基本定石36型を取り上げ、派生問題を178題収録しています。 実戦にそのまま出てくるような死活形から、読みと手筋の練習になるような問題などさまざま。実戦の即戦力になる知識も身につき、読みや手筋といった囲碁の基礎体力を磨くにもぴったりです。 星の死活は、一局に一度は出現するほど重要なテーマですが、アマチュア五段、六段レベルの高段者の方でも完璧にマスターできていないのが実情です。 初段を目指す級位者の方、碁敵に差をつけたい有段者の方、基本死活の再確認をしたい高段者の方など、幅広い方に手に取っていただきたい一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ゴキゲン中飛車を指したい全ての人へ 現在プロ棋界では振り飛車の勝率、特に後手番の振り飛車の勝率が落ちている傾向にありますが、その中にあって唯一奮闘している戦法があります。それがゴキゲン中飛車です。角道を開けたまま中飛車に振り、2筋は受けなくても大丈夫。この発見は振り飛車の常識を変えました。大平六段は、「ゴキゲン中飛車は、現時点で藤井システムと並ぶ、平成の二大発明と言えるでしょう」と書いています。 ではゴキゲン中飛車はどういう戦法かというと、それは「対応の戦法」です。居飛車側には超急戦、丸山ワクチン、超速の急戦、超速の持久戦、一直線穴熊といった有力なゴキゲン中飛車対策があります。ゴキゲン中飛車を指しこなすためにはこれらの戦法すべてにある程度対応できなくてはなりません。そして、本書はその「勝つために必要な最低限の知識」が詰まっています。 本書の内容をマスターすれば、自信を持ってゴキゲン中飛車が指せるはず。すでにゴキゲン中飛車を指している方も、これから指したいと思っている方も、ぜひ読んでいただきたい一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 定跡を外して勝つ! 将棋上達に定跡の知識は欠かせません。棋力向上を願う将棋ファンのために定跡書は日々生み出されています。しかし、その定跡書も完全無欠というわけにはいきません。紙数の制限その他の事情から、定跡書に紹介されているのはいわゆる「本筋」と称される部分で、本筋の隣に隠れるように存在している有力手順は紹介しきれないため、省略されています。また、端歩の突き合いなど定跡局面とはわずかに違った箇所があるだけで結論が全く逆になることもあります。 本書は通常の将棋戦術書で紹介される定跡の「本筋」ではなく、そこからわずかに外れた、実は優秀で勝ちやすい指し方を紹介した「定跡外伝」と「定跡外伝2」の2冊を合わせて文庫化したものです。 定跡外の手を使うには、相手が定跡に詳しい人ほど効果的です。その知識を逆手に取って罠を仕掛け、相手を「定跡の落とし穴」に引きずり込んでください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 奇襲が大歓迎になる本 将棋をやっていれば誰でも、奇襲を見事に喰らい、なす術もないまま敗れたことがあるでしょう。 実力を出し切って負けたのならまだしも、「対策を知らないから負けた」では悔しすぎます。 筋違い角、急戦石田流、鬼殺し、パックマン戦法、嬉野流・・・。 奇襲は確かに最善の指し方ではないのかもしれませんが、そう簡単に勝てないようになっているのも事実。特に優秀な奇襲には2重3重のワナが張り巡らされているのが普通で、プロ公式戦で採用されることも少なくありません。 ではどうすれば奇襲を破れるのか?? 本書では、「奇襲に備えるには、まず足元を固めること」だと教えています。 つまり、まずは奇襲の狙い筋、成功例を熟知することから始めるのです。 書籍中では全ての奇襲について「奇襲成功図」までの手順を紹介しています。 そのうえで、対策の方向は3つに分かれます。 (1)相手の狙いを外す (2)がっちり受け止める (3)ハメ手の裏をかく (1)はそもそも奇襲の局面にさせないという方法です。これも有力ですが、少し逃げ腰でしょうか。(2)は奇襲を真っ向から受け止め、最善手で返すということ。これこそ奇襲破り、と言いたいところですが、最強の応手は(3)でしょう。 奇襲の狙いを看破したうえで、それを逆手に取って勝つ。これほど痛快な勝ち方はありません。 本書には奇襲の裏も表もすべて記載されていますから、奇襲破りはもちろん、奇襲を使うこともできてしまいます。 いち早く本書を手にとって、奇襲の世界を完全に自分の物にしてください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 良い手と悪い手の本質を知る、それだけであなたの碁はガラリと変わる! 筋が良くなると当然、石の働きの効率が良くなり棋力はぐんぐん向上します。さらに、相手が打ってきた俗筋にも気が付けるようになり、いわゆる「筋悪碁」や「力碁」にも強くなります。上達に、筋が良くなることは必須と言ってもよいでしょう。 筋良く碁を打つための第一歩は、俗筋を知ることです。そこで本書は、「多くの方が打ちそうな悪い筋を紹介し、どのように悪くなるか」を説明しました。その上で、どの手をどう直せば筋が良くなるかの解説をしています。 アマチュアの悪い手や筋にはパターンがあり、以下の5つに気をつけると劇的に筋が良くなります。 ・まずは、自分の着手が悪手ではないか、と疑問を持つこと ・定石や定型を正しく打てているか ・着手に一貫性があるか ・石の形は正しいか(愚形を打っていないか) ・石の方向は正しいか 本書はアマチュアの碁を題材に、悪手や俗筋をテーマ図として、正しい着手や筋を考えられる構成になっています。 棋力向上を目指す方、碁敵に差をつけたい方など、多くの方に手に取っていただきたい一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 終盤の手筋のバイブルが文庫化! 「いくら序盤、中盤が良くても、終盤が悪くては、勝つことはできません。棋友同士で『あいつは、序盤はうまいが、終盤が甘いからなあ』といわれる人と『あいつは、序盤はまずいが、終盤がしっかりしているからなあ』といわれる人がおります。前者は仲間から軽く見られている場合であり、後者は仲間から恐れられている人です。終盤の強さイコール将棋の強さでもあるわけです」(まえがきより) 本書は関根茂九段による終盤の名著「終盤の総手筋」と「スッキリ明快詰将棋」の2冊を合わせて1冊の文庫として復刊したものです。 第1部「終盤の総手筋」では将棋に勝つために絶対に必要な寄せと詰みの手筋を総まとめにして解説したもの。関根九段が例題を出しながら手取り足取り教えてくれるので読むだけできちんと理解できますし、すぐに実戦で使うことができます。 第2部「スッキリ明快詰将棋」では元の書籍から3~7手詰を抜粋し、108問収録しています。第1部で学んだ手筋を使って問題を解くことで、さらに手筋の理解が深まります。 序盤・中盤はうまくいくのに、いつも終盤で負けてしまう、もっと終盤が強くなりたいという方にぜひ読んでいただきたい一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 二階堂プロがあなたに贈る、麻雀守りの技術 「攻撃も守備も、いずれもちゃんとできなければ、真の強者にはなれないと信じています。そういった信念のもとに、私なりの『守備の基本』を総動員してまとめました」(二階堂亜樹・まえがきより) 本書は多くのタイトル戦やテレビ対局で活躍中の日本プロ麻雀連盟・二階堂亜樹プロが麻雀の守備について書いた戦術書です。物理的安全牌、スジ、ワンチャンスといった基本的な考え方から、読みや実戦での押し引き、追っかけリーチの是非といった複雑な場面での守備まで、二階堂プロ自身の基準を紹介しながら解説しています。本書に書いてあるのはオリジナリティあふれる高等戦術ではなく、雀士であれば全員が身に付けておくべき「基本」です。しかし基本をおろそかにしてはトータルで絶対に勝てないのが麻雀です。本書で二階堂プロに「守りの基本」を教わりましょう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 端を制するものが現代将棋を制す 矢倉、美濃、穴熊、銀冠、舟囲い、金無双……。将棋にはいくつもの囲いが存在しますが、その全てに共通する弱点があります。 それが端です。 囲いは基本的に玉を端の方に囲うものであるため、端攻めが脅威になることは必然の結果であるともいえます。将棋において最も堅固な囲いであり、現代将棋の象徴ともいえる穴熊でさえ、端攻めをまともに食らってはもろくも崩れ去ります。 そうであれば、端の攻略の仕方、そして逆に端を攻められたときの正確な受け方は将棋を指す上での必修科目といえます。 本書はまさにそのニーズに応えるものです。 第1章「矢倉編」では、中盤での仕掛けから本格的な戦いまでの端攻め。 第2章「美濃囲い編」では、終盤を中心とした玉を直接攻める手筋と、相振り飛車での仕掛けに威力を加える端攻め。 第3章「穴熊編」では、いつも悩まされている堅さを、かなり弱体化させてしまう端攻め。 第4章では銀冠、舟囲い、金無双といったその他の囲いの端攻めを紹介しています。 見開き2ページで一つの手筋を紹介する形になっているので、自分の興味のあるところから読めるようになっています。 本書を読んで▲1五歩△同歩▲1三歩!の端攻めを常に狙う姿勢と逆に攻められたときの正確な対処を身につければ端はあなたにとって強力な武器になるはずです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 北浜八段が贈る詰みの教科書 「より実戦的な詰み手筋の紹介と詰将棋を合わせたような本はできないかと思って書いたのが本書である。本書ではあくまで『実戦で使える』ということを最優先にした」(まえがき) 言うまでもないことですが将棋の勝敗は玉を詰ますことで決まります。将棋を指していれば玉を詰ませば勝ち、詰ませられなければ負け、という状況にも何度も直面するものですが、そこで勝ちたいなら詰ます力をつけるしかありません。そして本書はその力をつけていただくためにあります。 まず第1章「絶対覚えたい基本手筋20」では頭金から始まり、尻金、一間龍、送りの手筋、金頭桂など、最も基本的な詰み手筋を紹介しています。 続く第2章「ワンランク上に行くための重要手筋」では退路に捨て駒、駒の打ち場所を作る桂捨て、左右挟撃、上下挟撃、開き王手、両王手といったやや高度な詰み筋を解説しています。 第3章「手筋応用編」ではやや複雑な局面で第1、2章で覚えた手筋の形に持ち込んで詰ます方法を伝授します。 第4章「囲い攻略の詰み手筋」では矢倉、美濃、穴熊、左美濃、銀冠といった囲いに対して使える詰み筋を囲い別に紹介します。 そして第5章「練習問題」で北浜八段作の詰将棋に挑戦します。徐々に難しくなりますが第1~4章の手筋を駆使すれば解くことができる問題です。 このように、頭金から始まって高度な詰み筋まで、段階的に詰み筋を学んでいけるのが本書の大きな特長です。難しいと思ったら前の章に立ち返って繰り返し読めば、必ず全ての手筋を身につけることができます。 本書で紹介された詰み筋を完全に自分の物にして、実戦で詰みがある局面で詰みを逃さない力を身につけてください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 動対静、不滅の対戦 「江戸時代に作られた宗看、看寿の詰物は名品で現在も色褪せていない。同じように升田対大山の名局は棋界が続くかぎり不滅であろう」(内藤國雄・まえがきより) 大正7年3月21日、升田幸三誕生。 その5年後の大正12年3月23日、大山康晴誕生。 この2人がのちに生涯のライバルとなり、我々に遺してくれた名局の数々は、彼らが亡くなって四半世紀たった今でも、その輝きを失うことはありません。 このたび、将棋界の宝ともいうべき大山VS升田の対局、全174局を全て解説付きで収録した一冊「大山VS升田全局集」が完成しました。昭和14年、木見会勝ち抜き戦(角落ち)から始まって、高野山の決戦、升田の三冠達成、大山の復活と絶頂、そして升田式石田流シリーズとなった最後の名人戦まで、30年に及ぶ棋界の頂点をめぐる戦いを余すところなく収録しています。 将棋史上に残るライバル対決。たっぷりとご堪能ください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 武宮の常識に触れたとき、あなたの碁は格段に上達する! 「アマチュアの皆さんはどんなことを考えて碁を打っていますか?」 武宮正樹九段と言えば、宇宙流。自由な発想から繰り広げる模様作戦に多くの囲碁ファンが魅了されてきました。しかし、その打ち方は実は非常に合理的で、アマチュアの参考になるものです。 では、武宮流を真似すれば碁に勝てるか、というと、そううまくはいかないもの。その理由は、真似をされる多くの方は代名詞といえる「大模様」を張ることだけを真似されるからです。武宮流は闇雲に模様を張る碁ではなく、ある考え方に基づいて打ち進めると自然に外回りの碁になると言います。 武宮の碁を構成する本質は、「碁は二人で打つゲーム」という考え方です。 いかがでしょうか?「当たり前じゃないか」という感想を持つ方が多いでしょうか。 しかし、本当に理解できていますか?この考え方に基づいて、碁を打てていますか? この言葉の真の意味を理解したとき、あなたの碁は変わり、ぐっと棋力が上がるでしょう。 本書で「武宮の常識」に触れれば、碁が一層楽しくなり、格段に上達することをお約束します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 世界中の高級時計を網羅。あなたに合う最高の時計が見つかります! 世界の高級腕時計71ブランド・約270モデルを豊富な写真と情報で紹介。 名だたるブランド・名機を収めた完全保存版です。 また、時計の構造やムーブメント等の歴史もわかりやすく紐解きます。見て読んで楽しめる一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ていねいでわかりやすい、フラの教科書決定版! 基本のステップ15種類、頻出のハンドモーション31種類の動きを 大きい写真とポイントでくわしく・わかりやすく解説しています。 レッスンの予習や復習にぴったりの一冊です。 日本人フラダンサーのパイオニア、クウレイナニ橋本先生が振付けた 『カイナマヒラ』『ウルパラクア』『レイ ナニ』も紹介。 またそれ以外にも、パーウースカートの作り方や ステージメイクの仕方など、フラに役立つ知識が満載です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 電車のメカニズム、運転のしくみ、駅のはたらきがよくわかる! 電車のメカニズムや運行のしくみを、豊富な写真&精密なイラストでわかりやすく徹底解説しています。 電動機(モーター)や動力伝達装置、扉の開閉装置、運転台の設備、台車の構造、ブレーキ装置、自動列車制御装置といった車両の設備や電車を動かすしくみはもちろん、変電所や第三軌条などの電車に電気を届けるしくみや、線路や駅のしくみまで紹介。 身近な電車のしくみを知れば、通勤や通学など、日々の生活で利用する際にも電車を楽しめるようになるはずです。 鉄道ファンにとっても、これから鉄道のことが知りたい人にとっても満足できる一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 先手中飛車戦術書の決定版! 真ん中に飛車を振り、中央から敵陣を突破する先手中飛車戦法。 単純でありながら破壊力は抜群で、プロ間でも非常に優秀な戦法として認識されています。 先手中飛車VS居飛車の対抗形では先手中飛車が有利、というのが本書の著者村田顕弘五段の持論。「▲7六歩に△8四歩をとがめるつもりで▲5六歩と指している」と言います。本書は村田五段が対抗形における先手中飛車有利を証明するため、有力な居飛車の5対策すべてに挑戦した一冊です。 第1章 5筋位取りVS右銀急戦 第2章 5筋位取りVS△6三銀型急戦 第3章 5筋位取りVS後速△7三銀型 第4章 居飛車穴熊VS先手中飛車 第5章 居飛車△5四歩型の攻防 プロ公式戦で現れた最新の変化はもちろん、実戦で現れなかった研究手順まで惜しみなく披露しています。まさに先手中飛車戦術書の決定版といえる内容であり、最先端の定跡が学べる一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 四間飛車の急戦、持久戦、藤井システムの考え方が分かる! 「本書には、四間飛車を指しこなすうえでの大事な心得が詰まっている」(まえがき) 角道を止め、四間に飛車を振り、美濃囲いに囲う。 序盤の駒組みの簡明さと常に自分のペースで戦えるという大きな利点から将棋ファンに最も愛されている戦法、四間飛車。 本書は定跡手順を暗記するのではなく、指し手の方針や考え方を教える「将棋の考え方シリーズ」の四間飛車編です。四間飛車を指す上で常に念頭に置いておくべき考え方を「15の心得」として提示し、例題を出しながら解説してきます。 著者は「定跡ナビゲーター」の異名を取る長岡裕也五段。全ての戦法の序盤戦術に精通しており、羽生善治三冠の研究パートナーとしても有名です。 本書では昔ながらの居飛車からの急戦策、各種持久戦や居飛車穴熊対策、藤井システム等の戦型を、仕掛け周辺を中心に細かく解説しており、本書を読めば四間飛車については間違いなく人並み以上の知識が得られます。 ぜひ本書で、美濃囲いの堅さを生かしたカウンターや、四間飛車のさばき・攻めの破壊力をマスターしていただき、日々の実戦に役立ててください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 置石がみるみる減っていく! 本書は、置碁(9~7子局)を題材に碁の考え方を示した書籍です。級位者の方を対象としており、細かい手の良しあしよりも、全体の石の働きやつながりに重点を置いて解説しています。 従来の置碁書籍は、うわ手目線から互先で打つような手法を良い手としていました。しかし、そのような手は難しく、した手は「なぜその手がいいのか」が理解できないまま打ち続け、上達の妨げになっていました。 そこで本書は、置碁ならではの分かりやすい手法を推奨しています。「石と石をどう関連させて働かせるか」という考え方を学べるように、やさしく解説しています。 この考え方はどのレベルにおいても通用するもので、碁において最も重要な考え方です。具体的な手よりもこのような基本的な碁の考え方こそ、置碁で学ぶべきものと言えるでしょう。本書は、指導経験豊富な著者がした手目線に立ち、分かりやすさを追及した渾身作です。繰り返し読んで棋力向上に役立ててください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 北海道から九州まで、全国に広がる新幹線の車両、路線など、その魅力のすべてがわかる1冊です。 2016年3月、北海道新幹線の開業によって新幹線は北海道から九州までがつながりました。本書では全国に広がる新幹線の車両、路線、しくみ、歴史など、そのすべてを紹介します。 歴代の各路線の車両、開業から未来構想・リニアモーターカーまでを紹介、スピードと快適性の技術、無事故を続ける安全のしくみなど、日本が誇る新幹線のすばらしさを伝えます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 終盤のメカニズムを解き明かせ! Zとは「何枚駒を渡してもぜったい詰まない形」の意味で、トラック一台分の駒を持っていようが、東京ドーム一杯分だろうが詰まない。それが“ゼット”です。自玉が“ゼット”になった瞬間に、飛車でも角でも切って必死を掛ければ勝つことができるのです。 (まえがきより) 本書は日浦市郎八段による終盤をテーマにした名著「Zの法則」「投了の真相」の2冊を合わせて1冊の文庫にしたものです。 「Zの法則」では何枚持っても絶対詰まない形(=ゼット)をテーマにしています。自玉をゼットにして相手玉に襲いかかる必殺の終盤術を体得してください。 「投了の真相」はプロの実戦で現れた詰みの局面を出題しています。詰将棋は駒を捨てる手が多くなりますが、実戦では駒を取る手が多くなるもの。問題を解くことでより実戦的な終盤力を身につけることができます。 勝敗を分けるのは終盤。本書で「将棋の勝ち方」をマスターしてください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 相居飛車の手筋が満載! 本書は矢倉、角換わり、横歩取り、相掛かりといった相居飛車の戦いにおける手筋を解説したものです。実戦ですぐにでも使えそうな手筋が100以上も紹介されています。 さらに本書には三つの大きな特長があります。 一つ目はタイトルにもなっている「格言・用語」で覚えるという点。 ただ手筋を羅列しただけではなかなか頭に入ってきませんが「と金は金で金以上」「下段の香に力あり」「角筋には玉を囲うな」「飛車の横利き受けに強し」といった格言や「継ぎ歩」「垂れ歩」「合わせの歩」「焦点の歩」などの用語と一緒ならぐっと覚えやすくなります。 本書にはこういった格言や用語が散りばめられているため、将棋に対する考え方とともに数多くの手筋を覚えることができるのです。 また、加藤治郎著「将棋は歩から」(東京書店)、加藤治郎・木村義徳・真部一男著「将棋戦法大事典」(大修館書店)などの名著からの引用も随所にあり、本書を通して先人の知恵と努力、遺してきたものの偉大さにも触れることもできます。 二つ目の特長は、手筋を例題とともに解説する本でありながら、次の一手問題集としても読める、ということです。 本書は右ページに例題、左ページに正解図、という構成になっており、右ページの解説文には正解手順が現れないように工夫して書かれています。 腕に自身のある方は左側を隠して、自分がどれだけ手筋を知っているか力試しをしていただければ幸いです。 最後の特長は、何と言っても「読んでいて面白い」ということです。 「その手は桑名の焼き蛤(はまぐり)」 「堅いなぁ、片倉小十郎やなぁ」 「角のにらみは、歩で“遮断法人”」 などなど、丁寧な解説の中に縁台将棋で飛び出すようなジョークが混在していて楽しく読み進められる内容となっています。 神崎健二八段が精魂込めて書いた、まさに居飛車基本手筋の決定版といえる一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 横歩取りの現在が手に取るように分かる! 「本書では横歩取りの今現在の流行型である△8四飛・7二銀・5二玉型、その中でも一番激しい変化に絞って解説している。面白い変化がいっぱいあるので一度将棋盤に並べていただきたい」(まえがきより) 本書は日浦市郎八段がプロ・アマ問わず流行している横歩取りにおいて、特に頻出の2つの形「△2四飛ぶつけ」と「△8六歩合わせ」に絞って、プロの実戦を題材に解説するものです。 第1章の「△2四飛ぶつけ」では初期の△2四飛▲同飛△同銀▲8四飛の変化から最新の△2四飛▲同飛△同銀▲8六歩の変化まで時系列に沿って詳しく解説、どのような曲折を経てこの形が指されるようになったのかがよく分かります。 第2章の「△8六歩の合わせ」ではそもそも▲3六歩に△2四飛ぶつけはなぜ成立しないのか?から始まり、▲3六歩△8六歩▲同歩△同飛▲3五歩△8八飛成▲同銀△5五角打以下の変化を徹底的に解説しています。こちらもプロの細かい工夫の積み重ねがよく理解できる内容になっています。 本書を読めば、「今プロが何を問題にしているのか」も、その前提条件となる変化についても精通することができます。アマチュアでも大流行の横歩取りですが、ライバルに一歩も二歩も先んじることができるでしょう。 最新戦術書としても、プロ棋戦の観戦ガイドとしても非常に有用な一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 今、一番レベルの高い麻雀戦術書 「ネット麻雀での統計データをもとに生まれた『現代流データ麻雀』は“必勝法”ではありません。なぜなら、すでに世に広く知られた戦術を使う相手同士で対戦した場合は大きく勝ち越すことができないからです」(まえがきより) 本書は自団体で最高位と發王位を同時獲得、テレビではモンド杯優勝、ネットでは天鳳名人戦優勝の現在最強の打ち手と呼び声高い石橋伸洋プロによる、最高レベルの麻雀戦術書です。 現代流データ麻雀をマスターしている打ち手の考え方、打ち方を透視し、予測し、それを逆手に取って勝つ方法を伝授しています。本書は「弱い人に勝つ方法」ではなく、「強い人に勝つ方法」が書いてある本だといえます。 前著「黒いデジタル麻雀」で概念的に説明された戦術論を具体的な局面に落とし込んで解説しています。41の例題が収録されていますが、それらは決して単なる何切る問題ではなく、何を切り、何を考えておくべきかを問うています。ハイレベルになった現代麻雀において勝ち続けるにはここまで深く考えなければいけないのかと驚かされます。 相手の打ち方や動向を予想し、人より常に一歩、二歩先に行った麻雀、現在のベストの麻雀の打ち方がこの本にあります。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 四間飛車で勝ちたい方必見! 「四間飛車は、一番人気があるといえる戦法です。また、序盤の作戦を覚えるのが一番簡単ではないかと思えることもあります」(まえがきより) 好守のバランスに優れ、アマチュアに最も人気のある戦法、四間飛車。 四間に飛車を振り、玉を美濃囲いに囲う。序盤は比較的スムーズに行きますが、相手に急戦を仕掛けられたときのタイミングや居飛車穴熊を始めとする持久戦でこられたときの戦い方がいまいち分からない、という方も多いのではないでしょうか? そこでぜひとも読んでいただきたいのが本書です。 急所を分かりやすい解説することに定評のある大平武洋六段が、四間飛車のポイントを丁寧に説明しています。 序盤の要点、急戦・持久戦への対策、さらに攻めと守りの部分的な手筋までしっかり解説。 本書を読んで四間飛車の勝ち方を身につけてください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 内藤國雄棋士人生56年の集大成 自在流と呼ばれる華麗な棋風で活躍した大棋士、内藤國雄。 タイトル戦登場13回。獲得は王位2、棋聖2の合計4期。棋戦優勝は13回。空中戦法で升田幸三賞受賞。通算1132勝1000敗達成、そして2015年3月、引退。 詰将棋作家としても知られ、「攻方実戦初形」で看寿賞特別賞を受賞。 本書には、内藤九段が棋士人生56年のうちに残した名局の自戦解説(30局)に加え、観戦記を収録しています。 升田幸三九段戦 憧れの人との初対局 大山康晴王位戦 生涯最高の一着「▲3六歩」 中原誠棋聖戦 初タイトル獲得の一局 加藤一二三三段戦 前代未聞の一局 谷川浩司戦 光速の寄せの片鱗を見る 羽生善治棋王戦 予定の順に誤算 など、将棋史に残る名局から知られざる加藤九段(当時三段)、谷川九段(当時9歳)との駒落ち戦まで、幅広く収録しています。 しかし、内藤九段の才能は指し将棋だけにとどまるものではありません。 本書では、内藤九段作の珠玉の詰将棋、必至、どっちが勝ち(各10題)、エッセイを収録しています。 詰将棋編では有名な「ベン・ハー」「玉方実戦初形」「攻方実戦初形」を本人の解説付きで読むことができます。 まさに「内藤國雄のすべて」というタイトルにふさわしい内容で、将棋ファン必携の記念碑的一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 誰も知らない必殺の石田流! 江戸時代の盲人棋士石田検校が生み出し、升田幸三実力制第四代名人によって奇襲からプロでも通用する戦法に変貌をとげた石田流。 本書第1部「真・石田伝説」では升田が編み出した升田式石田流に始まり、その他アマチュアによって独自のアレンジが加わった立石式石田流、楠本式石田流などを解説しています。大駒を大胆に使い積極的に勝ちにいく、攻め好きな振り飛車党の方にお勧めです。 第2部「役に立つ将棋の格言99」では古くから伝わる将棋の勝ち方を言い表した格言を例題とともに解説しています。 本書でライバルの知らない戦法や考え方を身につけ、棋力アップを成し遂げてください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 模様がこんなに簡単に地になる! 本書は、「模様作戦の勝ち方」をテーマに、アマチュアが理解すれば強くなる碁の考え方を示した書籍です。碁は最後に地が多いほうが勝つゲームなので、「模様作戦」においても「いかに、模様を地にするか」が最大のポイントです。 「模様を囲えたのに負けてしまった」、「模様の真ん中で生きられてしまった」など、悩みは尽きないのも事実ですが、本書で「模様を地にする方法」を身につければ、驚くほど勝率がアップします。 模様を効率良く地にするための、重要な考え方は以下の4つです。 ・弱点があればしっかり守る ・自分の模様のほうが大きい場合は囲う ・攻めながら模様を囲う ・侵入してきた相手を厳しく攻める 本書では問題を解きながら、4つの考え方を学ぶことができます。これらの考え方を身につければ、自信を持って模様作戦を実践できるでしょう。 また、金八段の前書『効率良く地を囲う4つの基本』とセットで読めば、効果は倍増です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 上達への最短の近道は基本死活にあり! 「囲碁に興味を持っていただき、ありがとうございます。囲碁を打ちたいと思ったらすぐに始めましょう。」 2016年は囲碁界にとって、激動の一年となっています。アルファ碁の出現や井山裕太の七冠達成など、一般ニュースでも大きく取り上げられる出来事が連続で起こりました。そのようなニュースを目にして、囲碁に興味を持たれた方も多いのではないでしょうか。また、以前やっていてこの機会に再び始めたい、という方もいらっしゃるかと思います。 そんな声に、今日本で一番囲碁が強い男、井山裕太七冠が応えます。 囲碁を打つのにまず学ぶべきテーマは、「手筋」と「詰碁」です。本書は、その第二弾の詰碁編です。 石が生きているか、死んでいるかはとても重要で、勝敗に直結してきます。石の生き死にのことを「死活」と呼びますが、死活を身につけることが上達への最短の近道であり、囲碁をより面白くする要因となります。詰碁にはやさしい問題からむずかしい問題まであり、レベルは幅広いですが、死活の基本を身につけるにはやさしい問題をたくさん解くことが重要です。 第1章では、「欠け眼」や「ナカデ」など、死活の前提となる基本的な知識を紹介します。第2章で問題を解きながら、基本死活の理解を深めることができます。第3章は練習問題を71題用意していますので、ぜひいろいろな問題に挑戦しましょう。 死活は、問題を解いた分だけ強くなる、つまり努力が棋力向上に反映しやすい分野です。本書を繰り返し解けば、初段レベルの死活力を身につけることができます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ゴキゲンVS超速の決定版! ゴキゲン中飛車の最大の難敵といえば超速。一直線に▲4六銀と繰り出し、そこから左の銀も攻撃参加する「超速二枚銀」と後手の動きを封じて穴熊に組む「超速穴熊」の2つの有力策を自在に使い分けられる、非常に優秀な戦法です。ゴキゲン中飛車を指したいのなら、超速は避けて通れないところですが、手を焼いている方も多いのではないでしょうか?そこで本書が救世主となります。中飛車のスペシャリスト杉本昌隆七段が超速に対して最も有力だという「銀対抗△4四銀型」の指し方を徹底的に解説しています。 序章で「対超速△4四銀対抗の考え方」を述べたあとに、第1章では急戦の「超速二枚銀」を解説。△4四銀で持久戦に持ち込んでしまえば超速急戦は怖くありません。先手の攻めを受け止めるコツを学んでください。 続く第2章は「対超速穴熊編」。この場合は後手も穴熊にして相穴熊の戦いになります。先手の7七角を目標に巧みにリードを奪う手順が非常に参考になります。 第3章では先手中飛車対後手の超速を紹介。超速は後手番でも有力な戦法ですが、一手の違いが大きく、中飛車が有利に戦いを進めることができます。 第4章では別の超速対策として△3二銀型を解説しています。角道を止めずにさばいて勝ちたい方にはこちらがオススメです。 また、コラムでは弟子の藤井聡太新四段のことも書かれており、こちらも必見です。本書の内容をマスターすればもう超速を恐れることはありません。杉本七段が惜しげも無く研究を披露した一冊。中飛車党の皆さん、必見です!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 形から入るのが一番の近道 本書は形と感覚でヨセを上達することを目指しています。「布石」や「定石」などの分野と比べ、「ヨセ」の勉強は気が進まない、と感じる方が多いようです。それは、計算のイメージが強く、どうしても難しいイメージがあるからでしょう。しかし、初級~中級の段階では、細かいヨセの目数を知るより、形からアプローチするほうが効果的です。本書でも、蘇耀国九段が級位者の方にまず覚えてもらいたい基本的なヨセの形を厳選しています。先手でヨセるべき形や、似たような形でも価値が大きく変わるヨセなど、収録されている問題は実戦頻出のものばかりです。まずは本書でヨセの基本を形から身に付け、終盤力アップをぜひ実現させましょう!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 車両や駅の構造、運行や整備、秘密の回送ルートまで 東武鉄道の各路線や車両、駅、車両工場&基地、運行、保守などについて、その成り立ちやしくみを余すところなく徹底紹介。 走行中のさまざまな車両の詳細(形式図や駆動方式、制御方式など)はもちろん、駅の構造や過去に走った臨時列車、自動列車制御装置(ATC)のしくみまで写真&イラストで解説します。さらに「東上線と日光線を結ぶ秘密の回送ルート」や、「西新井駅にある不思議な改札」など、東武鉄道がより一層好きになる情報も満載です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 逆転力を身につけろ! 本書は、級位者の方から有段者の方まで、すぐに実戦で役立つ全213題を収録したヨセの問題集です。 出題されている問題は、実戦でよく現れる形ばかり。これまで何気なくヨセていた形にも、さらに得する手段があることに驚かされるはずです。第1章と第2章では、隅、辺の初歩的なヨセ方や得するツギ方など、知っておきたい基本テクニックを網羅しました。第3章と第4章では、先手でヨセる手筋や相手の地を大きく荒らす手筋など、碁敵に差をつける高級テクニックを厳選して出題しています。 本書の問題を繰り返し解いて正しいヨセ方を身につければ、きっとヨセだけで10目得できるようになるでしょう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 新しい武器を身につけろ! 日本だけでなく、世界中で大流行している、一路ずれた「中国流」と「ミニ中国流」。この形を2007年に初めて打ち始めたのが、本書の著者である河野九段なのです。 本書では、一路ずらした中国流を「スモール中国流」、一路ずらしたミニ中国流を「スモールミニ中国流」と名付け、「なぜ一路ずらすのか」といった基本的な考え方はもちろん、世界最先端の手法までを詳解しています。 河野九段も「現時点で僕が知っている知識はほとんど網羅したつもり」と言っている通り、相手が打ち込んできたときのあらゆる対応策はもちろん、相手が避けてきた場合の考え方まで丁寧に解説してあります。 本書をマスターすれば、「スモール中国流」がきっとあなたの新しい武器になることでしょう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 偶然ではなく、実力で一手勝ちをもぎ取る! 石と石がからみ合う『攻め合い』は、最も白熱する戦いです。一局の命運を左右するといっても過言ではありません。みなさんは『攻め合い』をどのように戦っていますか?「とにかくダメを詰めていって、運が良ければ勝てる」というふうに思っている方は少なくないと思います。 そんな方に特に読んで頂きたいのが、この一冊。河野臨天元が、9つの『攻め合い』必勝テクニックを伝授します。偶然ではなく、狙って確実に『攻め合い』に勝つことを目指します。 本書を繰り返し読むことによって、みなさんの攻め合い力は確実にアップします。今までハラハラ戦っていた『攻め合い』に、堂々と自信を持って臨めるようになるでしょう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 これが山下の眼だ! 山下敬吾棋聖が、アマチュアの碁を鋭く分析し、弱点を浮き彫りにします。 碁で特に大切なことは「大場・急場の考え方」「石の守り方」「石の攻め方」の3つ。 例えば、大場・急場の考え方では、「弱い石がなければ大場へ」「相手が広げてきたときが、模様を荒らすタイミング」、石の守り方では、「守るときは、利きを残さずしっかりと」など、基本的な考え方を山下棋聖ならではの視点から解説しています。 「少し気がつくだけで、こんなに見えるものが違うのか」ということが実感でき、実戦でも効果てきめんの一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 初級者でもスラスラ目で追える、好評打碁シリーズ第5弾は、日本最強棋士・山下敬吾本因坊の碁です。本格的な碁なので、アマチュアが手本とするのに最適です。 激闘!! シリーズ第5弾は、いよいよ山下本因坊の登場です。 2010年に開催されたアジア大会で、李昌鎬九段、古力九段を破った対局はもちろん、張栩九段、趙治勲九段、武宮正樹九段など超一流棋士との熱戦を、とことん解説しています。 山下本因坊は、従来は「手厚く構えて攻めを狙う」という棋風でしたが、最近は実利を求める傾向が強くなってきたそうです。 本書を読めば、さらなる高みを目指している山下本因坊の、新たな一面を実感できることでしょう。 もちろん、戦いの急所や勝負所の決め方なども詳しく解説していますので、アマチュアの皆さんの棋力向上にも、きっと役立つはずです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ボールペンで描くかわいいイラスト練習帳。メールやスマホでも使っちゃおう! 手帳やスケジュール帳、手紙、ノートの端にかんたんにイラストが描けるようになる実用書です。友だちとの約束、買物の予定や料理のアイデアなど…サラサラッとかわいいイラストを添えるだけで、毎日の出来事がもっともっと楽しくなります。本書ではボールペンやサインペンを使った簡単なイラストの描き方、初めての人でも上手に描けるコツ、実践的でおしゃれなイラストの使い方を人気イラストレーターのyukkyさんが紹介します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 光速の寄せの秘密がここにある 光速の寄せ―。谷川浩司九段の鋭い終盤を称する言葉としてあまりにも有名なフレーズです。本書はこの光速の寄せの秘密を伝授する一冊。 日本将棋連盟から平成16年に発行された「谷川流寄せの法則 基礎編」と「谷川流寄せの法則 応用編」の2冊を合わせて1冊の文庫にしたものです。 どんな囲いにも急所があり、その急所を逃せば早い寄せにはつながりません。基礎編では囲いの崩し方を基本に、実戦的な寄せ手筋を解説しています。応用編では汎用性の高い格言を紹介、さらに谷川九段の実戦から寄せに直結する例を選んで問題にしています。 本書の内容をマスターすれば、寄せは決して難しいものではなくなるはず、と谷川九段は言っています。ぜひ皆さんも本書で光速の寄せの神髄に触れてください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 矢倉は大事なのは手順よりも考え方 「矢倉囲いができれば初段」という言葉がありますが、囲いの手順だけ覚えれば良い、と思ってはいけません。棒銀、右四間飛車、矢倉中飛車、スズメ刺し…、いろいろな戦略に対応する力が大事になります。「対応力」というのは、一手一手交互に指す将棋では実は一番大事なことです。その力を付けるには矢倉戦はうってつけなのです。(まえがきより) 本書は将棋の各戦法において、定跡手順を覚えるのではなく、その考え方(=心得)を身につけることを主眼とする「将棋の考え方シリーズ」の第5弾、矢倉編です。 まえがきにあるように矢倉をきちんと指すためには原始棒銀をはじめとする急戦に対応する力が必要です。逆に言えば、そのような対策を身につけて矢倉が指せる人は、十分初段の力がついているといえます。 本書は矢倉の駒組みから始まり、序盤の急戦への対応、さらに中盤の進め方の方針や終盤での考え方まで丁寧に解説。個々の場面での指し手を示すのではなく、どのような考え方で指し進めていけばよいかが解説されているので、相手に変化された場合でも幅広く応用が効く内容となっています。 まさに矢倉で勝つための鉄則と心得が網羅された内容で、この一冊を読めば自信を持って矢倉が指せるようになるはずです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 JRで運行している現役車両を一同に紹介する列車図鑑です。ジョイフルトレイン、SLにも対応しています。 現在全国を走っているJRの列車を項目別に紹介する鉄道図鑑です。項目は次の通りです。 ・新幹線 ・特急 ・寝台列車・ジョイフルトレイン ・SL ・普通列車 ・レストラントレイン 山手線新型車両「E235系」、2016年デビューの新列車「GENBI SHINKANSEN(現美新幹線)」「IZU CRAILE(伊豆クレイル)」など最新車両からローカル線を走る普通列車まで、様々な現役列車が満載です。気鋭の鉄道写真家山崎友也氏率いるレイルマンフォトオフィスの写真で紹介する列車数は249種類、掲載写真数は500枚超、常に全国を飛び回るカメラマンたちが印刷開始ぎりぎりまで撮影した最新写真で鉄道の魅力を余すところなくお伝えします。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 井山流で強くなる!七冠王直伝の手筋入門書 「囲碁に興味を持っていただき、ありがとうございます。囲碁を打ちたいと思ったらすぐに始めましょう。」 2016年は囲碁界にとって、激動の一年となっています。アルファ碁の出現や井山裕太の七冠達成など、一般ニュースでも大きく取り上げられる出来事が連続で起こりました。そのようなニュースを目にして、囲碁に興味を持たれた方も多いのではないでしょうか。また、以前やっていてこの機会に再び始めたい、という方もいらっしゃるかと思います。そんな声に、今日本で一番囲碁が強い男、井山裕太七冠が応えます。 囲碁を打つのにルールの次に必要となる知識はズバリ、「手筋」と「死活」です。本書は、その第一弾の手筋編です。囲碁で手筋と呼ばれるものはたくさんありますが、実戦で使う手筋は限られており、最初に覚えるべきものはそんなに多くありません。本書では、囲碁の醍醐味である「石を取る」手筋を紹介しています。第一章で紹介している手筋を、第二章と第三章の問題を解きながら覚えましょう。全ての問題にヒントがついていますので、問題がなかなか解けない方はそちらも活用してください。何回も繰り返し挑戦して、全ての問題をヒントなしで解けるようになれば、基本手筋が身に付いたといってよいでしょう。自信を持って実戦に臨んでください。コラムでは、「七冠制覇」と「世界戦への想い」について井山七冠が語ってくれています。囲碁に興味を持つ、全ての方に手にとっていただきたい書籍です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 この一冊で将棋界の1年が分かる! 1年間の将棋界の動きが分かる、昭和43年から続く日本将棋連盟の定期刊行物です。タイトル戦から主要アマチュア棋戦まで、合計500局以上を収録。例年同様七大タイトル戦、竜王戦決勝トーナメント+1組、A級順位戦、王将リーグは全局収録しています。さらに毎年好評の巻頭特集も充実!今回は以下のような内容となっています。 (1)先崎、鈴木が語るこの1年と羽生善治論 (2)現代に生きる升田将棋 (3)飛躍する女流棋士・奨励会員 (4)詰将棋の最高峰・看寿賞とプロ棋士 (5)はやった戦法・消えた戦法。 人気の棋士名鑑は健在、また、先後別、戦型別の勝率などのデータも掲載、まさに将棋をあらゆる角度から楽しめる、ファン必携の一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 これを読まずに矢倉は指せない! 本書は将棋の基本といえる矢倉囲いにおける必須手筋を77紹介したものです。「組めたら初段」と言われる矢倉ですが、大平武洋六段の分かりやすく丁寧な解説で基本から中盤、終盤の手筋まで幅広く理解できる内容になっています。 まず第1章では「矢倉囲いの基本」と題して金矢倉、銀矢倉、菊水矢倉、片矢倉といったさまざまな矢倉囲いのメリットとデメリットが解説されています。続く第2章~第4章で端、タテ、横からの攻めとそれに対する受けの手筋を紹介、さらに第5章では終盤の手筋、第6章ではプロの実戦に現れた手筋を解説しています。 本書に書かれている77の手筋をマスターすれば自信を持って矢倉が指せるようになるはずです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 関西のトップランナー二人の才能が激突! 糸谷先生と意見交換するところでは、私自身楽しく参加させていただきました。「先手の責務」などのフレーズからは糸谷先生の将棋観が見えてきて楽しめる内容になっていると思います。(斎藤) 本書は、糸谷哲郎前竜王と昨年度勝率1位賞、新人賞を獲得した関西きっての若手精鋭斎藤慎太郎六段が現代将棋の27のテーマ局面について語るものです。 斎藤六段の深すぎる研究、糸谷八段の独特の視点に感嘆し、読むだけでプロの読みと大局観が学べます。「相矢倉 ▲4六銀―△4五歩型」から始まり、「横歩取り △7二銀早上がり」「角換わり腰掛け銀 端歩問題」。振り飛車では「角交換型振り飛車」「ゴキゲン中飛車対超速 銀対抗」「糸谷流右玉」など。バリエーションに富んだ、美味しいとこどりの一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 厚い碁の真髄がここにある 「世界一厚い碁」といわれるほど、厚み重視の棋風で知られる今村俊也九段。 本書は今村九段が厚い碁を打つうえでの必須事項を解説した初の著書となります。 今村九段が一番重要視するのが「石のつながり」です。 自分の石がつながっていると、必然、弱い石がなくなり、厚い碁形になりやすいからです。地では遅れをとりますが、後の攻め、寄り付きで取り返します。 本書では「石のツナギ方」や「本手の打ち方」といったテーマを通じ、厚い碁形を実現するための基本を押さえていきます。 さらには、今村九段の実戦譜を通じ、厚く打って勝つストーリーを体感していただきます。愚形といわれるアキ三角でさえも、厚い手と考える今村流の思想は、多くのアマチュアにとって新鮮でしょう。 厚い碁で勝ちたい方は、必読の一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 将棋史始まって以来の究極の殴り合い! 本書はゴキゲン中飛車に対して7手目▲5八金右とわずかな得を求めた手に対し△5五歩▲2四歩と互いに一歩も引かずに大決戦となる「超急戦」について解説したものです。 ゴキゲン中飛車の存続に関わるこの戦型の進化が、時系列にそって壮大な一つの物語のように語られています。 第1章 始まりはいつもこの男たちから 第2章 帝王の参戦 第3章 中飛車党の憂鬱 第4章 遠見の角が見てきたもの 第5章 息を吹きかける若者たち 居飛車が新手を出せば、振り飛車もそれに対抗し、現在も結論は出ていないこの戦型。これまでに公式戦やタイトル戦の舞台で数々の棋士がユニークな新手を生み出してきました。 堀口新手▲7五角 室岡新手▲3三角 阿久津新手△5三香 佐藤新手△8九馬 そして、▲1三龍、▲3三香、△5七歩…。 その間に第59期王将戦第6局での久保利明棋王の3連続銀合(書籍内では「トリプル・ダイヤモンド・シールド」)をはじめ、多くの名局が生まれました。 棋力向上が図れることはもちろん、将棋の戦法進化のドラマとしても楽しむことができます。さらに、プロ棋士の将棋に対する情熱も堪能できる一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 西武鉄道の車両や駅、運行のしくみを徹底図解! 西武鉄道の各路線や車両、駅、車両工場&基地、運行、保守などについて、その成り立ちやしくみを余すところなく徹底紹介。走行中のさまざまな車両の詳細(形式図や駆動方式、制御方式など)はもちろん、懐かしの名車『レッドアロー号』や過去に走った臨時列車、自動列車装置(ATS)のしくみまで写真&イラストで解説します。巻末には、100年を超える西武鉄道の歴史が時系列で分かる年譜も掲載。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 横歩取りの定跡はこの本に全て書いてある 定跡伝道師こと所司和晴七段が戦法の定跡をあますことなく伝授する早分かり定跡ガイドシリーズ。第7弾は横歩取りです。現在プロ・アマ問わず大流行している横歩取り。本書は基本の駒組みから相横歩取り、△8五飛戦法、そして最新の△8四飛・5二玉・7二銀型まで7章にわたって解説したものです。これまでの早分かりシリーズ同様、先手、後手どちらにも肩入れすることなく中立の立場で定跡を紹介しており、先手になっても後手になっても使える内容となっています。 横歩取りは複雑、難解というイメージがありますが、まずは各戦型における定跡手順を知ることが理解の第一歩となります。定跡とはプロ棋士が試行錯誤の果てに作り上げた互いの最善手の応酬ですから、定跡を覚えることはそれだけで大きなアドバンテージとなります。日々の実戦の将棋にも、プロの対局観戦にも大いに役立つ一冊。ぜひ本書で横歩取りの定跡をマスターしてください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 地を与えたほうが勝ちやすい!? 囲碁界で大局観が優れているとして評価が高い小林覚九段。その小林九段が指摘するアマの大きな弱点が「ヤキモチを焼いた手の多さ」です。相手の陣地が大きく見えてしまい、慌てて打ち込みに走ってしまう「ヤキモチ」の手。結果、自分の石が一方的に攻められ、形勢を悪くする大きな要因になります。そこで本書はどういった手がヤキモチなのか、さらには、ヤキモチを焼かずに打ち進めれば、なぜ優位に立てるかを解説していきます。「相手の陣地を一目でも減らしたい」と思うのは打ち手の当然の心理です。しかし、本書を読めば「相手に地を与える」ことも立派な戦略であると実感していただけるでしょう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 知名度はB級、破壊力はA級の最強マイナー戦法を伝授 本書はプロ間では指されることのないマイナーながら有力な戦法=B級戦法を紹介するものです。得意戦法をメジャー戦法に求める限り、対抗上ライバルもその戦法に詳しくなる可能性は高くなります。「自分の得意は相手も得意」状態です。これでは楽しく将棋が指せません。「自分は得意、相手は不得手」という策はないものでしょうか?というわけで「B級戦法ノススメ」と相成る次第。プロの定跡書で触れられることが少ないからといって侮るなかれ。「B級戦法を笑う者はB級戦法に泣く!」マイナーだからこそそれを知らない対局相手の意表を突き、未知の世界へ引きずり込んで戦いを有利に進めることができるのです。格上相手に勝てることも珍しくありません。対藤井システム猫ダマシ、右四間端棒銀、ポンポン桂、擬装宗歩四間、矢倉崩し左美濃中飛車、最短!ノーガード戦法、横歩取り素抜きトリックなど合計14のB級戦法を伝授します。本書でメジャー戦法とは一味違う自分だけの得意戦法を身に付けて、実戦で大暴れしてください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 この一冊で中飛車左穴熊対策は万全! 中飛車左穴熊は、まず飛車を5筋に振って、相手の様子を見ながら、自玉を左右のどちらに囲うか決める柔軟で合理的な作戦。菅井竜也七段が連採して高勝率をあげ、今泉健司四段がこれでプロ合格を勝ち取ったことで一気にメジャー戦法となりました。これまで今泉四段や杉本昌隆七段による中飛車左穴熊目線の戦術書は出ており、これに苦しめられてきた方も多かったと思います。 そんな方にぜひ読んでいただきたいのが本書で、現在主流となっている指し方△2四飛△2五歩型から藤森四段らしさ全快の超攻撃的な対策(鬼殺し風藤森スペシャル)や一風変わった作戦(△7六飛パックンチョ戦法)まで、なんと10個もの中飛車左穴熊の撃破法が書いてあります。これを読めば中飛車左穴熊はもう怖くありません。 自分の棋風に合った形を見つけて、ぜひ実戦で試してください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 シリーズ第2作! LaQランドの地下に発見された不思議な「迷宮」の謎を追って…。 本書は『LaQ(ラキュー)』のあそび方、つくり方を面白い漫画のストーリーに沿って紹介するガイド本となります。LaQとは、ヨシリツ(株)が販売するオリジナルのブロック玩具。角度のついた連結パーツを使って曲面や球体も表現できる新発想の人気玩具です。 LaQをベースに日夜、研究・開発に励む「LaQハカセ」、そしてLaQ大好きな小学生のヨシオくん、リツコちゃんが、おもしろくふしぎな世界を大冒険しながら、さまざまな作品づくりのアイデア、組み立て方のテクニック、あそび方のヒントや裏技などを紹介していきます。ハカセが作った愉快なLaQ作品たちが繰り広げるシリーズ第2弾! 今回は、LaQランドの地下から、偶然にも発見された「迷宮(ダンジョン)」の謎に挑むストーリーです。地下に広がる摩訶不思議な世界の探索に乗り出したLaQハカセ、ヨシオくん、リツコちゃんでしたが…。3人の前には、どこからともなく忍者が現れ、LaQハカセをさらって行ってしまいます。迷宮に迷い込んだ3人の運命は果たして…??? 【※ 本書は2011年2月刊行の『LaQランド 地下迷宮の謎』の内容に一部変更・修正を加え、改装した新版です。】
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ですが、やはり基本をおろそかにすると、トータルでの成績は安定させられません。本書は、私なりに『これだけは外せない!』と思っている基本をまとめました」(まえがきより) この本はルールは覚えて麻雀を打ち始めたもののなかなか思うように勝てない方や、かなり麻雀をやっているけれども改めて基本を確認したい方のために二階堂亜樹プロが贈る麻雀基本講座です。牌効率やスジの話から現代麻雀において特に重要なリーチや鳴きの判断。守備に役立つ実戦によく出る形における読みや、半荘の後半での着順を意識した打ち方まで。麻雀に勝つ上でのきちんとした基礎作りができるようになっています。 麻雀には「絶対」と呼べる打ち方はほとんどないため、何を切るか、リーチをするかといった判断にも正解がない場合が多くなります。そんな中で本書では「こうしておけば正解になる可能性が高い」という二階堂亜樹オススメの基準が示されています。もちろん、その基準に絶対に従う必要はなく、基準をある程度試した上であとは自分流にアレンジして欲しいと二階堂プロも言っています。まずは本書で基本をしっかりと身につけ、その上で日々の麻雀の実戦を続ければ、成績も安定し、勝率も目に見えて上がっていくはずです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 これを読まずに現代矢倉は語れない。 本書は、数十年にわたって続いた矢倉の基本形▲4六銀・3七桂型を根底から覆し、矢倉戦法を百花繚乱の戦国状態に陥れた張本人「矢倉△4五歩反発型」について解説したものです。現在プロ間ではこの△4五歩反発型が非常に優秀であるため、▲4六銀・3七桂型は使えないことが当たり前になっており、すでに早囲いなど他の形が模索されています。本書にも書かれている通り、▲4六銀に対する△4五歩自体は昔からあった手です。しかし、この歩を突くと後手が苦しくなる、という結論に達したのが2009年。その前提のもとに▲4六銀・3七桂型が矢倉の主戦場になり、いわゆる銀損定跡や91手定跡といった研究が進みました。そのような状態の中で、それでも△4五歩はあるのではないかと秘かに研究を続けていたのが本書の著者である塚田泰明九段です。準備を整え2013年の6月に遂に△4五歩と突いて、勝利を収めます。その後△4五歩反発型の優秀性が見直され、矢倉の景色は一変してしまいました。しかし、長い間▲4六銀・3七桂型に親しんできた多くのアマチュアファンにとって、「なぜ△4五歩反発型で▲4六銀・3七桂型は滅んだのか」はきちんと説明されないまま、「謎」として残っているのが実情ではないでしょうか? その謎の解明を△4五歩復活の口火を切った塚田泰明九段本人が解説したのが本書です。 △4五歩反発型の基本コンセプトは「後手番でも攻め合う」ことだと塚田九段は言っています。本書では▲4六銀に対する△4五歩の反発はもちろん、▲4六銀に代えて▲2六歩とした場合、▲1六歩とした場合も詳細に解説、すべての場合において後手番でも攻め合いで互角以上になることが明らかにされています。本書を読めば、「なるほど、そういうことだったのか」と納得でき、矢倉戦法の理解が一層深まるはずです。矢倉の今を解明する一冊、本書を読まずして現代矢倉は語れません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 自分だけの武器を身に付けて碁敵をアッと言わせよう 定石とは互角に分かれるもの、というのが囲碁の常識です。しかし、それは定石を知り尽くしたプロ同士の対局で言えることです。アマチュア同士の対局では、定石はあらかじめ勉強しておくと、実戦においてそう苦労せず、形勢に差をつけられる「美味しい」分野なのです。 本書は、基本定石のちょっとした裏変化を30型紹介しています。取り上げる定石は、以下の点を考慮して厳選しています。 ・実戦形で実現度の高いもの ・「ハメ手」とは違い、相手に正しく受けられても互角に分かれるもの ・相手が間違えれば、形勢がはっきり良くなるもの 解説も、変化の威力や使いやすさが☆表記でひと目で分かるようになっていたり、目指すべき変化(仕掛けが成功した変化)をマークで明記しているなど、分かりやすいような工夫を徹底しています。裏変化だけではなく、その定石で最も有名な形も掲載しているので、定石を基礎から勉強したいという方にもオススメです。 本書の内容を身に付けて、碁敵をアッと言わせましょう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 温故知新! 2008年に発売し大好評の「依田流 並べるだけで強くなる古碁名局集」の続編が、ついに登場。本作では、江戸時代初期に打たれた碁を中心に26局を、依田九段独特の観点から解説します。本因坊道策はもちろん、道策が参考にしたとされる中村道碩の碁にも大きくスポットをあて、現代でも十分に参考になる打ちまわしを鑑賞していただきます。本書では、ハイライト図を掲載するなど前作よりもより丁寧に棋譜を解説しており、級位者から有段者まで、だれでも手軽に棋譜並べを楽しめる一冊となっています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 地を取るよりも、形を整えよ!「自然流」武宮九段が、上達を妨げているアマ特有の4つの感覚を指摘し、矯正します。なかでも最もやっかいなアマの悪癖は、訳も分からず地を欲しがること。地はあくまで最終的な結果であるにも関わらず、アマは常に地のことばかり考えています。しかし実際には「身分をわきまえることと、良い形をたくさん作ることを心がけていれば、結果的に勝つことができる」と武宮九段は説きます。囲碁観がガラリと変わり、勝率がアップするだけでなく、楽しく打てるようになる一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 呉清源師 推薦! 依田が感動した 究極の熱闘譜 「歴代の棋士たちが命がけで残した棋譜は、熱気を感じます。たとえこの世を去ったとしても、棋譜のなかで生き続けていくのです」と、著者・依田紀基九段は話します。 本書は、依田九段が感動した古碁名局全32局を厳選した一冊です。本因坊家の棋士たちや呉清源師が命がけで残した熱闘譜を、依田九段の研究成果、感じたこと、長年の疑問などを中心に解説していきます。同時に、対局当時のエピソード、依田九段のエッセイなどもふんだんに盛り込まれています。 並べれば並べるほど強くなり、読めば読むほど感動する一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 アマチュアは 欲張りである!「宇宙流」「自然流」でおなじみの武宮九段が、陥っていることにすら気づいていない、アマチュアの4つの錯覚を鋭く指摘します。アマチュアに共通して言えることは、非常に欲張りなこと。なんでもかんでも欲しいと思うあまりに、正しい判断ができず、結果的に自分で自分を苦しくしてしまいます。本書では、「力の入れどころ」「地」「石の方向」「打った石の意味」における錯覚を指摘し、克服法を解説します。いつも目一杯に打ってはいけないことが納得できる一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 狙いのない手は、本手ではない! 「本手」とは何? と聞かれて、正しく答えられるアマチュアの方は、ほとんどいないと思います。「何となく形っぽいから守ろう」という手は、実は本手ではない場合が非常に多いのです。逆に、本手を打たなければならない局面なのに、間に合わせの手で済ましてしまう場合も、毎局必ずといって良いほど打っているはずです。 本書ではまず、本手の正しい意味を理解していただきます。そしてその活用法から本手とウソ手の見極め方まで、実戦ですぐに役立つ本手の打ち方をきっちり身に着けていただきます。何が大切な守りかが、しっかり理解できる一冊です。
-
-大手レコード会社を経て、マルチメディアの黎明期に数々のヒット作品を世に送り出し、現在はハイレゾ音源の普及に関わる著者は、音楽と出会うことで人生が変わったと言います。本書はこれまでの人生を振り返り、「音楽の力」を自伝的に綴ります。第1巻は音楽を志した学生時代から、音楽業界に就職した頃までの話です。 1. 音楽との出会い 2. 好きな音楽を仕事にしたい! 3. レコーディングに挑戦 4. いざ就職活動へ 5. 学生時代の音楽の楽しみ方! 6. 就職活動終了! 7. レコード会社へでの営業研修 8. レコード会社での工場研修 9. 工場での仕事 10. やってしまった! 11. 工場での試聴会 12. 新たな出会い!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 スラスラ読める打碁集、登場! 棋譜並べは、囲碁の上達には欠かせません。しかし、重たい本を手に持って碁盤に向かうというイメージがあって、なかなか気軽にできないものです。本書は、電車でも、布団の中でも、いつでもどこでもスラスラ読める「世界一わかりやすい打碁シリーズ」の第1弾です。シリーズ第一作目は、羽根直樹本因坊の碁。1譜の進行手数はほぼ4手以内で、布石から戦いの急所まで、一手一手の意味を多数の変化図を用いて丁寧に解説しています。張栩棋聖、井山裕太名人など、一流棋士との対局を、初級者の方でもやさしく理解できる一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 あなたが負けるのは、形勢判断をしないからだ! 「形勢判断は、難しくて面倒くさい」と思われている方が多いと思います。しかし、実はとても簡単なのです。本書では片岡九段が、簡単に形勢判断ができる3つのポイントをやさしく解説しています。「戦うか、戦わないか」「模様をどう考えるか」など、一局のなかでは、迷う場面が必ず何度か出てきます。そんなときに、(1)石の形・働き(2)石の強弱(3)地の比較、という、たったこれだけの形勢判断のポイントをおさえておけば、楽に次の一手を見つけることができるのです。地を数える必要など、ありません。本書で大ざっぱな形勢判断法を身につければ、あなたの勝率は大幅にアップするでしょう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 戦いを避けるなら、ハサミを打て! 力自慢の碁敵の、強烈な攻めに悩まされている方は、多いのではないでしょうか。本書は穏やかな棋風でタイトルを奪取した羽根本因坊が「戦いを避けて勝つ方法」を伝授します。「戦いを避けて勝つ」とは、「序盤でリードしてそのまま逃げ切る」ということ。本書は「ハサミはむしろ戦いを避ける打ち方」「模様を早めに消すのが乱戦を避けるコツ」など、穏やかな展開にもっていく布石の考え方とテクニックを徹底的に解説しています。 碁敵が中国流、三連星などを布いて戦いに引きずり込もうとしてきても、乱戦を避けて穏やかに勝つ方法は確かにあるのです。戦いが苦手で頭を悩ませていた方、ヨセ勝負が好きな方にとっては、まさに目からウロコの一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 一手の大きさは数字で判断できる! 自分が打った一手を「大きい」あるいは「小さい」と言われた経験は誰にでもあるでしょう。しかしそうは言われても漠然としていてよくわからず、実感できない場合が多いのではないでしょうか。 本書は布石から大ヨセまでを題材に、一手の大きさを考えます。次の一手を選ぶ上で重要な考え方を解説し、正しい一手とアマチュアが誤って選びがちな一手の価値を、可能な限り数値化して比較します。自分が選んだ一手が予想以上に小さく、正しい一手が見た目以上に大きいことを、驚きとともに実感できるでしょう。題材は、ほとんどが著者・片岡聡九段の実戦譜。藤沢秀行九段、加藤正夫九段、小林光一九段、依田紀基九段といったトップ棋士との名勝負を並べながら、一手の大きさを学ぶことができる一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 とっておきの振り飛車破りが4つ身につく本 一つ、オッサンは流行戦法で勝負しない 一つ、オッサンは細かい手順を気にしない 一つ、オッサンは取れる駒は取る 本書で解説されるのは若手の最新研究とは対極に位置する「オッサン流」の振り飛車破りです。プロの実戦で現れることは少ないマイナー作戦ではあるものの、実際は非常に優秀で、スペシャリストになれば勝ちまくることも十分可能という代物です。 本書の構成は以下のようになっています。 第1章 ゴキゲン退治 盛り上がり戦法 第2章 四間飛車退治 鳥刺し戦法 第3章 四間飛車穴熊退治 ホラ囲い 第4章 石田流退治 棒金戦法 中飛車、四間飛車、三間飛車と一通りの振り飛車に対して神谷八段がユニークな作戦を紹介してくれます。特にゴキゲン中飛車に対する盛り上がり戦法は神谷八段のオリジナル。はやりの「超速」とは一風違います。右銀が▲3七銀→▲4六銀と出て行く前に左銀を▲6八銀→▲7七銀→▲6六銀と前線に繰り出すのです。金銀で中央を制圧する雄大な構想には現代将棋では味わえない快感があります。鳥刺しや棒金をご存知の「オッサン世代」の方はもちろん、たまには居飛車穴熊以外の楽しい対振り戦法を指してみたい若い世代の方にもオススメの一冊です。また、特筆すべきは神谷八段の原稿の面白さ。ここまでユーモアの利いた戦術書はこれまでにない、といって過言ではありません。 以下にまえがきを転載します。本書で神谷流のとっておきの振り飛車破りをマスターしてください。 まえがき(本書の正しい使い方) この本を読んだら早速将棋大会やネット対局で使ってみる。その際うまくいったときは喜び、棋友に「良書だ、ぜひ買って読め」と勧める。うまくいかなかったときは自分の力が足りなかったと考え、著者や出版社を恨んだりしない。読み終わった後、オッサンらしくコンピュータ操作が苦手なことを自覚してネットオークションに出したりは絶対にしない。 オッサンらしく読み終わった数ヵ月後に読んだこと自体を忘れて再び購入する。できればこれを数回繰り返す。以上です。 八段 神谷広志
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 こんな手があるのか! 「え?こんな手があるの?」という手筋が囲碁には存在します。それもプロアマ問わず、よくある布石の形で登場する手です。相手が知らないと、すぐに有利になる「荒らし」・「分断」の手筋や、自分が知らないとすぐにピンチになってしまう「整形」の手筋などです。プロの間ではその手が存在するために、互角だと考えられてきた分かれが、一方の有利な分かれと結論が変わった形もあります。そんな、知っているのと知らないのでは天地の差が生まれる手筋を36型紹介します。 また、一つの手筋ごとにまとめページを設けているので、一通り本書を読んだ方は、まとめページを活用して復習するとスッキリ覚えることができるでしょう。オススメの棋力は初段前後の方ですが、中には高段者が知らない手筋も紹介しています。本書の手筋を身につけ、碁敵だけではなく、普段、石を置いている相手にも「アッ」と言わせてください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 石の方向は苑田流格言に聞け!「囲碁観が180°変わる苑田流格言」と「苑田流格言 実戦講義」の2冊が文庫で登場! 独自の格言、理論で囲碁の本質を伝えている苑田勇一九段。そのわかり易い手法は囲碁界でも随一です。本書はその理論の詳細と実戦での活用法が余すことなく書かれた一冊です。 前半部では、まず苑田流格言の基本となる考え方をマスターします。 ・「美人は追わず」の格言はどういった局面で役立つのか? ・「地は囲わず囲わせる」ほうがよいのはなぜか? ・「いじめる」とはどのような折衝のことをいうのか? 等々、正しい石の方向を身につけるための理論を丁寧に解説します。一方、後半部では、苑田九段の実戦譜8局を題材に、格言、理論を実戦でどう生かすかがテーマです。都度変化していく局面に対して、石の強弱、石の数などを基に、次の一手を導き出す苑田流の手法は必見です。対局で石の方向に悩んだ際にはぜひ「苑田流格言」を思い出してみてください。きっとその有用性がおわかりいただけるでしょう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 天才・青嶋の最強居飛車穴熊本! 本書は2015年度の順位戦C級2組で1期抜けを成し遂げた若手精鋭、青島未来五段による戦術書です。 青嶋五段の快進撃を支える原動力は何といっても穴熊。元々は居飛車穴熊だけしか指していなかったものの、居飛車党相手にも穴熊を指したいと思って振り飛車穴熊も指すようになったという筋金入りの穴熊好きで、高勝率をあげています。本書ではその穴熊のスペシャリスト青嶋五段が解説する相穴熊の戦術書です。ゴキゲン中飛車に対して居飛車が穴熊を目指し、中飛車側も堅さ負けを嫌って穴熊にした場合、本書が力を発揮します。 序章で相穴熊という独特の戦型における考え方を示した後、第1章で超速からの穴熊、第2章で一直線穴熊、さらに第3章で後手番での一直線穴熊を深く掘り下げています。居飛車からの有力な狙いである▲8六角や▲2六飛~▲4六飛の揺さぶり、それに対する振り飛車の対応が詳細に記されており、居飛車党はもちろん、振り飛車党の方にも大いに参考になる一冊になっています。 各章の終わりには「青嶋の結論」としてまとめが入っており、終章では「将棋とチェス」と題して趣味のチェスについて将棋と比較しながら語っています。本書をマスターして、ゴキゲン中飛車には自信を持って穴熊を目指してください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「詰将棋パラダイス」から200問を厳選! 本書に収録された問題は詰将棋専門誌「詰将棋パラダイス」に掲載された3手詰と5手詰の中から、良問200題を厳選したものです。また、書籍化に当たって丁寧な解説を加えてあります。 短手数の詰将棋を数多く、繰り返し解くことが将棋上達の近道です。本書に収録された質の高い詰将棋にチャレンジして、ひと目で解けるようになればあなたの棋力は格段にアップしているはず。本書を手にとって、早速第1問に挑戦してください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 カス石の見分け方、教えます! 「石を捨てる意味がわからない」「捨てて良い石、悪い石の区別がつかない」とお悩みの囲碁ファンの皆様に、ぴったりの一冊が登場! 本書では、捨て石の意味はもちろん、捨てて良い石と悪い石の見分け方、そしてシメツケの考え方まで、捨て石の基本から応用法までを徹底的に解説しています。大切なのは、その石が、ねらいを持っているかどうかと、強い石にくっついているかどうか、の2点。 本書を読めば、石を取ることよりも、捨てることのほうが面白いと思えるようになるでしょう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 愚形よ さらば! アマチュアの気持ちをよく理解している三村九段による、石の形問題集が誕生しました。プロは、子供のころから強い人の打った碁を盤にならべ勉強し、たくさんの良い形を体に染み込ませています。 本書では、「サカレ形」「二目の頭」「利かしと味消し」「重い石と軽い石」など、アマチュアが間違いやすいありとあらゆる石の形を、135題の練習問題を解くことで身につけていただきます。三村九段による前作「石の形 集中講義」と併せて繰り返し練習すれば、無意識にプロ級の良い形が打てるようになることは間違いありません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 週刊将棋の人気企画をもう一度! 「週刊将棋はプロの公式戦報道を核として紙面を制作してきた。その一方で、オリジナル企画も重視し、いつの時代の編集部も知恵をしぼった。それではオリジナル企画の中で最もインパクトがあったものは何か。おそらく『週将アマプロ平手戦』だろう」(週刊将棋編集長 雨宮知典) 週将アマプロ平手戦はアマチュアタイトル保持者とプロ棋士との真剣勝負で週刊将棋の30余年の歴史の中で8回行われました。プロ陣営は若き日の島朗、羽生善治、村山聖、森内俊之、佐藤康光、屋敷伸之といった後のトップ棋士が参加し、アマからも谷川浩司九段の兄の谷川俊昭さんや、第2回でプロを4連破してA級八段の南芳一プロを引きずりだした小林庸俊さんなどのスターが生まれました。 本書は2016年3月30日をもって休刊となった週刊将棋の歴史を人気企画で振り返るものです。上記の週将アマプロ平手戦の他にも、人気オリジナル企画の対コンピュータ将棋対局「COM3強VSA級棋士 指し込み3面指し」と「週将アマCOM平手戦」を収録しています。いずれも負ければ血の出る真剣勝負で、観戦記からは当時の将棋界が持っていた「熱」が伝わってきます。週刊将棋の30年を振り返る記念碑的一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ムツゴロウさんは麻雀も凄かった! 「私は、短期決戦は苦手である。長くなければ面白くない。その日のツキの具合や、相手のクセなどを見抜き、じっくり打ってこそ麻雀だと思っている。そうして得た知識をまとめたのがこの本である。この度、再版になり、世の中に出て行くことが決まり、私は大変よろこんでいる」(まえがきより) 本書はテレビ番組『ムツゴロウのゆかいな仲間たち』で有名な「ムツゴロウさん」こと畑正憲氏による麻雀戦術書『畑正憲の精密麻雀』に若干の修正を加え再版したものです。ムツゴロウさんは日本プロ麻雀連盟初代十段位(全3期優勝)であり麻雀界初のリーグ戦形式のタイトル戦「最高位戦」の発案者でもある麻雀界の重鎮。 東京大学理学部大学院卒の明晰な頭脳は麻雀という高度な知能ゲームをも攻略しようとします。技術と運、確率論の周辺、迷彩の功罪、テンパイ読み・・・。本書は麻雀という強大な敵に立ち向かった一人の天才の記録であり、麻雀戦術書のバイブルです。高度に発達した現在の麻雀戦術論の中にあってもそのオリジナリティと完成度の高さは他の追随を許すものではありません。 麻雀技術書の原点、すべての麻雀ファンの皆様に読んでいただきたい一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ヨセの手筋をこの一冊で制す! 山下敬吾九段による大好評「出る順」シリーズ。第3弾は勝敗に直結する「ヨセ」がテーマです。ヨセは手筋を身につけていないと、平凡にヨセてしまい、知らないうちに1、2目の損を重ねてしまいかねません。そこで本書は実戦に現れるヨセの手筋を、手筋の種類ごとに分類。「ツケ、ハサミツケ」から始まり、「オキ」、「切り」…と頻出度の高い順から攻略していきます。ランキング上位の手筋ほど問題も多く収録しており、様々なパターンを身につけることが可能です。加えて、問題は実戦形にこだわって出題しているので、実際の対局にもすぐに役立つでしょう。 全207問の問題を制覇したとき、あなたのヨセの力は飛躍的に向上しているはずです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 読めば読むほど強くなる実戦詰碁集が登場! 囲碁にとって「読み」はどのようなものでしょうか。 読みが楽しくて、囲碁をやっている」という方から「正直読むのはシンドイ・・・」という方もいるかと思います。しかし当然ながら、囲碁は手が読めたほうが有利なゲームです。「楽しく、読みの力をつけたい!」・・・全てのアマチュアが望んでいることだと思います。そんな願いにプロの中でも詰碁作りに定評のある、三村智保九段が応えてくれました。 7手、9手、11手と手数は長めですが、初手が見つけやすいものや、基本手筋だけで解ける問題を集めているので楽しく解き進めながら実力アップが図れます。また、「読み」以外にも、基本手筋や死活に関する豆知識などお得な情報が満載で、まさに”読む”たびに強くなる実戦問題集になっています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 早囲い抜きに現代矢倉は語れない! 本書は矢倉の早囲いについて、気鋭の若手上村亘四段が詳細に解説したものです。 平成25年に▲4六銀に△4五歩と反発する手の優秀性が見直されたのをきっかけに、それまで「矢倉といえばこの形」と思われていた▲4六銀・3七桂型が激減、現在先手の矢倉作戦は百花繚乱状態にあります。そんな状況の中で先手矢倉の主力になり得るのが本書で解説されている「早囲い」。矢倉戦において玉を6八→7八→8八と二段目を通るルートで動かすことで一手早く囲うこの手法。従来の囲い方では十分に組めないとすれば、囲いを手早く済ませて少しでも早く攻撃陣を構築すべきという発想からスタートしています。 本書では、まず早囲いの歴史と理想的な展開を解説。相手が早囲いについて何も知らなければこれだけで十分勝てるでしょう。さらにその後、それを阻む相手の対策を紹介し、それに応じた組み方を説明しています。従来の形と、その天敵といえる急戦矢倉との戦い。藤井流早囲いの解説。藤井流への対策と最新の早囲い。さらに力戦と相早囲いまで。まさに「早囲い・完全ガイド」の名にふさわしい一冊。この本を理解すれば早囲いに関してあなたの回りの誰よりも詳しくなることができるはずです。ぜひ実戦でスピーディでスリリングな矢倉戦を楽しんでください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 あなたと一緒だと、楽しくて ここち良くて あったかい。一羽の小鳥があなたへのあふれる気持ちを届けます。大切な人のお誕生日に、いつも思っているけどなかなか言葉に出せない感謝の気持ちを伝えるグリーティングブック。 「今日は あなたが生まれた 大切な日」 「ずっと 伝えたかったキモチが 私の中から あふれだす」 あなたの大切な人に、是非とも心温まる言葉とイラストのプレゼントを贈ってください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 迷い、孤独を感じ、歩き疲れてしまった一匹の犬が、元気を取り戻し、ふたたび走り出すストーリー。元気をなくしてしまった大切なひとへ応援のメッセージを届けるグリーティングブックです。 「時には 道に迷ったり 疲れてしまうことだって あるよね」 「大きく深呼吸して 気持ちを 全部 はき出してみよう」 あなたの大切な人に、是非とも心温まる言葉とイラストのプレゼントを贈ってください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 基本死活には法則があった! 「基本死活」の理解は上達のためには必要不可欠ですが、アマチュアにとっては敬遠しがちな分野ともいえます。実際、著者の依田紀基九段も「プロとアマの一番の差は死活の理解度にある」と述べています。そこで、本書では依田九段が発見した独自の法則を用い、基本死活を体系的に理解することを目指しています。 核となる法則は「隅は2・3・4、辺は4・5・6」です。本書はこの法則の説明から始まり、具体的な運用法、法則外の形の説明、実戦頻出の「一合マス」の考え方、といった具合にステップアップしていきます。 「筋場理論」に代表されるように、近年独自の囲碁理論を提唱している依田九段。今回の法則も、自身の囲碁教室での指導経験から有効であると証明されています。実戦でも本書の法則を使い、迷わずに生き、確実に相手の石を仕留める楽しさを味わってください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 アマ棋界の覇者が明かすとっておきの即戦力戦法 本書はアマ王将を始め、数々のタイトルを獲得しているアマトップ棋士中川慧梧さんがとっておきの4つの即戦力戦法を明かしたものです。中川さんは言っています。「アマ大会で勝つ戦略として、棋士による変遷目まぐるしい最新型を追うのではなく、自分のテンポで指せる戦型を持つことも有効である」 本書で中川さんが解説しているのはプロ棋界では「消えた戦法」として考えられているものです。 (1)スズメ刺し(2)角換わり△6四角型(3)角換わり▲4六角型(4)丸山ワクチン これらの4戦法について中川さんは独自の研究を進め、それがプロ相手にすら通用することを実戦で証明しています。また、見逃せないのがこれらの戦法の「勝ちやすさ」です。一気に終盤になる戦法ではなく、いずれも堅い玉を盾にしたねじり合いになるため時間の短い対局では強力な武器となります。 本書で最強アマのとっておきの即戦力戦法を身につけ、ぜひ実戦で使ってみてください。プロの流行形を追っている相手をあっと驚かせ、圧勝することができるはずです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 対石田流の考え方がわかる本 角道を開けた▲7六歩をさらに▲7五歩とつき、その筋に飛車を回る石田流。飛車を浮いた手が角頭を守っており、駒の連結がよく、現在プロ間でも最も勝率の高い戦法となっています。 居飛車側は組み上がった時点ですでに指しにくくなっていることもあるという恐ろしい戦法で、駒組み段階から気をつける必要があります。 本書は石田流の対策を、序盤の鉄則9つ、中盤の技術8つ、終盤の技術7つにまとめ、具体例とともに解説したものです。 石田流と戦う上で、手順を暗記するのではなく、考え方を示す内容になっています。 合計24の鉄則+技術を覚えるだけでもう石田流に苦労することはないでしょう。 もちろん、現在石田流を指している方にとっても参考になる内容ですので、振り飛車党の方にもオススメの一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 巨人の足跡を妙手で振り返る 「大山の記録が全て塗り替えられたとしても、その人生の価値は変わらない」(まえがきより) 棋士・大山康晴は大正12年3月13日、岡山県浅口郡西阿知町(現在の倉敷市西阿知町)に生まれ、50数年に及ぶ棋士生活ののち、平成4年7月26日に亡くなりました。本書は若き日から亡くなる69歳までトップ棋士であり続けた巨人・大山康晴の足跡を妙手と当時のエピソードで振り返るものです。少年時代、近所のおじさんに指した一手から始まり、木村義雄、升田幸三、中原誠、谷川浩司、羽生善治らを相手に指した将棋史に残る名手の数々。 対中原戦の△8一玉 対飯野戦の▲4九銀 対米長戦の△1二飛 対加藤戦の▲6八竜 対谷川戦の▲6七金 などなど。 数多くの名手や鬼手によって与えられた感動と、その生きざまが見せた人間ドラマを堪能できる一冊です。ささやかなる大山ツアーにご同行ください。 (日本将棋連盟発行)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「囲碁は読まなくても勝てる!」 囲碁において「手を読む」ことは、どれくらい勝敗に影響するのでしょうか? 実際、「読み」が影響するのは高段者同士、つまり囲碁人口のほんの一握りだといえるでしょう。 プロやトップアマは序盤や中盤で迷ったとき、「読む」のではなく、「勘」で着手を決めることがあります。しかし、ただあてずっぽうというわけではなく、それまで培ってきた経験からある一定の法則に従って着手を決めているのです。 本書は、その法則を5つにわけて「新格言」として紹介しています。 その5つとは、「急場がなければ大場に打つ」、「厚みに近寄るべからず、模様には近づくべし」、「助けるか、迷ったときは後の狙い」、「碁盤の広いほうから打つべし」、「岡目八目で打て」です。 これらの格言の意味を理解し、実戦で使いこなせるようになれば、まったく「読み」の練習をしなくても、誰でも二目は強くなります。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書では序章に、詰めの手筋講座をご用意してあります。いずれも詰将棋に頻出する基本的なテクニックなので、ぜひとも解く前にマスターしてほしいと思います。問題は週刊将棋に掲載された「詰将棋入門」から、3手詰めを134問と5手詰めを68問、全部で202問をご用意してあります。 監修の渡辺明竜王はまえがきで、繰り返し解いて、詰みの形に慣れることが大事だと述べています。終盤力アップのために、がんばって解いてみてください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「正確に読む」力を身につける! 林海峰名誉天元による死活三部作の第三弾です。前作「基礎力のつく死活」「必殺力のつく詰碁」を読んだ方はもちろん、多くのの囲碁ファンの皆さんにさらに力をつけていただけるよう、厳選した詰碁問題を200問収録しています。 出題内容は、実戦頻出の詰碁はもちろん、「攻め合いの手筋」や「トビを活用する手筋」を体系的に出題するなど、死活力アップに直結するよう工夫されています。3分間考えてわからなければ、飛ばして次に進んで構いません。繰り返し解くうちに、手どころで確実に手にする力が、驚くほどついていることしょう。 本書に根気強く取り組んで、棋力アップを目指しましょう!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 あっという間に 地が消える 本書は、実戦でよく現れる定石後の辺への打ち込み方と、打ち込まれたときの対処法を、パターン別にまとめたものです。 たとえば小目のツケヒキ定石。カカった側は必ず三間にヒラきますが、どこに入ったらいいのか、また、入られたときにどう応じたらよいのか、本当に理解している方は少ないのではないでしょうか。 本書では、知ってそうで知らない辺の打ち込みの急所を徹底的に解説しています。ノビるのかハネるのか、たった一路の差で勝負が決まってしまう場合もあるのです。 4つの鉄則をマスターすれば、明日から打ち込みがあなたの大きな武器となることでしょう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2016年3月26日、北海道新幹線(新青森~新函館北斗)がいよいよ開業、東京から新函館北斗までが最速4時間02分で結ばれます。北海道にとっては初めての新幹線、本書では開業に先立ち北海道新幹線の車両H5系の技術としくみ、新規開業の各駅、各駅を利用する観光案内など、その魅力と楽しみかたを紹介します。 また、新幹線開業によって第三セクター線として新たにスタートする道南いさりび鉄道や、在来の北海道のJR線についても紹介、北海道の鉄道の総ガイドブックになっています。 北海道の鉄道とは密接な関係にあったかつての青函連絡船、新幹線前史としての青函トンネルについても詳細に紹介し、読み物としても充実しています。 北海道新幹線の時刻表、料金表も掲載しており、開業後も使える1冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 序盤で差がつくのは、たった一路の差である! 本書は、序盤や中盤での相手の陣地の減らし方について解説しています。「相手の模様のどこにワリ打つか?」、「深く打ち込んでいくか、浅く消すか?」、「模様を消すとき、ツケとボウシと肩ツキをどう使い分けるか」、「地が大きくなる急所はどこか?」など、どれもアマが実戦で迷う局面を取り上げています。失敗図では、一路間違えただけで形勢に大きな差が出てしまった変化が多く取り上げられており、相手の地の消し方の重要さがよくわかります。 本書には、上で挙げたような局面でどういう選択をするかの考え方が書いてあるので、アマの強い味方になります。また、どのテーマ図も実戦形なので、自分の碁に生かしやすい点も特徴です。山田九段の前著『荒らしのテクニック』と合わせて繰り返し練習すれば、地に対する考え方は高段の域に達するでしょう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 これを読まずに美濃囲いは指せない! 「美濃囲いの最大の魅力は何といっても5手で囲えることです。手数のかからない囲いは他にもありますが、これほど堅くて安定している囲いはありません」(本文より) 手数の割に堅く、金銀の連結が美しい美濃囲いは振り飛車の基本の陣形です。ほぼすべての振り飛車党が指したことがある囲いであり、これを相手にしたことがない居飛車党もいないでしょう。それほど優秀な囲いである美濃囲いにも弱点があり、美濃崩しの手筋は数多くの棋書で紹介されてきました。 飛車を成り込んでの横からの攻め、玉頭の圧力による縦からの攻め、5五角のラインを生かした斜めからの攻め、そして最大の弱点と言ってもいい端からの攻め。本書では上記のような部分的に定跡化された攻め筋をまず紹介し、そのうえで振り飛車側がどのように戦えばいいかが示されています。底歩で囲いを強化する、▲2六歩と突いて玉を広くする、角のラインをあらかじめ止める、端攻めが決まってしまう条件を覚えそれに備える…。ここまで美濃囲いの受けに徹底的にこだわった本はありません。普段から美濃囲いで戦っている振り飛車党の方にはもちろん、美濃囲いを攻略したい居飛車党の方にもぜひ読んでいただきたい一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 名手・北浜健介八段による実戦で使える詰将棋 本書は詰将棋の名手・北浜健介八段による詰将棋問題集『脳トレ7手詰』、『脳トレ9手詰』の2冊を1冊にまとめたものです。7手・9手と言っても、前半は基本的な詰め手筋や実戦に出てきそうな自然な形が中心になっており、級位者の方でも取り組める問題が並んでいます。また、本書の特長は何といっても全問実戦型であること。囲い図式と言われる美濃囲い、穴熊、銀冠の形をした詰将棋が多く出題されています。実戦に現れそうにないパズルのような詰将棋でなく、あくまで実戦を想定して作られているため、本書で詰め手筋を覚えれば同じ手筋をそのまま実戦で使えることも十分あるでしょう(日本将棋連盟発行) 玉位置は全て三段目まで、さらにシンプルな配置で解いてみたくなる問題ばかりです。解けない場合は解答を見ていただいて構いません。数多くの問題を繰り返し解き、詰め手筋を覚えていくことで棋力向上につながります。