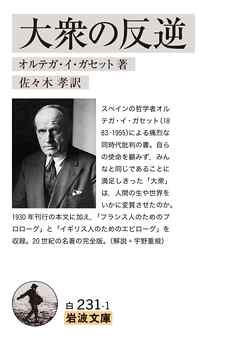あらすじ
スペインの哲学者オルテガ・イ・ガセット(一八八三─一九五五)による痛烈な時代批判の書。自らの使命を顧みず、みんなと同じであることに満足しきった「大衆」は、人間の生や世界をいかに変質させたのか。一九三〇年刊行の本文に加え、「フランス人のためのプロローグ」および「イギリス人のためのエピローグ」も収録。(解説=宇野重規)
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
無知無能な人間が外部に開かれた目的に向かって、ーー何の介入も受けずにーー 努力できることが自由の意味であったが、内なる欲望のままに活動できることが自由の意味にすり替えられた結果、能力を過信した人間が他者の影響を排除しながらやりたいことをやりたいようにやる権利を持っていると"勘違い";人間をたくさん生み出してしまった、、
Posted by ブクログ
概要
人々は自由主義や産業革命の進展により、歴史的に類を見ない高い生活水準を達成した。しかし、その副作用として、大衆による支配の時代が始まった。大衆は、自らの凡俗さを認めながらも、その凡俗さに安住し、変化への努力を怠る人々である。オルテガは彼らのことを、「満足したきったお坊ちゃん」と称した。また、彼らは、文明の繁栄を享受しながらも、感謝や貢献といった義務を果たすことを考えず、自らの権利だけを主張する。大衆の増殖により、政治が愚鈍で自分勝手な人々によって支配され、イノベーションは衰退する。
このように空虚で中身のない大衆が増えたのは、産業革命や自由・平等主義を背景とした歴史的な生活水準の向上である。今日の人々は、今の時代が歴史の中でも一番優れているという確信に満ちており、過去への尊敬や謙虚さを失った。歴史的に、人間社会は知識の蓄積とその継承によって、発展を遂げた。ニーチェ曰く、超人とは「最も長い記憶を持つもの」である。しかし、過去への謙虚さや憧憬を喪失した現代人は、過去を参照することは無くなった。かくして、現代人は歴史上最も優れていると確信しつつ、根無草のように自分がどこに向かえばいいのか分からない空虚さを抱えることになった。
大衆のもたらす悪影響のうちでも、最も憂慮すべきは政治の支配である。本来、文明とは共生の意志を問うものである。そして、国家は慣習や宗教、言語、血縁では統一できない人々を積極的に組み込んでいこう(連合、植民地化)とする形態である。国家の統一基準は、慣習や法律、宗教などの内部存立要素だけに求めることはできない。理由は二つある。①そもそも画一的に統一されていないこと。②特に経済的関係から、内部存立要素から外れた人々や企業との関わりが必ず生じること。そのため、それらの所与の条件を超えて、外部存立と内部存立双方を達成できる仕組みを構築する必要がある。
このような他者への拡張と共生を究極の目標とした国家や文明の基盤となるのは自由主義デモクラシーである。自由主義デモクラシーは、自分を犠牲にしても自由な空間を残し、権力に抑圧される少数の人々が生きることのできる場所を残すことで、その命題を解決しようと試みてきた。しかし、大衆は自らの利益や快楽のために権利を主張し、他者との共存を排除する野蛮な方向へと向かう。このように、今や全世界を蔓延る大衆の反逆は、多様な人々が共生する社会の実現を不可能へと近づけている。
感想
2年前に読んで途中で挫折してしまったので、再チャレンジをした。
まず感じたのは、これは大衆への全力の悪口本であると言っても過言ではないだろう。オルテガのストレートな批判は、かなり賛否が分かれそうである。今で言うと、ホリエモンにやや近い語り口と思想だと思う。「みんなバカすぎて呆れる」のスタンスである。
オルテガの主張には色々ツッコミどころが多い。そもそも大衆が大衆たる所以を、個人の自堕落へと責任を収斂させていく姿勢はいかなるものか。また、若干ヨーロッパ諸国による他国の支配を正当化する(時代が時代なので仕方がない)論理も鼻につく。
しかし、ここで描かれている大衆の出現の分析は、現代の衆愚政治の問題を考える上で多分に役に立つ。また、本書の要約では取り上げられることが少ないが、オルテガの国家や文明への考え方、そして共生の意志は、グローバル化した世界で一国家としてのスタンスを確定する上でも、一例として非常に参考になるだろう。
個人的には、オルテガの生の哲学、あるべき人間像には共感することが非常に多かった。しかし、そうではない人々を馬鹿にする態度はいただけないし、その性質の形成要因に関する分析は正直甘いと思う。そのため、この本を大衆の出現構造の完全理解を求める目的ではなく、自分なりの卓越した生と反面教師にしたい生を見つけ、自己を啓発する目的で読むのがいいんじゃないかと思う。
卓越した人間とは、自らに困難を課す人である。自らに多くを求める人間である。オルテガは以下のようにいう。
選ばれた人にとって、何か超越的なものに奉仕することに基づかないような生では、生きた気がしないのだ。だから彼は奉仕する必要性を抑圧とはみなさない。たとえば、たまたま彼に抑圧がないとしたら不安を感じ、もっと難しい、もっと要求の多い、自分を締め付けてくれる新たな規範を案出する。これが規律ある生、つまり高貴な生である。高貴さは、要請によって、つまり権利ではなく義務によって規定される。これこそ貴族の義務(Noblesse oblige)である。「好き勝手に生きること、これは平民の生き方だ。すなわち貴族は秩序と法を希求する」(ゲーテ)。
そのため私たちが今までの体験の中で知り合った、自発的で貴重な努力ができるごく少数の人たちが、孤立した記念碑のように見えてくる。彼らこそ選ばれた人、高貴な人、単なる反応ではなく自分独自の行動ができる人であって、彼らにとって生きるとは永続的な緊張、絶え間のない習練なのである。習練とはすなわち苦行(áskesis)であり、したがって選良・貴族は苦行者なのだ(21)。
(この文だけでも、オルテガのなんだか気取った嫌な感じは伝わるんじゃないかなと思う。私は嫌いじゃないですが笑)
私は卓越した人間は苦行者であるという考え方に賛成だ。努力なしで成功できる人間は天才だけである。苦しい道も自分の卓越性を高めると思ったら、少しでも飯の足しにはなるだろう。
私はこれを読んだ時、ゲーテのファウストを思い出した。ファウストは苦しみながら,目の前の事に使命感を持って取り組んだ。その生き様は、まさに卓越していると言えるだろう。
これに対して、大衆の描き方は笑ってしまうぐらいに酷い。
むしろ現代の特徴は、凡俗な魂が、自らを凡俗であると認めながらも、その凡俗であることの権利を大胆に主張し、それを相手かまわず押しつけることにある。
ここまでスパッと切り込んで描いてくれると、反面教師にしやすいものである。凡俗....。